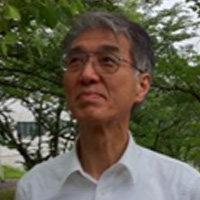ヴィクトリア・ヌーランドとは何者なのか③ ―ネオコンの衰退を防いだ「リベラル介入主義」との融合―
国際
国連に国務長官のブリンケン(手前)と共に登場したヌーランド。ブリンケンも「リベラル介入主義者」とされる。
ヴィクトリア・ヌーランドの夫のロバート・ケーガンについて特筆すべきは、ネオコンと呼ばれる右派政治勢力の代表格と目されつつ、米国の軍事・外交政策への影響力が大きく、かつ影響力を及ぼしている時間が異例に長い点にある。しかもネオコン自体はブッシュ(子)政権以降退潮を余儀なくされながらも、ケーガンはほぼ一人、未だ健在ぶりを示している。
前項でも取り上げたように、ケーガンと盟友のウィリアム・クリストルと組んで1997年に立ち上げたシンクタンク「米国新世紀プロジェクト(Project for the New American Century, PNAC)は、ネオコンを総結集するための強力な軸となった。そしてPNACが公表した特に重要な三つの文書、すなわち①1997年6月のPNAC発足にあたっての「原則に関する声明(Statement of Principles)」②1998年2月に当時の大統領ビル・クリントンにイラクへの武力行使を求めた「書簡(Letter to President Clinton on Iraq) 」③ネオコンが総力を挙げて次期共和党政権向けに世界戦略を描いた2000年9月の戦略文書「米国防衛の再構築(Rebuilding America’s Defenses)」―への賛同者、執筆者の現在を追跡すると、時代の流れを痛感せざるを得ない。
そこには同政権時代の高官、例えば副大統領のディック・チェイニーや国防長官のドナルド・ラムズフェルド、国防副長官のポール・ウォルフォイッツ、国防次官のダグラス・ファイス、国務次官のジョン・ボルトン等を筆頭に、知識人、政治家ら右派陣営の有力メンバーが綺羅星のように名を連ねていた。だが、そのなかで今日のワシントンにおける影響力を維持している存在としては、自身が準備した①はともかく、②と③に名前が見出せるケーガンが際立つ。
ケーガン以外にワシントンでの活動が健在なのは、実弟で③のプロジェクトに参加した軍事評論家のフレデリック・ケーガンがいる。フレデリックの妻のキンバリー・ケーガンは、ウクライナ戦争報道でしばしば主流派メディアの「情報源」となったシンクタンク「戦争研究所 (ISW)を主宰している。
またバイデン政権でこの7月、大統領と国務長官、連邦議会に意見を具申する「米国公共外交諮問委員会」の委員に指名されたエリオット・エイブラムス(注1)もその一人で、①と②に賛同の署名をしている。だが両人とも、「米国が現代に生み出した最も有害な影響力を持つ外交政策の知識人の一人」(注2)という評価もあるロバート・ケーガンに及ぶべくもない。
PNAC結成から四半世紀以上も経った現在、ネオコンの栄枯盛衰を感じさせるが、イラク戦争を始めとした「対テロ戦争」が行き詰まった末に任期が切れたブッシュ(子)政権の後に、彼らが支持した共和党の故ジョン・マケインが大統領選挙に敗れ、2009年にバラク・オバマ政権が誕生した。それは、ネオコン、あるいはネオコン的なるものが更なる打撃を受けた時期だった。それでも基本的にその潮流は温存されるが、従来のような在り方とは少し異なったものとなる。

ケーガンが2009年に旗揚げしたネオコンの新組織であるFPIのHP。ケーガン(左上)の斜め下にいるのが盟友のクリストル。ヌーランドのチェイニー副大統領補佐官時代の前任者であったエーデルマンも登場している。
ネオコンを延命させた政府風土
ケーガンは2007年にPNACが解散を余儀なくされた後、逆風が吹くワシントンで2年後の2009年に、再びクリストルらと組んで「外交方針イニシアチブ(Foreign Policy Initiative、FPI)」というシンクタンクを設立した。その結成趣旨では、「米国の外交、経済、軍事における世界への継続的な関与の促進と、米国を孤立主義への道に導く政策の拒否」が強調。さらに「政治的及び経済的自由を広めるために努力する米国のリーダーシップ」や「、米国が21世紀の脅威に立ち向かう準備ができていることを保証するために必要な国防予算を備えた強力な軍隊の確保」等が提言され、PNACの二番煎じという印象を強くしていた。
FPIはトランプ政権が発足した2017年に、有力スポンサーで共和党の億万長者ポール・シンガーがそれまで提供していた資金を打ち切ったためにこれも活動が停止となる。だが、イランやシリアへの軍事的対応の強化や、ロシアや中国の「人権問題」の追及といったテーマを取り上げ、「政策提言や主要新聞への論説の掲載、同じ考えを持つ団体と協力しての議員・政府関係者とのイベント共催など、さまざまな方法で政策課題を推進した」(注3)とされ、ケーガンはその先頭に立った。
それによって衰退したネオコンという存在が忘れ去られるのを防げたかもしれないが、ケーガン、あるいはヌーランドにとって幸いした事情があった。まず第一に、オバマ新政権になってもネオコンが生まれ、活動できた政治風土は必ずしも全面的に崩れていなかったという点だ。
米国の調査報道を代表する一人で、先駆的にヌーランドの危険性について警鐘を鳴らしてきた故ロバート・パリーは、オバマ政権誕生後も「ネオコンは決して終わったわけではなかった。彼らは賢明にも自分たちの立場を維持していた」として、以下のようにその理由を語っている。
「彼らは依然として、全米民主主義基金(NED)のような政府資金による事業を管理していた。彼らは、アメリカン・エンタープライズ研究所(AEI)から外交問題評議会、ブルッキングス研究所に至るまで、シンクタンク内で重要な地位を占めていた。彼らにはジョン・マケイン上院議員、リンジー・グラハム上院議員、ジョー・リーバーマン上院議員といった強力な同盟者が議会にいた。そして彼らはテレビのニュース番組や新聞のオピニオンページ、特に首都の地元紙である『ワシントン・ポスト』を支配していた。1970 年代後半から 1980 年代前半にネオコンがワシントンで顕著な勢力として初めて台頭して以来、ネオコンは“インサイダー”になっていた」(注4)。
ちなみに『ワシントン・ポスト』 は、ケーガンにオピニオン欄の常連執筆者の地位を与えて影響力の確保に貢献している。
イラン人を「抹消する」と叫んだヒラリー
第二には、オバマ政権に極め付きのタカ派であるヒラリー・クリントンが国務長官として就任した点が挙げられる。ヒラリーのそのような体質を示す言動は事欠かないが、中でも有名なのは、大統領選挙の民主党候補者選びでオバマと争っていた2008年4月22日、ABCのニュース番組「グッドモーニング・アメリカ」での次のような発言だ。
「私が大統領なら(イスラエルを攻撃すれば)イランを攻撃するということをイラン人に知ってもらいたい。……今後10年以内に、イラン人が愚かにもイスラエルへの攻撃を検討するかもしれないが、我々はイラン人を完全に抹消(obliterate)することができるだろう」(注5)
ヒラリーは感情を思慮もなく外に出す性格が顕著だが、おそらく戦後の米国内外の著名政治家で、特定の国民を「抹消」するなどと口にした例は稀有のはずだ。そうしたタカ派で「好戦的」とされる外交政策は、「リベラル介入主義者」あるいは「リベラルタカ派」と呼ばれる民主党を中心とした勢力の典型といえる。
一般にネオコンは、「米国は他国の政治に積極的に干渉して望ましくない政権を排除し、全力で自由民主主義を推進し、あらゆる可能な手段で地球規模の覇権を確保し、敵対する国々と戦わなければならない」(注6)とする意識が強いが、その点で基本的に「リベラル介入主義」と大差はない。無論、イスラエルのほぼ無条件の擁護も共通する。ネオコンは一時まで共和党が中心でユダヤ系が多いという印象が強かったが、国連等の国際機関に対してあからさまに無視したがる彼らと比べ、利用価値があれば重視するという「リベラル介入主義」のスタンスの差も確認できる。
民主党では、1990年代初めのビル・クリントン政権で国連大使や国務長官として影響力を発揮し、ヒラリーの師匠格にあたる故マデレーン・オルブライトが「リベラル介入主義者」として名高い。またカーター政権の国家安全保障問題担当大統領補佐官だった故ズビグネフ・ブレジンスキーや、現大統領のジョー・バイデンもこの系列とされる。
ヒラリーはオバマ政権の2期目が始まったばかりの2013年2月1日に国務省を去るが、翌2014年の6月15日付の『ニューヨーク・タイムズ』紙には、ケーガンとの蜜月状態を物語る記事が掲載されている。そこではケーガンが「ヒラリーの外交方針に関しては心地よさを覚える」と語り、「我々にとってヒラリーが追求するだろうと考える方針をその通りに追求してくれたら、その方針はネオコンと呼ばれるようなものだ」(注7)と期待を寄せている。
さらに、米国の著名な政治学者で、ネオコンに対する代表的な批判者として知られるピッツバーグ大学名誉教授のマイケル・ブレナーは、ケーガンのみならず「他のネオコンの著名人から賞賛の言葉を集めたのは偶然ではない。彼らは、ヒラリーを自分たちの外交政策の構想に共感を覚える(将来の)大統領として思い浮かべた」(注8)と指摘している。

オバマやヒラリー、バイデンを始めとした当時の政権の要人たち。2011年5月1日に米特殊部隊がオサマ・ビンラディンを急襲した際の「実況中継」を見ている場面とされる。
国務省の広報官に就任したヌーランド
そして第三には、民主党政権内にヌーランドの守護者がいたことだ。ヌーランドはNATO大使から左遷された国防総合大学での1年間の勤務後、2010年2月からブリュッセルで欧州通常戦力削減条約 (CFE条約)に基づく欧州の米国軍事特使を務めていたが、2011年5月に国務省に戻され、報道官という脚光のあたるポジションを与えられた。
この人事にどこまでヒラリーが関与していたか不明だが、前政権の副大統領ディック・チェイニーのネオコンの巣窟だったインナーサークルに属すると思われていたヌーランドが、国務省の「顔」として再登場したことに驚いたワシントンの住民は少なくなかったに違いない。前出のブレナーは、ヌーランドがビル・クリントン政権時代に首席補佐官として仕え、ヌーランドを「自分の弟子と見なす」元国務副長官のストロボ・タルボットによって「オバマ政権に送り込まれた」(注9)と述べる。
なおケーガンも同じ2011年の11月に、米国の外交政策について国務長官と国務副長官、国務省政策企画局長に助言する諮問委員会である外交政策委員会の25人の委員の1人に選出されている。当時の同委員会の理事長はタルボットで、ケーガンが研究員として勤務するブルッキングス研究所の上司でもあった。ここでも、民主党内に隠然たる影響力を有していたタルボットの関与がうかがえる。
ケーガンはオバマと大統領選挙を闘った共和党のマケインの選挙チームにおける外交政策顧問であり、イラク戦争に積極的に賛成し、推進した中心的人物の一人であったから、客観的には当時のオバマ政権で「市民権」を得るのはヌーランドと同様に容易ではなかったはずだ。夫婦にとって、タルボットの存在は大きかっただろう。
無論、これもヒラリーが国務長官であったからこそ実現した人事だろうが、この2人がヒラリーとの接点を持ちえたことがネオコン
「リベラル介入主義」との合体をもたらし、ネオコンが新たな政治的外観をまとう結果となったように思われる。
ジャーナリストのダイアナ・ジョンストンによるヒラリーの批判本『QUEEN of CHAOS』によれば、ヒラリーはヌーランドを「恐れを知らぬ私の報道官」と呼び、声明の草稿の「作成に協力」してもらうなど、ヒラリーの「密接なメンバーの一人」となったという。
ヌーランドが報道官に就任した2011年5月は、その2ヵ月前に米英やNATO加盟諸国によるリビアのカダフィ政権打倒に向けた攻撃が始まっていた。さらに同時期には、米英やトルコ、サウジ、カタール等の湾岸諸国が「アルカイダ」を始めとするスンニ派過激派を秘密裏に軍事支援し、シリアのアサド政権転覆を狙った攻勢が本格化している。一部には「国務省の報道官としてヌーランドは『政権転覆』の策動を正当化するため、このシナリオを推進する主要人物だった」(注10)とする記述も見受けられるが、少なくとも時間的に「このシナリオ」を事前に作成する側にいなかったのは確かだ。
オバマの「支離滅裂」と右派への屈服
ただヌーランドの報道官就任は、リビアとシリアへの攻撃に象徴される国務長官ヒラリーの「リベラル介入主義」と齟齬をきたすことなく受け入れられたはずだ。政権内には当時、大統領特別補佐官のサマンサ・パワー(後に国連大使に就任)、国連大使のスーザン・ライス(後に国家安全保障問題担当大統領補佐官に就任)、さらに国務省政策企画本部長のアン・マリー・スローターの「三人組(gang of three)」を中心とした「リベラル介入主義者」がヒラリーの強硬路線を支えており、そうしたチームへのヌーランドの参入によって、「ネオコンとリベラル介入主義の連合」(注11)が誕生したと見なされている。
また前出のパリーは、この「連合」によってネオコンが延命し影響力を発揮できるのを可能にし,ヒラリーが「ネオコンや “リベラル介入主義者 “と呼ばれる、世界中で米国の帝国主義的な企みの継続を支持する多くの人々の選択肢となった」(注12)と指摘している。
別の見方をすれば、この「連合」は民主党、あるいはオバマ政権の変化があってこそ可能になった。オバマは一時期「ここ数十年のどの大統領候補よりもネオコンのイデオロギーと対極的な一連の外交政策を掲げて大統領に就任した」(注13)と見なされながらも、結局「ブッシュ・チェイニー時代の永久戦争と政権転覆」という「ネオコンの外交・国家安全保障政策を受け継いだ」(注14)と酷評されるに至る。同じ見地から、パリーもオバマに対する厳しい批判を浴びせている。
「バラク・オバマ大統領の外交政策が支離滅裂なのは、2009年の就任以来、彼自身が好んでいる好戦的ではない “現実主義 “と、ネオコンやそれに近い “リベラル介入主義 “といったワシントンの支配的な強硬イデオロギーを混ぜ合わせ、相反する戦略を追求してきたからだ」
「オバマの弱さは、彼がネオコンや”リベラル介入主義 “の仲間たちに対し、毅然とした態度をとったことがほとんどないという点にある。……(アフガニスタン戦争での増派やリビア・シリアの政権転覆策動、対ロシア強硬策等で)オバマはヒラリーや他のタカ派の圧力に屈したのだ」(注15)
そのヒラリーは、繰り返すように2013年1月の第2期オバマ政権発足直後に辞職し、後任に民主党内では必ずしも「リベラル介入主義者」とは定義されてはいないジョン・ケリーが就任するが、5月になってヌーランドはオバマによって国務次官補(欧州・ユーラシア問題担当)に指名された。その直前までヌーランドが国家安全保障会議の中東調整官になると予想されており、ワシントンではヌーランドの昇進が「ヒラリーの後援のおかげ」という観測もあったが、ヒラリーが去った後にこの人事が決定した事情を説明する情報は乏しい。
いずれにせよ、ヌーランドは国務省のロシア・東欧政策の実権を握れるポストに就いた。振り返ればこの昇進こそは、現在のウクライナ戦争に直結する出来事として記憶されるべきだろう。それまで武力衝突など予想もされていなかったウクライナの国内事情や対ロシア関係が、ヌーランドがキエフに乗り込んで工作の一端を担った2014年2月のクーデターによって激変することになったからだ。
しかもオバマは第2期以降、野に下ったヒラリーのシリアに対する「弱腰」を口実とした激しい「右」からの批判に加え、ケーガンからも標的にされていくが、それらに対し自身の堡塁を固めるよりは、むしろ迎合するような姿勢を示した。

ウクライナ戦争で、欧米から供与されたウクライナ軍の戦車や装甲車がロシア軍に破壊されたシーン。この戦争が、2013年のヌーランドの国務次官補就任と関係しているという指摘が少なくない。
ウクライナ戦争に直結したヌーランドの昇進
ケーガンは2014年の5月に発行された保守誌『The New Republic』に「超大国は引退しない(Superpowers Don’t Get to Retire)」と題した長文の記事を掲載し、話題を集めた。内容は露骨な米国例外主義に満ち、その軍事力による世界支配の歴史を高尚な用語を駆使して正当化するものだが、最大の要点は中国やイラン、シリア、ロシアを例に挙げて過剰にかつ不正確に「危機」を煽りながらの、以下のような指摘にあった。
「多くの米国人と、オバマ大統領を含む両党の政治指導者たちは、過去70年間米国の外交政策を支えてきた前提を忘れているか、あるいは否定している。特に米国の外交政策は、米国の利益と世界中の多くの人々の利益を同一視するグローバルな責任感から離れ、より狭く、より偏狭な国益の擁護へと向かっているのかもしれない」(注16)
そしてこのままだと「世界を救うために待機している民主的超大国は存在」しなくなるかのような「警告」までしているが、ケーガンがクリストルや他のネオコンの一派と共にフセイン政権(当時)のニセ情報を捏造してまで旗振り役を演じたイラク戦争一つとっても、それがイラク人はもとより「米国の利益と世界中の多くの人々の利益」と無縁であったのは多言を要しない。
本来なら一笑に付されて当然だが、議会関係者すら私的な会合の機会をあまり設けなかったオバマは、異例にもその後ケーガンを招いての昼食会をわざわざ設定した。オバマは2015年に、英独仏中ロの5ヵ国と共にイランとの間で同国の核開発を制限する包括的共同作業計画(イラン核合意)の調印にこぎつける成果を挙げるが、それ以外は多くない。そのため「2期目になって右傾化を進めており、(外交の)実務者は政治家の外交政策信条の気まぐれさに注意しなければならない」(注17)という皮肉まで寄せられている。
そのようなオバマの姿勢を象徴するものとして、ヌーランドの昇進とケーガンへの迎合があったのは疑いない。そしてヌーランドに加え副大統領(当時)のバイデンと、その国家安全保障問題担当補佐官(当時)のジェイク・サリバンを中心としたチームが計画したウクライナクーデターへの事実上の無関心と、それに伴う以降の対ロシア関係の急激な悪化に対する無策も含まれよう。
周知のように2016年の大統領選挙では、政策が「介入主義」とは異なる「孤立主義」であるかのような印象を与えたトランプに対抗し、ケーガンを先頭に大半のネオコンは初めて民主党に鞍替えしてヒラリーの応援にはせ参じた。だがヒラリーを破って大統領に就任したトランプが激化させた中国への敵対政策と、現在のバイデンのロシアへのそれを観測するならば、もはや米国の政権中枢にはネオコンと「リベラル介入主義」の差異など見出し難い「連合」が支配しているように思える。その端緒が示されたのは、ヌーランドとケーガンのオバマ政権との関係であったろう。
だがその結果、生じたのは第3次世界大戦まで移行しかねないウクライナ戦争と危機的な新冷戦構造の出現ではなかったのか。女性を中心とした反戦団体「CODE PINK」の共同創立者の一人で、優れた理論家でもあるメディア・ベンジャミンは、「ヌーランドと夫のケーガン、そしてネオコンの取り巻きたちは、米国とロシアの関係を危険な下降スパイラルに陥れることに成功した」と指摘し、ヌーランドが「オバマの2期目の外交を弱体化させた」と断じて、以下のような教訓を提示する。
「オバマ大統領が遅まきながら学んだように、間違った時に間違った場所に間違った人物がいれば、間違った方向に突き進むだけで、何年にもわたる手に負えない暴力、混乱、国際的不和を引き起こす可能性がある」(注18)
だがウクライナ戦争が勃発から近く2年目を迎えようとしながらも、依然圧倒的な主流派メディアの言説支配によって「ロシア=悪、ウクライナ=善」という二項対立の図式に呪縛されている米国の世論が、この教訓を汲んだ形跡は極度に乏しい。
(この項続く)
(注1)エイブラムスについては、本サイト2023年10月04日付「CIAの公然部隊『全米民主主義基金(NED)』と『台湾独立派』」(中)(https://isfweb.org/post-28374/)を参照。
(注2)February 14, 2023「THE COMEBACK Robert Kagan and Interventionism’s Big Reboot」
(注3)November 1, 2019「Foreign Policy Initiative」
(注4)March 14, 2014「Neocons Have Weathered the Storm」
(注5)April 22, 2008「Clinton says U.S. could ‘totally obliterate’ Iran」
(注6)January 21, 2021「Neocons and liberal hawks in Biden’s Team」
(注7)「Events in Iraq Open Door for Interventionist Revival, Historian Says」
(注8)「Is Hillary Clinton a Warmonger?」
(注9)(注7)と同。
(注10)February 11, 2021「QUEEN OF CHICKEN HAWKS: VICTORIA NULAND HAD A HAND IN EVERY US INTERVENTION IN THE PAST 30 YEARS」
(注11)(注8)と同。
(注12)February 25, 2016「Neocon Kagan Endorses Hillary Clinton」
(注13)August 26, 2009「Neoconservative Resurgence in the Age of Obama」
(注14)December 5, 2014 「Victoria Nuland and Robert Kagan: Obama’s Favorite Neo-Cons Scheme for War on Russia」
(注15)August 21, 2014「Behind Obama’s ‘Chaotic’ Foreign Policy」
(注16)(https://newrepublic.com/article/117859/superpowers-dont-get-retire)
(注17)Winter 2015「Countering the Neocon Comeback」
(注18)January 19, 2021「Who is Victoria Nuland? A really bad idea as a key player in Biden’s foreign policy team」
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 成澤宗男
成澤宗男
1953年7月生まれ。中央大学大学院法学研究科修士課程修了。政党機紙記者を経て、パリでジャーナリスト活動。帰国後、経済誌の副編集長等を歴任。著書に『統一協会の犯罪』(八月書館)、『ミッテランとロカール』(社会新報ブックレット)、『9・11の謎』(金曜日)、『オバマの危険』(同)など。共著に『見えざる日本の支配者フリーメーソン』(徳間書店)、『終わらない占領』(法律文化社)、『日本会議と神社本庁』(同)など多数。