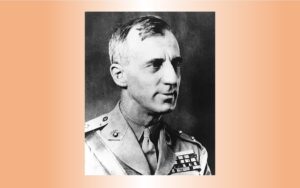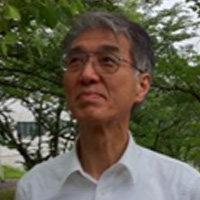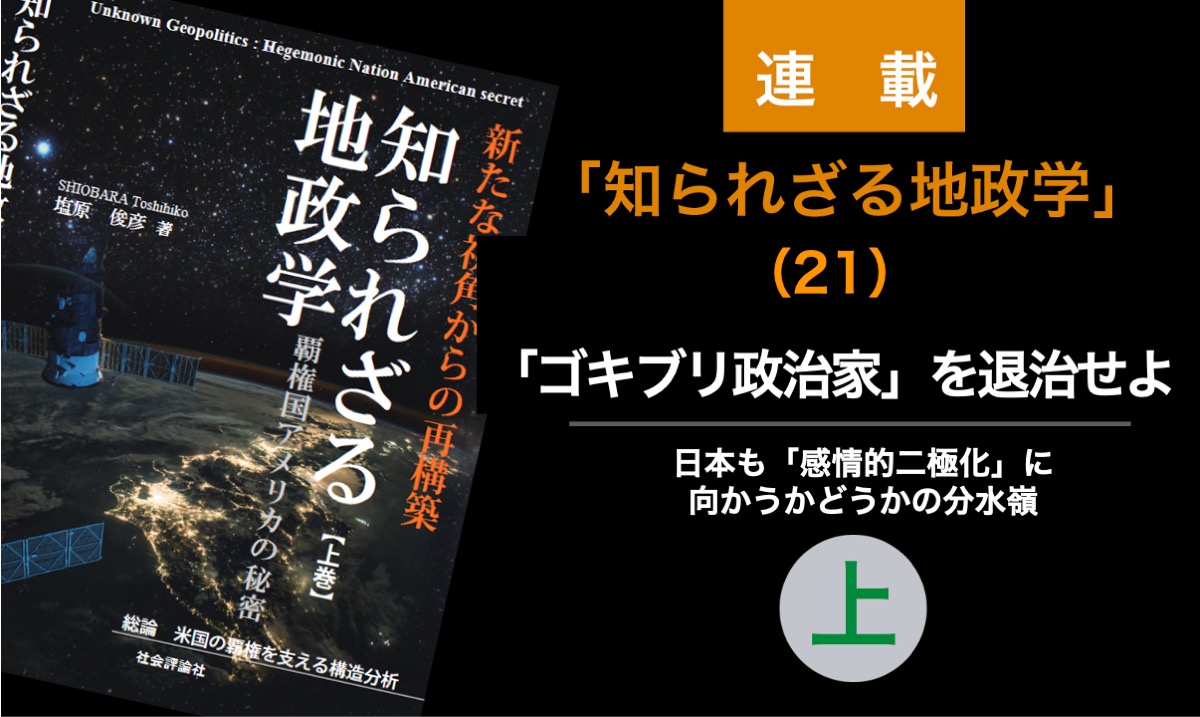
「知られざる地政学」連載(21) :「ゴキブリ政治家」を退治せよ:日本も「感情的二極化」に向かうかどうかの分水嶺(上)
映画・書籍の紹介・批評国際
地政学を研究していて興味深いのは、世界中の人々が「ゴキブリ」を嫌っているらしいことだ。今回は、そんな話からはじめて、日本におけるゴキブリ退治の話について書きたい。
「ストップ、ゴキブリ野郎!」(Stop, Cockroach!)
2020年8月9日に実施されたベラルーシの大統領選を前に、ブロガーのセルゲイ・チハノフスキーが逮捕された。彼は、「ストップ、ゴキブリ野郎!」(Stop, Cockroach!)をスローガンにしてアレクサンドル・ルカシェンコ大統領と対決しようとしたのだが、5月上旬に一度拘束され、釈放された後、同月29日に再び拘束された。その逮捕拘留期間は延長されて立候補断念に追い込まれた。この「ストップ、ゴキブリ野郎!」というスローガンはゴキブリを叩き潰すための「スリッパ」とセットになって民心をとらえた(下の写真を参照)。もちろん、ゴキブリとは、ルカシェンコ大統領を指している。だからこそ、当局の標的になったのだ。
どうやらヨーロッパでは、ゴキブリが相当嫌われものらしい。ゴキブリをめぐっては、2023年12月18日付のThe Economistにおいて興味深い記述を見つけた。
「ゴキブリは頭を切り落としても1週間は生きられる。ゴキブリの柔軟な外骨格は、体重の900倍にも曲がる。また、トイレに流すことも解決策にはならない。ゴキブリの種類によっては、30分以上も息を止めることができる。ほとんどの人にとって、ゴキブリは歓迎されない害虫である。ゴキブリは不滅の存在であるため、その存在感はさらに増している。」
2020年5月24日、ベラルーシのミンスクで、次期大統領選の候補者を支持する署名を集める人々が、スリッパでベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領の肖像が描かれたポスターを叩く。
(出所)https://www.voanews.com/a/europe_slipper-revolution-shakes-belarus/6191532.html
「ゴキブリ政治家」
日本では、辛口の評論家として知られる佐高信が2023年12月10日、「政治家にモラルを求めるのはゴキブリにモラルを求めるに等しいとテレビで言って物議を醸したことがある」と述懐している。
佐高のいう「政治家=モラル(倫理)ゼロ」でありながら、そんな「政治家=ゴキブリ」が日本中に徘徊し、しかも、その存在感は増しつづけてきたのではないか。裏金づくりに邁進していることに気づかれないまま、ゴキブリは日本の政治を動かし、誤った方向に導いてきたともいえる。ここでは、この佐高の言葉を参考に、「ゴキブリ政治家」について論じたい。「ゴキブリ政治家」の裏側には、日本人の精神性がある。
「甘えの構造」から脱却できない日本人
日本人の大多数はいまでも、土居健郎によって1971年に出版された『甘えの構造』のなかで、個人の「自由」を獲得できずにいるのではないか、これが私の率直ないまの想いである。個人の自由という、西欧的価値の意味を知らないから、自由な意志で行った行為だからこそ、その行為に責任を負わなければならないという大原則さえ軽んじられてしまっている。そうしたムードが「ゴキブリ政治家」につながっているような気がする。
個人による集団への従属を善とする社会規範がいまでも残存する日本では、自由を「わがまま」とみなす風土が存在する。こんな精神性をもつ人が圧倒的に多い日本では、政治家の不祥事に対する見方も「甘い」。あるいは、ジャニー喜多川による性加害事件に対する旧ジャニーズ事務所やその所属タレント、そのファンに対する批判も「甘い」。宝塚歌劇団内に横行するパワハラに対する批判も「甘い」。日本大学アメリカンフットボール部の大麻事件およびその廃部をめぐる議論も「甘い」。クルマの認証不正を何十年にもわたって行ってきたダイハツ工業に対する見方も「甘い」。
いずれも、集団に属する者と、それと距離を置く者との関係において、個々人が自らの行動にどう責任をとるかが曖昧で、生ぬるいのだ。そこには、「甘えの構造」がある。本当はどんな集団・組織に属していても、人はそこでの行動に責任を負っている。それは、「知らなかった」という弁解さえも許さない。
内部への依存=「甘え」
いまの情けない政治状況は、日本人の倫理性の弱さと関係がある。なぜ「甘えの構造」は個人の倫理性を弱めるのか。その答えは、「相手への依存を暗黙のうちに期待する感情が「甘え」である」という柿本佳美の指摘をヒントにすればいい(柿本佳美著「「甘え」の構造と「自由」・「権利」の両義性」を参照)。柿本がいう甘えが成立するためには、自分の回りに母親をはじめとする自分以外の人間および社会集団が存在し、「甘え」を可能とする関係が成立しているということが必要となる。
日本の場合、人間関係のなかでも親子関係が他の関係とは異なる特権的な関係にいまでもある。「赤の他人」という言葉は「血縁関係のない人」、「無関係な人」を指すが、兄弟や夫婦といった血縁関係や家族関係に関しては「他人」となる可能性があるけれども、親と子に関しては「他人」となることはない。親と子はたしかに「他者」かもしれないが、「他人」ではない。ゆえに、「親子関係だけは無条件に他人ではなく、親子関係から遠ざかるにしたがって他人の程度を増す」と土居は指摘している。
この感覚は、会社、学校、政党などの組織内部の人間と、外部の人間の関係にも波及している。ゆえに、柿本は、日本社会においては生活空間において「内と外」が区別され、それぞれ異なる行動規範を用いており、そこでは「パブリック」となるべき空間も遠慮を擁しない外部の世界に対しては内と意識されるため、個人の自由が前提される、西欧世界での本来的な「公共精神」は、存在しないと指摘している。
こうした内部への依存は、一人ひとりの自由な行動の結果に対する責任という意識を弱めてしまう。内部の規範に沿って行動していれば、個人の行動は大目にみてもらえると、多くの日本人が内心で感じているのではないか。
日本人の倫理性の弱さの原因
こうした倫理性の弱さの原因は、外的な力による強制の欠如ないし不足にあると考えられる。ジークムント・フロイトは1924年に公表した「マゾヒズムの経済的問題」の最後の段落で、「最初の本能的な放棄は、外的な力によって強制されるものであり、それこそが倫理的な感覚を生み出し、良心に表現され、本能のさらなる放棄を要求する」と書いている。これは、倫理的要求が第一義的なものとしてあり、それに従って本能的な放棄がなされるという倫理観と180度異なる見方を示している。
このわかりやすい例が、憲法第9条を強制されたあとに、それを自発的に支持した日本人だろう。日本人はこれまで、その長い歴史のなかで、外国人によるこれほど強烈な外的な力による強制を受けたことはなかった。だからこそ、戦争放棄という倫理観を多くの人々がもつようになったのである(柄谷行人著『ニュー・アソシエ―ショニスト宣言』を参照)。
このように考えると、「外的な力による強制」としての一撃に基づく「良心」の形成を実践する必要性を強く感じる。たとえば、おそらく赤ん坊の一人寝は「外的な力による強制」として、親と子の距離を教え込む一撃になりうるだろうと、私は考えている。日本の親はいまでも一人寝を敬遠する傾向がある。親自身が「外的な力」となって、子どもに一人寝を強制する必要がある。そうすれば、その強制は必ず子どもに親との距離のとり方という倫理的感覚を生み出すはずだ。
同じように、「世襲議員は認めない」とか、「企業献金は禁止」、1万円以上の支出には領収書添付が必須といった「外的な力による強制」があって、はじめて政治倫理を鍛えることにつながると考えるべきなのだ(「ゴキブリ政治家」は必ずや抜け穴を探し出すだろうが、そのときは「より厳しい外的な力による強制」を考えるしかない)。
「政治にカネがかかる」という理屈は「ゴキブリ政治家」の方便であり、そんな声に耳を傾ける必要はない。「派閥は教育機関でもある」といって派閥解消に反対する者は、派閥が裏金のつくり方を教えてきた事実をどう説明するのか。要するに、「ゴキブリ政治家」の意見に耳を傾ける必要などまったくないのだ。大切なのは、「ゴキブリ政治家」に政治倫理を教え込むには、厳しい「外的な力による強制」しかないというフロイトの理論を実行に移すことなのである。ゆえに、政治資金規正法の強化・厳罰化は当然であり、これに反対する人物はそもそも議員にしてはならない。まさに、「ストップ、ゴキブリ野郎!」なのである。派閥解消問題は枝葉末節の目くらましであり、問題の核心は「外的な力による強制」にある。その究極の強制はスリッパで叩き潰すことであり、落選させるしかない。
日本にはびこる「悪」
倫理と法は別物である。そのうえで、法に違反していなくても、倫理に反しているケースがありえることに気づかなければならない。国家が犯罪の抑止や予防という面からつくり出したメカニズムたる法制度は、倫理とは別であり、その法に違反していなくても、人間としての正しい動機に基づいて行動するという義務に違反すること自体、法律違反と同じく「悪」である。「悪」をなした以上、その責任は問われるできであり、叱責されて当然なのである。
ここでの関心は、倫理にある(因みに、私には『ビジネス・エシックス』[講談社現代新書]という著作がある)。倫理は正しい動機から行動するという内的義務にかかわっている。この内的義務を育む際に、倫理性の弱い日本人は、個人の自由な意志に基づく行為に伴う責任の重さを軽視しがちとなる。親や内部の仲間への依存が一人ひとりの個人の自由の大切さを知らないか、気づかないのである。逆にいえば、家庭に育っても、学校に通っても、あるいは、企業に就職しても、自分が「不自由」であることに気づかないまま、集団や組織のなかで同調しているだけですんでしまう。自分の「不自由さ」に気づかないから、「自由」の大切さにも気づかない。こうして、自由な意志決定に基づく行為に対する責任という感覚もどんどん鈍ってしまう。その結果、集団や組織としての不正がさまざまなところに広がる。そう、ゴキブリが至るところに蔓延するように、「悪」がはびこるようになるのだ。
この「悪」を減らす努力をしなければ、この「悪」を餌として、ゴキブリはどんどん増えてしまう。パンくずのような「悪」であっても、ゴキブリはりっぱに成長してしまう。
「知られざる地政学」連載(21)「ゴキブリ政治家」を退治せよ:日本も「感情的二極化」に向かうかどうかの分水嶺(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催公開シンポジウム:鳩山政権の誕生と崩壊 ~政権交代で何を目指したのか~
●ISF主催トーク茶話会:斎藤貴男さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)