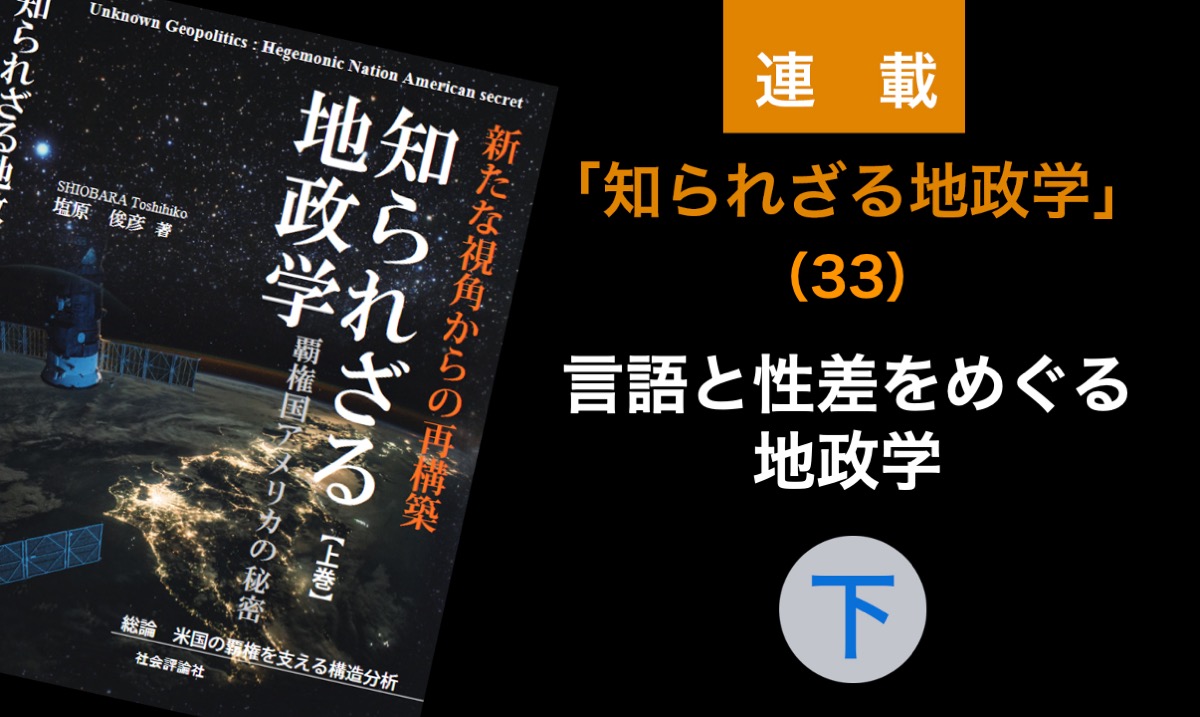
「知られざる地政学」連載(33)言語と性差をめぐる地政学(下)
国際
「知られざる地政学」連載(33)言語と性差をめぐる地政学(上)はこちら
「政治言語学」
ここで、「政治言語学」という見方があることを紹介したい。紹介したような社会による言葉の変化は、政治による言葉の変化とも密接にかかわっている。たとえば、ロンドン・メトロポリタン大学の社会学者スヴェトラーナ・スチーブンソンは、「ここ何年もの間、ロシア指導部やクレムリンの宣伝担当者たちは、犯罪用語を盛んに使ってきた」と指摘している。権力者がどのような言葉遣いをするかによって、政治情勢を垣間見ることにつながる。
最近の日本でいえば、またしても「秘書の責任」が繰り返され、政治家本人は「知らなかった」ですませようとしている。この言葉を見る限り、日本の政治風土はこの数十年、まったく変わっていないことがわかる。
ロシアの場合、ソ連時代から、多くのロシア人は刑務所での生活やスラングに奇妙な魅力を感じてきたし、いまになっても、その傾向は変わっていない。もっとも有名なのは、おそらく「ブラトノイ」という犯罪にかかわる言葉だろう。拙著『ロシア革命100年の教訓』において、つぎのように説明しておいた。
「ロシア語では無頼の徒を「ブラトノイ」ないし「ヴォール」と呼ぶ。後者は「法にのっとった盗賊」のようなかたちで使われ、「盗賊」の意に近い。前者は、内村によれば、「ブラート(コネ)の人」、「結びあった人」、「血盟の人」を意味する。「ブラート」はユダヤ人の言葉、イディシが起こりで、一九世紀から、いまのウクライナのオデッサで用いられはじめた。その後、ロシア語化し、犯罪者たちの頭目がロシア全土にわたる組織をつくったのだという。ブラトノイ同士の連帯は固く、ブラトノイを文字通り命をかけて守る。ブラトノイ集団は集団側が新メンバーを採用することによって増員してゆく。だが、希望者側の申し出を検討することはしない。既存のブラトノイが入会を提案するのだ。ブラトノイは「法」なるものを軽蔑し、自分たちだけの不文律が彼らにとっての「法」となる。
内村は、ソヴィエト政権はよく組織だった連帯の堅固なブラトノイの世界に対して、「一九一七年以来不断の戦いを挑(いど)んで今日に至っている」と記している。しかし、それはソヴィエト政権とブラトノイの世界の異質性を意味しない。むしろ、両者は驚くほど近似している。「無頼は彼ら固有の人間の尊厳を守るためにこそ掟があると信じているが、その掟を制定する原理を見ると、まず目につくのは全体主義である」という内村の指摘は興味深い。全員一致を原則として例外を認めない全体主義を特徴としており、「無頼全体主義社会へいったん入った者は、全体が一致しない限りそこを出られないといったことになる」のだ。だからこそ、ソヴィエト連邦はロシア無頼に通じるものがある。そこに通底するのは、無産の原則である。「無頼も共産主義者も無産の原則においては似た者同士である」のだ。さらに全員一致の原則も共通している。「民主集中制」と称して、事実上、全員一致の「民主主義」がソ連でまかり通っていたことはあまりにも有名だ。」
なお、ここでいう内村は、内村剛介のことであり、『ロシア無頼』(高木書房、1980年)を参考にしている(ロシアの本質を理解したい人はこの本を読まなければならないと、私は思っている)。
「便所の小便」
1999年9月24日、当時、首相だったプーチンは記者会見で、前日の第二次チェチェン紛争、すなわちロシア軍機によるグロズヌイ空爆についてコメントした際、「我々はテロリストをあらゆる場所で追跡する。空港で、空港で。ですから、失礼ですが、トイレで捕まえますよ、やはりトイレにも浸けます」と発言した。この「(小便を)便所でする」という言葉は、「ブラトノイ」の間で、「密告者を殺して便所で溺れさせる」という意味をもっていた。スターリン時代の収容所には、1万人を超す者が集められたところもあり、通常、巨大な便所が掃き溜めのある丘の上に建っていた。この便所に密告者を殺して放り込むと、春になるまで汲み取らないから、死体は見つからないのである。
こんな言葉がプーチンおよびその周辺から漏れ聞こえるようになったことで、社会の荒廃がまさにプーチンを中心に深化していることが暗示されるようになっている。前述のスチーブンソンは、「一貫して法と社会制度を破壊し、普遍的な道徳規範を仰々しく軽蔑し、社会基盤を破壊してきたプーチンの権力トップは、それ自体が準暴力団と化している」と的確に指摘している。
気になるバイデンの言葉遣い
プーチンはいわば、「無頼」の親玉として、まさに刑務所で用いられているような言葉をクレムリン内で話しているのかもしれない。ロシア全体がプーチンの言葉遣いによってすさんでいることがわかる。
だが、他方で、アメリカのホワイトハウスの主、ジョー・バイデン大統領の言葉遣いもひどい点も指摘しておきたい。
バイデン大統領は、2024年3月15日、「アイルランドの友」という年次昼食会でスピーチしながら、プーチンのことを「thug」と呼んだ。「悪党」、「チンピラ」といった意味をもつ俗語を使い、万雷の拍手を受けたのだ。この様子はYouTubeで見ることができる。
同年2月21日には、カリフォルニア州での夜の資金集めの席で、ロシアのプーチン大統領を「クレイジーなS.O.B.」と呼んだ。S.O.B.とは、 “son of a bitch”の略であり、「馬鹿で苛立たしくあほらしい人々に対して向けられる侮辱的言葉」とされている。米国では、NYT、CNN、NBCなどで、この発言が紹介された。大統領の発言として、いかに品格に欠けるものであったがわかる。これが、バイデン大統領の本性であり、プーチン大統領とその品性においてどこが違うのだろうと思わせる。
こんな現実から強く感じるのは、政治指導者の下劣さである。こんな最低の人物がアメリカやロシアを率いているのかと慨嘆せざるをえない。しかも、そんな大統領の言葉遣いを周辺の政治家は軽蔑するどころか、楽しんでいる。政治家そのものが劣化しているのだ。
プーチン大統領も、バイデン大統領も、その言葉遣いの下劣さによって、それぞれの国の国民に影響をおよぼしている。じわじわと、無意識の世界にも働きかけているに違いない。もちろん、この傾向に火をつけたのは、品性下劣な極みともいえるドナルド・トランプ前大統領であったことを忘れてはならない。
日本もまた品性も倫理観もない政治家ばかりが目立つ。こうした現実について、目をつむってはならない。おそらく、ときとして、言語と性差のような観点から、地政学を洗い直してみると、新しい発見があるのではないかと思う。読者も言葉遣いに敏感になってほしい。それは、ときに厳しい言葉をつかいたくなる筆者にとっても同じだ。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
☆ISF公開シンポジウム:小沢事件とは何であったのか ~司法とメディアの共犯関係を問う~
☆ISF主催トーク茶話会:孫崎享さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:吉田敏浩さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)




























































































































































































