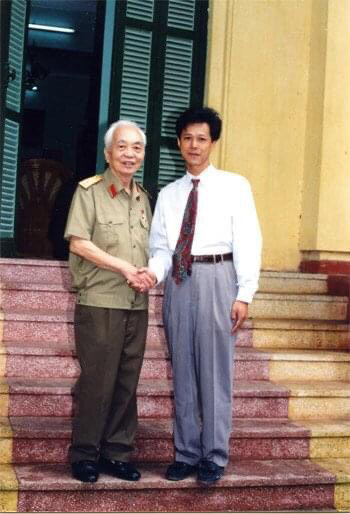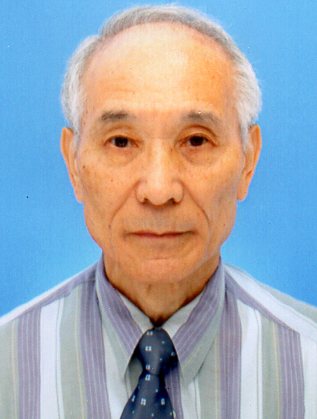秋嶋亮(社会学作家)連載ブログ/8:統一教会の殷賑は変わっていない
社会・経済審議中止を求める24万もの署名が寄せられながら、共同親権の改正案が強行採決されたのだ。
政府は「離婚の増加などで家族関係が多様化する中、子どもの利益を確保するのが狙い」と説明している。しかしDVや精神的虐待などの問題が生じることは明らかであり、また両親の合算所得により諸々の優遇措置が撤廃され、子どもの権利の確保どころか、子どもの人権を侵害する事態となるだろう。
しかしこの真の目的については全く報じられていない。つまりコメンタリー(法律の逐条解説)が皆無なのだが、実はこの法案は、こども家庭庁設置法と同じく、統一教会の主導によって成立したのだ。
要するに共同親権は、統一教会の中心思想である家父長制と、父権の復権を実現するための手段であり、教会から離れた次世代(いわゆる宗教二世)を回収し連れ戻すための法案であり、戸籍の一本化により信徒の財産の散逸を防ぎ、教会の管理下に置くための措置なのである。
ここで注意すべきことは、最大野党である立民がここでまたも自公政権に協力したことだ。
この法案の成立で中心的役割を果たした「共同養育支援議員連盟」の役員名簿には、立民の代表である泉健太と、同最高顧問である野田佳彦が自民党の議員らと共に名を連ねている。つまりこれは統一教会の采配の下で政権与党と最大野党が統合されていることを物語っているのだ。
立民はこのところ日米統合司令部の設置、セキュリティ・クリアランスなどの軍国化法案に立て続けに賛成しているが、日本・イギリス・イタリアの三国が次期戦闘機を共同開発するための政府間機関「GIGO(ジャイゴ)」の設立でも与党に全面協力しているのだ。
このような立民の軍国化路線へのシフトが金目であることはもちろんだが(統一教会から献金を拝受していることはもちろんだが)、彼らの支持母体である連合は三菱重工を始めとする軍需産業の労組から成り、その票田や献金を目当てに自公の軍国化路線に追従するという事情があることも付記しておく(立民が原発行政を批判しないのも支持母体の労連に電力会社の労組が多く加盟しているためなのだ)。
この続きは会員制ブログで購読できます。
http://alisonn.blog106.fc2.com/blog-entry-1398.html
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う
☆ISF主催トーク茶話会:エマニュエル・パストリッチさんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:
☆ISF主催トーク茶話会:
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
☆秋嶋亮(あきしまりょう:響堂雪乃より改名) 全国紙系媒体の編集長を退任し社会学作家に転向。ブログ・マガジン「独りファシズム Ver.0.3」http://alisonn.blog106.fc2.com/ を主宰し、グローバリゼーションをテーマに精力的な情報発信を続けている。主著として『独りファシズム―つまり生命は資本に翻弄され続けるのか?―』(ヒカルランド)、『略奪者のロジック―支配を構造化する210の言葉たち―』(三五館)、『終末社会学用語辞典』(共著、白馬社)、『植民地化する日本、帝国化する世界』(共著、ヒカルランド)、『ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ―15歳から始める生き残るための社会学』(白馬社)、『放射能が降る都市で叛逆もせず眠り続けるのか』(共著、白馬社)、『北朝鮮のミサイルはなぜ日本に落ちないのか―国民は両建構造(ヤラセ)に騙されている―』(白馬社)『続・ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ―16歳から始める思考者になるための社会学』(白馬社)、『略奪者のロジック 超集編―ディストピア化する日本を究明する201の言葉たち―』(白馬社)、『ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへOUTBREAK―17歳から始める反抗者になるための社会学』(白馬社)、『無思考国家―だからニホンは滅び行く国になった―』(白馬社)、などがある。