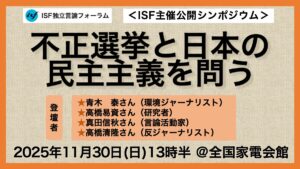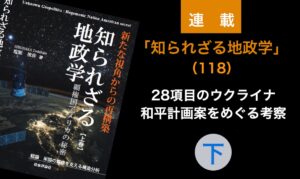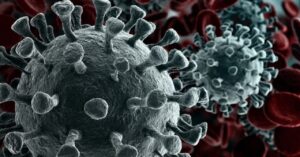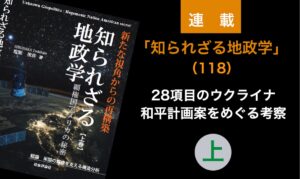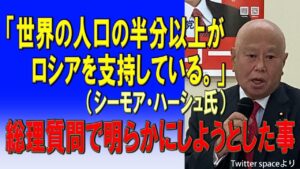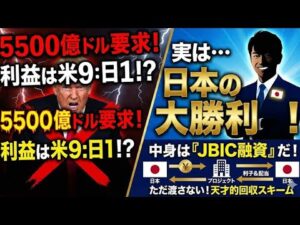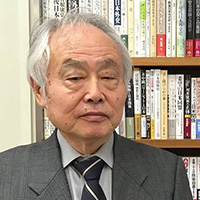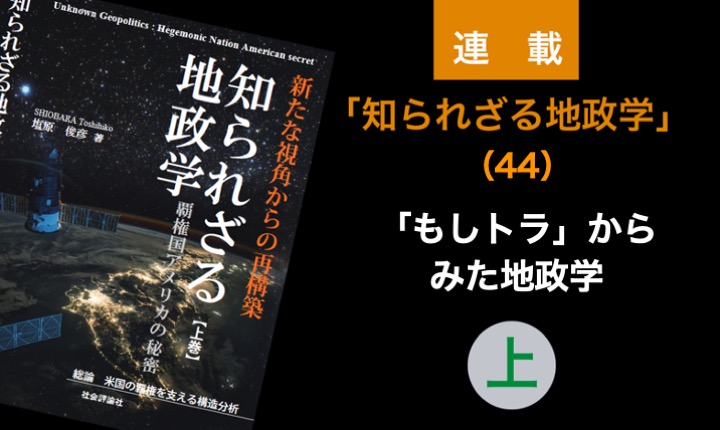
「知られざる地政学」連載(44)「もしトラ」からみた地政学(上)
国際
「もしドナルド・トランプが大統領選に勝利し、次期大統領になったら」(「もしトラ」)、世界はどう変化を迫られるのだろうか。陰りはみえるとはいえ、ヘゲモニー国家アメリカの最高責任者になる以上、その政策は世界全体の今後に大きな影響をおよぼすことになるだろう。そこで、今回は「もしトラ」がおよぼす地政学上の変化について考察してみたい。
「もしトラ」による政策変更
NYTによる分析では、2024年6月16日時点で、「もしトラ」の実現に伴って、主に六つの種類の政策変更が想定されている。
1.移民政策
①大量の強制送還の実施:トランプ氏の移民問題最高顧問であるスティーブン・ミラーは、第2期トランプ政権は強制送還の量を10倍(年間100万人以上)に増やすことを求めるだろうとしている。
②移民捜査局(ICE)捜査官の増加:さらに、連邦捜査官と州兵を入国管理局に配置転換し、移民逮捕に連邦軍を使えるようにする。
③移民を拘留するための「広大な収容施設」を建設するために軍資金を使用する。
④中米諸国との「安全な第三国」協定を復活させ、アフリカなどにも拡大する(その目的は、亡命を求める人々を他国に送ることである)。
⑤バイデン大統領が2021年に撤回した渡航禁止令を復活させ、国の難民プログラムを一時停止し、主にイスラム圏からの入国を再び禁止する。
⑥非正規滞在の両親から生まれた子どもに市民権を与える権利(「生まれながらの市民権」)はないと宣言し、社会保障カードやパスポートなどの書類の発行を停止する。
なお、ジョー・バイデン大統領は2024年6月18日、2012年の厳しい再選争いを控えた夏、ラテン系有権者からの支持を失いつつあったバラク・オバマ大統領が数十万人の若い不法移民を強制送還から免れるという大統領令に署名したように、アメリカ市民の配偶者である不法滞在者の法的保護を拡大する大統領令を発表した。米国に10年以上住んでいる約50万人に影響する。
2.敵対勢力への復讐
①バイデンとその家族に対する犯罪捜査を指揮:再選されれば、バイデンとその家族を「追及する」特別検察官を任命すると、トランプは公言している。
②政治的に挑戦した敵を起訴させる:トランプは自身の起訴という前例を引き合いに出し、もし自分が再び大統領になった時、だれかが政治的に挑戦してきたら、「降りて行って起訴してこい」と言うことができると宣言している。
③トランプの側近、カシュ・パテルは、トランプが政権に返り咲いた場合、ジャーナリストを訴追対象にすると脅している。その後、選挙キャンペーンでは、この発言をトーンダウン。
3.大統領権限拡大に伴う国内政策
①独立機関を大統領の管理下に:議会は、ホワイトハウスから独立して運営されるさまざまな規制機関を設置している。トランプは、それらを大統領の管理下に置くと宣言しており、法廷闘争に発展する可能性がある。
②資金を「押収」する慣行を復活させる:トランプは、気に入らないプログラムのために議会が計上した予算の支出を拒否する権限を大統領がもつ制度に戻すと宣言している。
③何万人もの長年の公務員から雇用保護を剥奪:トランプは大統領在任中、キャリア官僚を解雇し、忠実な職員に置き換えることを容易にする大統領令を出した。バイデンはこれを取り消したが、トランプは2期目には再発行するとのべている。
④情報機関、法執行機関、国務省、国防総省の職員を粛清(パージ)する:トランプは、国家安全保障や外交政策に関わる機関のキャリアを、彼が破壊しようとする邪悪な「ディープ・ステート」(深層国家)として蔑視してきた。
⑤トランプのアジェンダを合法とする弁護士を任命:第一次トランプ政権では、政治的に任命された弁護士がホワイトハウスの提案に異論を唱えることもあった。トランプにもっとも近いアドバイザーの何人かは現在、大統領権限の範囲について積極的な法理論を受け入れる可能性が高いとみられる弁護士を吟味している。
4.変更する経済政策
①ほとんどの輸入品に新たな税金を課す「ユニバーサル・ベースライン・タリフ」を導入:新たな輸入税として10%という数字を浮上している。同政策は、消費者物価を上昇させるだけでなく、報復関税で米輸出企業が打撃を受け、世界的な貿易戦争を引き起こす危険性がある。
②中国に対する新たな貿易制限を強化:電子機器やその他の必需品の「すべての中国からの輸入を段階的に排除」し、米国企業の中国への投資を阻止する新たなルールを課すと、トランプはのべている。
③企業利益に課される規則を削減:規制緩和のアジェンダを復活させ、いわゆる「行政国家」(空気や水をきれいに保ち、食品、医薬品、自動車、消費者製品の安全性を確保することを目的とした制限など、企業のために規則を発行する機関だが、企業の利益を削る可能性がある)の抑制をさらに進めると宣言している。
④減税の延長と拡大:トランプは、2017年税制改正で期限切れとなる減税措置(個人所得や多額の遺産を含む)を延長するとのべている。また、法人税率をさらに引き下げたいと、ビジネスリーダーに内々に語っている。
5.欧州との軍事的関与からの撤退
①NATOを弱体化させるか、NATOから米国を脱退させる可能性がある:選挙キャンペーンサイトでは、NATOの目的を根本的に見直すつもりだとのべており、同盟を縮小または終了させるのではないかという不安を煽っている。
②ロシア・ウクライナ戦争を「24時間以内に」終結させる:トランプはウクライナの戦争を1日で終わらせると主張している。その方法については明言していないが、ウクライナのロシア占領地域をロシア側に割譲するといった内容が示唆されている。
6.対メキシコ政策
①メキシコの麻薬カルテルに宣戦布告:メキシコの麻薬カルテルと軍事力で戦う計画を発表した。米国がメキシコの同意なしにメキシコ国内で武力を行使すれば、国際法に違反する。
②国境で連邦軍を使う:国内の法執行に軍を使うことは一般的に違法だが、暴動法は例外を定めている。トランプ・チームは、移民捜査官として兵士を使うために、この法律を行使するだろう。
③民主党が支配する都市で連邦軍を使う:トランプは2020年、暴動に発展することもある人種差別撤廃デモに現役の軍隊を投入する寸前まで行った。次回は、民主党が支配する都市に秩序をもたらすために、一方的に連邦軍を派遣するとのべている。
復讐に燃えるトランプを慮る
移民政策については、「「知られざる地政学」連載【37】移民をめぐる地政学(上、下)」で論じたことがある。ここでは、「敵対勢力への復讐」について、ややトランプに同情する見解をのべておきたい。
「「知られざる地政学」連載【43】情報統制の怖さ」(上、下)で書いたように、民主党支持者の多かった連邦捜査局(FBI)が2020年11月の大統領選で、トランプに有利な情報(ジョー・バイデンの次男ハンターの見つかったノートパソコン情報)を露骨に握り潰したのは事実であり、こうした妨害工作がなければトランプが再選されていた可能性が高かった。FBIによる政治的圧力は、トランプ再選を阻んだ最大級の原因であり、トランプがこうした機関に恨みをいだくのは、少なとも理解できる(復讐まで行うかは別問題だが)。
あるいは、反トランプの立場を鮮明にするNYTやWPなど、民主党に傾いた報道している主要マスメディアを引用するだけの日本の主要メディアは、トランプが被った「屈辱」を報道しない。その結果、おそらく日本人の大多数は、トランプの「敵」への恨みを理解できないだろう。
たとえば、拙著『ウクライナ3.0』で詳述したように、モスクワのホテル「リッツカールトン」での騒動という「でっち上げ」が報道されるといったトランプ潰しが平然と行われてきた。なお、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』において、「復讐」について哲学的に考察したから、そちらも参考にしてほしい。
「もしトラ」に伴う経済政策などについては、機会を改めて、「関税の地政学」や「貿易をめぐる地政学」といったかたちで、今後、このサイトの議論の対象としたい。
ウクライナ和平をめぐって
2024年6月25日付のロイター電は、「モスクワとの和平交渉がなければ、キーウへの米軍支援を停止する計画を手渡されたトランプ」という特ダネを公開した。それによると、2017年から2021年のトランプ大統領在任中、マイク・ペンス副大統領の国家安全保障顧問やアメリカ合衆国国家安全保障会議の事務局長兼首席補佐官を務めたキース・ケロッグ退役陸軍中将と、トランプ大統領副補佐官兼同会議首席補佐官を務めたフレッド・フライツがウクライナにおけるロシアとの戦争を終わらせるための計画をトランプに提示したと報じたのである。
「もしトラ」となったら、まず、米政府はウクライナとロシアの政府に公式に接触する。戦争当事国である2国を交渉のテーブルにつけるためである。ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領に対しては、「交渉のテーブルにつかなければならない、そうしなければ米国の支援は打ち切られる」と言い、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領には、「交渉のテーブルにつかないなら、ウクライナ人が戦場であなたを殺すのに必要なものはすべて与える」と言う――これが基本姿勢だ。
ウクライナが対話と停戦に応じれば、「追加の安全保障」も約束される。フライツによれば、提示された和平案の重要な要素は、「ウクライナを徹底的に武装させる」ことだという。
他方で、ロシアはウクライナをNATOに加盟させる計画を「長期間」放棄することを約束される。これは、プーチンを和平交渉に参加させるための最低限の条件となるだろう。「もしトラ」でトランプ大統領になれば、他のNATO首脳も、安全保障を伴う包括的かつ検証可能な和平協定と引き換えに、ウクライナのNATO加盟を長期間見送ることを提案すべきだと、二人は指摘している。
議会も共和党が勝利へ
トランプが勝利すれば、共和党は上院を掌握し、おそらく下院でも過半数を拡大するだろう。議会共和党はすでに、そうなった場合の可能性を検討している。
もっとも問題となるのは、「トランプ税制」の継続だ。個人と遺産に対する税率引き下げは、企業に対するいくつかの変更とともに、2025年末までに失効する。そうなると、アメリカの約60%の世帯が、毎年より多額の小切手を税務署に送ることになる(The Economistを参照)。租税合同委員会によると、この法律を延長するだけで、今後10年間で約4兆ドルの財政赤字が増加するという。「2023年にはGDPの6%を超えるアメリカの巨額の財政赤字を拡大させることなく、成長を促す政治的に実行可能な法案を提出することが、一見不可能にみえる課題である」と、The Economistは書いている。
大統領の4000人の政治任用者のうち約1200人は上院の承認が必要である。上院の過半数を共和党が占めれば、ここでも、トランプの推薦する候補者の承認が容易になる。ただ、「共和党上院の多数派は、官僚機構での一時的な仕事よりも、連邦司法の終身任命を承認することを優先するだろう」とみられ、民主党の反対などで承認が遅れれば、連邦司法関連人事が先になる見通しだ。
バイデン外交のひどさと知られざるトランプ外交
「知られざる地政学」連載【43】情報統制の怖さ」において指摘したように、日本のマスメディアは親バイデン政権の立場から報じているNYTやWPなどのアメリカの主要マスメディアの報道を日本に伝えているにすぎない。その結果、多くの日本人は大多数のアメリカ人とともに、つぎのような質問に答えを見つけるのに窮するだろう。
「アフガニスタンやイラクで勝利を約束した政治家の多くが、なぜ責任を問われなかったのか。」
「ウクライナの全領土の奪還という達成不可能と思われる目標を掲げたウクライナに、アメリカはいつまで数百億ドルを費やすのだろうか。」
バイデン政権のやってきた外交戦略はどうにもわかりにくいのだ。前者の問いかけは、「エスタブリッシュメント」と呼ばれる既存の支配層への強烈な不信を呼び覚ます。後者は、国内の軍産複合体への利益供与であり、金持ち優遇にすぎない。
加えて、ガザ戦争の勃発によって、アメリカがパレスチナの子どもたちの命を、イスラエル人やウクライナ人の命と同じくらい大切にしていないことがだれの目にも明白になった。だからこそ、「グローバル・サウス」と呼ばれる国々に住む人々は、バイデン外交の「ダブルスタンダード」(二重基準)に騙されまいとしている。
これに対して、トランプ外交はどうであったのか。トランプ政権下の2019年から2021年まで国家安全保障アドバイザーを務めたロバート・オブライエンは、論文「力による平和の復活:トランプの外交政策を論証する」(『フォーリン・アフェアーズ』2024年7/8月号)のなかで、つぎのように記している。
「トランプ大統領は、新たな戦争や終わりのない対反乱作戦を避ける決意を固め、ジミー・カーター大統領以来、アメリカが新たな戦争に参戦せず、既存の紛争を拡大させなかった大統領となった。トランプはまた、イスラム国(ISIS)を組織的な軍事力として一掃し、その指導者アブ・バクル・アル=バグダディを排除するという、アメリカとしては珍しい勝利で戦争を終結させた。」
もっとも大きな成果は、政権最後の16カ月間で、アメリカによるアブラハム合意(イスラエルとの国境正常化)の促進で、イスラエルと中東の隣国3カ国とスーダンに和平がもたらされ、セルビアとコソボはアメリカの仲介で経済正常化に合意し、アメリカはエジプトと湾岸主要国にカタールとの軋轢を解決し、同首長国への封鎖をやめるよう働きかけることに成功したことである。
こうした第一期トランプ政権の外交実績を知っていれば、「もしトラ」による大混乱の喧伝で、トランプの勝利を再び「盗もうとする」勢力がいかに恥知らずであるかがわかるだろう。
「知られざる地政学」連載(44)「もしトラ」からみた地政学(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う
☆ISF主催トーク茶話会:エマニュエル・パストリッチさんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:安部芳裕さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:浜田和幸さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)