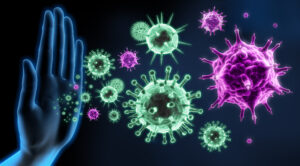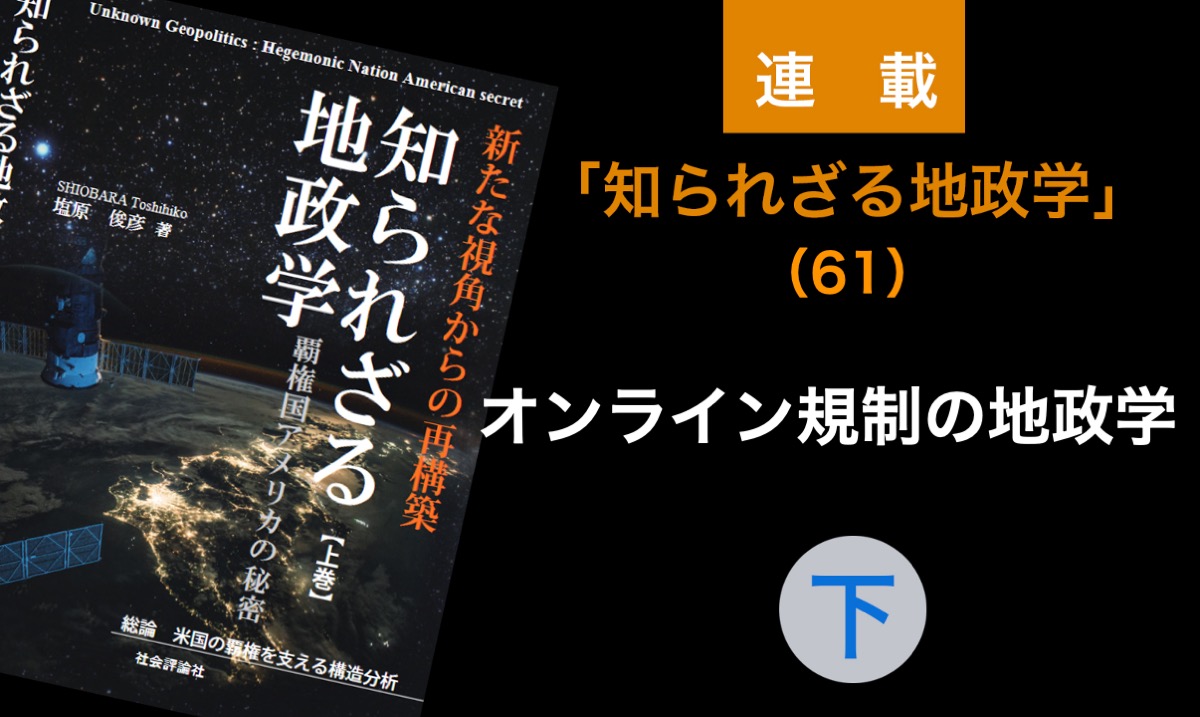
「知られざる地政学」連載(61):オンライン規制の地政学(下)
国際「知られざる地政学」連載(61):オンライン規制の地政学(上)はこちら
広告会社との結託
②のプレーヤーと戦術の進化については、「近年、ディスインフォメーション・キャンペーンに関わる人々、彼らの動機、そして彼らが用いるテクノロジーは進化している」として、注意を促している。「関与を否定できるような形跡を残さないために、政治指導者たちは、ソーシャルメディアのインフルエンサーや、高額な契約や政治的なコネクションから利益を得ている怪しげな広報会社に、コンテンツ操作を外注することが多くなっている」という指摘は、日本にもあてはまる。
連載(53)「権力への再挑戦は、同じことの繰り返しになりかねない!?」(下)において、つぎのように書いておいたことを思い出してほしい。
「2022年1月16日、「長周新聞」は、「ブルージャパンへの9億円」という記事を配信した。「自民党から資金提供を受けて世論煽動に勤しんでいたDappiの騒動に続いて、今度は野党の立憲民主党もブルージャパンなる広告会社に4年間で9億円もの資金を提供していたことが明るみになっている」という出だしではじまっている。「自由で民主的な日本を守るための、学生による緊急アクション」として誕生した、学生運動SEALDs(シールズ:Students Emergency Action for Liberal Democracy – s)の元メンバーを養うために、立民がブルージャパンにカネを流し、彼らを養っていたのではないかという疑いについて書かれている。」
さらに、報告書は、「コンテンツ操作に参加するインフルエンサーは、フォロワーとの間に築いた信頼と忠誠心を利用して、虚偽、誤解を招く、あるいは分断的なメッセージを拡散する」とも指摘している。たとえば、台湾では2024年1月の選挙を前に、ファッションやメイクのインフルエンサーが、投票の不正操作に関する虚偽の主張を投稿した。この主張は、台湾での投票を思いとどまらせることを目的とした、中国発の影響力行使キャンペーンを反映したものだった。
生成AI対策
テクノロジーの進化に関連して、生成AI対策が重要な課題となっている。Freedom on the Net 2023 では、政治や社会に関する話題の歪曲手段として、生成AI が早期に採用されたことが報告されている。たとえば、2024年7月のルワンダ大統領選挙を前に、現職の大統領ポール・カガメ氏を支援するアカウントのネットワークが、AIで生成されたメッセージや画像を拡散した。
ただし、Freedom on the Net 2024は、「市民社会、学術界、メディアによる調査から得られた証拠によると、生成AIが支援するディスインフォメーション・キャンペーンは、選挙結果にほとんど影響を与えていないことが示唆されている」、とのべている。OpenAIは2024年5月、中国、イラン、イスラエル、ロシアに関連する行為者が、より従来型の影響工作の一環としてChatGPTを使用しようとした試みを阻止したと報告しているという。
生成AIについては、まだその実態が発展途上にあるため、解明できていない。今後、この連載で詳しく解説する予定であるとだけ書いておきたい。
ファクトチェック問題
もう一つ、報告書がファクトチェックについて論じているので、この問題を紹介したい。報告書は、信頼できる情報を増やすことに専念する独立した研究者やファクトチェック担当者の活動に対して、「いくつかの国の政府関係者が、デマキャンペーンやオンライン上の嫌がらせ、その他の政治的干渉といった形で直接攻撃を仕掛けた」とのべている。その結果、一部の取り組みは活動を縮小または停止せざるをえなくなり、有権者は虚偽情報の拡散工作について何も知らされず、選挙操作に対する社会の回復力は損なわれたという。他方で、「政府は、信頼性の高いファクトチェックの手法を政治的利益に活用しようと、独立したファクトチェック機関に代わるより協力的な代替手段を確立した」とも指摘している。さらに、「もっとも抑圧的な環境下では、政府は長年にわたりファクトチェックの正当性を否定したり、取り込もうとしてきた」とも記している。
具体例として、2023年12月のエジプト大統領選挙の当日、同国のメディア当局はファクトチェックプラットフォーム「Saheeh Masr」の調査を開始した。このサイトは、国営複合企業ユナイテッド・メディア・サービスが、投票率の低さや特定の候補者を選ぶよう圧力をかけられている有権者の様子などを伝える選挙報道を抑制するよう、関連報道機関に命じたと報じていた。
インドでは、総選挙で投票が始まる数週間前、中央政府は、公式業務に関する誤った報道とされるものを「訂正」するファクトチェック部門の設立を目指していた。インドのジャーナリストや市民団体は、このプロジェクトが悪用される可能性が高いと批判し、同国の最高裁判所は一時的にこの部署の設立を中止した。他方で、2023年12月10日付のWPは、2020年以降、インド政府の情報機関職員によって設立・運営されるDisinfo Labと名乗る不透明な組織がモディ政権を批判する外国勢力を調査し、その信用を失墜させることを目的として活動していると報じた。
韓国では、ユン・ソンニョル大統領(尹錫悦)と彼が率いる国民の力党は、2024年4月の立法選挙を前に、政府を批判的に報道した独立系メディアを当局が家宅捜索し、ブラックリストに載せた。国民の力党の議員たちは、韓国の主要なファクトチェックプラットフォームである非営利団体SNUFactCheckを偏向的であると中傷するキャンペーンを開始した。この告発により、ソウル国立大学と多数の有力メディアとの提携により運営されていたSNUFactCheckの主要スポンサーが資金提供を取りやめたと伝えられている。
アメリカでは、2020年の選挙期間中に虚偽の選挙関連情報の分析を行い、時にはソーシャルメディア企業に通知していた「選挙の透明性向上を目指す連合」(EIP)への圧力が高まった。報告書によれば、「EIPの活動に関する誤った主張、たとえば政府の検閲を煽っているという主張などにより、訴訟の波が起こり、米国下院司法委員会の共和党議員から召喚状が出され、EIPの参加者に対するオンラインでの嫌がらせが行われた」。この結果、この問題に関する米国の専門家コミュニティ全体に萎縮効果が生まれ、専門家や機関は、同様の敵意や高額な弁護士費用を避けるために、活動規模を縮小し、自らの業務に関する公開討論を制限するようになっている。
加えて、企業もまた、自社のプラットフォーム上での活動に関するデータへのアクセスを制限し、ファクトチェック担当者や独立系研究者が情報空間を調査する能力を妨げた。2024年8月、メタはフェイスブックとインスタグラム全体にわたるコンテンツのリアルタイム分析を可能にする重要なツール、CrowdTangleを閉鎖し、はるかに限定的な代替ツールに置き換えた。2023年9月、Xは自社サイト上でのデータを自動的にかき集める(スクレイピング)をほぼ全面的に禁止し、研究者の主なデータソースを断ち切った。研究者がプラットフォームデータにアクセスできることで、嫌がらせやデマキャンペーンを明らかにし、その背後にいる行為者を暴き、ソーシャルメディア上の重要なトレンドを指摘することができるにもかかわらず、この情報へのアクセスを制限することで、インターネットの自由を強化するための効果的な政策や技術的介入を設計することをより困難にしたのである。
報告書が紹介している事例は、まだあまりスポットを浴びていない「ファクトチェック」の仕組みが今後、さまざまなかたちで問題化する可能性を教えている。たとえば、連載(35)「「自衛隊機が民間機をミサイルで撃墜した」はディスインフォメーションか」(上、下)で紹介した「日本ファクトチェックセンター」(JFC)は、総務省やIT企業との不可思議な関連が疑われる組織であると書いておきたい。ファクトチェック機関は「腐敗」の温床となりうる組織であり、本当は厳しい監視が必要なのだと強調しておきたい。
参考になるEUの事例
報告書は、日本にも参考になるEUの事例を紹介している。
2024年6月の欧州議会選挙を前に、EUは独自の市場規模と規制ツールキットを活用し、ソーシャルメディア・プラットフォームや検索エンジンに透明性の向上と選挙リスクの軽減を迫った。同年2月に全面施行されたデジタルサービス法(DSA)では、大手プラットフォームや検索エンジンに、詳細な透明性報告書、リスク評価、プラットフォームデータへの研究者のアクセス権の付与などを義務づけている。同年4月には、欧州委員会が選挙ガイドラインを作成し、政治広告やAI生成コンテンツへのラベル付け、選挙関連の社内チームへの適切なリソースの確保など、DSA下において企業が採用すべき措置を定めた。同委員会は、メタによる欺瞞的な選挙広告の制限に関する疑わしい不遵守や、Xによる選挙関連リスクの緩和における不備など、多数の違反の可能性について、メタとXに対する正式な調査手続きを開始した。
EUの非義務的な「デマに関する行動規範」は、情報の完全性を強化する別のメカニズムとして機能した。この規範は、大手プラットフォームや広告会社を含む署名者に、事前に「デジタル加工」されたコンテンツを否定し、明確にラベル付けすること、透明性センターを設置すること、虚偽や誤解を招く情報を収益化しないことを求めている。これらの措置は、有権者が選挙について十分な情報を得た上で意思決定を行い、投票に完全に参加するために必要な信頼できる情報を提供するのに役立つ。しかし、自主的な性質をもつこの規範では、その有効性は不明瞭であり、追跡も難しい。
アメリカでの混迷
アメリカでは、何が起きているのだろうか。報告書は、訴訟大国アメリカにおいて、混乱が生じていることを紹介している。ルイジアナ州とミズーリ州の州当局は、2022年に民間原告団とともに連邦政府を提訴し、2020年の選挙期間中および新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック発生時のテクノロジー企業とのやり取りは「検閲」に等しいと主張した。最高裁は2024年6月、原告側が被害を証明していないこと、また下級裁判所が原告側に有利な判決を下した根拠となった事実が「明らかに誤り」であったことを指摘し、この訴訟を却下した。それでも、2州当局からの法的措置に直面した連邦政府機関は、2024年11月の選挙を控えた重要な時期にプラットフォームとの協力関係を縮小した。最高裁は、憲法で保障された言論の自由を尊重しながら、政府機関がプラットフォームとどのようにコミュニケーションを取るべきかについて、より詳細な指針を示さなかったため、連邦捜査局(FBI)は、プラットフォームとの関わりについて透明性を高め、より明確なガードレールを設定する計画を明らかにした程度にとどまっている。
台湾とインドの好ましい事例
報告書は、台湾とインドにおける好ましい事例を紹介している。「台湾の市民社会は、事実確認とデマの調査に透明性があり、分散化され、協調的なアプローチを確立しており、これは世界的なモデルとなっている」、と報告書は高く評価している。
2020年8月の別の情報によると、「今ではLINEやフェイスブックでDr. Messageは40万人、Cofactsは18万人が利用、ディスインフォメーションによる被害を減らしている」という。かなり前から、複数のファクトチェック組織が存在したことになる。
たとえば、「Dr. Messageは毎月5500万件の情報を判読し、これまでに200万件以上のディスインフォメーションや詐欺情報を識別、阻止してきた」という。2020年2月、米国在台協会(AIT)と資訊工業策進会(III)が共同で開催したUS-Taiwan Teck Challengeにおいて、Dr. Messageは一等に輝き、賞金17.5万米ドルを獲得した。
Cofacts(真的假的)は、一般ユーザーの協力を得て、多くの人が協力してファクトチェックをする仕組みを作り上げた。創設者のジョンソンは、LINEのグループで、しばしば本当かどうか疑わしいデマや噂が転送されてくるのを何とかしたいと考え、タップするだけで真偽を確認できるプログラムを作りたいと考えたのである。
2024年1月の選挙の前後には、Cofactsのプラットフォームでは、ソーシャルメディアやメッセージングプラットフォーム上で目にした主張を投稿し、Cofactsの投稿者(プロのファクトチェッカーと非プロのコミュニティメンバーの両方を含む)によるファクトチェックを受けることができた。選挙期間中、Cofactsは、メッセージングプラットフォームのLINEにおいて、台湾の外交関係、特に米国との関係に関する誤った情報が優勢であることを発見した。
いずれにしても、こうした台湾の取り組みを知ると、日本がまったく遅れていることに気づくだろう。
インドでは、2024年4月の総選挙開始を前に、50以上のファクトチェック団体とニュース発行者が、同国史上最大の連合である「シャクティ・コレクティブ」(Shakti Collective)を立ち上げた。このコンソーシアムは、虚偽情報やディープフェイクの特定、ファクトチェック結果のインドの多数の言語への翻訳、ファクトチェックとAI生成コンテンツの検出能力の拡大に取り組んだ。さらに、Shakti Collectiveのメンバーの多様性により、さまざまな有権者コミュニティに働きかけ、電子投票機が不正操作されているという虚偽の主張が現地語で増加しているといった新たな傾向を特定することができたという。
衆院選を前に、日本でも同じようなことは起きたのだろうか。こうした話を知ると、日本がいかに後進国であるかがわかるだろう。要するに、専門家も政治家もマスメディアも、こうした他国の進んだ状況を日本国内において拡散させる努力がまったく足りないのだ。とくに、マスメディアの不勉強がこうした体たらくを招いているのである。私からみると、アホばかりの最低な組織に成り下がってしまっている。
報告書批判
最後に、米国務省のカネが拠出されているこの報告書が十分に注意を払っていない問題点について指摘しておきたい。親米的価値観は批判の対象となりうるからである。
まず、強く感じるのは、報告書が全般に、「自由」の意味をはき違えているという点である。ゆえに、報告書の「自由」、「一部自由」といった評価は笑止千万だ。
単刀直入にいえば、いわゆる「自由意志」は存在しない。とくに、「不自由」を意識できなければ、「自由」が何を意味しているかを説明できる者はいないだろう。
自由は、カントのいう「超越論的仮象」にすぎず、その存在を認めなければ、理性を働かせることができないから仮定されたものにしぎない。そう考えると、自由の程度をどう定義するかについては、さまざまな考察が必要であることに気づかなければならない。
極端な言い方をすると、「北朝鮮の国民ほど、言論の不自由を感じている人々はいない」とすれば、自由の尊さを世界でもっとも痛感しているのは北朝鮮国民かもしれないのだ。
別言すると、マスメディア、政治家、官僚、学者が皮相で、いい加減なことしか言わず、情報操作が頻繁に行われているにもかかわらず、自分たちが自由を謳歌していると誤解している人が多い日本のような国では、ただ情報操作によって大多数の国民が「踊らされている」だけであるとも言える。そこには、自由は存在しない。自分たちが情報操作されて不自由であることに気づいていない以上、自由意志はないし、自由の大切さにも気づいていないのである。
「自由」そのものの「危うさ」に気づくことが何よりも大切だと強調しておいたい。報告書が「自由」であると評価した国では、自らの「不自由」さに気づいていない者が多いだけであり、彼らがマスメディアの情報に過度の信頼を置くことで簡単に情報操作されてしまっている可能性をみていない。
ソーシャルメディア企業による「シャドーバン」に留意せよ
もう一つ、この報告書で問題なのは、ソーシャルメディア企業における「シャドーバン」(shadowbanning)について、まったく無視している点である。
よく知られているように、共和党はこの10年間、ソーシャルメディア企業が保守的な視点を「検閲」し、民主党に有利なようにプラットフォームを歪めていると非難してきた。しかし、現在は、民主党がその不満を逆手に取り、イーロン・マスクという共和党の盟友が所有するXがドナルド・トランプ前大統領の再選を助けるためにカマラ・ハリス副大統領に有利なコンテンツを抑制しているのではないかと疑問を呈している。
いずれの場合にも、ソーシャルメディア企業はアルゴリズムを操作することで特定の情報を流さないことができることが前提とされている。これに対する反発から、2017年頃になって、「シャドーバン」(shadowbanning)という言葉、すなわち、「ユーザーが主張するソーシャルメディア企業によるコンテンツや意見を隠すための卑劣な行為」という表現が広がった。
最近では、企業は「推奨ガイドライン」という用語を好む傾向にある。一部のテクノロジー評論家は「アルゴリズムによる抑制」という用語を使用している。いずれにしても、ソーシャルメディア企業、すなわち、プラットフォーマー側には、情報選別が可能であり、この段階から情報を操作できる。つまり、彼らは、「検閲」可能であり、受信者の情報選択の「自由」を毀損することができる。
WPによれば、たとえば、TikTok、インスタグラム、YouTube、Snapchat、Twitchは、子どもにとって不適切と判断したコンテンツの表示を制限している。銃器や違法薬物の表示は禁止という明確なルールもある。一方で、TikTokでは、年齢に関係なく「制限モード」に設定でき、このモードでは「脅迫的なイメージ」や「複雑なテーマ」の動画が制限される。さらに、TikTokは「あなたにおすすめ」ページのアルゴリズム上の「時事問題」のダイヤルを、年齢に関係なくユーザーが下げることもできる。
注目されるのは、メタがFacebook、インスタグラムおよびスレッドにおける政治的内容の制限に取り組んでいることだ。別のWPは、インスタグラムのユーザーのアカウントをみせてもらい、調査を行ったところ、「過去6か月間、彼女が政治関連の話題に触れるたびに、政治以外の投稿と比較してフォロワー数が約40パーセント減少していることがわかった」と報じている。さらに、彼女が11件の投稿のキャプションで「投票」という単語を使ったところ、「平均的な視聴者数は63%減少した」という。
このように、ソーシャルメディア企業のレベルで、何らかの情報操作が行われている。そう考えると、フリーダム・ハウスが「自由」な国と評価した場所でも、それは「自由」とほど遠い幻想にすぎないことがわかるだろう。
いずれにしても、紹介した報告書『フリーダム・オン・ザ・ネット』は、世界中の国々における自由の問題を考察するヒントにはなる。米政府の価値観に基づいた偏向した報告書にすぎないことを肝に銘じながら、地政学的考察を行うことの重要性を知ってもらえれば幸いである。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:アメリカ大統領選挙と分断する社会〜激動する世界の行方
☆ISF主催トーク茶話会:高橋清隆さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:原一男さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)