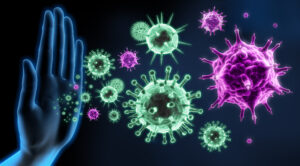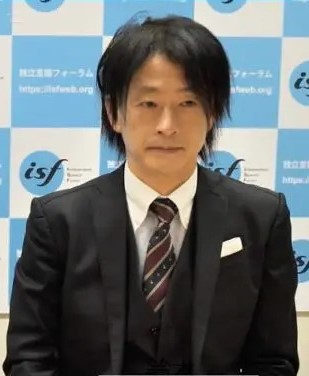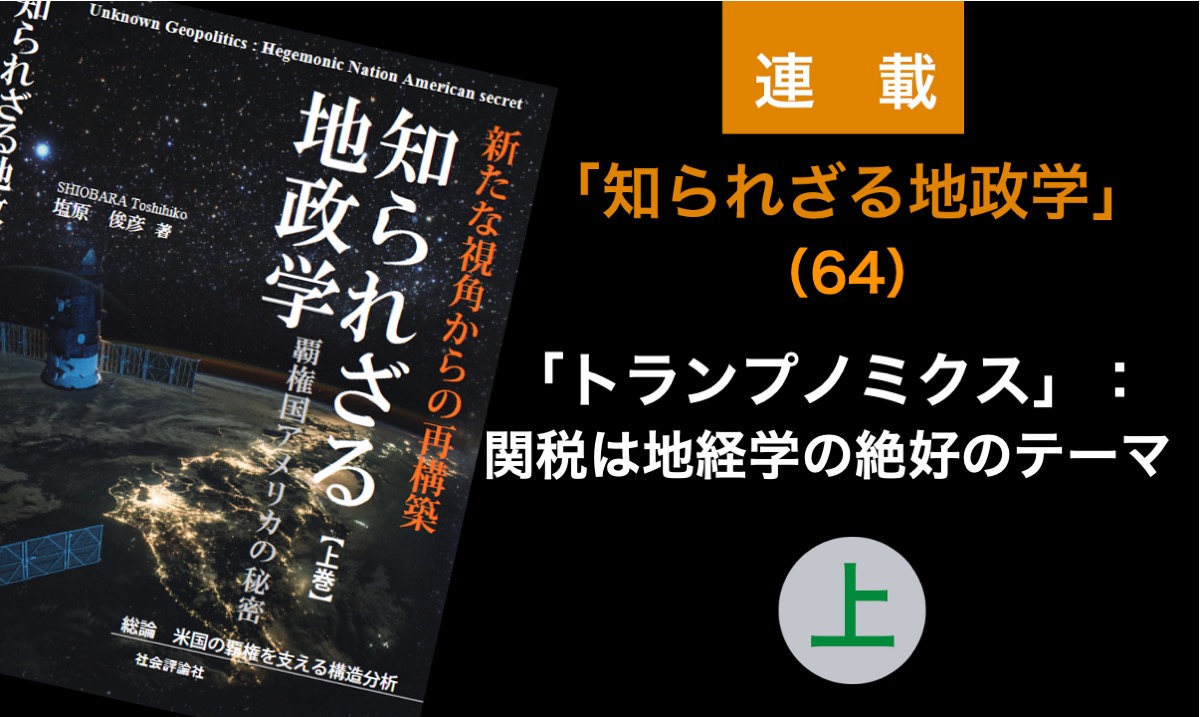
「知られざる地政学」連載(64):「トランプノミクス」:関税は地経学の絶好のテーマ(上)
国際
新ドナルド・トランプ政権がとろうとしている経済政策、「トランプノミクス」について俎上に上げたい。とくに、関税引き上げ問題は国際問題を引き起こす点で注目に値する。ゆえに、関税は「地経学」の絶好のテーマと考えられる。だが、日本には、まともな地経学の専門家がいるとは思えない。そこで、ここで模範となる議論を展開してみよう。
関税をめぐる基礎知識1
最初に、関税の目的について説明したい。関税とは、物品の輸出入に際して課せられる税金のことである。物品の輸入に際して課せられる輸入関税を指すのが一般的だ。その目的は、①国内産業の保護、②財源、③制裁――といったものが考えられる。「トランプ2.0」と呼ばれる二期目のトランプ政権が関税政策を大幅に拡充するねらいは、Make America Great Again(MAGA)というスローガンからみると、国内産業の活性化による雇用増加と、中国に代表される特定の国への制裁的な攻撃にあるように思われる。
国内産業保護によって雇用増加にまで至れば、MAGAの実現とみなすことができる。これは、後述するように、北米自由貿易協定(NAFTA)後に空洞化したアメリカ産業をどう国内に呼び戻すかという問題につながっている。
「トランプノミクス」にあっては、関税は減税の財源となる。米国は年間約3兆ドル相当の商品を輸入しているため、10%の関税を課せば理論上は約3000億ドルの連邦歳入が得られる。経済学者のキンバリー・クラウジングとメアリー・ラブリーによる2024年8月の研究によると、トランプ大統領の関税計画は、一律輸入税が10%または20%に設定されるかによって、一般的な米国の世帯で年間1700ドルから2600ドルの負担増となる(WPを参照)。もちろん、後述するように、現実には密輸などの横行によって、これが絵に描いた餅に終わる可能性も高い。
トランプは、米国が輸入するすべての製品に10~20%の課税を課し、中国からの全製品には60%、メキシコからの自動車にはさらに高い関税、おそらく500%の関税を課すことを検討していると語っていた。この中国への高い関税は制裁的色彩が濃いと言えそうだ。トランプは、米国製品に高関税をかける国があれば、まったく同じ関税で反撃するという方針も明らかにしている。この方針は、ヘリテージ財団を中核とするこのグループによって策定された、共和党新政権の政策・人事プラットフォーム「プロジェクト2025」の貿易の章において、トランプ氏の経済顧問ピーター・ナバロは、中国やインドなどの国々が米国の商品に対して米国よりも高い関税をかけていることを嘆き、これが「米国の農家、牧場主、製造業者、労働者の組織的搾取」につながっていると主張している。原則的に、相互主義を実現するには、他国を説得して関税を引き下げるか、米国が自国の関税を引き上げるかの二つの方法しかない。
関税の仕組み
関税は、物品毎に割り当てられた関税分類番号と、それぞれの番号に対応する関税率とからなる関税率表に基づいて各国によって賦課されている。関税分類のために、「商品の名称及び分類についての統一システム(HS:Harmonised System)」(HS 条約)が締結されており、191カ国および地域(2005年9月)が自国の関税率表として HS 品目表を採用し、現在では関税番号で6桁までの関税分類が世界の大半の国において統一されている(経済産業省の資料を参照)。
関税の賦課に際しては、賦課の基準額を査定する関税評価も重要な要素となっている。仮に、関税賦課の基準額を各国が恣意的に認定すれば、関税率の設定は無意味となってしまうからだ。そこで、関税評価については、ガット第7条およびガット第7条の実施に関する協定(関税評価協定)により、国際ルールが定められている。
移転価格対策という面から説明すると、企業はさまざまな部品を海外で製造し、どこか法人税の安価な国で組み立てて販売している。同じ企業集団内であれば、部品の値段を恣意的に操作して、法人税率の高い国では利益を出さないように、部品価格を低く設定して別の組み立て国に輸出できる。こうした企業内の価格操作に対抗するためには、部品の品目ごとに賦課基準額を市場価格に近い価格に設定して、監視することが必要になる。
こうした仕組みは過去の貿易管理ルールをもとに、国際的なルールを策定する努力が積み重ねられてきた結果として整備された。いまでは、あまり機能しているとは言えない世界貿易機関(WTO)がこうしたルールづくりに従事してきたのである。
関税をめぐる基礎知識2
関税を支払うのは輸入業者である。米国の場合、輸入業者が、自社製品が米国内に入った時点で、関税をすべて米税関・国境警備局に支払っている。したがって、関税率が引き上げられると、輸入業者は増加した関税分を捻出するためにいくつかの選択肢に直面する。①輸入業者は輸出先と交渉して輸入品価格の引き下げを求める、②仕方ないので、輸入業者が自腹を切って増税分を負担する、③国内の販売先(消費者)に価格転嫁して増税分を捻出する――というのがそれである。これが意味しているのは、個々の製品の需要や代替品の有無に応じて、関税負担は外国の生産者、米国の輸入業者、最終顧客の間で分担される場合もあるということだ。たとえば、その製品を製造する外国企業は、コスト削減のために生産ラインを再設計したり、米国での販売を維持するために利益率の引き下げに応じたりする場合もある。多くの場合、三つを組み合わせた対応策になるのかもしれない。
とくに、留意すべきは、①に関連して、為替レートの変動によって、大幅に関税分が相殺可能となる点だ。簡単に言えば、インフレを見越して米国内金利が引き上げられれば、大幅なドル高によって輸入業者は相対的に安価に輸入品を購入できるようになるから、関税による増税分を、ほとんど懐を傷めずに支払うことさえ想定できるのである。
すでに、一部の企業は、新たな関税が発動される前に備蓄を確保しようと、異例の大量の輸入注文を出しているし、在庫を積み上げる動きもある。「米国勢調査局によると、米国は2024年7月と8月に、2023年の同じ2か月間よりも11%多い中国製品を輸入した」という情報もある。さらに、トランプ大統領が主な標的としている中国国外のサプライヤーに切り替えることで、最も高い関税を回避する動きもある。わかってほしいのは、経済の「理論」と「現実」とはまったく異なっているということだ。
もちろん、厳しい見方もある。全米小売業協会(National Retail Federation)は11月4日、「輸入品に対する提案関税の影響予測:アパレル、玩具、家具、家電、履物、旅行用品」という調査を発表した。すべての外国からの輸入品に対する一律10~20%の関税、および中国からの輸入品に対する追加の60~100%の関税が、アパレル、玩具、家具、家電、履物、旅行用品の6つの消費者向け製品カテゴリーにどのような影響を与えるかを検証したもので、「消費者は、衣料品に139億ドルから240億ドル、玩具に88億ドルから142億ドル、家具に85億ドルから131億ドル 、家庭用電化製品に64億ドルから109億ドル、履物に64億ドルから107億ドル、旅行用品に22億ドルから39億ドルをそれぞれ追加で支払うことになる」としている。
しかし、実際には、別の抜け道もある。密輸業者、裏取引、不正な出荷ラベルなどの地下市場を使って、米国輸入をする方法もある。たとえば、連載(7)「ドラッグをめぐる地政学」(上、下)で紹介したフェンタニルの場合、南部国境でフェンタニル密輸の罪で有罪判決を受けた人の80%以上が米国籍であることが連邦政府のデータで示されている(2024年9月28日付のNYTを参照)。バー、スポーツジム、リハビリ施設、トレーラーパークなど、近年、こうした場所でリクルーターが運び屋を見つけていることが、裁判記録から明らかになっているそうだから、運ぶ「ブツ」にもよるが、米国の一般市民を抱き込んで、大量の密輸をすることも可能だろう。現実は、経済理論とはまったく異なることを肝に銘じてほしい。
関税をめぐる基礎知識3
ここで、関税の変遷について説明したい。関税引き上げというと、すぐに目くじらを立てる論調が目立つ。歴史を知らない者がディスインフォメーション(騙す意図をもった不正確な情報)を垂れ流しているのだが、そんな情報に騙されないようにするために、簡単に米国における関税導入についてのべておきたい。
1922年、米国議会はフォードニー・マカンバー法を制定した。これは、米国の歴史上もっとも懲罰的な保護主義関税の一つで、輸入税を平均40%にまで引き上げるものだった。 同法は欧州各国政府の報復を促したが、米国の繁栄に水を差すことはほとんどなかったという(ブリタニカの情報を参照)。
しかし、1920年代を通じて、ヨーロッパの農家が第一次世界大戦から立ち直る一方で、米国の農家は過剰生産による激しい競争と価格下落に直面したため、農業関係者は連邦政府に農業製品の輸入保護を働きかける。1928年の大統領選キャンペーンで、共和党候補のハーバート・フーヴァーは、農産物への関税引き上げを公約する。大統領就任後、他の経済部門のロビイストたちから、より大幅な関税引き上げを支持するよう促される。ただ、関税の引き上げは共和党員のほとんどから支持されていたが、1929年には、米上院の中道派共和党議員からの反対が主な原因となり、輸入関税引き上げの試みは失敗に終わった。
それでも、1929年の株式市場の暴落を受けて保護貿易主義が勢いを増した結果、ユタ州選出の上院議員で上院財政委員会議長のリード・スムートと、オレゴン州選出の下院歳入委員会議長のウィスリー・ホーリーにちなんで名づけられたスムート・ホーリー法が1930年に両院を通過した。フーバー大統領は1930年6月17日に法案に署名し、法律として成立させた。米議会が実際の関税率を設定した最後の法律と言われている。
平均関税率を約20%引き上げたことで、外国政府からの報復を招き、多くの海外銀行が破綻しはじめる。2年以内に24カ国が同様の「隣国を苦しめる」関税を採用し、すでに苦境にあった世界経済をさらに悪化させ、世界貿易を減少させる。米国のヨーロッパからの輸入およびヨーロッパへの輸出は、1929年から1932年の間に3分の2ほど減少した一方、世界貿易全体では、この関税法が施行されていた4年間で同程度の減少となったという(ブリタニカの情報を参照)。
その後、1934年、フランクリン・D・ルーズベルト大統領は相互通商協定法に署名し、関税率を引き下げ、貿易自由化と外国政府との協力を推進する。それでも、一部の専門家は、こうした関税政策が世界大恐慌を深刻化させ、政治的過激主義の台頭を招き、アドルフ・ヒトラーのような指導者が政治力を高め、権力を握ることを可能にしたと主張している。
関税の法的位置づけ
ここまでの説明で、「米議会が実際の関税率を設定した最後の法律と言われている」という記述が気になったかもしれない。実は、米憲法は、輸入品を含む課税の全権限を議会に与えているのだが、1930年と1974年には、議員たちは不公正な貿易慣行への対応として、より高い関税を課す限定的な権限を大統領に委任したという歴史がある(WPの情報を参照)。だが、これらの法律は大統領がすべての輸入品に一律関税を課すことを認めていない。別言すると、トランプには、対全世界各国共通の関税を導入する明白な権限がない。ただし、大統領が「深刻かつ大規模な」国際収支赤字に対応するために、150日間、最大15%の汎用関税を課すことを認める1974年通商法の条項に頼ることができる。この条項はこれまで一度も使用されたことはない。
もちろん、トランプは普遍的な関税について議会の承認を求めることもできる。法案の成立には時間がかかるが、そうした広範囲にわたる措置は、法的にも政治的にもより持続性のあるものになりうる。それでも、もし大統領が、米国が毎年輸入する総額3兆ドルに上る商品すべてに関税を課そうとした場合、影響を受けるグループは連邦裁判所に介入を求めるだろうとみられている。一律関税の合法性に関する最終判決が下されるまでには、数カ月から数年を要する可能性がある。その間、関税は有効なままである。
しかも、裁判になっても、トランプ政策が勝利する可能性もある。たとえば、2023年、米最高裁は輸入業者による2018年のトランプ大統領の輸入鉄鋼・アルミニウム関税導入決定に対する法的異議申し立てを却下し、大統領が国家安全保障上の懸念を理由にこの措置を正当化したことを尊重した。
他方で、通商法232条は、国家安全保障を守るために大統領が輸入を制限することを認めている(鉄鋼とアルミニウムへの関税の根拠は疑わしい)。同301条は、大統領が差別的な貿易行動をとる国に対して関税を課すことを認めている(対中措置の根拠としてはより合理的と考えられている)。しかし、どちらも時間のかかる調査が必要であり、トランプとそのアドバイザーが望む迅速な行政措置とは相反するとみられている。
もうひとつの選択肢は、国際緊急経済権限法を発動することだろう。トランプは2020年に、中国のソーシャルメディアの雄であるTikTokとWeChatを米国のアプリストアから削除するよう命じた。同法の発動は国家非常事態が前提とされているため、トランプは非常事態を宣言し、その対応策として普遍的な関税を発表する必要がある。ただし、何を根拠に非常事態というのかは不透明である。
なお、互恵関税という、相互の関税率を等しくするという考え方もある。米国の課す関税率よりも高い国には、その国と同じ税率を課すように引き上げるものだ。しかし、米国の自動車関税がわずか2.5%であるのに対し、欧州連合(EU)は10%である。他方で、米国は以前からピックアップトラックの輸入に25%の関税をかけており、木材や食品の輸入にも高額の関税をかけている。関税を一行一行調べれば、米国の関税が他国より高い例は枚挙にいとまがないから、互恵関税は関税引き上げ策の根拠とはならないだろう。
「知られざる地政学」連載連載(64):「トランプノミクス」:関税は地経学の絶好のテーマ(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)