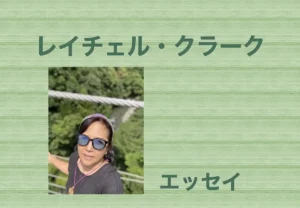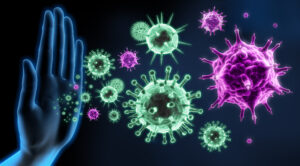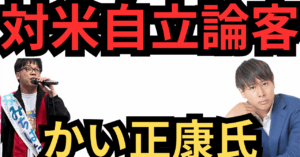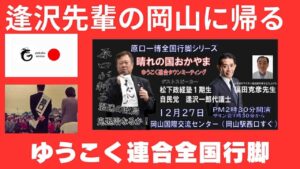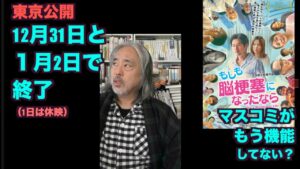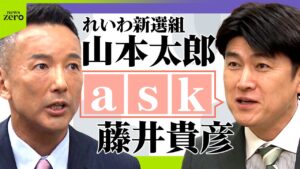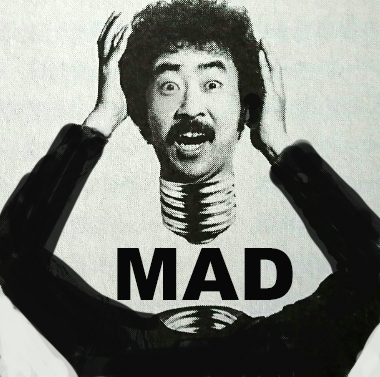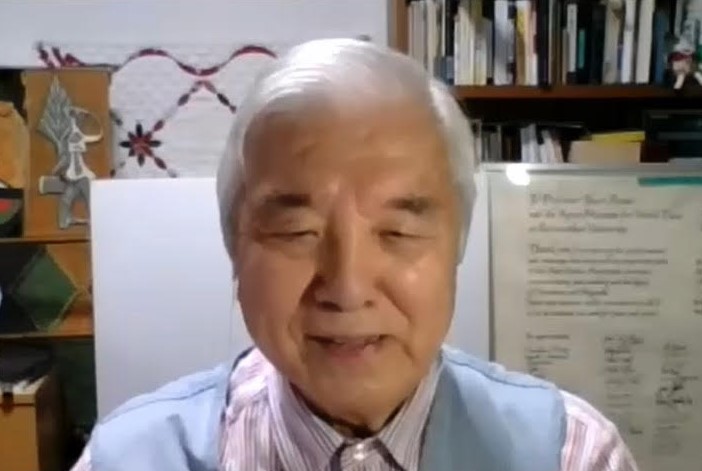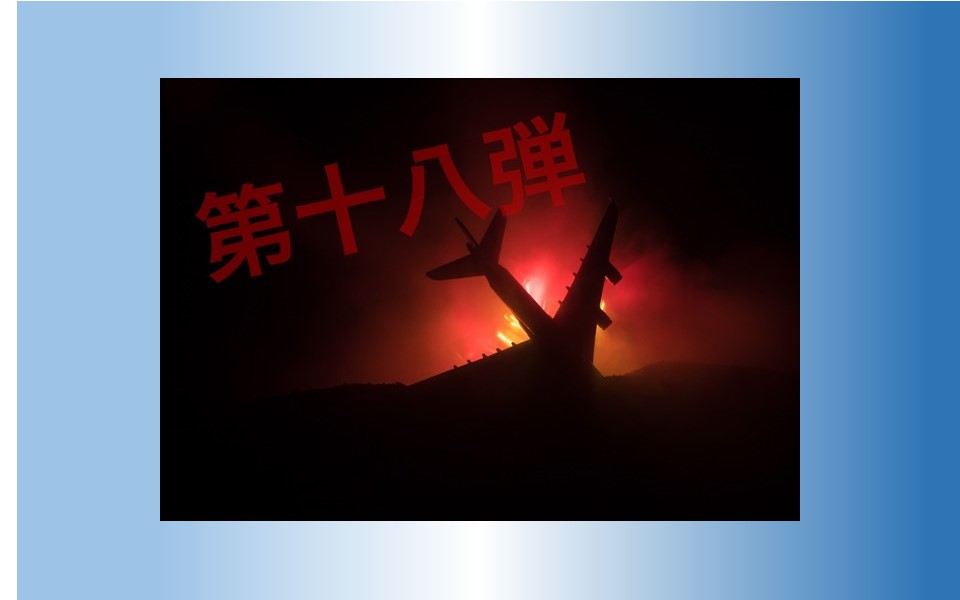
日航123便墜落事故:事故の1ヶ月前にJA8119機内で発生した現象が報告書から外されていた
社会・経済今回の記事では、以下の2つの情報について紹介する。
①事故の1ヶ月前にJA8119機内で発生した現象が報告書から外されていたことについて
②「事故調査委員会や事故調査報告書は必ずしも信用できるわけではない」ということがよくわかる資料
上記の2点について、以下に紹介する。
①事故の1ヶ月前にJA8119機内で発生した現象が報告書から外されていたことについて
まず、御巣鷹山墜落事故の約1ヶ月前に、事故機であるJA8119機内で発生した現象が、報告書から外されていたことについて紹介する。
『第28回安全工学シンポジウム講演予稿集』(発行日:1998年6月30日)に掲載されている藤原源吉氏(元日航)による記事「航空機のACTと構造強度安全率の問題」に、以下の通り書かれている。
≪231 航空機のACTと構造強度安全率の問題
藤原 源吉 (元日航)
(中略)
従って、後部胴体半球殻圧力隔壁L18の疲労き裂が進展したところへ,曲げ,捩り,内圧荷重の加わった場合の後部胴体殻構造応力解析としては,Saint Venantの捩り理論を適用しなければならない.つまり胴体構造の捩り変形のみならず,機軸方向の断面変形(warping free)も考えなければならないのである.事故発生のほゞ1ケ月前,当機に乗務した客室乗務員の証言によると,後部圧力隔壁の前にある化粧室ドアの飛行中独りでに開閉する現象を解明するための,1つの手掛かりを得るための解析である.なぜなら,事故調では当現象を矛盾なく説明できないので,報告書から外したとの証言を事故調専門委員から得ている故参考までに論述した.≫
なんと、上記の藤原氏の記事によると、事故機であるJA8119機は、事故の約1ヶ月前に「後部圧力隔壁の前にある化粧室ドアが飛行中独りでに開閉する」という現象を起こしていたのにもかかわらず、事故調では当該現象を矛盾なく説明できないという理由から、当該現象は報告書から外されたというのである。
運輸安全委員会には、今からでもよいので、なぜ事故の約1ヶ月前に「後部圧力隔壁の前にある化粧室ドアが飛行中独りでに開閉する」という現象が発生したのか、再調査していただきたい。
また、上記の情報は現在あまり知られていないと思われる。上記の情報がより広く周知されることを願っている。
② 「事故調査委員会や事故調査報告書は必ずしも信用できるわけではない」ということがよくわかる資料
次に、「事故調査委員会や事故調査報告書は必ずしも信用できるわけではない」ということがよくわかる資料を紹介する。
日本では、1983年に「日本近距離航空機中標津空港事故」、1982年に「南西航空石垣空港オーバーラン事故」が発生している。
これらの事故について『エコノミスト』1985年12月17日号掲載の岡本棟守氏による記事「疑問だらけの航空事故調査 規制緩和でつのる安全性への不安」に、以下の通り記載されている。
≪中標津、石垣はどうなのか。中標津、石垣のケースは過去の事故と違いパイロットが生存している。そして両方のパイロットは口をそろえて「機材について疑問あり」と指摘している。だが事故調査委員会はそれを無視したばかりか、パイロットの証言まで勝手に修正して結局「パイロットミス」にしてしまった。≫
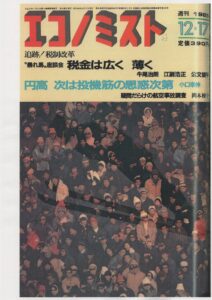
なんと、上記の岡本氏の記事によると、両事故において、事故調査委員会はパイロットの証言を「勝手に修正」したというのである。パイロットの証言を「勝手に修正」したのが事実であれば、それは「捏造」以外の何物でもないだろう。
また、日本では、1966年に「カナダ太平洋航空402便着陸失敗事故」も発生している。この事故は、羽田空港で発生した事故である。
当該事故について、『コミューター・ビジネス研究』No. 6掲載の「講演録 航空安全の傾向と課題」(航空評論家 関川栄一郎)に、以下の通り記載されている。
≪そうこうしているうちに、大変厄介な問題が起こりました。というのは、日本側の調査とは別に、カナダ側が専門家を日本に送り込んで来たのです。そして独自の調査をやり、新しい事実を見つけました。
それは、事故が起こってから消防車が現場に駆けつけるまでにかなりかかっている。これはちょっとおかしいわけで、ご承知のように空港の中にも消防車は待機していますから、滑走路をつっ切って全速力で走れば端まででも1~2分で行けるはずです。
そこで、どういうわけでおくれたか調べてみたところ、この事故は羽田空港ができてから初めての大事故でした。同時に夜の真っ暗ななかで、火の手が上がったものですから、実際よりかなり大きく見えた。それで空港の消防所員が自分たちの手に負えないというので近所の消防署に電話をかけ、その応援がくるのを待って一緒に走りだした。
そのため現場に着くまでかなりかかった。もちろん報告書にはそんなことが書いてありません。事故発生直後に消防車が現場に駆けつけたと書いてあるのですが、実際にかなりかかっている。カナダ側がそういう事実を見つけたのです。≫
上記の関川氏の記事によると、実際には消防車が現場に駆けつけるまでにかなり時間がかかっていたのにもかかわらず、報告書にはその事実が書かれていないというのである。
確かに、当該事故の事故調査報告書を読むと、以下の通り書かれている。
≪20時15分ごろ東京国際空港の管制機関から,滑走路33R末端付近で航空機事故発生の通報を受けた空港消防機関は,直ちに出動し,20時20分ごろ現場に到着して消火および生存者救出活動に入った.≫
上記の通り、報告書には「消防車が現場に駆けつけるまでにかなり時間がかかった」という情報は書かれていない。
関川氏の証言が事実であれば、報告書は事実を隠蔽しているといえるだろう。
上述した3件の事故に関する情報は、123便墜落事故と直接的な関係はないが、「123便墜落事故の事故調査報告書は信用できるかどうか」を考える際には、参考になるだろう。上記の情報が広く周知され、多くの人の参考になることを期待している。
また、123便墜落事故の約1ヶ月前に、事故機であるJA8119機内において「後部圧力隔壁の前にある化粧室ドアが飛行中独りでに開閉する」という現象が発生したという情報を、運輸安全委員会が事故調査報告書に加筆することを願っている。
付記:高井正憲氏が経験した事故当日の出来事について
私の第八弾目の記事「123便が18時40分ごろレーダーから一時的に消えた可能性について」と、第十五弾目の記事「日航123便墜落事故とヘリコプター会社」では、123便が墜落時だけでなく、迷走中にもレーダーから消えた可能性について述べた。
今回、その可能性の裏付けとなり得る新たな資料を発見したので、紹介する。
『財界』1994年1月18日新春特別号掲載の村田博文氏による記事「私の雑記帳」に以下の通り記載されている。
≪私の雑記帳
村田博文
(中略)
取材の原点
記者の活動は、昔も今も変わらない。(中略)
テレビ朝日アナウンサーの高井正憲さんと話していて、その感を強くした。
昭和六十年夏の、あの痛ましい日本航空のジャンボ機墜落事故。高井さんはその日午後六時すぎ、仕事を終え、帰宅しようとしていた。
そこへ、「日航ジャンボ機が行方不明」の第一報が飛びこんできた。次いで、「厚木方面へ飛んでいったらしい」という報が入ったが、その後の消息がわからない。
ディレクターから、「とにかく西へ行け」という指示を受けた。≫
上記の村田博文氏の記事によると、高井正憲氏は18時台に第一報に接し、次いで「厚木方面へ飛んでいったらしい」との情報に接したというのである。
やはり、123便は迷走中にレーダーから一時的に消えたのではないだろうか。
高井正憲氏が事故当日の記憶を再発信してくださることを願っている。
【参考文献】
- 藤原源吉. 231 航空機のACTと構造強度安全率の問題. 第28回安全工学シンポジウム講演予稿集, 1998, p.249-252. 国立国会図書館デジタルコレクション. https://dl.ndl.go.jp/pid/10291446/ (参照 2025-02-03)
- “日本近距離航空機中標津空港事故”. Wikipedia. https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BF%91%E8%B7%9D%E9%9B%A2%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E4%B8%AD%E6%A8%99%E6%B4%A5%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E4%BA%8B%E6%95%85(参照 2025-02-03)
- “南西航空石垣空港オーバーラン事故”. Wikipedia. https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E8%A5%BF%E8%88%AA%E7%A9%BA%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E4%BA%8B%E6%95%85(参照 2025-02-3)
- 岡本棟守. 疑問だらけの航空事故調査 規制緩和でつのる安全性への不安. エコノミスト, 1985, 12・17, p.24-30.
- “カナダ太平洋航空402便着陸失敗事故”. Wikipedia. https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E8%88%AA%E7%A9%BA402%E4%BE%BF%E7%9D%80%E9%99%B8%E5%A4%B1%E6%95%97%E4%BA%8B%E6%95%85(2025-02-03)
- 関川栄一郎. 講演録 航空安全の傾向と課題. コミューター・ビジネス研究, 1988, 6, p.19-31. 国立国会図書館デジタルコレクション. https://dl.ndl.go.jp/pid/3330827/(参照 2025-02-03)
- “カナダ太平洋航空会社,ダグラスDC-8,CF-CPK事故調査報告書”. 日本航空学会誌, 1968年12月5日, 第16巻第179号, p.435-446. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsass1953/16/179/16_179_435/_article/-char/ja/(参照 2025-02-03)
- 村田博文. 私の雑記帳. 財界, 1994, 1月18日新春特別号, p.208-209.
– – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内