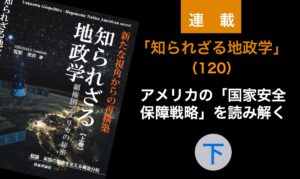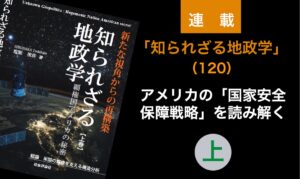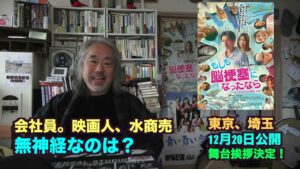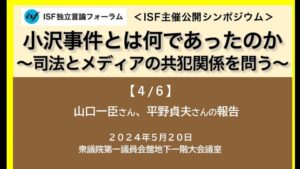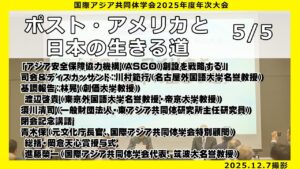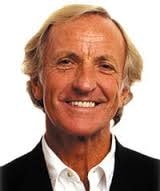「知られざる地政学」連載(76):検閲をめぐる地政学(下)
国際
「知られざる地政学」連載(76):検閲をめぐる地政学(上)はこちら
すでに消えたGEC
同じ報告書のなかで、厳しい批判にさらされた「グローバル・エンゲージメント・センター」(GEC)は、2024年12月24日にその権限が失効した。報告書では、「調査結果3」として、米国務省に設置された省庁間組織であるGECは、国内検閲能力をもつ民間企業に対して、ディスインフォメーション検出分野におけるテクノロジー系スタートアップ企業やその他の小規模企業への資金提供、開発、そしてプロモーションを行うことで、厳格な国際的任務を回避した、と指摘されている(後述)。
GECはもともと、2016年3月14日にオバマ大統領によって署名された大統領令13721に基づいて設立されたものだ。海外に向けられた政府全体のテロ対策コミュニケーション活動を支援するための統合グローバル・エンゲージメント・センターをつくろうとしたのである。2020年4月の国務省監察総監室の報告書によれば、2016年12月、2017年度の国防権限法(NDAA)はGECの責務を拡大し、「外国の聴衆を対象とした公共外交の取り組みに関連する、外国の国家および非国家のプロパガンダおよびディスインフォメーションの取り組みとコミュニケーションに関する研究およびデータ分析のための記録を維持・収集・使用・および配布する」という機能が第10項として追加された。同報告書には、「GECは2018年度に約9870万ドルを受領した。この金額には、議会計上の約7870万ドル(外交プログラム不朽の公共外交に2460万ドル、海外有事作戦に3430万ドル、イラク・シリアのイスラム国を打倒するグローバル連合発足に1980万ドル)が含まれている。さらに、GEC は国防総省から2000万ドルの移転を受けた」と書かれている。その資金は、主にDemocracy Council of California、CNA Corporation、Park Capital Investment Group LLCに流れていた。民主党と関係深い組織であったり、海軍関連組織であったりするところにカネが流れたことになる。
こんな組織だから、同センターの権限を2031年まで延長する法案は、上院を通過した国防権限法案の最終版から削除されたことで、12月24日をもってその権限を失った。「国務省が提供した数字によると、GECのスタッフは約120名、年間予算は6100万ドルである」という情報がある。
前記の報告書の「調査結果4」では、米議会によってほぼ全額の資金提供を受けている民間非営利団体である全米民主主義基金(NED)もやり玉に挙げられている。NEDは国内報道機関が信頼性団体に加盟する資格を評価するにあたり、ファクトチェックを行う団体と協力したことで、国際的な制限に違反したというのである。
なぜ、NEDの話をしたかというと、このNEDこそ、米国のリベラルデモクラシーの輸出のための拠点であり、米国の外交戦略の根幹を担ってきた機関だからである。これは、2014年2月のウクライナのクーデターを事実上、背後で煽動したヴィクトリア・ヌーランド(当時、国務省次官補)が2018年から2021年まで、NED理事を務め、さらに、2024年3月に国務省を辞めた彼女を再び同年9月に理事に就任させた人事をみれば一目瞭然だろう。思い出してほしいのは、マスクが2023年2月23日、ソーシャルメディアサイトXに「ヌーランドほどこの戦争を推進している人物はいない」と書き込んだことだ。そう、彼女ほど、リベラルデモクラシーの「裏技」、すなわち、必要があれば戦争を厭わない、リベラルデモクラシーをウクライナに普及させようとした人物であったのだ(コロンビア大学の教授にも就任した彼女は給与の二重取りをしているのだろうか?)。
NEDは、世界中の民主主義制度の発展と強化に貢献する、独立した非営利の助成財団である。 議会からの年間予算により、NEDは100カ国以上で2000以上の助成金を提供している。 NEDの助成金プログラムは、民主主義研究国際フォーラム、ジャーナル・オブ・デモクラシー、レーガン・ファシル・フェローシップ・プログラム、世界民主化運動、国際メディア支援センターによって補強されている。
だが、おそらくNEDもまた、「検閲産業複合体」の一角として、マスクがトップを務める「政府効率化省」の標的になるだろう。トランプは、リベラルデモクラシーに批判的であり、マスクも同じだからである。
すでに研究者も標的に
「検閲産業複合体」を支えてきた研究者はすでに標的となり、打撃を受けている。2024年5月、トランプの元顧問であるスティーブン・ミラーが率いる保守派の支持団体(America First Legal)は、ルイジアナ州の連邦地方裁判所に集団訴訟を起こした。対象は、スタンフォード大学、クレムソン大学、ニューヨーク大学、ワシントン大学、ワシントンの超党派の非政府組織である大西洋評議会、ジャーマン・マーシャル基金、市民権に関する全国会議、サンフランシスコのウィキメディア財団、オンライン・ディスインフォメーションを調査する会社グラフィカなどである。有害とされるコンテンツの研究者や技術企業の広告収入を遮断するために共謀し、反トラスト法に違反したというのだ。さらに、COVID-19のパンデミックに関する政策や、2020年の選挙結果を含む米国の政治システムの完全性に関わる「好ましくない言論の検閲」を、各団体に対して非難している。
この集団訴訟を起こしたグループは、スタンフォード大学インターネット観測所の2人の研究者、ワシントン大学の教授、Kate Starbirdらを被告に指名した。訴訟が進めば、彼らは裁判を受けることになり、告発が支持されれば民事賠償を請求される可能性もある。America First Legalの社長であるミラーは、この訴訟は「検閲産複合体の核心を突いている 」として、被告らを血祭りにあげることで、検閲産業複合体の勢力を弱体化させようとしたのである。
この結果、2024年6月14日付の「ワシントンポスト」が、「スタンフォード大学のディスインフォメーション研究グループ、圧力に屈して崩壊」という記事を公表するまでになる。大学側は組織の解体自体は認めていないが、助成金が集まらないなかで活動休止に追い込まれた。
日本の不可思議な動き
ここまで紹介したように、トランプ政権の発足で、国家や国家支援に基づく検閲が断固として撤廃されつつあるようにみえる。不可思議なのは、日本では、こうした流れとは逆行して、ファクトチェックを行う機関が総務省の支援を受けて育成されているようにみえることだ。「知られざる地政学」連載(62)「ディスインフォメーションをばら撒くNHK」(上、下)で紹介したように、あるいは、拙著『帝国主義アメリカの野望』で指摘したように、日本ファクトチェックセンター(JFC)を運営する一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)はきわめて由々しき機関である。誤ったディスインフォメーション理解を広げて、真偽や正誤についてのファクトチェックを行うことを正当化しているからだ。
ファクトチェック団体を考察した論文によると、「ほとんどの団体は収入をGoogleやMetaなどの大手プラットフォームやジャーナリズムや民主主義を支援する欧米の財団などからの支援に頼っている」という。パブリシャー、すなわち、情報を提供する仲介者からカネをもらって、ファクトチェックをするという姿勢自体に「腐敗」のニオイがする。
論文では、インターナショナル・ファクトチェッキング・ネットワーク(IFCN)の認証を受けた機関が真っ当なような印象を与える。JFC自体も認証機関であるのだが、そもそも誤った定義の上に成り立つファクトチェック機関など、カネ儲けの手段にすぎない。
すでに何度も指摘してきたように、ディスインフォメーションの根幹は、「騙そうとする意図」であり、必要なのは騙されないようにする情報リテラシー教育なのだ。正誤を決める基準は権力に大いに依存しているから、正誤の判断を少なくとも総務省のような公的機関の支援を受けているJFCが行うのは笑止千万だ。
真偽についても、そう簡単に判断することはできない(この点については、拙著『サイバー空間におかる覇権争奪』を参考にしてほしい)。だからこそ、安直なファクトチェックはきわめて危険なのである。とくに、ファクトチェックをビジネス化しようとする場合、その判断は明らかにカネの方向に「ブレる」ことになるだろう。
TikTok問題
最後に、検閲とは少し論点がずれているが、昨今、注目されているTikTok問題についても書いておきたい。
先に紹介した大統領令はいわば、「トランプ大統領が大統領執務室からオンラインコンテンツの節度に対する闘いを継続する意思を示すものだ」と、WPは指摘している。そのうえで、この命令は基本的に政府に対して「ソーシャルメディアに干渉するな」と言っているのだとする、カリフォルニア大学教授デビッド・ケイの意見が紹介されている。
他方で、外国、とくに中国政府がかかわっているとされるTikTokについては、その利用自体を禁止するかどうかという問題が脚光を浴びてきた。同じSNSであっても、外国が関与するSNSについては、干渉するのが当然とみなしていることになる。
TikTokをめぐる騒動については、拙著『帝国主義アメリカの野望』のなかで詳しく説明したので、ここでは繰り返さない。ただ、2025年に入ってからの出来事についてだけ簡単に概観してみよう。
ジョー・バイデン大統領の任期最終日に施行された「外国の敵対者によって管理されたアプリケーションから米国民を保護する法律」(PAFACA)は、「外国の敵対者」によって管理されたアプリの「配布、維持、更新」を違法とし、TikTokを名指しで挙げている。1月17日、最高裁は同法を支持し、TikTokの法的申し立ては却下され、中国企業が所有する動画アプリは1月18日に閉鎖を余儀なくされた。しかし、そのブラックアウトは数時間しかつづかなかった。だが、トランプが解決策を模索する意思を示したため、TikTokはサービスを再開する。翌日、TikTokは1億7000万人のアメリカ人ユーザーのために復活した。トランプはホワイトハウスに復帰した初日、TikTokアプリに75日間の執行猶予を与える大統領令に署名した。彼の行政命令は司法長官に対し、75日間PAFACAを執行しないよう指示している。
PAFACAの禁止措置を逃れるには、TikTokは中国企業ByteDanceとの関係を断つ必要がある。同社は長い間、TikTokは売却対象ではないと主張してきた。このアプリの買収は、民間企業を厳しく管理する中国政府に反対されている。中国の当局者は、アメリカがTikTokを買収しようとしていることを「略奪」と表現し、このアプリの推奨アルゴリズムを輸出できない機密技術に分類している。
トランプは1月17日、中国の習近平国家主席との電話会談でTikTokについて言及した。その数日後、トランプは、中国がこのアプリの販売を阻止すれば「ある意味で敵対行為」であり、関税が課される可能性があるとした。中国政府は、イーロン・マスクを潜在的な買い手、または他社による買収の仲介者として検討していると言われている。「自動車メーカーのテスラを通じて中国に投資しているマスクは、中国当局にとって信頼できるパートナーか、あるいは影響力を行使できる相手であることを示唆しているのかもしれない」と、The Economistは指摘している。トランプは、別の買い手候補として、TikTokがアメリカでクラウドサービスを提供しているオラクルのラリー・エリソン会長を挙げている。さらに、1月27日の夜、トランプはマイクロソフトがTikTokの買収を争っているとのべた。
どうやら、TikTok禁止問題は、検閲にまつわる問題というよりも、米中間の覇権争奪にかかわる問題としてクローズアップされているようにみえる。そう考えると、中国政府としては、TikTokが禁止になれば、中国ではFacebookやYouTubeなどの米国のソーシャルアプリをすでに禁止しているから、別の米企業の報復措置を検討しなければならなくなるかもしれない。
なお、TikTokが利用不能に陥るかもしれないという危機に直面して、ソーシャルメディアアプリ「小紅書」(Xiaohongshu,しばしば「RedNote」と呼ばれる)の人気が急拡大している。このアプリは、上海に拠点を置く民間企業、行吟信息科技有限公司(Xingyin Information Technology)が所有している。もともと上海で女性向けのショッピングプラットフォームとして立ち上げられたRedNoteは、2024年7月時点で3億人以上のユーザーを擁する中国で最も人気の高いショートビデオアプリの一つに成長した。
ただし、「このアプリは、中国のソーシャルメディアプラットフォームすべてにみられるのと同じ厳格な検閲を課している」、という見方をWPは報じている。そうであるなら、TikTokと同じように、米国人の情報が中国側に遺漏する懸念を払拭できない。つまり、TikTokを潰しても、もぐら叩きのように別のアプリが問題化する可能性がある。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権とウクライナ戦争の行方 ~戦争終結に何が必要か~
☆ISF主催トーク茶話会:松田智さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:櫻井春彦さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:植草一秀さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)