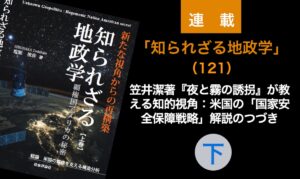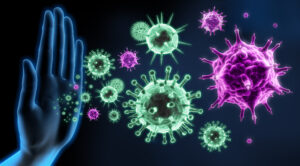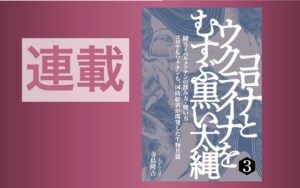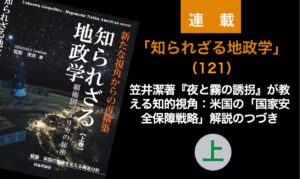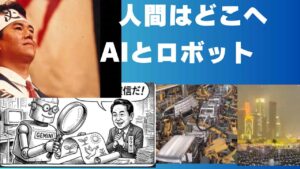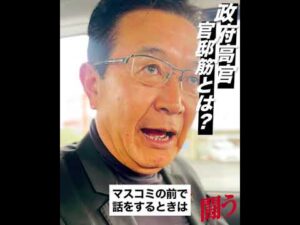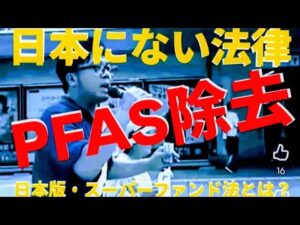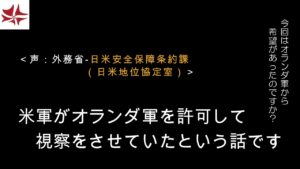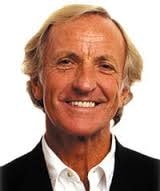登校拒否新聞15号:販促
社会・経済2月27日付で、「不登校の中学生の進路には「いまやたくさんの選択肢がある」違いや“戦略”を不登校専門家庭教師が解説」という記事がAERA with Kids+に載った。
中学卒業後の進路には、いまやたくさんの選択肢があります。教え子たちを見ていても、全日制の高校を選ぶ生徒、自分の体調に合わせて通いやすい時間帯を選択できる定時制高校を選ぶ生徒、通信制高校を選択する生徒、高等専修学校で専門性の高い技術を身につけながら提携先の通信制高校に通う生徒、そもそも高校進学自体を選択せず高等学校卒業程度認定試験(高認)を利用し、専門的な資格を取得しながら大学進学をした生徒、本当にさまざまです。・・・結論から言うと、どの道を選ぶにしても、中3までの学習範囲を中学卒業までに習得することが最重要事項。その先に進む鍵になります。
https://dot.asahi.com/aerakids/articles/-/250645
記事とはいえ、執筆者は『これだけで大丈夫!ずっと不登校でも1年で希望の高校に合格する方法』という本を昨年12月6日に出した植木和実氏。つまり、その「不登校専門家庭教師」本人である。出版社となる日本実業出版社の販促だろう。記事の本文は本からの引用である。おなじような記事が昨年12月7日付で、東洋経済オンラインにもあった。「入試や就活で「不登校が武器」に変わる深い理由」という題で、やはり抜粋記事だ。
https://toyokeizai.net/articles/-/842978
本の発売日の翌日に抜粋記事が載るのだから、やはり販促だ。広告記事について何か言うつもりはない。本の抜粋なのだから書いてあることは本と同じだ。では、なぜ登校拒否新聞として扱うかと言うと、いつものように記事がヤフーニュースで再配信された際にコメントが集まったからである。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a11036fe1ab5e6f052cc36af43440fa8cd52597c
コメント数としては35件と少ないけれども、その中に一つ長文で実例が紹介されていたので記録しておきたい。その前に、短いけれど一つだけ全文引用しておく。
中卒や商業工業高校で手に職つけて働ける時代がよかったなと思う。何が何でも大卒みたいな画一的な感じだから不登校も増えるんじゃないでしょうか。(匿名)
次号では工業高校から慶応大学に進学した例を扱う。士農工商ならぬ普農工商が流行語となった時代もあった。国民皆就学を達成した戦後の教育制度は六三制と知られる。男女平等、就学年限を定めての小中学校の義務教育制である。その制度はまた実質的に六三三制として始まった。新制中学校の第1期卒業生の高校進学率は50%に接近。それがどんどん上昇する中、普農工商と知られる時代に突入。しかし能力別の選別が問題となった。
旧制下であれば、小学校中退で職工という例はいくらでもあった。職工といえば、せいぜい小学校高等科を出ている程度で、つまり六二制といったところだ。小学校教員になるなら小学校を卒業してから師範学校に入る。中学校への進学というのはインテリコースだ。戦間期は中学相当の実業学校も増えたとはいえ、学校制度が複々線であるから「不登校」などという問題は生じない。それが、六三三制の単線型となると一律であるから欠席するリスクが高まり登校拒否も出てくる。そこで、画一的だから良くない。手に職をつければ、というような話になる。
しかしポスト産業時代である。例えば印刷工と言われた職工はもういない。活字を拾って植字する時代ではないからである。旋盤工のような金属工にしても工場が機械化して数は減った。半導体技師なんてのは高卒で稼げた仕事だが、これも海外との競争に負けたことで、工場が閉鎖されたとたん行き場を失っている。手に職をつける、という時代ではなくなっている。
いわゆる第三次産業が大卒を採用する。師範教育を否定して始まった戦後の教育改革により小学校の教員免許も大学で取ることに決まった。土台、六三三四制となる。画一化は避けられない中で、欠席者の存在をどう考えるか。私はむしろ公教育の画一性が破れているところに「不登校」という問題があると考えている。いつも言っているように画一性が問題なのではなく、画一性を担保すべき問題なのである。
さて、35件のコメントの中で気になった1件の実例である。長くなるが以下、丸ごと引用させていただく。途中で「コメ主、補足します」とあるのは自らのコメントに返信する形でコメントした本人が補足したことを意味する。
子どもが小〜中学で約6年間不登校でした。小学校5・6年で、なんとなく復学しかけたものの中学進学時に環境のギャップにやられ、以降復学の気配は絶望的に低い様子でした。自分次第で環境を選ぶ事ができることを理解した方がいいように思え、中2からまず親単独で進路のリサーチを開始。中2の夏〜秋は、本人の視野に情報を入れつつ、様子を伺いながら通信制高校の説明会に親子で足を運びました。2年生の内に気楽に見て回る事ができたこと、最終学年になる前に心構えをしっかり持って、状況や必要な判断を本人自身で理解したことはよかったです。本人も進路の不安が軽減し、安心したようでした。ここでの心構え次第で公立校の受験も視野に入ったはずですが、本人の捉え方と行動がそういう方向にはいかず。結局志望校の決定は中3の秋〜冬、全日制(学びの多様化学校)を受験し、今は毎日しっかり通っています。一連の過程を通して成長を実感しました。コメ主、補足します。子どもが選択した全日制高校(学びの多様化学校)は私立でした。選択肢があるだけありがたいことですが、だいぶ学費が嵩みます。通信制にしても高額です。ある程度は仕方ないと思いつつ、金銭的負担や選択肢の少なさは、もう少しなんとかならないものかと思ってしまいます。大学も本人の視野に入ってきており、成長をうれしく思う反面経済的には想定外の負担感です。ただ、どうにかして社会に出るまであと少しだけ時間が欲しい。学校環境に恵まれなかった子という認識なので(私の中で)、失った学生生活を少しでも取り戻す事ができるようにサポートをしたい気持ちが有ります。我が家にはもう1人不登校の子がいるので、2人分どうしたらいいのやら悩ましいです。(匿名)
以上、かなり長い間にわたって学校に通っていなかった例である。それが私立全日制高校に入学、通学できている。元記事は「中3までの学習範囲を中学卒業までに習得することが最重要事項」と植木氏の本を引いたものだが、このコメントには学力や試験についての記載がない。文科省の用意した「学びの多様化学校」(旧不登校特例校)に進学した例であるから、あまり学力試験は重視されていなかったのかもしれない。
旧不登校特例校はすべて義務教育学校であったが、今は高校も含まれているようだ。調べてみると、鹿児島城西高等学校普通科(ドリームコース)、NHK学園高等学校、星槎高等学校、精華高等学校普通科(フリーアカデミーコース)、岡山県美作高等学校普通科(Bloomコース)の5校がある。いずれも私立である。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387004.htm
コメ主さんが「金銭的負担や選択肢の少なさは、もう少しなんとかならないものか」と言っているように私立校であるから負担が大きい。その上、5校しかない。星槎高等学校は中学校も「学びの多様化学校」として指定されている。NHK学園高等学校は広域通信制高等学校である。尾木直樹氏がアドバイザーとして就任している。この2校は有名だろう。では、残りの3校は?それが募集人員を合わせても100名に満たない。その上、なくもがなの条件がついている。
美作高等学校普通科のBloomコースの受験資格としては「①岡山県内及び兵庫県佐用郡佐用町内に居住する者。②心因的理由により、年間の欠席日数が30日以上又は登校できていても、別室や校外の適応指導塾、フリースクール等に登校している者。且つ、医師の診断書の提出が可能な者」と説明されている。募集人員は20名程度。
http://www.mimasaka.ed.jp/006pdf/20240104bloom.pdf
城西高等学校普通科のドリームコースは「心因性不登校の生徒を対象とした全国初のコース」ということだ。募集人員は20名程度。専門機関の「心因性による不登校の診断書」が出願書類として必要だ。
https://kjh.ed.jp/mss/recruitment/
精華高等学校普通科のフリーアカデミーコースは「受験にはいくつかの条件があります」として次のように記してある。心因性(対人恐怖、社会不安等)の不登校であることを中学校が理解している(確認書の提出)。または、起立性調節障害、過敏性腸症候群、強迫症等の医療機関による診断書を有している。出願までに複数回の面談をおこないます(第3学年第1学期終了時より受け付けます)。※募集は専願30名で、入学試験は国語・英語・作文となります。
https://www.seika-h.ed.jp/course-fa/
いずれも「心因性不登校」と明記している。あるいは、診断書の提出が条件となっている。3校とも全日制高校の普通科であるから履歴書には堂々と高校名が書ける。ところが入学に際しては「心因性不登校」であることが学校と医師によって確認されていることが条件となる。この点に関して、この3校は星槎とN学とは異なっている。
では「心因性不登校」とは何か?
これがじつは拙著『不登校とは何であったか?心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(社会評論社)の主題なのだ。結局、心因性登校拒否が社会病理化されたものが「不登校」なのである。それを一口に言えば、「心因性不登校」となる。うつ病と診断を受けた教員が休職するのと同様、「対人恐怖、社会不安等」とによる心因性障害と診断された児童生徒が長期欠席している。それを学校が合わなくなったと騒ぎ立てる。そこで勢い「多様な学び」へと傾斜するわけだが、そこで不問に付されるのが「学校の勉強」だ。
植木氏は「中3までの学習範囲を中学卒業までに習得することが最重要事項」と言っていた。当たり前のことだ。しかし「寄り添う」などと説く教育学者たちがそういうことを言わないのだから私教育の立場から敢えて言うしかないのだろう。中学不就学の私もいわゆる五教科の勉強は完全にやった。「学び」などしていない。「学校の勉強」を自学自習した。「多様な学び」ではない。一様に学校の勉強をしただけ。であるけれども、それがどれだけたいへんなことか。英語をゼロから一人で勉強することかいかに難しいことか。それを志す子に辞書の一冊でも授けるのかと思いきや、まるで「勉強」の二字を禁句として、「休息の必要性」などと言う。
植木氏の本は具体的な勉強方法を説いたものとして貴重だ。目を通したところ頷ける部分もあれば足りない部分もあった。一つ決定的に欠けているものがあったけれども、それについては書評ということで別に書こう。似たような本としては、山田佳央氏の『不登校からの進学受験ガイド 受験で不登校を解決する方法』(2022年)がある。こういうコンセプトの本がここ数年の間にようやく出てきたというだけでも驚くべきことである。山田氏の本は副題に「受験で不登校を解決する」とあることから立ち位置ははっきりしている。
小生も『登校拒否論×反不登校論』(2017年)の「まえがき」において次のように書いた。従来の「不登校」論は学歴社会を敵に回すものであった。それは、学歴偏重の価値観や受験戦争に象徴される学歴社会のあり方が子どもたちを「不登校」へと追いやるのだという通念があったからである。しかし、小中学校にほとんど通わなかった「不登校」の人たちにおいても大学に進学した者は多い。大学全入の時代、それはまた「不登校」であっても進学が可能になった時代でもある。――と、まあ登校拒否新聞としても販促を試みてみた。現在、この本は「学校哲学叢書」の一冊として四六判でアマゾンから販売されている。
拙僧は塾に通ったこともなければ家庭教師に教わったこともない。フリースクールに籍を置いたこともない。自学自習である。学校に行かずに学校の勉強をする。登校と試験勉強で争ったって分が悪い。とどのつまり、受験に活路を見出すのには限度がある。であれば、独学の力を身に着けるチャンスとしてこの機を掴もうと思った。と言いつつ、思い出した。英語は最初、母親から教わったのだ。筆記体から教わったのだ。家庭教師や塾の利用もけっこうだが親が教えるという基本の教育も必要ではなかろうか。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。