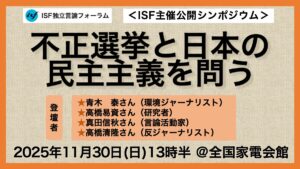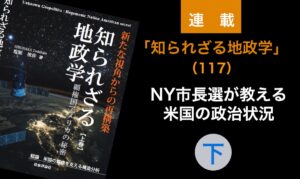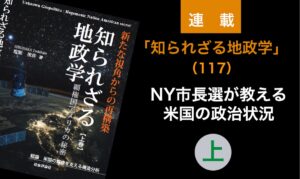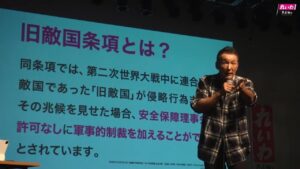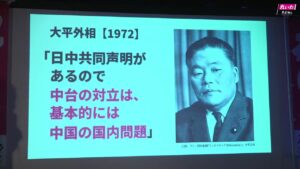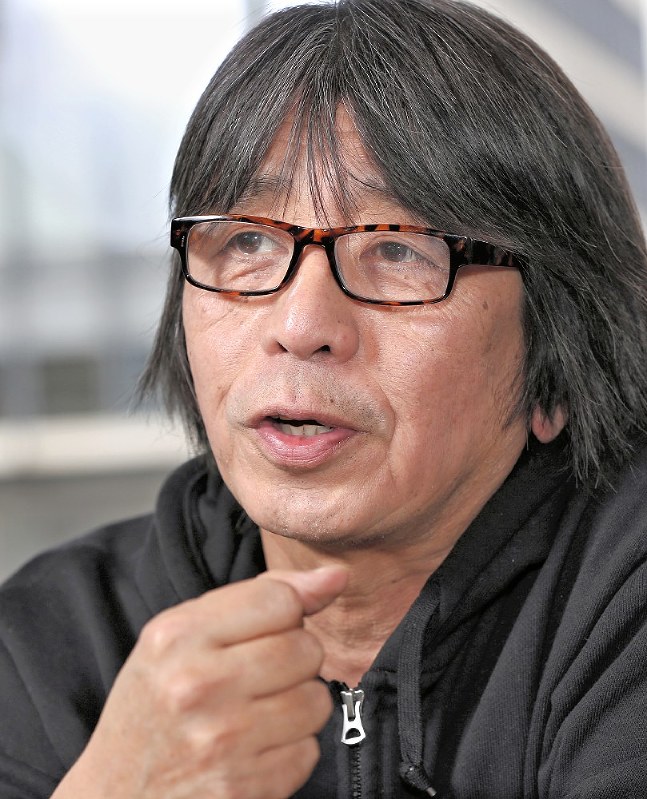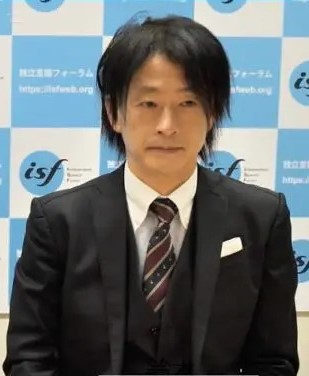情報流通プラットフォーム対処法の言論統制 ◉足立昌勝(紙の爆弾2025年5月号掲載)
社会・経済政治昨年五月十日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(「プロバイダ責任制限法」)の一部を改正する法律が第二一三回国会において成立し、同月十七日に公布され、一年後の、今年五月十七日までに施行される予定。この改正に伴い、法律名も、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(「情報流通プラットフォーム対処法」)に変更された。
この情報流通プラットフォーム対処法で対象となるサービスは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(二条一号)」と定義づけられている「特定電気通信」であり、それには、①ウェブサイトの掲示板への書き込み、②SNSのコメントなどが含まれる。したがって、不特定の者を対象としない、一対一のやり取りである電子メールは対象外である。
また、「他人の権利を侵害する情報」とは、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報(二条六号)」とされ、誹謗中傷や名誉毀損、プライバシーの侵害に該当するものを包含している。
情報流通プラットフォーム対処法の概要
情報流通プラットフォーム対処法は、誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、 ①対応の迅速化、②運用状況の透明化に係る措置を義務付けている。
大規模プラットフォーム事業者とは、迅速化及び透明化を図る必要性が特に高いものとして、権利侵害が発生するおそれが少なくない一定規模以上等の者のうちから総務大臣が指定する事業者であり(二十条)、大規模プラットフォーム事業者として指定された者は、総務大臣に氏名・住所等を届け出なければならず、さらに外国事業者の場合は、日本国内における代表者等を選任し、その者の氏名・住所等も届け出なければならない(二十一条)。これは、事業者の各種義務の履行を確保するためだといわれている。
一 投稿の削除対応の迅速化
この迅速化のために、改正法では、次の四つのことを大規模プラットフォーム事業者に義務付けた。①被害者からの申出の受付方法の公表(二二条)、②被害申出があった投稿の調査(二三条)、③調査専門員の選任(二四条)、④申出に対する通知(二五条)。
①は、被害者に過重な負担を課すものではなく、簡単に被害報告ができるようにするためである。②では、申告された情報が流布することにより、申告者の権利が不当に侵害されているかどうかを確認するために、必要な調査を行なわなければならない。③では、適正な調査をするため、専門的知識・経験を有する者を専門員として選任しなければならず、④では、投稿削除の申出があった場合には、必要な調査を行ったうえで、投稿の削除をするかどうか判断し、申出の日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、申出者に対し、投稿を削除した場合には削除した旨を、削除しなかった場合には削除しなかった旨とその理由を通知しなければならないとされた。
二 削除の申出に対応する運用状況の透明化
被害者からの申出への対応を透明化するために、次の三点が大規模プラットフォーム事業者に義務付けられた。
①投稿削除やアカウント停止の基準の公表(二六条)
この基準を公表することにより、どのような投稿が削除されるのかを、利用者が事前に知ることができ、投稿に際しての一つの基準となる。
②発信者に対する通知等の措置(二七条)
投稿の削除またはアカウント停止の事実については、その理由とともに、発信者に対して通知しなければならないとされた。
③措置の実施状況の公表(二八条)
投稿の削除やアカウントの停止の措置に関しては、毎年一回、被害申告の受付状況、削除等の実施状況などの実施状況を公表しなければならない。
三 勧告、罰則等の新設
情報流通プラットフォーム対処法では、前述した二点については、プラットフォーム事業者が行なわなければならない義務とされた。そこで、義務違反に対する罰則等も定められた。事業者に義務違反が疑われる場合には、総務大臣がそれに関する業務を報告させ(二九条)、勧告・命令を行なう(三十条)。
命令に違反した場合には、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に科せられ(三六条)、大規模プラットフォーム事業者に指定された者の住所等届出義務に違反した場合や業務報告義務に違反した場合には、五十万円以下の罰金が定められた(三七条)。
昨年十一月に、総務省事務局が出した「情報流通プラットフォーム対処法の省令及びガイドラインに関する考え方」には、対処法では定められていない事項についての詳細な考え方を明らかにしている。その項目の一つとして、「違法情報ガイドライン」がある。
そこでは、次のように二つの類型に分けて例示している。
1.他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合(権利侵害情報)
イ.対象となる権利・利益については、名誉権、名誉感情、プライバシー、私生活の平穏、肖像権、氏名権、パブリシティ権、著作権及び著作隣接権、商標権、営業上の利益について、どのような場合に各権利・利益の侵害が成立するかを明確化する。
ロ.情報の送信を防止する義務が生ずる場合としては、大規模特定電気通信役務提供者に送信防止措置を講ずる義務が生ずる場合として、「人格権侵害その他法令の規定に基づく差止請求」及び「条理上の義務があると認められる場合」を規定する。
2.その他送信防止措置を講ずる法令上の義務がある場合(法令違反情報)
ハ.対象となる情報として、わいせつ関係、薬物関係、振り込め詐欺関係、犯罪実行者の募集関係、金融業関係、消費者取引における表示関係、銃刀法関係、その他の区分に基づき、関係法令を分類するとともに、どのような情報を流通させることが各法令に違反するのかを具体的に示す。
ニ.情報の送信を防止する義務が生ずる場合については、大規模特定電気通信役務提供者に送信防止措置を講ずる義務が生ずる場合を規定する。
Yahoo、X(旧ツイッター)、Meta(フェイスブック等)などの大規模プラットフォーム事業者に掲載された情報により名誉が毀損された経験がある者は数多くいるであろう。しかし、その投稿に対しどのように対応してよいのか分からずに、対応しきれていない者も数多くいるであろう。
そのような現状を背景にして情報流通プラットフォーム対処法は成立したが、果たしてその立法事実に十分に対応しているのであろうか。
名誉を棄損された者からの苦情を受け付け、それを解決しなければならないことは当然である。しかし、その苦情の対象とされた情報が削除に値するものなのかについては、表現の自由の観点からも、十分に検討しなければならない。
削除の対象となるのか、またアカウントの停止に相当するのかについては、事業者の判断に任されている。その際の客観的な基準はあるのだろうか。それについては、総務省は、前述したガイドラインで対応するという。
しかし、このガイドラインなるものは、事例を示しているにすぎず、それに該当するか否かの個別的判断は、当該事業者に委ねられている。これでは、事業者の行なう個別的判断が恣意的であったか否かはわからない。この個別的判断に客観性を持たせることが大切なのだ。そのような判断基準がなければ、事業者ごとに判断が異なる場合も存在することになり、投稿者に不信感を与えるだけであろう。
法は、法は迅速化と透明化を求めているが、それは、被害を申し出た側からのものである。投稿した側の立場については、何らの配慮もされていない。
このような欠点を持つ法は、使い方によっては、事業者による投稿者の表現の自由を侵害し、一つの価値を強制しかねない。また、ガイドラインの作成を通じて、総務省の目指す価値が事業者に反映され、総務省の価値基準に統一された投稿内容しか許可されないことになってしまう。
この事実は、戦前における統一した価値の強制に行きつき、軍国主義に邁進した現実を想起させるものである。このような表現の自由の抑圧は、安倍内閣以降引き続き受け継がれてきた仮想敵国の構築と戦争推進国家への転換に向け、国民を思想的に統一しようとするものに他ならない。
体制側が決めた価値観に基づく内側の情報統制
二〇二二年十二月二十七日、総務省は、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」において提示された「誹謗中傷等の違法・有害情報に対するプラットフォーム事業者による対応の在り方について」の意見募集を行なった。この意見募集には多くの意見が寄せられたが、それが「情報流通プラットフォーム対処法」に反映されたか否か、また反映されたとした場合、どの程度の反映だったのかについては、不明である。
そこで、出された意見のいくつかを紹介する。
①プラットフォーム事業者が措置を講じることに伴って生じる言論空間への影響や経済的負担の観点についての意見
・外国の政府機関が著作権を理由とした削除申請を行なっている。もしこれが国際的で日本の立場や将来を左右する問題に関する発言や資料に対して『外国政府による越権的ともとれる日本側に立った発言や資料に対する削除要請』が乱発されたらどうなるのか。国際世論を形成する場の一つがインターネットである事を考えると非常に由々しき事態であることが分かる。プラットフォーム事業者に対して検閲や発信制限等を行なわせてはならないということを『良識』とすべき。
・表現をすること自体を生業としている芸能人などの場合、ひとたび権利が侵害されてしまうと、侵害案件とは全く関係のない表現活動に際しても、話題を蒸し返され、無限に侵害されてしまう状況にあることを留意。
・プラットフォーム事業者が措置を講じることにより、発信者に対して相当な萎縮効果を働かせることになるため、本観点は非常に重要である。
・インターネットの普及により双方向の情報流通が容易となり、実質的に言論の自由の確保に大きく寄与してきたが、他方、インターネット上の情報流通については技術の開発と提供が先行し、利用者に求められるモラルやリテラシーが追いついていない状況がある。インターネット上の偏見や差別、誹謗中傷に当たる情報が多数存在している現状を見たとき、プラットフォーム事業者が自ら提供するサービスにおいて、基本的人権が保障される適正な言論空間を維持することは、社会的な責務として極めて重要である。
・そもそも情報発信とデマや風評被害などは人類の情報発信の歴史からして常について回っていた問題であり、それが個人で出来るようになったからと言って特別な規制を施す根拠に乏しい。それらは事業者の問題ではなく、発信者の問題であり、マスメディア全般の捏造・歪曲・虚偽内容もまともに規制できない現状を放置し、SNSなどのプラットフォームを規制するのは誤り。 現在のSNSプラットフォームにおける世論とは、マスメディアへの不信が根底にあることを忘れてはいけない。
②AIによる自動処理
・AIの自動処理を必ずしも否定しないが、AIの利用には人間による確認も介在させるといった、AIと人間のバランスも必要であると考える。AIは必ずしも適切な判断をしない場合があるし、文脈まで読み取らないのが弱点だ。
・AIは、機能しているとは言い難い。機能しているなら、今頃状況は劇的に改善しているはずだ。不安定なAIに頼るのではなく、複数アカウント禁止や匿名コメント禁止など、根本的な解決法が有るはず。それにも関わらず、殆どのプラットフォーム事業者は経済面を優先して実施していない。事業者の怠慢。
③網羅的モニタリング
・プラットフォーム事業者に対し権利侵害情報の流通を網羅的にモニタリングすることを法的に義務づける場合、権利侵害をめぐる、プラットフォーム事業者側と投稿者側との責任の範囲を明確にする必要がある。
・法律による監視義務のない言論空間は、表現の自由に密接に関連するプラットフォームビジネスの基盤であり、オンラインでのユーザーの基本的な権利を保護するために不可欠であり、そもそもプラットフォーム事業者のサービスの規模・目的に応じてコンテンツモデレーションの程度も変わりうるのであり、法律における画一的な規制に馴染まないので、法令において監視義務を課することには、反対。
・それは、プラットフォーム上でクリエイターが創意工夫してコンテンツを作り出す等のために確保されるべき表現の自由への著しい委縮につながることが懸念される。
このように多くの疑問が提示されている。
この問題は、本来、表現者のモラル等の問題であり、プラットフォーム事業者の問題ではなく、ましてや、国が登場してくる問題では全くない。
衆議院に提出された質問主意書
昨年十月三日、立憲民主党原口一博議員から「インターネットにおける表現の自由の確保に関する質問主意書」が提出されたが、これに対する答弁は、いまだなされていないようである。
それは、インターネット上での投稿等において、表現の自由や通信の秘密を確保することが必要だとの観点からなされている。
「全世界に普及するSNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者は、そのユーザーに関する多くの個人情報や個人関連情報を保有し、その情報を用いて自らのマーケティング活動等の役務を提供し、莫大な利益を上げているとされる。また、それだけでなく、例えば前述のとおり、事業者による通信の秘密を侵す行為、言わば検閲を行う事案が現に起きるなど、言論の自由を奪う活動も見られる。こうした横暴な行為は、我が国の安全保障や国民生活の保護、加えて表現の自由の観点から決して看過できることではない。政府は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、電気通信事業法第四条やいわゆる独占禁止法を厳正に執行し、その行為やあるいは事業そのものを正すべきだと考えるが、どうか。政府の認識を問う。」
すでに述べたとおり、事業者が行なう削除やアカウントの停止は、投稿内容を把握し、その内容の是非を判断してうえで決定されるもので、まさに検閲である。それも、政府公認の下で、民間の事業者が行なうのだ。
国会は、なぜこのような無謀なことを通してしまったのであろうか。
四月号で問題提起を行なった能動的サイバー防御が国外のPCへの攻撃だとすれば、情報流通プラットフォーム対処法は、国家が決めた価値観に基づき、事業者自らが行なう情報統制であることを忘れてはならない。
これでは、外へ向けてのサイバー攻撃と内に向けての思想統制が合体化し、戦争推進体制が確立せれようとしていると判断することは、間違いなのであろうか。
質問主意書は、さらに、「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」が昨年九月十日に公表したとりまとめで提言した「情報の真偽を検証するファクトチェックの普及」を取り上げ、これは、「ファクトチェック団体に国が関与することにより、いわば官製ファクトチェック団体となって偽・誤情報対策の名を借りた検閲・言論統制を招くもの」であり、政府批判を封じるおそれがあることを指摘しているが、これは、前述したことをさらに鮮明化させるものとなろう。
本原稿は「紙の爆弾5月号」に掲載されたものです。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。
ISF会員登録のご案内