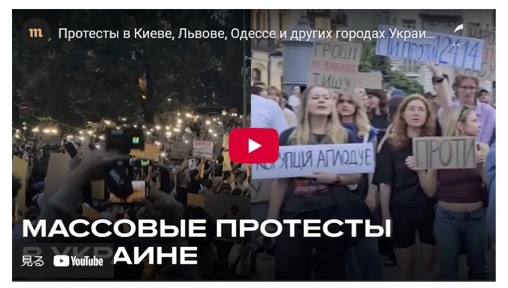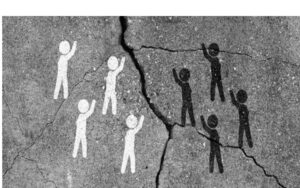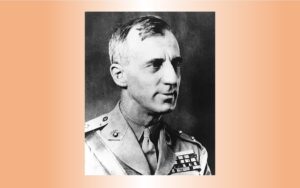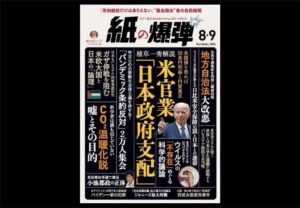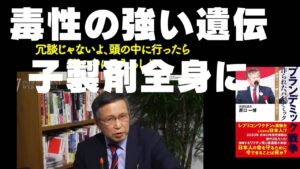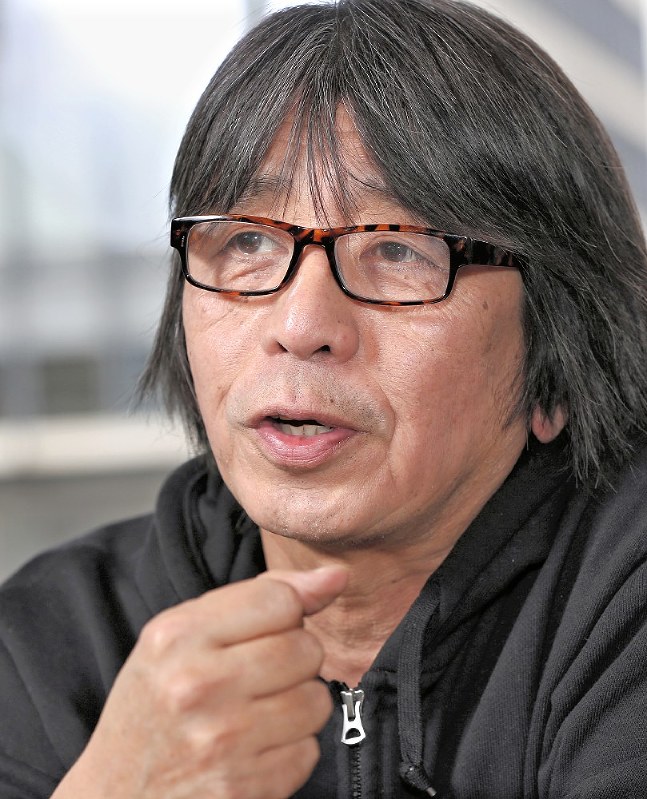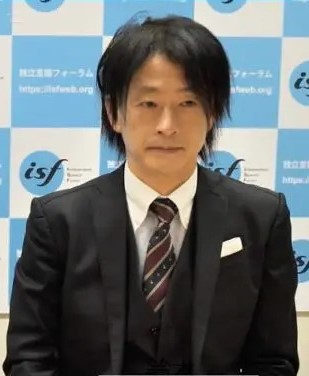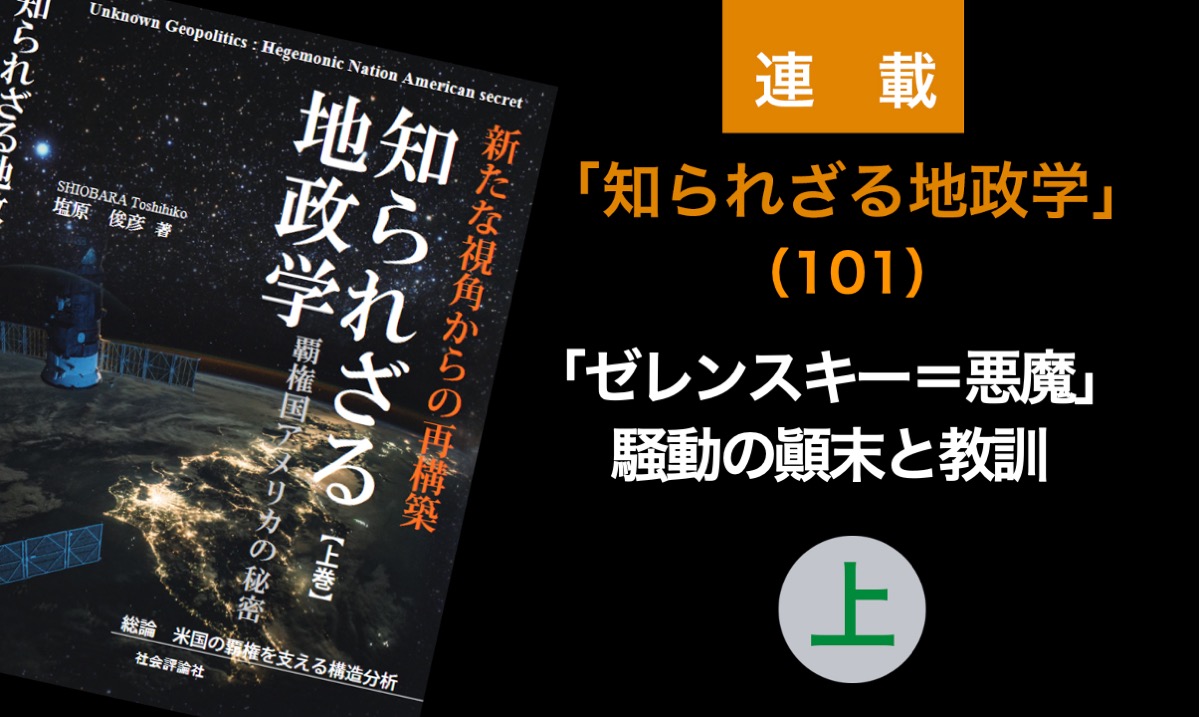
「知られざる地政学」連載(101):「ゼレンスキー=悪魔」騒動の顚末と教訓(上)
国際
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の政権はずっと腐りきっている。それにもかかわらず、ロシアに全面侵攻されると、その腐敗がないかのように、民主主義を守るという錦の御旗の元に欧米諸国や日本はウクライナを支援してきた。しかし、腐敗が蔓延してきた以上、その本質はそう簡単に改められるはずもない。
それどころか、2025年7月22日、ゼレンスキーは、ウクライナの二つの反腐敗機関を骨抜きにする法案を突然、成立させた。彼はその日のうちに署名し、翌日から施行させるという暴挙に出た。戒厳令下であっても、数千人規模の市民が抗議デモを2日間にわたって展開したり、わずかながら、西側の一部が批判したりした結果、今度は24日夜、その二つの機関の独立性を保証するための法案がゼレンスキーによって議会に提出された。同日、ゼレンスキーは英国のキア・スターマー首相とこの問題について協議し、英首相などの助言を受けて、その独立性を保証する新法案の提出に至ったのだ(FTを参照)。議会は休会中だが、31日に議会は審議する予定である。そこで、ここではこの一連の騒動について考察したい(なお、本稿脱稿時点は日本時間7月28日午前11時である)。
出発点
私は、講談社の運営するサイト「現代ビジネス」において、1年以上前の2024年6月25日付で拙稿「もはやここまで…汚職で腐りきったウクライナ政府の実情を全暴露する」を公表した。そのなかで、つぎのように書いたことがある。
「たとえば、タタロフ(大統領府:引用者注)副長官は2020年、NABU(国家反腐敗局)により、元議員マクシム・マイキタスの代理として法医学専門家に25万フリヴニャ(1万ドル)の賄賂を渡した罪で起訴されたことがある。この事件は、ゼレンスキーの子分であるイリーナ・ヴェネディクトワ元検事総長、ウクライナ保安局(SBU)、ウクライナの腐敗した司法当局によって妨害され、事実上破棄された。
2020年、オレクシー・シモネンコ副検事総長(当時)は裁判所の判決を口実に、タタロフ事件を独立したNABUから大統領管理のウクライナ保安庁(SBU)に移管した。NABUは、タタロフ事件は完全に同局の管轄内であるため、移送は違法であると考えている。その後、シモネンコはタタロフ事件を担当する検事団を交代させ、事件を妨害しようとした。2021年、裁判所はタタロフ事件の捜査延長を拒否した。シモネンコの部下である検事たちは、裁判にかける期限に間に合わなかったことで、この事件を事実上葬り去ったのである。」
こうした出来事を知っていれば、ゼレンスキーなる人物がいかに「悪人」であるかがわかるだろう。悪人だと強く感じるのは、彼が大ウソつきだからである。腐敗との闘いは、ゼレンスキーの2019年の大統領選キャンペーンの核心だった。就任後の2019年9月、彼は公の演説でウクライナ人に対し、NABUのホットラインを共有して賄賂を報告するよう促した。だが、これはポーズにすぎず、彼および彼の側近はどんどん腐敗していったのである。
アドルフ・ヒトラーも民主的な選挙で当選し、姑息な手段で独裁者となった。ゼレンスキーも同じ経路をたどることで、独裁者に近づきつつあることに気づいてほしい。彼は、先の新法とは異なり、議会が2025年8月15日に可決した戒厳令の延長と総動員に関する法案に25日になって署名した。目立たぬようにしながらも、90日間の延長によって、11月5日まで大統領の地位を守れる。戒厳令がつづくかぎり、任期切れでも大統領に居座れるからだ。
タタロフの事例からわかるように、ウクライナへのロシアによる全面侵攻が開始前でも、ゼレンスキーは民意を無視し、自分および取り巻きの利益を優先する専制政治を実践していた。だからこそ、私は拙著『ウクライナ3.0』、『復讐としてのウクライナ戦争』、『ウクライナ戦争をどうみるか』などで一貫してゼレンスキーを厳しく批判してきた、もちろん、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領も。だが、西側の政治指導者はゼレンスキーの裏面に目もくれず、「プーチン=悪人」説だけを流し、それにマスメディアも似非専門家も従った。その不誠実な連中の節穴がこのゼレンスキーの暴挙によって露見したことになる。
悪人ゼレンスキーを庇うボンクラ
The Economistは、西側は戦争の初期の流れを変えたゼレンスキーを英雄視するようになり、「そのために彼の失敗のリストが増えつづけていることに目をつぶるようになった」と指摘している。それだけではない。自らの過ちを認めず、あくまで「ゼレンスキー=善人」説に固執するようになっている。その典型例こそ、日本のオールドメディアだ。
たとえば、BS日テレの「深層News」は、7月25日、露骨にゼレンスキーの肩をもつ番組を流した(拙稿「いい加減にしろ!「深層ニュース」:ディスインフォメーションを垂れ流すオールドメディアの化けの皮」を参照)。こんな連中の垂れ流すディスインフォメーション(騙す意図をもった不正確な情報)に騙されてはならない。ゼレンスキーを「善人」とみなしてきたボンクラであっても、腐敗捜査・起訴を露骨に骨抜きにするゼレンスキーの手口によって、彼が「悪人」であることがわかったはずだ、よほどのボンクラでなければ。ところが、日本にあっては、ボンクラがテレビに出演して、何も知らない人々を騙している。
この原稿を執筆している28日午前の段階でも、日本のオールドメディアはボンクラのままだ。それどころか、この大ニュースを無視するか、分析記事や社説を掲載しないことで、過去の自らの報道を反省する素振りさえみせない。
民主主義の台座から転げ落ちたゼレンスキー
そこで、「フィナンシャル・タイムズ」(FT)が26日に公表した記事をぜひ読んでほしい。そのなかにある1段落を訳出したものを示してみよう。
「大統領選挙と議会選挙は戒厳令下で合法的に延期されたが、国民統合政府を樹立する試みはなく、野党と協議して決定することさえなかった。有能だが独立心旺盛な役人は、イエスマンやウーマンに取って代わられた。人気が出すぎた閣僚は脅威とみなされる。テレビ局は政府公認のニュース速報を流すことを強制され、自由な意見交換を妨げている。他の報道機関のジャーナリストは圧力や脅迫に直面する。ウクライナの対外情報機関が今週示唆したように、批判的なメディアの報道はロシアの情報操作として否定される。」
これがゼレンスキー政権の実態である。やっと、FTも本当のことを書かざるをえなくなったのだ。こんな政権だから、高いハードルの停戦条件を提示してプーチンに拒否させることで戦争継続をし、「選挙なしの独裁者」の立場を堅持しようとしている。ゆえに、記事の最後には、「ウクライナのロシアの暴政との闘いにおけるゼレンスキーの勇気と回復力のあるリーダーシップは、彼を民主主義の台座に立たせたが、今週、彼はその台座から転げ落ちた」と書かれている(前半はゼレンスキーを褒めすぎているが、後半はほぼ正しい指摘だ)。
ところが、日本のオールドメディアはFTの報じた事件の本質をまったく伝えない。彼らの報道が3年以上にわたって大間違いであった事実を認めたくないからだろう。
悲痛な叫び
つぎに何が起きたかについて説明しなければならない(ここからは、7月26日に「現代ビジネス」に公表された拙稿「ウクライナ各地でついに始まった「反ゼレンスキー」大規模デモ」の一部を多少加筆・訂正した内容となっている)。
まず、ウクライナ市民がゼレンスキーに対して猛烈に抗議する様子を映した下の動画①にアクセスしてほしい。7月22日の夜に、キーウ、オデーサなどで起きた大規模な市民による抗議の声が響いてくるはずだ。
動画① ウクライナで大規模な戦争が始まって以来初の大規模集会
(出所)https://www.youtube.com/watch?v=ANi4TMINwW8&t=17s
さらに、下の動画②では、市民は「ゼーリャ‐チョールト」(ゼレンスキー、悪魔!)と叫んでいる。反ゼレンスキーを叫ぶ抗議運動には、ペトロ・ポロシェンコ(前大統領)派や、キーウ市長のヴィタリイ・クリチコとその弟のヴォロディミルもいた。
23日にも、抗議デモは行われた。「ワシントンポスト」(WP)によると、大統領府の近くにあるイヴァン・フランコ広場にある劇場の前に、デモ参加者が集った。22日の夜に推定2000人が抗議したよりもはるかに多くの人が参集し、「恥を知れ(ガンバ)!」と叫んだという。FTは、1万人規模の人々が23日に集まったと報じているほどだ。
動画② 「ゼレンスキー、悪魔!」、このようにキーウのデモ隊はゼレンスキーを罵倒した
(出所)https://vk.com/clips-212929382?z=clip-212929382_456271205
何が起きたのか?
2025年7月22日付の「キーウ・インディペンデント」の社説は、「ゼレンスキーはウクライナの民主主義を裏切った ― そして民主主義のために戦うすべての人も」という悲痛なタイトルであった。この日、ゼレンスキーは、議会が可決したばかりの法案、すなわち、ウクライナの主要な反腐敗機関である国家反腐敗局(NABU)と特別反腐敗検察(SAPOまたはSAP)の独立性を事実上、剥奪する法案に署名し、成立させたのである。ゆえに、社説は、「ゼレンスキー大統領は、個人的な権力を拡大するために、ウクライナの民主的制度を弱体化させるという選択をしている」、とゼレンスキーを断罪している。
事態の深刻さは、数千人規模の抗議デモが同日夜に行われたことでもわかる。「ニューヨークタイムズ」(NYT)は下の写真とともに、「これは、3年半にわたる戦争のなかで、同国で初めての大規模な反政府デモとなった」と書いている。22日深夜、ゼレンスキーが法案に署名したとのニュースが伝わると、人々は「ゼレンスキーは悪魔だ!」というスローガンを叫び始めたという(動画②を参照)。
ウクライナのキエフ中心部で、反汚職機関の独立性を剥奪する法案に反対する抗議デモで、ウクライナ語で「拒否」と書かれたスマートフォンをもつ女性 Credit…Alex Babenko/Associated Press
(出所)https://www.nytimes.com/2025/07/22/world/europe/zelensky-protests-corruption.html
米国と欧州主導で設立した二つの反腐敗機関
実は、腐敗していたヴィクトル・ヤヌコヴィッチ政権を米国主導のクーデターによって倒した後、米国は欧州諸国と協力して二つの反腐敗機関(2015年4月にNABU、12月にSAPO)を誕生させた。NABUは最高レベルの腐敗を調査し、その案件はSAPOが監督・起訴する。その後、高等反腐敗裁判所(HACC)において審理される。その目的は、贈収賄の疑いがある高官を調査・起訴できる独立した反腐敗機関を設立することだった。政治的に従属的で腐敗にまみれた旧来の法執行機関は、この任務を果たせないとみなされていたのである。
西側諸国は、第三国に反腐敗機関のようなNGOを設立することは慣例的にしばしば行っている。ただ、腐敗が蔓延し、大統領、首相、大臣まで腐敗している可能性が高いウクライナについては、大統領にも首相にも従わない、政府の管理下にない法執行機関としてNABUとSAPOが必要とされたのだ。逆に、ウクライナのナショナリストはウクライナの主権を侵害するものとして、これらの機関を目の敵にした。もちろん、賄賂で得たカネなどを隠すうえでも、西側による監視の目は不都合であったからである。
ウクライナでは、NABU のほかに、国家警察、国家捜査局(DBR)、ウクライナ保安局(SBU)、ウクライナ経済安全保障局(BEB)による一次捜査が行われている。各機関の捜査権限は、刑事訴訟法第 216 条に細かく規定されており、かつ各機関の捜査権限が重なる場合は、NABU の優越性が規定されてきた。さらに、検事総長は大統領によって任命されるため、政治色が払拭されていない。これに対して、大統領や他の法執行機関などからの政治的影響力を排除し、各機関の独立性を担保するために、外国政府・国際機関が選考プロセスに関与する仕組みがウクライナの法律で定められるようになった。NABU長官にもそれが適用されている(詳しくは、「ウクライナの司法制度と汚職対策」[32頁]を参照)。
米国や欧州は、反腐敗のための捜査、立件、裁判までを政治的干渉なしに可能な独立したルートを設けることで、腐敗の蔓延するウクライナの近代化や民主化につなげようとしたわけである。この条件は、ウクライナ戦争勃発後の2022年6月、ウクライナの欧州連合(EU)加盟を急ぐためにEUとウクライナが合意した七つの加盟条件の一つとなっている。すなわち、第三番目の条件として、腐敗との闘いをさらに強化し、とくに高官レベルにおいて、予防的かつ効果的な調査を実施し、司法手続きの結果と有罪判決の信頼性を示すことが明記されていた。SAPOの新任長官の任命を、公募の勝者を承認することで完了し、ウクライナNABUの新任長官の人事選考・任命プロセスを開始し完了することまで書かれていた。
「知られざる地政学」連載(101):「ゼレンスキー=悪魔」騒動の顚末と教訓(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)