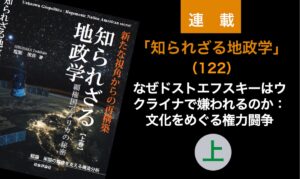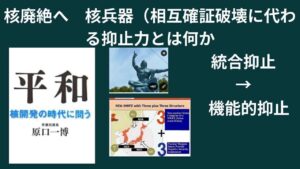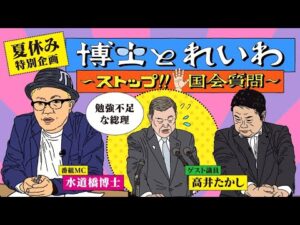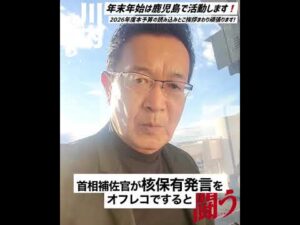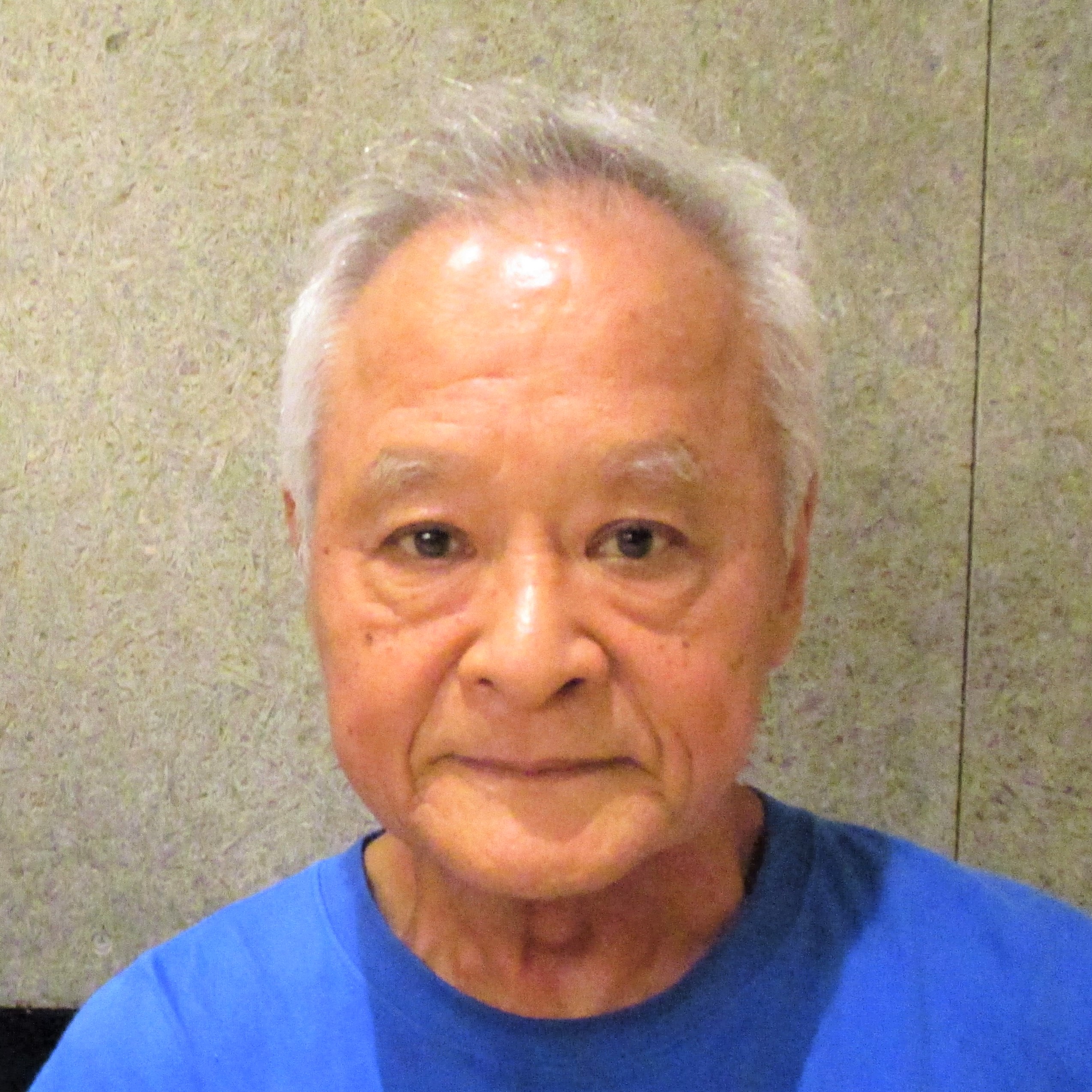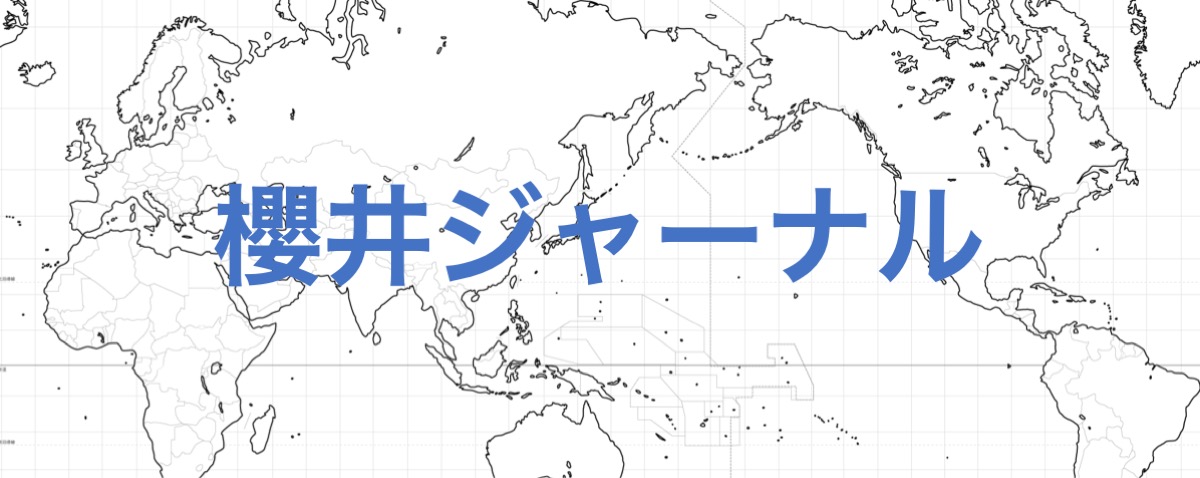
【櫻井ジャーナル】2025.09.08XML: チャベスが当選した直後から米国政府はベネズエラの体制転覆を試みてきた
国際政治アメリカ政府は確認石油埋蔵量が世界最大であるベネズエラに対する軍事的な圧力を強めている。
アメリカの軍事や外交を支配してきたネオコンは1991年12月にソ連が消滅した直後、世界制覇プロジェクトを始動させた。唯一の超大国になったアメリカは誰にも気兼ねせず、世界を軍事的に屈服させられると考えたのである。プロジェクトの内容は1992年2月にアメリカの国防総省のDPG(国防計画指針)草案として描かれている。
最初のターゲットはユーゴスラビア。第1期目のビル・クリントン大統領はユーゴスラビアへの軍事侵攻に消極的だったが、第2期目に方針が変わる。象徴的な出来事が国務長官の交代だった。戦争に消極的なクリストファー・ウォーレンが退任、ズビグネフ・ブレジンスキーの教え子であるマデリーン・オルブライトが就任したのだ。
オルブライトは1998年秋にユーゴスラビア空爆を支持すると表明、そして99年3月から6月にかけてNATO軍はユーゴスラビアへの空爆を実施した。4月にはスロボダン・ミロシェビッチの自宅が、また5月には中国大使館も爆撃されている。この空爆を司令部はアメリカ大使館にあり、指揮していたのはブルガリア駐在大使だったリチャード・マイルズだと言われている。
そうした中、1998年にベネズエラでネオコンの計画を揺るがす出来事があった。アメリカへの従属を拒否するウゴ・チャベスが選挙で勝利したのだ。その瞬間からアメリカ政府はベネズエラの体制転覆を目論み始めた。
まずジョージ・W・ブッシュが大統領だった2002年。工作の中心にはイラン・コントラ事件に登場したエリオット・エイブラムズ、キューバ系アメリカ人で1986年から89年にかけてベネズエラ駐在大使を務めたオットー・ライヒ、そして1981年から85年までのホンジュラス駐在大使を務め、2001年から04年までは国連大使、04年から05年にかけてイラク大使を務めたジョン・ネグロポンテがいた。
ホンジュラス駐在大使時代、ネグロポンテはニカラグアの革命政権に対するCIAの秘密工作に協力、死の部隊(アメリカの巨大企業にとって都合の悪い人たちを暗殺する組織)にも関係している。クーデターが試みられた際、アメリカ海軍の艦船がベネズエラ沖に待機していた。ウィキリークスが公表したアメリカの外交文書によると、2006年にもベネズエラではクーデターが計画された。
2007年にアメリカの支配層はベネズエラの体制を転覆させるため、「2007年世代」を創設、09年には挑発的な反政府運動を行った。こうしたベネズエラの反政府組織に対し、NEDやUSAIDといったCIAの資金を流す組織は毎年40004万ドルから5000万ドルを提供していた。
その2年前、つまり2005年にアメリカの支配層は配下のベネズエラ人学生5名をセルビアへ送り込んだ。そこにはCIAから資金の提供を受けているCANVASと呼ばれる組織が存在、そこで学生は体制転覆の訓練を受けている。このCANVASを生み出したのは1998年に組織されたオトポール!なる運動だ。
この運動の背後にはCIAの別働隊であるIRIが存在した。このIRIは20名ほどのリーダーをブダペストのヒルトン・ホテルへ集め、レクチャーする。講師の中心的な存在だったのは元DIA(国防情報局)分析官のロバート・ヘルビー大佐だった。
抗議活動はヒット・エンド・ラン方式が採用された。アメリカの政府機関がGPS衛星を使って対象国の治安部隊がどのように動いているかを監視、その情報を配下の活動家へ伝えている。このとき、アメリカは情報の収集や伝達などでIT技術を使う戦術をテスト、その後の「カラー革命」におけるSNSの利用にもつながった。(F. William Engdahl, “Manifest Destiny,” mine.Books, 2018)
ユーゴスラビアで2000年9月に実施された大統領選挙はこうしたCIA配下のグループに攪乱されて混乱、軍隊がミロシェビッチを力尽くで退陣させてアメリカを後ろ盾とするボイスラフ・コストニッツァを大統領に据えた。ブルドーザー革命とも呼ばれている。ベネズエラでも似たことを試みたわけだ。
体制転覆の企てが成功しなかった理由のひとつはチャベスのカリスマ性にあったが、そのチャベスが2013年3月、58歳の若さで死亡した。その後継者が現大統領のニコラス・マドゥロにほかならない。
2014年2月から5月にかけて反政府行動があったが、その指導者のひとりだったフアン・グアイドは2019年に大統領を自称する。この人物はカラカスの大学を卒業した2007年にアメリカのジョージ・ワシントン大学へ留学している。
ネオコンはウクライナのビクトル・ヤヌコビッチ政権を倒すため、2013年11月から14年2月にかけてネオ・ナチを使い、キエフでクーデターを実行した。
ヤヌコビッチの排除には成功したものの、ヤヌコビッチの支持基盤でロシア文化圏の東部や南部の人びとはクーデターを拒否、軍や治安機関の約7割が離脱、その一部は反クーデター軍に合流したことからネオ・ナチ体制は劣勢になる。そこで反クーデター軍に停戦を持ちかけ、受け入れられる。これが2014年の「ミンスク1」と15年の「ミンスク2」だ。
本ブログでは繰り返し書いてきたが、この「停戦合意」はクーデター体制の戦力を増強するための時間稼ぎにすぎなかった。後にアンゲラ・メルケル元独首相やフランソワ・オランド元仏大統領がそれを認めている。
戦況はロシアが有利なまま現在に至り、ウクライナ/NATO軍の敗北は決定的である。少しでもロシアにダメージを与えたいイギリスをはじめとするEU諸国は戦争の継続を目論んでいるが、アメリカは見切りをつけて離れ始めている。ロシアとの戦争をヨーロッパ諸国に押し付けて逃げようとしているようだ。
ウクライナから離れて東アジアでの戦争をアメリカは準備していたのだが、中国やロシアの対応が厳しく、ここにきて朝鮮も中露との関係を強めている。そうした中、アメリカはベネズエラに対する軍事的な圧力を強めている。
**********************************************
【Sakurai’s Substack】
※なお、本稿は「櫻井ジャーナル」https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/
のテーマは「 チャベスが当選した直後から米国政府はベネズエラの体制転覆を試みてきた 」(2025.09.08XML)
からの転載であることをお断りします。
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202509080000/
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202410130000/
ISF会員登録のご案内