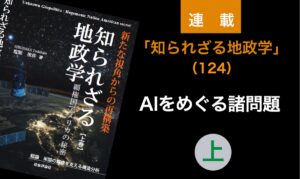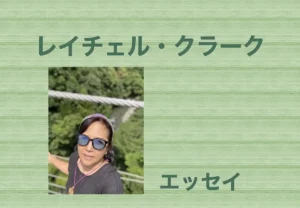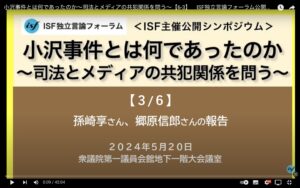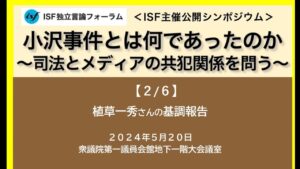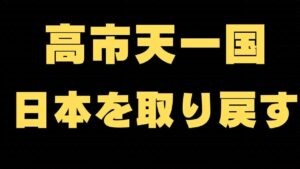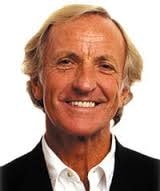「令和の米騒動」の正体その裏で進む複数の危険事態 植草一秀/文責=紙の爆弾編集部(下)
社会・経済政治「令和の米騒動」の正体その裏で進む複数の危険事態 植草一秀/文責=紙の爆弾編集部(上)はこちら
※この記事は、(月刊『紙の爆弾』2025年8・9月合併号掲載。最新号情報はホームページ https://kaminobakudan.com/)転載です。
自公「5つの難問」と「103万円プロレス」
さらに、私たちが気をつけなければならないことがあります。それは、参院選を前に「米騒動」のドサクサに紛れて進行中の複数の事態です。
昨年10月の総選挙の結果、自公政権与党の衆院議席が過半数を割り込みました。過半数233人に対して獲得議席が215。選挙後に無所属で当選した裏金議員等の6名が自民会派に入っても12足りないという状況です。
そこで自公政権は、7月20日投開票の参院選で、合計5つの難問に直面しました。その1つは、いま述べたとおり政権交代が起こりうる状況が生まれてしまったこと。2つ目は、参院選も衆院選の余波で敗北を重ねる可能性があること。加えて政策においても3つの重大な問題を抱えることになりました。まず、減税問題。総選挙では消費税減税に焦点が当たり、税率5%を掲げた国民民主党や廃止を訴えたれいわ新選組が躍進。共産党もそれ以前から5%を掲げ、立憲民主党も21年総選挙で消費税率5%を打ち出しています。こうして盛り上がった消費税減税を求める世論に、自公与党が対応を迫られています。
次に、政治と金の問題です。最大のポイントは自民党政治の根幹である企業団体献金の全面禁止です。自民党は企業献金で利益を上げるための政治勢力だと言って過言でありません。その全面禁止が、衆議院で過半数を確保している野党が結束すれば、少なくとも衆議院では可決できたはずでした。
3つ目が、米トランプ政権の高率関税政策への対応です。石破茂政権は日米交渉にあたり、いち早くアメリカに馳せ参じて機嫌をとろうとしたものの、結局は中国が優先され後回しとなり、これから先、何をもぎ取られるのかと戦々恐々の状態が続いています。
これら、自公にとって政局・政策の計5つの難問が発生した中で、現実に何が起きたのか。国民民主党の擦り寄りです。それにより、まず総選挙後、直ちに政権交代の可能性が消滅。さらに国民民主は2つの大きな方針を掲げ、その1つ「103万円の壁」が世間の話題をさらい、消費税減税論がかき消されました。
私はこれを「103万円プロレス」と呼んでいます。所得税の課税最低限が「103万円」から「160万円」に引き上げられ、これが手取りを増やしたとされるものの、大騒ぎに大騒ぎを重ねたにもかかわらず、2025年度の所得税減税規模は0.7兆円。「しょぼい減税」にすぎません。しかも、年収200万円以上の人の基礎控除の上乗せは2026年度までの2年間限定。27年度以降も継続するのはわずか300万人ほどにとどまります。
一方で、2024年度に「しょぼい」とさんざん批判を浴びながら実施されたのが定額減税2.3兆円でした。これは25年度には行なわれず、前年度比で増税になります。すなわち、2025年度は「103万円の壁変更」を含めて対24年度比で1.6兆円の増税ということになるのです。
「103万円の壁変更減税」が0.7兆円減税にすぎない事実も、2025年度所得税が前年度比で増税となった事実も、伝えたメディアは私の知るかぎりありません。他方、仮に消費税率を5%に引き下げる場合の減税規模は年間15兆円に達します。野党が結束すれば衆議院で可決できたのに、これが消え、代わりに決定されたのが1.6兆円の所得税増税でした。結局のところ、国民民主党が財務省と手を握り、八百長プロレス興行をしたというのが真相なのです。
さらに、国民民主は企業団体献金全面禁止法改正を潰しました。国民民主は自公政権が直面した政策課題の3つの危機のうち、対米交渉を除いた2つを消したことになります。こうして、いわば“用済み”となった国民民主党が、参院選前のゴタゴタで支持率を急落させたのは周知の通り。“自爆”とはいえ、昨年総選挙後のメディアの猛プッシュも併せて考えれば、この半年間の「上げ」「下げ」が、一貫したストーリーに沿った“演出”であったような印象を否めません。
残る対米交渉についていえば、先行きは不透明であるものの、日本政府は基本スタンスとして、国内自動車産業を重視して農業は軽視、日本国民ではなくグローバル資本の利益を基準に動いてきたのであり、歪んだ政策運営が維持される危険があります。
今回の対米交渉では「日本政府が切ってはいけない3つのカード」があります。「米輸入の拡大」「防衛費・駐留経費という名の米国への上納金増額」「日本政府保有の米国国債について規制を課されること」です。
米騒動では、国民世論を輸入拡大につなげる方向に報道が展開されています。日米交渉での米の輸入拡大を前提に「米騒動」が演出された可能性すら疑わざるをえません。グローバル資本と日本政府がタイアップして、昨年の総選挙から現在まで“劇場”が展開されているという見方が可能です。
「米騒動」への前述のような対策や米の備蓄量増大は、防衛予算の増額分を当てれば可能です。その防衛費増大も、現代のミサイル戦争においては何の意味もないどころか、逆に日本が攻撃されるリスクを高めることにしかなりません。また経済安全保障において、食料自給を高める政策を捨てて輸入に頼るのが日本政府の方針であるならば、なおのこと近隣国との友好を目指すべきであり、大きな矛盾を抱えています。
「米騒動」の裏で年金制度破壊の違憲立法
続いて言及すべきが、5月末に成立した年金制度改正法です。先の「103万円の壁」は、それを超えると所得税が課されて手取りの伸び率が下がるだけで、損をするわけではありません。
一方で「106万円の壁」「130万円の壁」という言葉もメディアに登場しました。こちらは社会保険料が発生する所得の境界線を指します。従業員51人以上の企業の場合、年収106万円、従業員5人以上の企業では130万円を超えると社会保険料が発生します。これが前者で3年以内、後者も段階的に撤廃され、被雇用者全員に社会保険料が課されることになりました。106万円を超えると16万円、130万円の場合は27万円ほど「手取りが減る」ことになります。これこそ重大な問題で、「103万円の壁」のどさくさに紛れて厚生労働省と財務省が進めたものです。
政府は「パート労働者が厚生年金等に加入しやすくなる制度変更」と説明しましたが、これは真っ赤な嘘。国民は加入・非加入を選べない、「パート労働者も強制的に加入させられる制度変更」です。「103万円の壁」とは明らかに異質であり、「106万円の“沼”」と呼ぶべきものなのです。この沼に嵌まらないためには、週の労働時間を1社あたり20時間未満に留めるしかありません。すると、社会の労働供給を減らすことになります。
さらに政府は、就職氷河期世代の将来の年金受取額(特に国民年金)の減少を穴埋めするために、厚生年金の積立金を流用することを盛り込みました。これは違憲立法に当たる可能性があります。当然ながら年金制度は、自分が積み立てたお金を将来受け取る前提のもと組み立てられています。その積立金が、知らないうちに公権力によって奪われ、別のところに流用されれば財産権の侵害です。これに立憲民主党が加担した意味は、極めて重大です。
公的年金制度が崩壊しないための最低限の鉄則は「インセンティブ・コンパティビリティ(誘引両立性)」です。つまり、年金に加入するインセンティブ(動機づけ)のある制度でなければ、人々はそれを忌避します。たとえば100万円を積み立てる場合、将来100万円以上を受け取れる見込みがないと、その制度に入る人はいません。自分で拠出した保険料が公権力によって、いつ抜き取られるかわからないのであれば、「そんな年金に誰が入るか」というのが当然の考えであり、年金制度が崩壊することになるのです。
憲法破壊の策動
最後に、憲法問題についても述べておきたいと思います。現在、自公や国民民主・維新・立憲民主の一部や参政党・日本保守党などで構成される、憲法改正を目指すグループが勢いを強めています。
6月までの通常国会における憲法審査会では、2つの大きな問題が明確になりました。1つは、憲法改正を規定した96条の国民投票制度についてです。そこで憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票等による過半数の国民の賛成を得て行なうと定めています
「衆参の3分の2以上の賛成で発議」というのは高いハードルであり、これを「硬性憲法」といいます。日本国憲法とは、簡単に変えてはならないという前提の下にあることを意味します。
その前提に従うならば、国民投票における「過半数の賛成」とは、全有権者の過半数だと解釈すべきと思われます。しかし、現在の国民投票法は「有効投票の過半数」としています。仮に最近の都道府県の首長選挙のように、投票率が3割程度であった場合、過半数とは全有権者の15%。それで憲法を改正していいのかを議論する必要があります。
加えて、2021年の国民投票法改正で、テレビやインターネット上のCMやSNS等の適正利用について規制を設けるための措置を、2024年9月までに講じることが附則で定められましたが、いまだになされていません。また、きわめて根本的な問題として、日本国憲法は96条で改定を認めているものの、憲法の制定までは認めていません。自民党草案のように国民主権や平和主義、基本的人権の尊重という基本原理を変えれば、それは改正の範囲を超えた“新憲法の制定”です。
もう1つの問題は、6月12日の憲法審査会の幹事会で、緊急時の議員任期延長の改憲骨子案が自公維国・有志の会の5会派から提示されたことです。憲法審査会規定で、審査会は公開かつ議事の記録が定められています。幹事会は、憲法審査会の運営に関する協議を行なう場であり、そこで憲法改正の議論を行なえば規定に違反します。要するに、公開・記録のない幹事会で、改憲の枠を超えた壊憲の議論が行なわれているのです。憲法破壊とは国家転覆行為に等しく、刑法第77条の内乱罪を、彼ら5会派に適用すべきだと私は思います。
こうして日本がいま、非常に危険な状況にあることがほとんど伝えられていません。自公と補完勢力による大連立も予想され、各党の動きに注意深い監視が必要です。
植草一秀(うえくさ・かずひで)
事実無限の冤罪事案による人物破壊工作にひるむことなく言論活動を継続。最新刊『財務省と日銀日本を衰退させたカルトの正体』(ビジネス社)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。
ISF会員登録のご案内
 植草一秀
植草一秀
植草一秀(うえくさ かずひで) 1960年、東京都生まれ。東京大学経済学部卒。大蔵事務官、京都大学助教授、米スタンフォード大学フーバー研究所客員フェロー、早稲田大学大学院教授などを経て、現在、スリーネーションズリサーチ株式会社代表取締役、ガーベラの風(オールジャパン平和と共生)運営委員。事実無根の冤罪事案による人物破壊工作にひるむことなく言論活動を継続。 経済金融情勢分析情報誌刊行業務の傍ら「誰もが笑顔で生きてゆける社会」を実現する『ガーベラ革命』を提唱。人気政治ブログ&メルマガ「植草一秀の『知られざる真実』」を発行。1998年日本経済新聞社アナリストランキング・エコノミスト部門1位。『現代日本経済政策論』(岩波書店、石橋湛山賞受賞)、『日本の独立』(飛鳥新社)、『アベノリスク』(講談社)、『国家はいつも嘘をつく』(祥伝社新書)、『25%の人が政治を私物化する国』(詩想社新書)、『低金利時代、低迷経済を打破する最強資金運用術』(コスミック出版)、『出る杭の世直し白書』(共著、ビジネス社)、『日本経済の黒い霧』(ビジネス社)、『千載一遇の金融大波乱』(ビジネス社、2023年1月刊)など著書多数。 スリーネーションズリサーチ株式会社 http://www.uekusa-tri.co.jp/index.html メルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」 http://foomii.com/00050