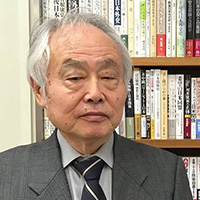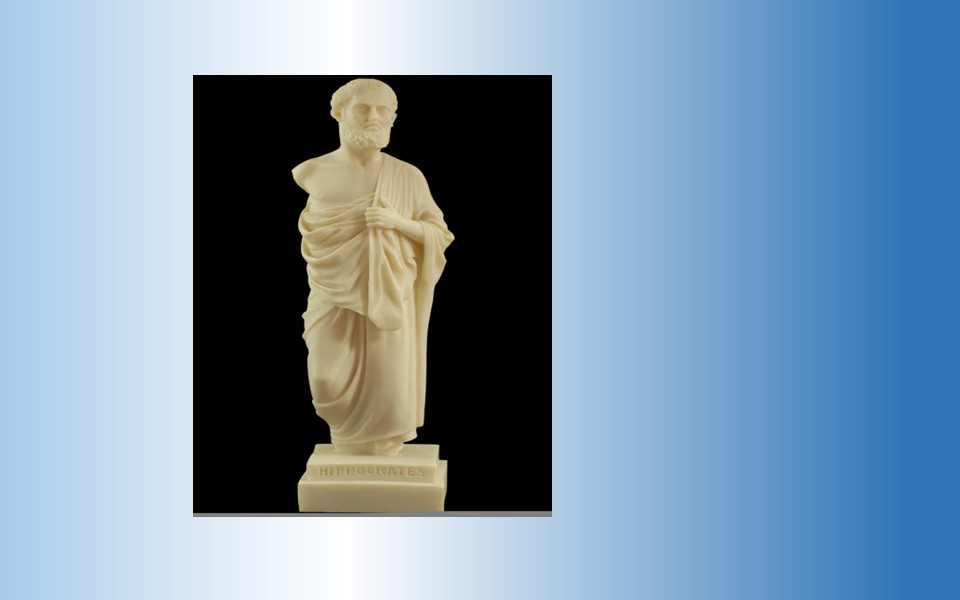
【評論】コロナワクチン副反応・後遺症・接種後死亡問題に、医学的観点から焦点を当てた映画『ヒポクラテスの盲点』―映画『WHO』との比較を通して 嶋崎史崇
映画・書籍の紹介・批評画像はpixabayの無料素材のヒポクラテス像。
https://pixabay.com/ja/images/search/hippocrates/
10月10日に公開された本作。題名は、患者に「害をなさない」という誓いを説いた古代ギリシャの医学の元祖の名前にちなむものです。本作の鑑賞を通して、その大原則が近年、大規模な仕方で蹂躙されてきたのではないか、という疑問が湧いてきます。
私が論じたことのある同じテーマの映画『WHO』(なるせゆうせい監督)と比較しながら、分析を試みます。
「評論:WHO(世界保健機関)とは何者・何様なのか? ―コロナ禍とワクチン禍の真相を掘り下げる映画『WHO?』が好評上映中」、2025年8月28日。https://isfweb.org/post-62460/
まず本作の監督は、1980年生まれの大西隼氏。現在はテレビマンユニオン所属の映像作家であり、NHKの『欲望の資本主義』などが代表作です。それに加えて、東京大学大学院理学系研究科で、タンパク質についての研究で博士号を取得した研究者でもある、という異色の経歴の持ち主でもあります。大学院時代は科学技術コミュニケーションにも取り組んでいたとのことで、その経験も生かされているといえます。
本作の特色は、コロナワクチンの副反応・後遺症・接種後死亡という医学的問題に絞っている、ということです。具体的には、次の通りです。
〇他の全てのワクチンを、2025年9月時点で約6倍も上回る「健康被害救済申請」の認定件数
〇厚労省データによると、大多数の年代で接種がコロナ感染予防に役立たず、むしろ逆効果になっている可能性が示唆されていること
〇厚労省が当初、接種箇所にとどまると主張していたコロナワクチンのスパイクタンパクという成分が、実は身体の様々な場所に拡散し、悪影響を与えている可能性
〇コロナワクチン接種後の死亡報告は接種翌日に集中し、その後少しずつ減少していることから、接種との因果関係が強く疑われていること
〇日本でコロナ禍が発生した1年目の2020年には従来通り日本の平均寿命は延びたが、21・22年には顕著な短縮に転じ、23年にまたわずかに伸びたこと。年齢調整をしても、21・22年の全死因死亡率の急増という傾向が見られること
〇国立感染研・厚労省の統計によると、コロナワクチン大量接種は感染者数や死者数の増加を必ずしも抑制せず、むしろ増やしているようにさえ見えること
〇従来のワクチンでは数人の死亡が発生したら接種が中止され調査が始まったが、コロナワクチンは千人単位になっても止まらない特別扱いになっていること
〇コロナワクチン接種と癌の関連を指し示す研究の紹介
〇ビタミンDがワクチン後遺症に有効、という厳密な学術的根拠を伴う見方
こうした焦点の当て方は、コロナワクチン薬害を中心的話題としつつ、次のような多様な問題にまで踏み込んだ『WHO』とは対照的です。
〇優生思想的な持論を持つビル・ゲイツから多額の資金提供を受けている世界保健機関(WHO)という国際組織の問題点
〇WHOがもくろむ国際保健規則・いわゆるパンデミック条約といった国際問題とそれに対する巨大デモ等の社会運動
〇東京や長崎で稼働するエボラウイルス等の危険な病原体をあえて扱う研究所の問題
〇新型のmRNAワクチンであるレプリコンワクチンの問題
本作のこうした問題設定とも呼応し、登場人物もまた、福島雅典・京都大学名誉教授、全国有志医師の会の藤沢明徳氏・児玉慎一郎氏(いずれも「ワクチン問題研究会」所属)、がんとワクチンについての重要な論文を発表した宮城県立がんセンターの虻江誠氏、唯一ワクチン推進派として出演に応じた森内浩幸・長崎大学教授、作家でもある大脇幸志郎氏といった医師らが中心です。それに加えて、分子生物学者の上田潤・旭川医科大学准教授、薬学者の上島有加里・東京理科大学客員研究員、免疫学者の新田剛・東京理科大学教授ら、隣接分野の専門家も登場し、本作の学術的な色彩を強めています。弁護士・記者として、SNSでのワクチン批判情報削除の異常性を指摘した楊井人文氏は、どちらかというと例外になります。過去の映像では、コロナワクチンを最も推進した政治家の一人である河野太郎氏も登場しています。
発言内容はともかく、堂々と出てきて薬害をほぼ全面的に否定する釈明をした森内氏はある意味では”立派”なのですが、出演を拒否した他の推進派医師らは、既に“逃亡”してしまった、とみられても仕方ないでしょう。
パンフレットではグラフや論文が出典情報として明示されており、大変貴重な客観的論拠を提供しています。
『WHO』の出演者は、WHOについての著作がある井上正康・大阪市立大学名誉教授や、小島勢二・名古屋大学名誉教授ら医師を中心にしつつ、原口一博・衆院議員、川田龍平・元参院議員、ユーチューバーの藤江成光氏、反WHO運動に取り組む林千勝氏・佐藤和夫氏・深田萌絵氏らまで多彩な顔触れでしたので、顕著な違いがあります。
厚労省前の日比谷公園出発で行われた数万人が参加したデモは本作では言及されませんが、代わりに健康そのものだったのにワクチン接種後に突如寝たきり状態になった若者の悲痛な叫び等が収録されていました。
本作と『WHO』のさらなる目立つ差異は、大手メディアによる扱いと、上映館、資金源です。『WHO』は既存メディアによってほぼ完全に不可視化され続けています。しかし本作は、これまでコロナワクチン薬害の追及に熱心だったとは到底いえない『東京新聞』が、10月9日付朝刊の文化娯楽面と10月10日付朝刊のシネマガイドで好意的な取り上げ方をするなど、相対的に注目されているといえます。コロナワクチン接種を一方的に推進してきたメディアは、本作をきっかけに、自分達のかつての一方的報道を真摯に反省し、本格的に検証、謝罪、ひいては基金を設けて自主的な補償もすべきでしょう。
『WHO』は、苦労してミニシアター系の上映館を増やしている状況ですが、本作はミニシアターだけでなくピカデリー、MOVIX等のシネコンでも大々的に上映される、という異例の厚遇ぶりです。
さらには、パンフレットによると、本作は文化庁文化芸術振興費補助金まで受けているとのことですから、「こうした国策に明確に批判的な内容でなぜ?」という疑問すら抱いてしまいます。本作のような学術的な内容の作品は許容範囲だが、WHOとその背景にあるグローバリズムの問題(「ワンヘルス」という一元的支配)や、日本で度々開催されてきた巨大デモに言及することは許されない、ということなのでしょうか…。
他方で、本作が医学的観点に論点を絞っていることは、上映時間の限定を考えれば、妥当であるとも評価できます。視点の違いがある両作品に優劣をつけることはできませんが、本作はコロナワクチン薬害問題の学術的側面を客観的に把握するためには、最適の作品の一つであると思います。本作を鑑賞して基本を押さえた上で、『WHO』で社会的・政治的背景や隣接する諸問題について学んでみる、という順番がいいのかもしれません。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
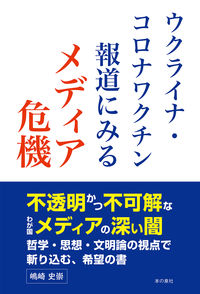 嶋崎史崇
嶋崎史崇
独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki