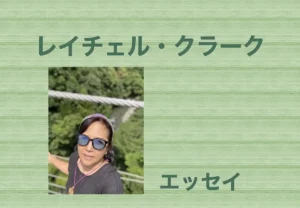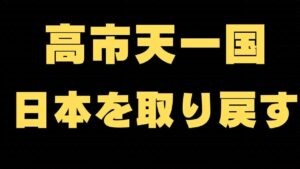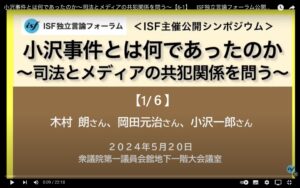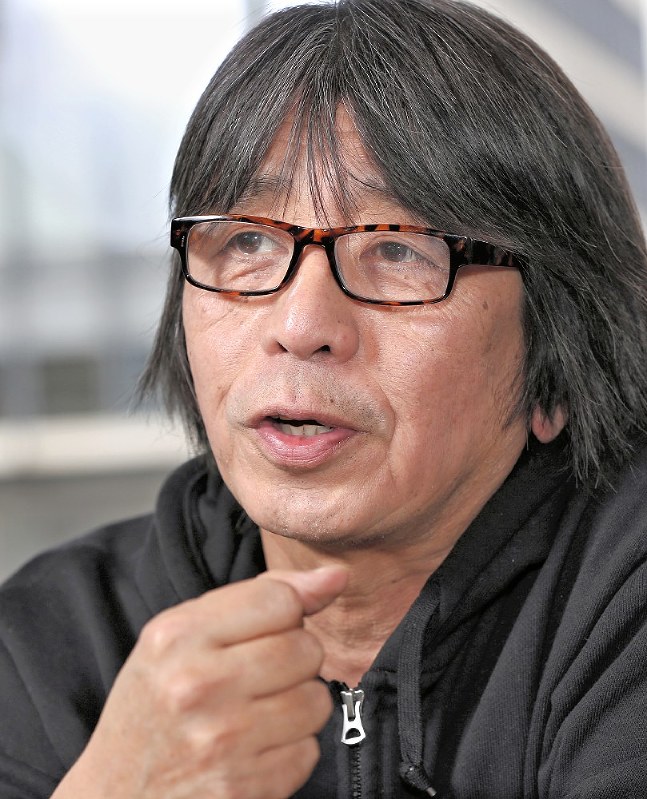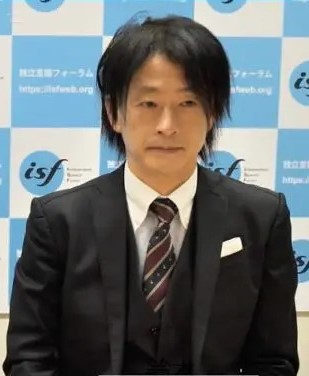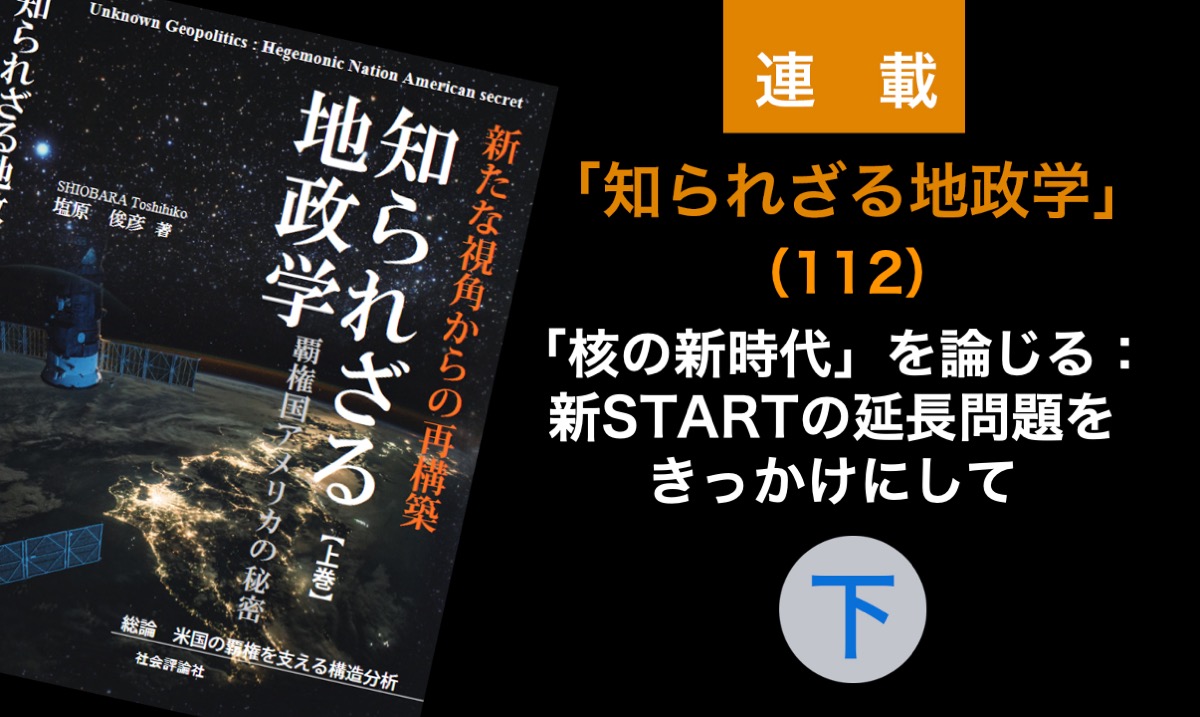
「知られざる地政学」連載(112):「核の新時代」を論じる:新STARTの延長問題をきっかけにして(下)
国際
「知られざる地政学」連載(112):「核の新時代」を論じる:新STARTの延長問題をきっかけにして(上)はこちら
「核の新時代」
『フォーリン・アフェアーズ』に2025年6月に公表された、マサチューセッツ工科大学の研究者ヴィピン・ナランとプラナヤ・ヴァディによって著された論文「核の新時代をどう生き抜くか 増大するリスクと蝕まれる制約の世界における国家安全保障」では、「(新STARTの)後継の協定がなければ、米国は半世紀ぶりに本格的な核軍拡競争に巻き込まれることになるかもしれない」と指摘されている。「ガードレールがないことが、新たな核時代をより危険なものにしている」というのが二人の基本認識だ。
米国はこれまで何をしてきたのだろうか。米国は核態勢をアップグレードしてきた。政府は15年間にわたり、米国の核「三位一体」を構成する陸・海・空軍兵器を更新するため、1兆ドルを超える核近代化プログラムに取り組んできた。たとえば、1970年代のミニットマンIII ICBMとオハイオ級核弾道ミサイル潜水艦は、最新のセンチネルICBMとコロンビア級核弾道ミサイル潜水艦に置き換えられている。新型ステルス爆撃機B-21は、敵の防空圏外から標的に向けて発射できる長距離核スタンドオフ巡航ミサイルを搭載する。2024年には、第5世代のF-35戦闘機が、ヨーロッパの地域抑止のために最新のB61-12重力爆弾の搭載を開始した。
しかし論文は、「このオーバーホールは2009年に考案されたもので、米国は中国と北朝鮮の核兵器拡張を予想していなかったどころか、説明すらしていなかった」とのべている。ロシアとの戦略的軍備管理協定のおかげで、米国は世界の核兵器備蓄が縮小しつづけることも想定していたのである。潜水艦を基盤とする核戦力を例にとれば、敵対国が米国本土を標的にするのを阻止するという核のサバイバビリティの後方支援であると同時に、敵対国のICBMを可能な限り多く標的にするためにも不可欠である
近代化計画によれば、(新STARTの制限なしに)最大336基のトライデント弾道ミサイルを搭載できる既存のオハイオ級潜水艦14隻は、最大192基のトライデントしか搭載できないコロンビア級潜水艦12隻に置き換えられるとみていた。しかし、これらの計画は中国と北朝鮮による核兵器の拡大を想定し、それへの対応として計画されたものではない。
さらに、「当時は核兵器による紛争の優先順位が低かったため、計画の多くの部分が遅れてスタートし、現在ではさらに遅れが生じている」、と論文は指摘している。センチネルICBMは予定より10年遅れそうで、レガシーのミニットマンIIIは少なくとも2050年まで維持する必要があるという。
米国の核戦略
論文は、「核時代の幕開け以来、米国の核戦略は、いかなる敵対国に対しても、米国や米国の同盟国に対する政治的・軍事的目標を達成するために核兵器を使用する実行可能な道筋がないことを納得させることに主眼を置いてきた」、と書いている。この戦略には三つの部分があるという。第一に、米国の核兵器は先制攻撃に耐え、その報復として攻撃者に確実な破壊を課すことができなければならないという大前提である。
第二に、可能な限り、攻撃者が米国とその同盟国に与える損害の量を有意義に制限できる必要がある。そのためには、攻撃側の核兵器が発射される前、あるいは発射された後に、できるだけ多くの核兵器を破壊する能力を維持しなければならない。したがって、エスカレーションを管理できる柔軟な地域核オプションに加え、米国は、敵の長距離兵器庫を破壊すると威嚇できる高精度の米国を拠点とする戦略核戦力を必要とし、限定戦争(激しい通常紛争のエスカレーションの段階として、1、2発の核兵器が戦場で交換されるかもしれない)が、はるかに破壊的な戦争に発展するのを防ぐ。被害を限定する能力は、米国の抑止戦略と同盟国に対する核保証の核心的要件であるとみる。
第三に、米国の核兵器は、弱体化した敵対国のさらなる攻撃や、小規模な核保有国による日和見的な侵略を抑止するために、最初の応酬の後にも十分な核戦力を保持できるよう、十分な規模と生存性を備えている必要がある。しかし、「現在の米国の核兵器のように、ロシアだけに対してこの三つの目標を達成するように設計された核戦力では、中国とロシアの両方に対して同時にこの目標を達成するには不十分である」というのがナランとヴァディの意見だ。とくに、中国の新型ICBMサイロの数とその地理的な広がり、そして中国が地域的な威圧を可能にする戦略に転換する可能性を考えると、「中国とロシアの両方を抑止できるようにするためには、米国はおそらく、より大規模で異なる配備の核兵器を必要とするだろう」ということになる。
その意味で、ウクライナ戦争の消耗戦化が中国とロシアの連携強化をより強くしている事態は米国にとって安全保障上の重大懸念事項と言える。カーネギー・ロシア・ユーラシアセンターの調査によれば、2023年、中国はG7の優先輸出規制リストに該当する商品の輸入の約90%をロシアに提供したという。膨大な輸入ギャップを埋めるこの中国のサプライチェーンは、ロシアの国内経済の維持や、枯渇した通常戦力の再建にも役立っている(なお、中国はウクライナにもドローン部品などを大量に輸出している)。その見返りとして、ロシアは宇宙、ミサイル防衛、早期警戒技術などの戦略的軍事領域で中国を支援している。
懸念される核拡散
こうした不安定な動きのなかで、米国の同盟国を含む多くの非核保有国は独自の核兵器開発を考えている。トランプ政権の日和見的な自国第一主義は、米国の核抑止の能力と意思に対する疑問としてすでに噴出している。米国の見放しを不安視する韓国は、現在、核拡散に関与する可能性がもっとも高いと言えるだろう(なぜか日本のオールドメディアは韓国の核兵器開発熱の高まりをしっかりと報道しようとしていない)。もちろん、そんなことになれば、日本の核兵器開発もないとは言えなくなる。
一部のNATO諸国もその候補となりうる。欧州では、イギリスとフランスの核兵器が、米国の関与の減少をある程度補うことができるが、これらの戦力は、追加の非核戦力と組み合わされたとしても、ロシアが同盟国に与えうる損害を制限することはできないとみるのが一般的だ。したがって、米国が提供する「核の傘」に取って代わることはできない。「その結果、ポーランドやドイツのような国々は、米国がもはや自国を守る意思も能力もないと確信すれば、自国の核保有を求めるようになるかもしれない」、と論文は明確に記している。
このようにみてくると、NPT体制がもはや風前の灯火となりつつあることがよくわかる。
「力による平和」
米国の近代化プログラムは、戦略核戦力と非戦略核戦力の両方を対象としている。最初に紹介したSIPRIによれば、戦略核戦力に関しては、LGM-30GミニッツマンIII ICBMに代わるLGM-35Aセンチネル大陸間弾道ミサイル(ICBM)、オハイオ級SSBNに代わるコロンビア級原子力弾道ミサイル潜水艦(SSBN)、B-2Aに代わるB-21レイダー重爆撃機が含まれる。米国はまた、これらの核運搬システムに関連する核弾頭と、包括的な核指揮・統制・通信インフラ構造の近代化も進めている。
2024年2月、アメリカ国家核安全保障局(NNSA)は、「過去1年間」(おそらく2023会計年度を指していると思われる)に「200以上の近代化核兵器」をアメリカ国防総省(DOD)に引き渡したと報告した。
第二次トランプ政権は「力による平和」を標榜している。それは、端的に言うと、Si vis pacem, para bellumということを意味している。すなわち、ラテン語で、「平和を望むなら、戦争に備えよ」ということだ。第一次トランプ政権において、トランプは2020年9月の国連総会で、米国は「平和構築者としての運命を全うしているが、それは力による平和である」と明言している(Robert C. O’Brien, “The Return of Peace Through Strength,” Foreign Affairs, July/August 2024を参照)。その「力による平和」は、あくまで「戦争への備え」としてある。
「ゴールデン・ドーム」プロジェクト
第二次トランプ政権が発足して注目されているのは、こうした「核の新時代」への対応策の一つとして、「ゴールデン・ドーム」プロジェクトを推進しようとしている点だ。トランプは1月27日、「アメリカのための鉄のドーム」という大統領令14186号を発出した。「弾道ミサイル、極超音速ミサイル、巡航ミサイル、およびその他の高度な航空攻撃による攻撃の脅威は、依然として米国が直面するもっとも壊滅的な脅威である」との認識から、「米国は、次世代ミサイル防衛シールドを配備・維持することにより、自国民と国家の共同防衛を図る」と記されている。このとき、意識されていたのが、イスラエルによって開発された「鉄のドーム」(アイアン・ドーム)だ。155mm砲弾、ロケット弾、ドローン(UAV)などによる攻撃に対する防衛のための近接防空をめざして構築された全天候型のシステムだ。米国の場合、もっとずっと規模が大きく、陸上だけでなく宇宙を拠点とする兵器も備えたもので、敵のミサイルが離陸するのを追跡し攻撃することができる何百、何千もの衛星などを使って、アメリカを攻撃から守ることを意図しているようだ。
5月20日、トランプは、ミサイル防衛シールド「ゴールデン・ドーム」の総工費が1750億ドル、完成までに2~3年かかり、「100%に近い」防御を提供するとのべた(The Economistを参照)
「大きくて美しい」税制法案に250億ドルの初期資金が含まれ、プロジェクトには総額1750億ドルかかるとした。議会予算局の試算では、20年間で5000億ドルを超える可能性があり、「2年半から3年」というトランプ氏の楽観的なスケジュールよりもはるかに長い時間がかかる可能性がある。
「ワシントンポスト」によれば、5月初め、米議会予算局は、新ミサイル防衛システムの宇宙ベースの迎撃ミサイルだけを配備・運用する場合、今後20年間で1610億ドルから5420億ドルの費用がかかると試算した。
ただし、ナランとヴァディが「第二次トランプ政権は野心的な「ゴールデン・ドーム」国土ミサイル防衛構造を追求しているが、この計画にはそれなりのリスクが伴う」と指摘するように、このプロジェクトの前途は多難である。たとえば、物理学者で構成される米物理学会の最近の報告書によれば、北朝鮮の開発した大陸間弾道ミサイル「火星18」ミサイル10発を確実に迎撃するためには、1万6000発の宇宙ミサイルが必要だという(The Economistを参照。なお、すでにその改良型の「火星20」が10月10日に披露された[下の写真])。さらに、米国の指導者たちが行動する前に30秒の判断時間を求めるとすれば、3万6000基の迎撃ミサイルが必要になるという。米国が極北の都市やアラスカ、中西部も防衛するのであれば、それよりも「多くの迎撃ミサイル」が必要になる。
他方で、敵対国がシールド回避のための戦術や技術に磨きをかければ、より高度なミサイル防衛が必要となる。

10月10日、朝鮮労働党の80周年を祝う大規模な軍事パレードで披露された「火星20」と呼ばれる新型大陸間弾道ミサイル (北朝鮮政府提供の写真:AP)
(出所)https://www.washingtonpost.com/world/2025/10/09/north-korea-kim-jong-un-military-parade/
予算がつけば動き出す
それでも、予算がついたことですでに「ゴールデン・ドーム」プロジェクトは動き出している。同プロジェクトへの参加申請は10月10日まで受け付けていた(2025年9月19日付「コメルサント」を参照)。ボーイング、ノースロップ・グラマン、RTX(旧レイセオン・テクノロジーズ)、ロッキード・マーチン、ブーズ・アレン・ハミルトン、L3ハリス・テクノロジーズといった米防衛産業の巨人がすでに関心を示している。イーロン・マスクの率いるSpaceX、高度なデータ処理システムを構築するPalantir、AI支援兵器システムを製造するAndurilといった著名なテクノロジー企業も参加する見込みだ。Palantirは、脅威を分析し、ミサイルの軌道を追跡するために必要なさまざまなシステムを制御するために、AIに支援されたプラットフォームの構築について議論しており、Andurilは、ミサイルを倒すためにレーザーのような実験的な迎撃装置を使用することについてかかわっている。SpaceXは、インフラを構築し、衛星を軌道に乗せる手助けをする可能性が高い。
9月8日付の「ニューヨークタイムズ」によれば、航空宇宙新興企業のヴァルダ・スペース・インダストリーズ、AI兵器企業アンドゥリル、航空宇宙企業レオラボのほか、Epirus、Ursa Major、Armadaといった小規模な防衛技術企業もこのプロジェクトへの参画をもくろんでいる。
よく知られているように、1980年代、ロナルド・レーガン大統領は 「スター・ウォーズ 」として知られるミサイル防衛システムを構築しようとした。しかし、このプロジェクトは失敗に終わった。同じことがトランプ主導の「ゴールデン・ドーム」プロジェクトでも起きる可能性は少なからずある。
私が興味深く思っているのは、プーチンと習が5月8日に採択した共同声明のなかで、このプロジェクトに言及していことだ。「新時代に入った包括的パートナーシップと戦略的協力関係の深化に関する共同声明」というものだ。このなかで、「双方は、戦略的均衡に反し、決定的な軍事的優位を確保しようとする米国の試みに対する深刻な懸念を再確認する」としたうえで、「これは主に、世界規模のミサイル防衛システムを構築し、その要素を世界のさまざまな地域や宇宙に配備しようとする米国の努力に関連している」と書いている。だからこそ、「国際科学月ステーションの創設、月および深宇宙研究、GLONASS(ロシアの全地球測位衛星システム)および北斗衛星導航系統(同中国版)の使用における協力など、ロシアと中国の共通の利益に合致し、各国の宇宙計画に含まれている大規模プロジェクトの実施を通じて、宇宙分野における長期的パートナーシップを強化する」という項目が共同声明に盛り込まれているのだ。
つまり、トランプの新構想が逆に中ロ連携を促す側面をもっていることになる。
大切な問題を真正面からオープンに議論せよ!
私は、ここで紹介したような問題について、真正面から議論できる場を国会に設ける必要があると思う。ここで紹介した程度の知識があれば、事態の深刻さを理解したうえで、日本という国家がどうすべきかを討議することくらいはできるだろう。
国家というわけのわからないものを盾にして、外務官僚やそれに踊らされるだけの政治家が勝手に決めるのではなく、核問題こそもっと開かれた場所で侃々諤々、議論すべきであると考える。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)