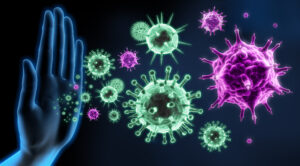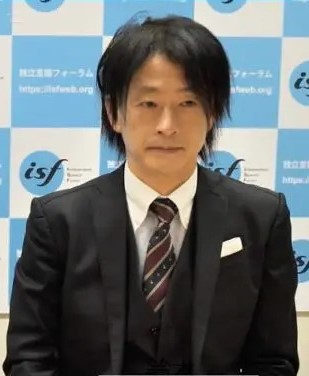「知られざる地政学」連載(125):地政学上の地殻変動について:ベネズエラの大統領「誘拐劇」を機に(上)
国際
アメリカのドナルド・トランプ大統領は2026年1月7日夜、「ニューヨークタイムズ」(NYT)とのインタビューで、自身のグローバルな権力に制限はあるかと問われ、こう答えた。「ああ、一つある。私自身の道徳観(morality)だ。私自身の心だ。私を止められるのはそれだけだ」。さらに、「私には国際法なんて必要ない」と彼は付け加えたという。
この発言こそ、2026年1月7日付のThe Economistの記事のタイトル「ドナルド・トランプの過激な正直さ」(The radical honesty of Donald Trump)に呼応するものかもしれない。この記事は、「政治家の公言する理念と行動の乖離は批判者にとって格好の標的となるため、トランプの露骨なシニシズム(冷笑主義)は彼に盾を与える」と書いている。トランプが「アメリカ第一」の基準に反していると愚痴る者もいるかもしれないが、「この点において彼は偽善者ではない」とも指摘する。「それは露骨な国益追求のためのアメリカの攻撃的行動を正当化するものである」と記事はのべている。
さらに、同じ記事において、こうしたトランプのシニシズムが国際法の化けの皮を剥いだことも指摘している。つまり、「国際法は、その欠点はあるものの、米国が旗振り役を務めるなかで、強制執行ではなく自発的な遵守によって機能してきた」だけの話であり、国際法とは名ばかりで、「偽善」(hypocrisy)であったと記しているのだ。
この偽善に基づいて、世界は第二次世界大戦後、80年以上の間、第三次世界大戦を経験せずにきた。2026年1月10日は、1946年1月10日、ロンドンで国連総会の第1回会期が開幕してから80年になる。その意味で、偽善であっても、平和の維持には一定の役割を果たしてきたと言えるだろう。だが、トランプはいま、この偽善を剥ぎ、力による支配、力による平和へと世界を導こうとしているようにみえる。
正直すぎる「柔軟な現実主義」がもたらす地政学上の地殻変動
トランプ政権は、自らの政策を、昨年公表した「国家安全保障戦略」において「柔軟な現実主義」(Flexible Realism)と呼んだ。「我々は、世界の諸国との良好な関係と平和的な商業関係を求めつつ、それらの国々の伝統や歴史から大きく異なる民主主義その他の社会的変革を押しつけることはしない」とした。これは、民主主義を輸出することで、米国の安全保障に資するとみなしたリベラルデモクラシー外交を否定する立場を意味している。
そのうえで、「我々は、このような現実的な評価に基づいて行動すること、あるいは統治システムや社会が我々と異なる国々と良好な関係を維持すること自体に、矛盾や偽善は一切存在しないことを認識し、断言する。同時に、志を同じくする友邦に対し共通の規範を守るよう促しつつ、そうした過程で我々の利益を推進していくこともまた、矛盾しないのである」と記されている。
私は、国際法の偽善を糺したり、民主主義の欺瞞を暴いたりする行為を否定しない。だが、問題はその先にある。トランプのいう「柔軟な現実主義」は80年以上つづいた世界秩序を破壊するものであり、これまでの地政学上の地殻変動をもたらす。おそらく戦争を近づけていると言えるだろう。そこで、今回はベネズエラ大統領夫妻の米国による「誘拐」事件で露わになったトランプ政権の外交戦略を再論する(米国の「国家安全保障戦略」については、本連載(120)(上、下)において考察した)。
「柔軟な現実主義」への批判
まず、法史学および思想史の研究者リンダ・キンストラーが1月9日付のNYTで公表した長文記事「トランプに攻撃の白紙委任状を与える理論 「柔軟な現実主義」の真の意味——国内外において」を参考にしながら、トランプ政権のいう「柔軟な現実主義」を批判したい。
記事は、「現実主義」の意味をトランプ政権ははき違えていると指摘する。現実主義の外交政策を提唱する学派は、世界は本質的に統治不可能であり、政治は結局のところ力の問題に帰着するという信念に根ざしている。これに対して、理想主義者は国際法が国家を善行へと強制する可能性を信じるかもしれないが、現実主義者はそのような夢想をほとんど重視したことがない。連載(92)「リアリズムから見たウクライナ戦争の停戦・和平をめぐる問題点」(上、下)に書いたように、この現実主義的アプローチの代表格はシカゴ大学のジョン・ミアシャイマー教授であり、日本では私もそのなかに属すると自負している。だからこそ、トランプ政権の「柔軟な現実主義」に強い違和感をもつ。
だからこそ、キンストラーは、「現実主義のさまざまな流派は豊富で時に矛盾しているが、トランプ政権はそのもっとも粗雑な形態の一つを体現している」と書く。「トランプとその側近たちは、海外での行動を正当化するために現実主義を掲げることで、それを米国独自の帝国主義の言い訳、好戦的な姿勢の口実として扱っている」というのである。
さらに、「彼らが理解していない世界政治の鉄則がある」という、ハーバード・ケネディ・スクールの国際問題教授、スティーブン・ウォルトの発言も紹介されている。「現実主義とは、競争の激しい世界において、単なる無意味な力の誇示ではなく、賢明に真の戦略的優位性を目指すことの重要性を理解することである」というのだ。
もっと単刀直入に言えば、まったく別の厳しい見方もある。キンストラーは、2025年10月に、How to Survive a Hostile World Power, Politics, and the Case for Realismを上梓した英バーミンガム大学のパトリック・ポーター教授の見方を紹介している。ポーターによれば、トランプ時代を定義するのは現実主義ではなく、その「腐敗した従兄弟」である「マハトポリティーク」(Machtpolitik)、すなわち「権力政治」であるというのだ。これは権力そのものを目的として追求し、「破壊、ニヒリズム、復讐による一種の暴力的な陶酔感」によって特徴づけられる。
おそらく、キンストラーが紹介した、スティムソンセンター(安全保障と政策研究に焦点を当てたワシントンD.C.に拠点を置くシンクタンク)の上級研究員エマ・アッシュフォードのつぎの発言が現実をうまく表現していると言えるだろう。「我々は30年間、極端なリベラリズムの行き過ぎた時代に過ごしてきた。その方向に大きく振り切れたため、軌道修正はほぼ必然だった。問題は、その修正がどのような形を取るかだ」というのがそれである。イラクとアフガニスタン戦争の苦い遺産に加え、中国の台頭と多極化世界の復活が、現実主義を政治の舞台に再び押し戻しているというわけである。
トランプ政権による過度に暴力的に修正しようとする状況を別言すると、「第二期トランプ政権は、まさに暴力的で世界的な「マハトポリティーク」(権力政治)の時代のはじまりを告げるかもしれない」ということになる。
ベネズエラで起きた現実
アメリカが帝国主義であることは、拙著『帝国主義アメリカの野望』のなかで詳述した。したがって、2026年1月3日にベネズエラで引き起こされたニコラス・マドゥロ大統領と妻の「誘拐劇」は、ドナルド・トランプ政権がまさに帝国主義を実践していることを示していると考えられる。興味深いのは、トランプによる暴挙が国家主権を蹂躙したにもかかわらず、非難や批判ができない国がたくさん存在するという現実である。つまり、依然として、何とか米国はヘゲモニー国家として君臨しているようにみえる。ヘゲモニー国家に従属している以上、米国の悪行を真正面から非難できないのだ。国際法の偽善が明確になった瞬間だ。
ただし、露骨な暴力の行使はいわば「伝家の宝刀」であるはずなのに、それを抜いてしまったことで、米国の本性という馬脚が露わになってしまった。「マハトポリティーク」のはじまりである。もう米国の同盟国は、「法の秩序」とか「民主主義」を守ることを「お題目」とすることはできないのかもしれない。そんなものを唱えれば、だれでも「大嘘」であるとわかってしまうからだ。もはや「力による平和」の時代に突入したのだ。
実際にベネズエラで起きたのは、石油をガブ飲みするトランプが描かれた下の写真が象徴しているかもしれない。トランプは1月9日、「米国とベネズエラ国民のためにベネズエラの石油収入を保管する」という大統領令に署名した。天然資源や希釈剤の売却による収益を米国の銀行システム内の特別口座(米国の場合、こうした口座の多くは外国人がニューヨーク連邦準備銀行に開設)に保管する必要性から、非常事態が宣言された。これにより、米国は、裁判所による判決によって他の者によって差し押さえられることなく、これらの資金を保管することができる。大統領令では、ベネズエラの資源の売却による資金は「米国内」での商業取引には一切使用されないと強調されている(第四条(b)- (i))。
同日、トランプはエクソンモービル、コノコフィリップス、シェブロンなど、米国の大手石油会社の代表者と会談した。トランプとしては、ベネズエラのエネルギー部門への1000億ドル規模の積極的な投資を行うところだが、民間企業は慎重な姿勢を示した。
ドナルド・トランプのベネズエラへの関心は、最後の石油が枯渇するまで衰えることはないだろう。
Фото: Marcos del Mazo / LightRocket / Getty Images
(出所)https://www.kommersant.ru/doc/8339129
米国による「西半球」支配
2025年12月4日夜、米国政府は「国家安全保障戦略」を発表した。今回の「誘拐劇」はこの戦略路線上にある。同戦略は、本連載(120)(上、下)において考察したように、戦略はもっとも優先順位の高い地域として、「西半球」(Western Hemisphere)を明示している。
これは、米国の外交政策上の核心的利益の確保と深く結びついている。①西半球が米国への大規模な移民を防止・抑制できる程度の安定性と適切な統治を維持することを確保したい、②麻薬テロリスト、カルテル、その他の国際犯罪組織に対して各国政府が我々と協力する半球を望む、③敵対的な外国の侵入や重要資産の支配から自由であり、重要なサプライチェーンを支える半球を望む、④戦略的に重要な拠点への継続的なアクセスを確保したい――という四つがその目標(利益)だ。そのうえで、戦略には「言い換えれば、我々はモンロー主義に対する「トランプ補則」(Trump Corollary)を主張し、実行に移す」とある。
この戦略をわかりやすく言えば、①米国に近い隣国を親米国家とし、②米国への移民やドラックの流入を阻止し、③有用鉱物資源の安定的なサプライチェーンとする――ために、西半球への米国のコミットメントを強化するというものだ。それを裏づけているのは、2026年1月4日のマルコ・ルビオ国務長官の「これが西半球だ。我々が暮らす場所だ―そして我々は、西半球が米国の敵対者、競争相手、ライバルたちの活動拠点となることを決して許さない」という発言だ。
さらに、トランプは1月5日、ホワイトハウスに戻るエアフォース・ワンでの記者とのやり取りのなかで、「モンロー主義は、制定当時は非常に重要だったが、他の大統領たち、その多くはそれを忘れてしまった」とのべたうえで、「私は忘れたことはない。決して忘れたことはない」と語った(BBCを参照)。つまり、1823年12月、米大統領ジェームズ・モンローが議会への教書のなかで、米国と欧州の相互不干渉の原則を表明し、ラテンアメリカ諸国へのいかなる干渉もアメリカに対する非友好的態度とみなすことを宣言したモンロー・ドクトリンに倣って、西半球への敢然たる干渉を宣言する「ドンロー・ドクトリン」(Don-roe doctrine)に基づいて行動したというのだ。これは、米国がこの地域でどのように自己主張するべきかというトランプ流のビジョンを示したものである。
トランプ自身、その場において、政権交代や国家再建に反対する過去の発言について問われ、「それは、我々の領域におけるドンロー・ドクトリンだ」とのべた。ただし、確認しなければならないことがある。それは、モンロー・ドクトリンが当初、欧州による西半球への植民地的介入を防ぐことを目的とした反帝国的なものだと考えられてきたが、その後、とくに1904年のセオドア・ルーズベルト大統領によって、ラテンアメリカ全域へのアメリカの介入を容認するものとなったことである。つまり、「ドンロー・ドクトリン」も、米国の権益がラテンアメリカにあると宣言しているのと同じだという点を忘れてはならない。
つぎに狙われるのはキューバ?
西半球に位置する国々のなかで、米国がつぎに標的にするのはおそらくキューバだろう。ただし、トランプはキューバが自壊するとみているようだ。前述したエアフォース・ワンでのトランクは、記者団に対して、「彼らが持ちこたえるつもりかどうかはわからないが、キューバにはいま収入がない。彼らはすべての収入をベネズエラから、ベネズエラの石油から得ている」と話した。「キューバは崩壊寸前のようにみえる」というのだ。つまり、米国政府が手出しをしなくても、手中に入るとみなしているように思われる。
他方で、NBCニュースとのインタビューで、トランプ政権のつぎの標的がキューバ政府かどうか問われたルビオは、「キューバ政府は大きな問題だ」とのべた。フロリダ州マイアミ出身の第二世代キューバ系アメリカ人である彼は、キューバの共産主義体制の終焉を精力的に提唱してきたことで知られている。
キューバのベネズエラ依存
トランプの言うように、キューバはベネズエラの援助に依存している。2026年1月5日付の「ニューヨークタイムズ」(NYT)によれば、ベネズエラとキューバは25年にわたる政治的・経済的パートナーシップを築いてきた。1999年にウゴ・チャベスが政権を握ると、フィデル・カストロがキューバに対して行ったように、何百万人もの貧しく権利を奪われたベネズエラの人々に力を与えようと社会主義革命を起こした。その結果、カストロは2002年のチャベスに対するクーデター未遂の際、自ら介入してチャベスを保護した。このため、チャベスやその後継者であるマドゥロは、キューバを財政的に支援することで恩返しをし、石油という経済的な生命線を提供して関係を深めてきた。他方で、燃料供給の見返りとして、キューバは数十年にわたりベネズエラへ医療団を派遣してきた。同時に、自国民を監視する中で技術を磨いた軍・諜報要員も送り込んでいた。このため、1月5日に大統領代行に就任したデルシー・ロドリゲスが残存するキューバ軍顧問団を退去させる必要に迫られるかもしれないという(The Economistを参照)。
ベネズエラからの石油供給は、ピーク時で1日約10万バレルに達し、キューバは自国のエネルギー需要を満たすと同時に、精製石油製品を海外に販売して切実に必要とする外貨を獲得できた。しかし米国による制裁と経営不振によりベネズエラの石油生産量は急減した。そのため、1月5日付のThe Economistによれば、ベネズエラ石油産業の管理不行き届きと国際制裁により、キューバ向け石油供給量は2021年の1日当たり10万バレル超(国内需要の約80%)から2025年には1万6000バレルへと、ほぼ4分の3減少した。
ベネズエラからの原油供給の減少に加えて、キューバの老朽化した製油所、機能不全のインフラ、時折発生するハリケーンが相まって、2025年は少なくとも5回の大規模停電が発生した。「フォーリン・アフェアーズ」に公表された論文、ウィル・フリーマン著「ベネズエラの衝撃波」によれば、国土の40%以上がピーク時にエネルギーが供給されない。1日に2時間から4時間しか電力が供給されない地方もある。もしワシントンがキューバをベネズエラの石油から遮断すれば、送電網は崩壊しかねない。それは、もう目前に迫っている。1月11日になって、トランプは「キューバへの石油も資金も一切流さない——ゼロだ!」とTruthSocialで宣言したからだ。
キューバへは、ロシアとメキシコが一部石油を供給している。だが、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領に対しては、キューバ支援停止を求める米国の圧力が高まる見込みだ(メキシコは昨年、キューバに日量約2万2000バレルを送っていたが、ルビオが2025年8月にメキシコを訪問し、メキシコ政府に多くの二国間問題について圧力をかけた後、この数字は7000バレルに減少したという[NYTを参照])。なお、米国検察はマドゥロを麻薬テロとコカイン輸入の共謀で起訴したが、その背後で、メキシコの有力組織シナロア・カルテルを含む麻薬密売組織と提携し、メキシコ経由で米国にコカインを輸送しているとみている(NYTを参照)。マドゥロがメキシコからベネズエラへの麻薬資金の還流を促進したとも考えている。このため、今後、米国はメキシコへの圧力も強めるだろう。
他方で、キューバの主要債務を保有する中国は支援にほとんど関心を示していない。加えて、トランプは、ロドリゲス大統領代行に対して、石油の増産とキューバへの援助の削減と引き換えに支援をすると約束するかもしれない。
キューバの主要産業である観光業は、少なくともパンデミック前の半分にまで縮小し、回復の兆しはない。資金不足のために法執行機関や病院が機能しなくなり、犯罪や疾病が増加している。このため、フリーマンは、「普段は長時間の停電から守られているハバナが暗闇に陥れば、政権は2021年7月のデモと同じかそれ以上の大規模な抗議行動に直面する可能性がある」と指摘している(2021年以降、キューバは人口の10%、100万人を失った。下降スパイラルの一因はアメリカによる制裁だが、それ以上に大きな原因はキューバ政府による経済管理のまずさにある[NYTを参照])。
難しいキューバの改革
1月6日付の「ワシントンポスト」(WP)によれば、2006年に病床の兄フィデルから権力を継承したラウル・カストロは、2010年にキューバ議会で行った長大な演説で改革の必要性を警告した。ラウルは、「我々は革命の命運を弄んでいる」とのべ、「状況を是正するか、あるいは絶望の淵をさまよいながら時を尽くし、沈んでいくかのどちらかだ」と危機感をもっていた。しかし、「民間部門の役割拡大と国有財産の削減を目指す彼の計画は矛盾に満ち、不十分な実施に終わり、結局キューバの構造的問題のほとんどを解決できなかった」、と記事は指摘している。①与党が民間企業や農場の市場価格での直接販売を認めない、②通貨改革の拒否、③不振の観光産業への政府の巨額投資、④経済の大部分を支配する軍系複合企業GAESAの権力拡大――などが障壁となっている。
The Economistによれば、キューバにとっての命綱となる最良の希望はロシアである。両国は近年、軍事・経済協力を強化しており、防衛協定を締結し、ロシア軍艦がハバナに寄港している。ロシアがウクライナに侵攻してから2年後の2024年、キューバのミゲル・ディアス=カネル大統領はロシアに対し「特別軍事作戦の遂行における成功」を願った。両国は貿易協定を締結し、ロシアのキューバにおける石油採掘や農業への投資は拡大している。「ロシアのキューバへの関与こそが、何よりもトランプを遠ざけるかもしれない」、とThe Economistは指摘している。
キューバとロシアの親密な関係は、ロシアの「特別軍事作戦」へのキューバ人の参加にも現れている。ウクライナの「キーウ・インディペンデント」(2025年10月15日付)は、ウクライナ軍情報部(HUR)が「少なくとも1076人のキューバ国民がウクライナでロシア軍として戦闘に参加したか、現在も参加している」と伝えた。10月5日付のロイター通信によれば、「米国外交官は、キューバ政府がロシアのウクライナ侵攻を積極的に支援しており、最大 5000 人のキューバ人がモスクワ軍とともに戦っていることを各国に伝える予定である」と報じている。さらに、10月7日付のForbesは、「最大2万5000人のキューバ人が間もなくロシア側で戦闘に参加する可能性があり、戦場における外国人部隊の最大規模として北朝鮮兵士を上回る見込みだ」と報道している。
だが、ウクライナ戦争をめぐる停戦・和平交渉の途上にあるロシアが思い切ったキューバ支援に踏み込むのは難しい情勢にある。他方で、こうした混乱が米国によってもたらされたとして、反米感情の新たな高まりを引き起こす可能性もある。
「知られざる地政学」連載(125):地政学上の地殻変動について:ベネズエラの大統領「誘拐劇」を機に(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)