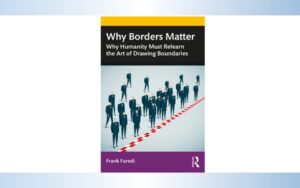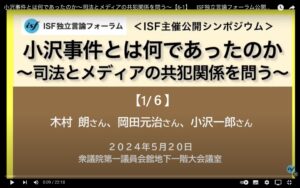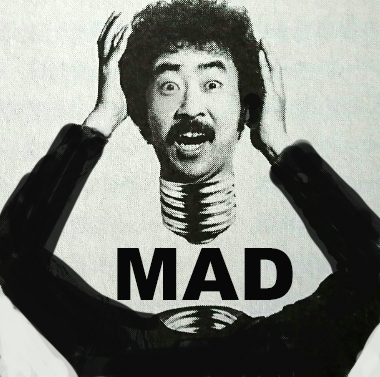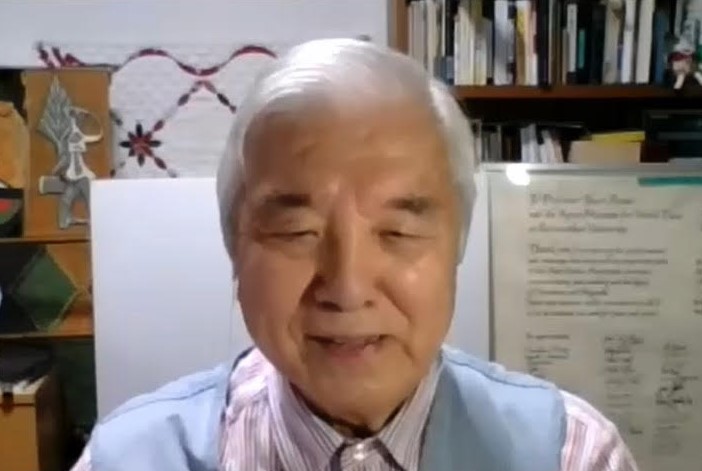制裁をめぐる補論:『復讐としてのウクライナ戦争』で書き足りなかったこと〈上〉
国際拙著『復讐としてのウクライナ戦争 戦争の哲学:それぞれの正義と復讐・報復・制裁』において、制裁について詳しく論じた(この本が上梓された経緯については、私の記事「「ウクライナ戦争3部作」をめぐって:ウクライナ戦争の本質を探るルサンチマンからの問いかけ」[https://www.21cryomakai.com/%e9%9b%91%e6%84%9f/1436/]に詳しいので参照してほしい)。
しかし、その内容は必ずしも十分とはいえない。そこで、ここで書き足りなかった制裁についての考察を紹介し、補論としたい。

News headline with “sanctions” written in Japanese
「私的制裁」について
拙著で取り扱ったのは、いわゆる「公的制裁」という、主権国家が国内の法人や個人に対して、対象国の法人・個人に強制的に制限を科すよう迫る制度についてであった。だが、ウクライナ戦争を契機に、民間企業がいわば自主的にロシアから撤退し、それによってロシア人従業員にウラジーミル・プーチン大統領への反対を促したり、ロシア企業の収益を減らすことで、戦争の停止を少しでも促したりする動きが広がる現象も起きた。
これは、いわば「私的制裁」であり、これまでになかった規模で実施されたといえる。そこで、拙著のなかではまったく無視してしまったこの「私的制裁」について〈上〉で取り上げ、「公的制裁」については〈下〉で補足的な考察を試みることにしたい。
よく知られているのは、イェール大学チームがウクライナへの侵攻が始まって以来、1200社を超える企業の対応を追跡してきた調査(https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain)である。1000社を超える企業が、国際的な制裁措置で法的に義務づけられている最低限の範囲を超えて、ロシアでの事業を自主的に縮小することを公表しているという。
ただし、こうした調査はいわば公的制裁以上の制裁を民間企業に促すキャンペーン効果をもつだけでなく、何もしない企業へのバッシングやボイコットにつながりかねない側面を持つことに注意しなければならない。その意味で、きわめて「うさん臭い」調査だが、ひとまず検討してみるだけの価値はある。
調査は、①撤退(ロシアとのかかわりを完全に絶ち、ロシアから撤退する企業)、②停止(一時的に業務の大半または大半を縮小し、復帰の選択肢を残している企業)、③規模縮小(一部の事業を縮小し、他の事業を継続する)、④新規投資・開発の延期(実質的な事業を継続しながら、今後予定している投資・開発・マーケティングを延期している企業)、⑤拒否(撤退や活動縮小を要求されても、それに応じない企業)――という5つのタイプに分けて公表している。
「撤退」といっても、公的制裁の余波で撤退を余儀なくされる場合もあれば、まったく自主的に撤退する場合もありうる。後者は「私的制裁」と呼ぶにふさわしいが、前者については「私的制裁」に値するかどうかは微妙だ。撤退に伴う損失は償却対象となる。その会計処理への税制面での対応が課題となる。何よりも、ロシア側への打撃の規模も問われる。
「停止」や「規模縮小」もまた「私的制裁」と呼べるかどうかはなかなか難しい問題である。生産を継続しようにも、部品やサービスの供給が遅滞して難しいケースも考えられる。「新規投資・開発の延期」については、「制裁」と呼ぶだけの影響力があるのかどうかという疑問符がつく。もちろん、「拒否」というケースは「私的制裁」にはあたらない。
こうした問題点を踏まえたうえで、イェール大学の調査をもとに下表を作成してみた。2022年12月20日に更新されたデータをもとに、日本企業の対応を一覧表にしたものである。
イェール大学のチームは、財務分析、経済、会計、戦略、ガバナンス、地政学、ユーラシア問題のバックグラウンドを持ち、ロシア、ウクライナ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、中国、ヒンディー、ポーランド、英語を含む10カ国語に堪能な専門家で構成されたチームを編成し、政府の規制当局への提出書類、税務書類、企業声明、金融アナリストのレポートなどの公的情報源を使用してこの独自のデータをまとめたという。さらに、250人以上の企業インサイダー、内部告発者、経営陣のコンタクトからなるグローバルなWikiスタイルのネットワークなどの非公開情報源も活用している、とされる。


(出所)https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain
個別企業について、さまざまな見方が可能だが、イェール大学の調査自体が大雑把なものにすぎず、実際に「私的制裁」に値するケースがどこまであるのかについては判然としない。むしろ、後述するように、「何かしている」ということを印象づけることで、国内向けにアピールしようとしているだけなのではないかとの疑いを禁じ得ない。
株主優先主義とステークホルダー(利害関係人)・アプローチ
そこで、企業が「私的制裁」を行う場合、その私的制裁を理論的にどう分析すればいいのかを別の面から考えてみたい。その際、参考になるのがまさに「私的制裁」という論文(Oliver D. Hart, David Thesmar, and Luigi Zingales, Private Sanctions, National Bureau of Economic Research, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w30728/w30728.pdf)である。
問題となるのは、企業は誰のために経営されるべきかという論争をめぐる2つの対立だ。株主優先主義とステークホルダー(利害関係人)・アプローチだ。
前者は、企業利益を優先させる経営を重視するから、企業による「私的制裁」も企業利益、すなわち株主利益のためになされるべきであるとみなす。後者は、企業経営がステークホルダーへの影響を考慮してなされるべきであると考えるから、「私的制裁」もステークホルダーの意向に沿ったものであるべきだとみなす。
紹介した論文によると、企業を制裁に駆り立てる理論として、たとえば、「私的制裁」を、「企業の評判を守るため、あるいは公的制裁を受けるリスクを最小化するための価値最大化の意思決定」とみなす考え方があるという。
「倫理よりも制裁が企業のロシア脱出に拍車をかけた」という記事(https://www.ft.com/content/fed1ebb5-e97d-424f-a313-2bb0d1cb8181)を2022年3月9日付の「フィナンシャル・タイムズ」に書いたアラン・ビーティー氏は、「多国籍企業の多くは、突然の企業良心の発作というよりも、直接的または間接的に公的制裁によって動かされているようにみえる」と指摘している。
禁止された企業と取引する企業はドル決済システムから切り離される恐れがあるために、こうした企業活動に重大な悪影響を与える重大な制裁をあらかじめ避けることで、ともかくロシアとのビジネスを縮小・撤退させようという企業が広がったというのだ。
他方で、ロシアのウクライナ侵攻に対する企業の対応をステークホルダーとの関係について分析した、Anete Pajuste & Anna Toniolo, Corporate Response to the War in Ukraine: Stakeholder Governance or Stakeholder Pressure?(https://ecgi.global/sites/default/files/working_papers/documents/ukrainefinal.pdf)では、いくつかの興味深い結論が得られた。
第一に、ロシアからの撤退を迅速に発表した企業は、実はロシアに対する収益エクスポージャー(企業収益において市場の価格変動リスクや特定のリスクにさらされている金額や残高)が少なかったことがわかった。つまり、ロシア撤退を決めても大きな痛手にならないから、撤退を広告イメージ向上のために利用するインセンティブが働いたというのである。
「社会的活動の言葉をマーケティング材料に転用する」と定義される、いわゆる「ウォーク・ウォッシング」(woke-washing)を一部の企業トップが試みたことを示唆しているのだ。
わかりやすくいえば、ロシアによるウクライナ侵攻に対して、ロシア撤退を機敏に決め、それをアピールすることで、「社会的不公正、人種差別といった問題に対して意識が高い」、覚醒した企業であるフリをして、社会的認知度を上げようという「あざとい」戦略をとった企業があるということになる。
さしずめ、紹介したイェール大学の調査は、世界的な規模の「公的キャンペーン」効果を持つ。ゆえに、この調査に協力してロシアへの制裁に積極的に取り組んでいるとアピールしようとする企業が現れても不思議ではない。その意味で、この調査において、撤退や事業縮小を決めた企業が本当は何を考えているかについては、慎重かつ詳細な分析が必要となる。
すでに指摘したように、この調査自体が「うさん臭い」のである(本稿でイェール大学の調査を紹介した理由はこの「うさん臭さ」に気づいてほしいからであったと書いておこう)。
第二に、ボイコットキャンペーンの口コミによる伝播性をツイッターで検証し、経営者がウクライナ支援やロシアからの撤退という前向きな行動をとるかどうかの判断との関係も検証した結果、ロシアからの撤退を決断することは、ボイコットキャンペーンと有意に正の相関があることがわかったという。
これは、ツイッターを利用したボイコットキャンペーンがビジネスリーダーにロシアからの撤退を促す影響を初めて証明したことを意味している。企業が利益最大化よりも幅広い課題を追求する意思決定に、ステークホルダーの圧力が重要であることが示されたことになる。いわば、「有名税」を大企業は課されており、それに応えなければバッシングに遭いやすいという現実があるのだ。
第三に、この圧力は大企業に集中し、中小企業の経営者をこの経営上の制約から除外している。したがって、中小企業の経営者は、大企業と同様に社会に害を及ぼす可能性があるにもかかわらず、この重要な経営上の制約を受けることなく自由に活動することができる。
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)