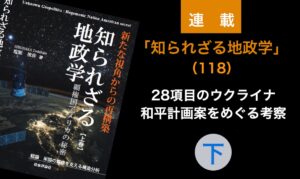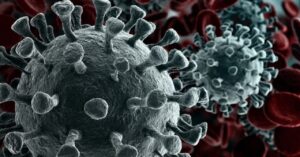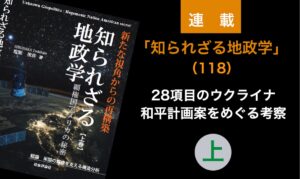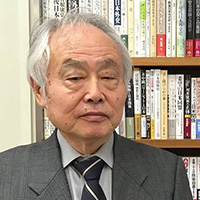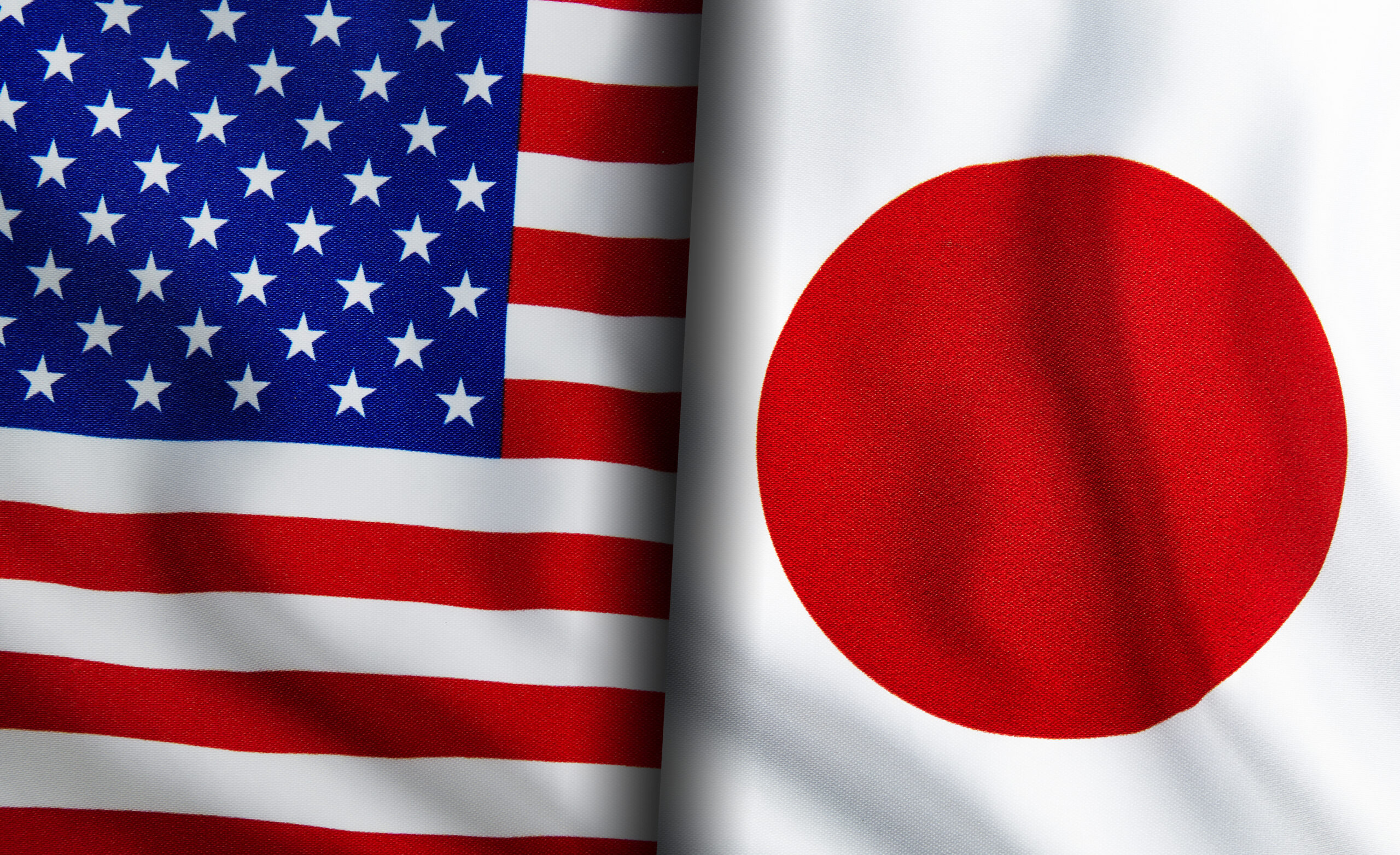
対米自立─敗戦後76年の占領状態を終わらせ、戦後ヤルタ・ポツダム体制を打破せよ!―
安保・基地問題5.戦略なき戦争目標であったが……
確かに、戦争目的の遂行と現場での戦闘行為のちぐはぐさ、まずさは、孫子の兵法の「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という基本に適っていなかった側面はある。情報収集能力が低かったために、その場しのぎの戦い方に終始し、むやみな犠牲を多く払ったことは、批判されて然るべきである。
また、どこまで戦いが展開されれば終戦交渉が妥当かなどの戦争終結目標の戦略が定まっていなかったことは厳しく非難されるべきであろう。その結果、相手側から揺さぶられたり、騙し討ちの陰謀に陥れられることによって、我が国国体の危殆が一時的にせよ促進されてしまったことは、重大な当事者の責任として問われなければならないからである。就中、昭和15年の段階でも、内閣総力戦研究所の机上演習において、我が国の産業、軍事力を総動員して総合的に日米開戦後のシミュレーションが行われた。その結果は、この時点ですでに対米戦必敗が予告されていた。
このように、冷静な総合研究が行われていたにもかかわらず、他方で結果は分かっていながら敢えて戦いに挑まなければならなかったという歴史的必然が存在するのである。どんな時代でも、物事を的確に把握している人間がいることはままある。しかし、その見識が採用されるとは限らず、結果として戦わねばならないことは、様々な事例が示している。もし我が国が決然立たなかったら、アジア諸国の独立はまだまだ時間がかかったことは想像に難くない。
ただし、こうした事柄は、時が過ぎ去り、結果が出て初めて明確に判別されるものではないか。何事も、終わってみればこうだったのか、というのは、ある意味で誰にだって理解できるところである。未来予測が完璧に可能であったならば、人間や社会は失敗などしないだろう。
したがって、当時の人々がぎりぎりの苦悩の中で葛藤を続けたプロセスを汲み取り、そして歴史の動きの中から、日本人が忘却したものを救い出さなければならない。結果だけを見て判定を下すのではなく、その中にあるプロセスをも考えなければならないのである。
それというのも、米国は、外交交渉なる引き延ばしと駆け引きを8か月間も続けた挙句、最終的に「ハル・ノート」という最後通牒を突きつけ、明らかに我が国を挑発してきたからである。しかもこの間、我が国の対中和平交渉を陰に陽に妨害し、「JB335」「レンドリース法」などによる中国への軍事支援計画を立てるとともに、それを実行していたのである。これは間接的な戦争行為であり、経済封鎖のABCD包囲網に至っては実質的な戦争行為であった。まさに外交巧者として我が国を揺さぶり続けていたわけである。
ところで、我が国は対中国和平を達成するため、律儀にルールを守り交渉を積み上げていこうとした。現在においてもその姿勢は指弾されるものではなく、むしろ称讃すべきではなかろうか。だからこそ、こうした米国の姿勢に、我が国国民は隠忍自重、はらわたの煮えくり返る思いを何回もしながら、ついに堪忍袋の緒が切れたのが、「ハル・ノート」であった。そして、国民の凱歌があがったのが昭和16年12月8日の開戦の日であったのである。
6.対米英戦に文化人は涙した!
米国による演出、陰謀の行われた時代にあって、日米開戦を我々の先人たちがどのような思いで迎えたのか。その一端をここに示したい。
二・二六事件で皇道派青年将校の至純性を支持し、自らも禁固5年の刑を受けた孤高の少将であり、歌人でもあった齋藤瀏は、当時、『週刊朝日』の特集欄で、「大詔勅を拜す」と題して、次の5首を詠んでいる。
大詔勅を拜す 齋藤瀏
米英に戰をのらす大詔勅天つ神國神開きにけらずや
天地に赫る日本を見る眼盲し驕りて杖を振る國は見よ
一億の民たたかひて盡くらくは滅ぶるにしてや潔よからむ
國民が死をこぞりたる戰なり必ずや勝つ必ずや勝つ
戰ひて時は過ぐとも敗くるなし押しぞ開かむその勝は見ゆ
まさに「一億の民たたかひて盡くらくは滅ぶるにしてや潔よからむ」とは、戦いに挑んでいって敗れたといえども、そこに潔さが残ればそれでよしという心情の発露ではなかったのか。義のために戦い、最も尊重すべき命を捧げようとする気高い精神が、この歌に示されているといえよう。また、「天地に赫る日本を見る眼盲し驕りて杖を振る國は見よ」とは、我が国を尊重せず、居丈高に抑圧を加えんとする驕り高ぶった米国へ挑んでいく気持ちを表明している。
さらに、『千恵子抄』で有名な詩人・高村光太郎は、昭和17年4月、詩集『大いなる日』を出版した。その序には、「支那事変勃発以来皇軍昭南島入城に至るまでの間に書いた詩の中から37篇を選んでここに集めた。ただ此の大いなる日に生くる身の衷情と感激とを伝へたいと思ふばかりである」とあり、日米開戦について次のような心情を吐露している。数ある中から一篇を紹介しよう。
12月8日 高村光太郎
記憶せよ、12月8日。/この日世界の歴史あらたまる。/アングロ サクソンの主権、/この日東亜の陸と海とに否定さる。/否定するものは彼等のジャパン、/眇たる東海の国にして/また神の国たる日本なり。/そを治しめしたまふ明津御神なり。/世界の富を壟断するもの、/強豪米英一族の力、/われらの国に於て否定さる。/われらの否定は義による。/東亜を東亜にかへせといふのみ。/彼等の搾取に隣邦ことごとく痩せたり。/われらまさに其の爪牙を摧かんとす。/われら自ら力を養ひてひとたび起つ。/老若男女みな兵なり。/大敵非をさとるに至るまでわれらは戦ふ。/世界の歴史を両断する/12月8日を記憶せよ。
高村光太郎は、「東亜を東亜にかへせ」と明確に断言し、米英の搾取が東亜諸国を貧困に導いていると指摘している。しかも、我々の戦いは義によって米英の行動を否定するものであると訴えているのだ。「大敵非をさとるに至るまでわれらは戦ふ」と、徹底して植民地主義者に対し、正義に立ち返ることを求めている。この目的が達せられるまで戦いを継続していくのだと、まさに継戦の思想を保持しているのである。米英が「さとるに至るまで」その姿勢を崩してはならないとは、至高の決意ではないか。
むろん、これを批判する人物もいる。伊藤信吉は、同詩を含め高村光太郎が詠んだ戦争詩について「人道的詩人としての姿勢に背を向けた」「七十余年の精神史の歪み」(『高村光太郎入門』より)などと断罪した。
これに対し、中村粲氏は著書『大東亜戦争への道』(展転社)の中で、「戦争詩といへども、その時は詩人の全人格の重みをかけて詠まれた筈である。その時その時の表現に人間の真実を見るのでなければ、そもそも文芸評論は成り立たぬであらう。開戦に感激したことを以て精神の『歪み』と呼ぶならば、当時の殆ど全日本国民の精神は歪んでゐた」と喝破している。まさにその通りであろう。
7.未だ大東亜戦争は終わっていない~米英戦勝国の横暴と日本の対米従属
ところで、中村粲氏が指摘した「当時の殆ど全日本国民の精神は歪んでゐた」というのは、今日の日本にこそ当てはまることだ。それは、敗戦を迎え、経済発展を遂げ、安逸を獲得した結果、我が国の多くの部分が歪んでしまったということである。確かに我が国は、この76年間、戦争に巻き込まれず、平和を享受してきた。しかし、その状況が、国家の独立を維持する姿勢を欠くことや、防衛意識を低下させることになっている。政府は国民に指針を与えられず、安全保障は外国に委ねるという体たらくが続いているのである。
対戦国である米国は、ますます驕り高ぶり搾取と抑圧を繰り返し、高村光太郎が指摘した搾取者が悟るべき点について、一向に改まっていない。ベトナムへの介入、イラク侵略など、戦後なおも搾取と植民地主義を、顔を変えて続けている。
例えば、戦勝国の原爆投下などの戦争犯罪は一切問われず、我が国だけが敗れたためにその罪科を問われてしまっていることも、その証左だ。昨今に至っては、戦争一般において、その悲惨さが多大な犠牲を残し得ることによって、戦争そのものの違法性が指摘されてきているが、米英の戦勝国は、この70年間、歴史的な反省が問われなかったため、現在においてもやりたい放題である。ここに不法、不当性が存在するのだ。
私は一貫して、戦後日本が占領憲法と日米安保条約の桎梏下にあり、米国から真の独立を果たしていないと認識し、それを表明してきた。そのことは、現在進行形の沖縄米軍基地の普天間基地移設問題にも如実に表れている。
特に、米ソ冷戦の終結によって米軍の配置が変化する中でも、先述したように我が国は以前にも増して対米属国化を強いられた。本来ならば冷戦終結に伴い、戦後の我が国を規定してきた占領憲法、日米安保条約、戦後教育体系などの根本的見直しがされなければならなかったが、現実はそれに逆行している。有体にいうならば、日本人の魂が入った独自の憲法を制定し、自国の国益を守るとともに、日本人が日本人自身の手で自国を守るという姿勢を打ち出すことのできる社会へと移行すべきだ。対外的には、国際社会の中で我が国の歴史、伝統、文化を守りながら、日本人が尊敬を受け得る生き方ができるような教育を実践していかなければならない。
どうも明治以来の我々の対外感覚は、「追いつけ追い越せ」の風潮が強く、鹿鳴館に代表される拝外姿勢に傾斜しすぎてきたように思われる。それを克服した時期も勿論なかったわけではないが、大東亜戦争で敗北した結果、終戦から今日に至るまで、我が国は戦後体制にがっちり縛られてしまっている。
とりわけ国防の一端である軍事面では、去勢されたがごとく米国に大きく委ねなくてはならなくなってしまった。これは、大東亜戦争の結果、一種の「お詫び状」として作られた占領憲法の条文操作によって日米安保条約が作られたことによるものである。
また、我が国の主権が制限されていた状況下で、旧ソ連によって北方領土は強奪され、韓国にも竹島を実効支配され、領土が奪われていった。尖閣列島は現在、我が国が実効支配しているものの、中国、台湾は領土的野心をむき出しにし、同地の領有権を主張している。
北方領土、竹島地域に関していえば、サンフランシスコ条約締結により、その第2条B項、C項で放棄した地域に含まれるか、含まれないかの議論がされていない。ところが、それを一切無視するかのような裏取引が行われ、我が国の脆弱さに付け込んで奪取されてしまった。むろん明らかに国際密約であり、我が国がこれに拘束を受ける必要はない。だが、その国際密約と火事場泥棒を合法的に取り繕うために東京裁判が行われ、占領終結を演出するサンフランシスコ条約が締結された。
このサンフランシスコ条約の発効によって日本は国際社会に復帰し、我が国の独立が保たれたとされるが、先述した通り、未だ米軍基地が存続し、魂まで抜かれた占領憲法体制が続いている中で、本当に独立を果たしたとはいえない。だからこそ、まず国家の基本である主権、領土、国民を確認するため、戦後体制を克服し、「対米自立」を実現しなければならないのである。
8.米英ソ戦勝国の戦争犯罪こそ裁くべきだ
大東亜戦争の理念とは、米英の顔を変えながら現在なおも続く帝国主義の抑圧に真っ向から対抗した輝かしい実行力であった。そして、アジア諸国の独立を達成したことにある。もし米英が高村光太郎のいうところの悟りを開いていれば、少なくとも東京裁判と同様のフセイン・バグダッド裁判はなかっただろう。
大東亜戦争後の東京裁判では、我が国は「敗戦」を理由に戦勝国側から一方的に断罪され、指導部はA級、B級、C級戦犯の認定を受け、刑罰を下された。私自身、戦争という手段を選択し、その結果敗戦という事態を招いたことについては、もちろん指導部の責任は免れ得ず、国民から断罪されなければならないと思っている。いわゆる敗戦責任である。だが、実際に指導部を裁いたのは日本国民ではなく、米国を中心とする戦勝国であった。
そうであるならば、冷戦期に入って激烈な戦闘を繰り広げたベトナム戦争において、米国は、誤解を恐れずにいえば、東京裁判の例に倣い、その「敗戦」を国際社会から裁かれなければ道理に合わないのではないか。戦いの最中の戦時国際法に抵触する行為や、軍人以外の民間人を故意に殺戮したことなどは、戦争犯罪として裁かれなければならないはずだ。また、近代以降の慣例に従ってみても、多くの被害を出している以上、それに対する謝罪や賠償、弁済などが実行されなければならない。
その後の米国社会は、ベトナムでの「敗戦後遺症」から荒廃が続いた。しかし、戦争に介入して敗北したことを検証しようとはしなかった。しかも、それに助けられたのが旧ソ連のアフガニスタンへの侵略であった。長く続いた旧ソ連のアフガニスタン統治はムジャヒディンの強固な抵抗運動に遭い、軍事的に大量の消耗をした結果、旧ソ連軍はアフガニスタンから撤退を余儀なくされた。当然、旧ソ連の指導者もアフガニスタンを侵略し、軍民問わず多くの人々を殺害している以上、国際法廷で裁かれなければならない。
さらに最近の例でいえば、米国のイラクに対する侵略戦争も同様である。私は湾岸危機以来、イラク共和国と関係を持ち、現地にも足を運び、国際社会の上っ面なイラク批判のプロパガンダの中で、イラク側の立場に理解を示し、米国の欺瞞を内外に訴えてきた。そのイラクが、平成15年3月に米国からの侵略攻撃を受け、サダム・フセイン政権は崩壊してしまった。ところが、ブッシュ政権の開戦理由は全くナンセンスなものであった。

A soldier loads up onto an American plane near Mosul, Iraq.
 木村三浩
木村三浩
民族派団体・一水会代表。月刊『レコンキスタ』発行人。慶應義塾大学法学部政治学科卒。「対米自立・戦後体制打破」を訴え、「国際的な公正、公平な法秩序は存在しない」と唱えている。著書に『対米自立』(花伝社)など。