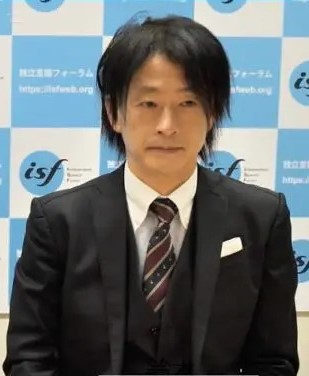ロシアが問いかけるLGBT問題(敬称をつけると不自然なので敬称は省略しています。)
国際
私は、ウクライナ戦争を復讐という視角から分析する際、キリスト教神学に注目した。拙著『復讐としてのウクライナ戦争 戦争の政治哲学:それぞれの正義と復讐・報復・制裁』において、パウロの贖罪論、トマス・アクィナスの『神学大全』における贖罪論のほか、刑罰と復讐の関係を考えるために、①イマニュエル・カント、②ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、③アルバート・ヘルマン・ポスト、④ロバート・ノージック、⑤キット・クリステンセンなどを取り上げた。
こうした分析は、西洋においてキリスト教が果たしてきた絶大な影響力を復讐という視角から論じるものであった。同時にそれは、キリスト教が人間の罪と罰にさまざまな価値観を植えつけてきた過程を探ることでもあった。
こう考えると、この研究はキリスト教社会の一部において声高に叫ばれるようになっている、いわゆるLGBT問題とも深くかかわっていたことになる。ミッシェル・フーコーは『性の歴史Ⅰ 知への意志』(渡辺守章訳)のなかで、「何故これほど長い間、人々は性と罪とを結びつけてきたのか」と書いている。キリスト教神学の探究は復讐という視点以外にも、こうした性をめぐる問題についても考察するチャンスをもたらしていたように思う。
そこで、ウクライナ戦争の当事国ロシア連邦にあって、ウラジーミル・プーチン大統領がとりつつある、性への守旧派的な対応について論じてみたい。フーコーが論じたように、権力と性が深くかかわっているとすれば、LGBTに対するロシア政府の態度を考察すれば、プーチン政権の権力構造分析にも役立つかもしれない。そんな想いから、この問題に取り組むことにした。ただし、ここでは紙幅が足りないので、概括的な話しかできないが、深く考えるためのヒントを示せれば幸いである。
2022年12月の新法
まず、2022年12月5日、プーチン大統領が非伝統的な性的関係、性転換、小児性愛の促進を禁止する法律に署名したことを確認しておきたい。そのなかで、「情報、情報技術および情報保護に関する法律」の改正が行われ、これまで禁止されていた未成年者に対する小児性愛やLGBTの宣伝以外にも、メディア、映画、広告におけるそうしたプロパガンダが完全に禁止されることになった。これとは別に、プーチン大統領はLGBT、小児性愛、性別適合を促進した場合に多額の罰金を科す法律にも署名した。LGBTプロパガンダの禁止に違反した場合、40万ルーブル以下の罰金、法人の場合は500万ルーブル以下の罰金となる。また、未成年に性転換を促すような情報を流した場合は、20万ルーブル以下、法人は400万ルーブル以下の罰金となる可能性がある。
もちろん、これらの法律は上下院で審議され、可決されたうえで、プーチン大統領が最終的に署名したものだ。ただし、こうした立法化の背景には、いわゆる「伝統的価値観」を守ろうとするプーチン大統領の強い意向がある。
オンライン映画館の「プレミア」、「スタート」、通信事業者の「メガフォン」(スタートの共同所有者)は、ロシア連邦行政法第6条21項2号「非伝統的な性的関係および(または)嗜好を示す情報の未成年者への流布」に違反したとして訴えられており、2023年6月から逐次、裁判がはじまる。LGBTコンテンツを上映したことで18歳以上という年齢表示に違反した容疑がかけられている。
2023年4月になって、司法相は法律改正によって、性別変更手続きを「厳格化」する方針であることを明らかにした。ロシアの人々は1997年から合法的に性別変更できるようになり、パスポートの性別変更を可能にするメカニズムが機能し始めた2018年から2022年までに2700件以上の性別変更(書類による)が登録され、その後、これらの人々が関わる約190件の婚姻が登録された。しかし、今後は、医療行為を行わずにパスポートの性別を書類上だけで変更することを禁止しようというのだ。5月30日には、下院議員によって、トランスジェンダー手術は「子どもの先天性生理的な性形成異常の治療」のためにのみ許可されるとして、「手術による性転換の禁止」を導入する「健康保護に関する法律」案が下院に提出された。
プーチン大統領の「伝統的価値観」という見方
ここで、プーチン大統領の「伝統的価値観」への考え方について紹介しよう。それがよく現れているのは、2022年10月27日のバルダイ国際ディスカッションクラブでの発言である。彼はつぎのように話している。
「伝統的価値観は、だれもが守るべき固定概念ではない。もちろん、そうではない。いわゆる新自由主義的な価値観とは異なり、それぞれのケースにおいてユニークなものであることが特徴だ。なぜなら伝統的価値観は具体的な社会の伝統、その文化や歴史的経験に由来するものであるためである。そのため、伝統的価値観はだれかに押しつけるものではなく、どの国も何世紀にもわたって選択してきたものを大切にする必要があるのだ。」
そのうえで、つぎのようにのべている。
「欧米のエリートたちが、自分たちの国民や社会の意識に、数十種類のジェンダーやゲイ・パレードのような、私の意見では奇妙な、新しいトレンドを植えつけることができると考えているなら、それはそれでよいだろう。好きなようにやらせてあげよう!しかし、彼らに権利がないのは、他人が同じ方向に進むことを要求することであることは確かである。」
このようにみてくると、どうやらプーチン大統領は、伝統的価値観を守ろうとする自分たちのやり方はあくまで何世紀にもわたって大切にしてきたものを守るものであり、他国からとやかくいわれる筋合いではないと主張しているようにみえる。これは、多国間主義といわゆる不干渉(人権侵害を批判するなど、互いの内政に干渉すべきでないことを主張)を支持するという、習近平が打ち出した「グローバル・セキュリティ・イニシアチブ」に呼応する主張であり、人権侵害批判を材料に介入する米国政府の主張と真っ向から対立している。
実は、前述の立法化の過程で、米国のアンソニー・ブリンケン国務長官は、「ロシアにおける表現の自由とLGBTの権利に対する新たな深刻な打撃となる」として、法案を拒否し「すべての人の人権と尊厳を尊重する」ようロシアの国会議員に促していた。だが、それは、ロシアからみると、「内政干渉」であり、それこそ「うっせいわ」ということになる。
「トラブルのもととしてのリベラリズム」
ここで、ジョン・ミアシャイマーシカゴ大学教授の鋭い指摘を紹介したい。彼は、The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities(Yale University Press, 2018)の「トラブルのもととしてのリベラリズム」という節で、「リベラル覇権の代償は、自由主義国家が権利を保護し、世界に自由主義民主主義を広めるために、果てしない戦争をすることからはじまる」と指摘している。そして、「ひとたび世界の舞台で解き放たれたリベラルな一極集中は、やがて戦争中毒になる」とつづけている。
何がいいたいのかというと、ソ連崩壊後、世界の覇権を米国のみに一極集中させたアメリカの政治指導者が自分たちの尊重する自由主義や民主主義、さらにLGBT尊重主義をも世界中に広めようとして、世界中で戦争を仕掛けてきたという事実である。共和党出身者が大統領であろうと、民主党出身者が大統領であっても、米国の外交戦略は長く「リベラルな覇権主義」を軸にしてきたのであり、それが1990年代以降、一極覇権を強めるなかで軍国主義へと傾斜していったのだ。米国が関与したセルビア(1999年)、アフガニスタン(2001年)、イラク(2003年)、シリア(2011年)、リビア(2011年)などでの「紛争」を思い起こせば、この国がいかに戦争好きであるかがわかるだろう。もっと正確に記せば、油井大二郎が『好戦の共和国アメリカ』(岩波新書)で指摘しているように、もっとずっと以前から米国は好戦的でありつづけたのである。
ミアシャイマーはこの米国の軍国主義を生じさせている要因としてつぎの五つあげている。
①地球を民主化することは、戦いの機会を豊富に提供する広大なミッションである。
②リベラルな政策立案者たちは、自分たちには目標を達成するために軍事力を行使する権利と責任、そしてノウハウがあると信じている。
③彼らはしばしば宣教師的な熱意をもってその任務に取り組む。
④リベラルな覇権主義の追求は外交を弱体化させ、他国との紛争を平和的に解決することを難しくしている。
⑤この野心的な戦略は、国家間の戦争を制限するための国際政治の中核的な規範である主権という概念をも損なうものである。
とくに、他国の主権を損なっても、自分たちの価値観である自由主義や民主主義、LGBTさえ強引に押しつけるやり方が「宣教師的」なのであり、そこには、キリスト教の「神」という後ろ盾があるかのようにふるまいがある。これこそ、2014年のウクライナ危機や2022年のウクライナ戦争を引き起こした一因ではないか。私にはそう思われる。
国家の口出しに「うっせいわ」
とはいえ、私はプーチン大統領の肩をもっているわけではない。私にとっての大きな違和感は、プーチンが主権を重視しすぎている点にある。プーチンのいうように、いわゆる「伝統的価値観」に他国が口出しするのはたしかにおかしい。だからといって、国家が「伝統的価値観」に干渉することもいかがなものか。
後述するように、人類の長い歴史をみれば、結婚といったセクシャリティに絡む人間活動への干渉はさまざまに変容してきた。教会や国家が規制してきた時代があったのはたしかだが、21世紀になったのだから、こんな口出しを「うっせいわ」と一喝して、一人ひとりの自由に任せる方向に移行する方策を考えるべきなのではないか、というのが私の意見である。したがって、私はプーチンの説に与しない。もちろん、宣教師的で戦争好きな米国の姿勢にも反対である。
ロシア人研究者の見解
ここで、ロシアの国立研究大学「高等経済学院」のアルチョム・コスマルスキー著「愛への接近と愛への拒絶としての世界史」および彼へのインタビューを参考にしながら、性の問題を大雑把に考察してみたい。
コスマルスキーによれば、①恋愛は文化的普遍主義であり、ほとんどすべての人間社会に存在する、②愛は歴史的に、ホモ・サピエンスが形成される段階の一つで出現する――という特徴がまず重要である。子どもの世話をするようになったのは、最初、父親と母親のペアが、生まれてから赤ん坊を育てるまでともに行動するようになった結果であり、その後、友情、セックス、子供の世話によって結ばれた、安定したカップルが出現するようになる。ただし、旧石器時代の狩猟採集民からはじまるすべての人間社会では、人々は異なる、しばしば厳格で複雑なルールに従って結婚したが、それは西洋のロマン主義革命までは、結婚は愛に関するものではなかった。
結婚は経済的、政治的、軍事的な同盟関係を築き、家族や一族の関係を構成し、分業、病中病後の生活、相続を保障し、「全世界」を貫く関係のネットワークを構築する。ゆえに、離婚は、結婚と同様、ほとんどの社会で、個人の問題ではなく、家族や一族の問題であった。
結婚の変容
ローマにおける結婚は、デジュール(法律上)ではなくデファクト(事実上)であり、配偶者間の同意の連続体であったという。つまり、パートナーの一方がそれを放棄すると、事実上、結婚が終了した。離婚は行為ではなく、契約の解消でもなく、文字通り、両配偶者が分離し、別々の道を歩み(これがdivortiumの語源である動詞divertereの意味)、新しい結婚をすることができる状態を意味していた。
これに対して、キリスト教では、唯一者たる神を世界の中心に据えて、その愛の重要性を説く。有限の世界における絶対的なものの人格的存在として受肉した神が、有限の世界における無限のものの現象としての愛に基づいてのみ可能な行為を福音書で明示し、最後に、使徒たちの神との人格的関係、互いへの愛、神への愛としてのキリスト教を説くのである。
結婚については、パウロの影響が強くみられる。コスマルスキーによれば、「パウロにとって、夫と妻、親と子、主人と奴隷の関係は同等であり、教会の使命はこれらの関係を調和させることである」から、彼にとっての結婚は世俗的な制度の一つにすぎないとされた。結婚は目的ではなく手段であり、神からの贈り物ではなく、抑えきれない性欲の解決策にすぎないのだ。クリスチャンの真の召命は処女と禁欲であり、もし、それに耐えられないのであれば、妥協案として結婚が認められるというのである。
その後、コンスタンティヌス帝によって313年のミラノ勅令でキリスト教が公認され、さらに、381年にテオドシウス帝が第一コンスタンティノープル公会議を召集し、アタナシウスの教義を補強した三位一体説を正統教義として確認、392年になって異教徒禁止令を出す。こうして、アタナシウス派キリスト教が事実上の国教となる。テオドシウス2世(5世紀)になって、共和国の「乱婚」的慣習に反して、正当な理由のない離婚の禁止を強調する新しい法律を出す。その後も、国家干渉によって紆余曲折があったが、コスマルスキーはつぎのようにまとめている。
「中世初期には、政治的にはともかく、宗教的・実存的な構造は安定したものであった。福音を生き、神と共にある、完全なクリスチャンライフを望む者は、処女と禁欲と修道院に行くことでしかそれを得られなかった。そして、結婚は必然的に世俗の領域に入り、その反映として、ビザンティウムのキリスト教皇帝による離婚に関する法律が制定され、結婚は神ではなく、人間や国家によって行われ、解消されるものであることが示された。」
同性愛をめぐって
旧約聖書の伝統では、同性愛はタブーであったが、キリスト教では、同性間のセックスは禁止された。新約聖書にある使徒パウロの手によるとされる書簡、『ローマ人への手紙』の第1章26節と27節においては、「こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の用を不自然なものに代え、同じように、男も、女の自然な用を捨てて男どうしで情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行なうようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです」と記されている。
パウロにとって、同性愛は自然(フュシス)に反する「不自然」であり、ユダヤ教からの禁止事項の再現につながっている。コスマルスキーは、パウロが「ユダヤ人の同性愛行動に対する批判と、ギリシャのストア派のフュシス、自然という思想を総合している」と書いている。パウロにとって、法(ノモス)とは社会の変化する慣習であり、フュシスとは神と自然の秩序の統一であり、神が創造した自然にこそ明白な真理があるにもかかわらず、もし人々がそれをみることができなければ、それは心の混乱であり、悪の利益のために真理を歪めることになってしまうというのだ。
ただし、社会におけるあらゆるものが自然であり得るという考えは常に嘲笑されてきた。社会制度について語るのであれば、自然は存在しない。たとえば、男性が家族の長であるという考え方は、ある時代や文化に特有の確立に過ぎず、「自然」ではないのだ。コスマルスキーは、「ブルデュー、フーコー、ラトゥールは皆、「自然」で不変と考えられていたものが、自然の法則ではなく、社会的関係から派生した変化しやすい文化的規範であることが判明したことを示したのである」と指摘している。
注意しなければならないのは、前述したように、ローマ時代からつづく「文化」として、性行為が厳格に規範化されていたことである。いわばだれが上に立つことができるのか、一人の人間が他の人間、一人の階級に対して権力を主張するものとして性行為が行われていたのである。ゆえに、キリスト教が同性愛を非難したことは、いわば権力者による性的抑圧からの解放という面をもっていたことになる。コスマルスキーは、「キリスト教は解放をもたらし、神の前に平等であるという考えをもたらし、性的タブーの導入を含め、いかなる地位の絶対性、社会的態度、権力に対する態度を解体したのだ」と語っている。
実際問題としては、ギリシャ社会においても、同性愛は存在したし、イスラーム教の中東においても、クルアーン(コーラン)で同性愛が禁止されていたにもかかわらず、それは行われていた。キリスト教の世界と同じである。
フーコーの見方
つぎに、フーコーの解説を紹介してみよう。前述した『性の歴史Ⅰ 知への意志』におけるつぎの指摘は重要である(48頁)。
「 18世紀の末まで――慣習に基づく規則や世論の桎梏を別とすれば――三つのはっきりした大きな法規が性的実践を支配していた。宗教上の法と、キリスト教司教要綱と、民事法である。この3者のそれぞれが、合法と非合法の分かれ目を定めていた。」
これらはいずれも結婚にかかわるルールとして定められていた。これがその後の性をめぐる規範の基礎をなすことになる。
フーコーは、1870年の『神経医学資料』において、カール・フォン・ウェストファールの論文「自然に反する性的感覚」を紹介しながら、「性的な関係のタイプによるのではなく、むしろ性的感受性のある種の質、自己の内部での男性的なるものと女性的なるものとを転倒させるある種のやり方によって定義された時」、同性愛という範疇が成立したと指摘している(ただし、これは「同性愛」ではなく「性的倒錯」であるという主張もある)。
問題は、それまでは、「ソドミー」(肛門性向を意味するが、18世紀まで「男色」一般の意に用いられた)という曖昧な行為が禁じられていた点である。この段階では、その曖昧さも手伝って、ソドミーは一人だけの罪ではなく、罪人やその村、都市、国に神の怒りをもたらす災厄、異端のようなものとしてあった。だが、同性愛は独立した大人の親密な関係にかかわる「私的な問題」として位置づけられるようになる。社会や国家はこの領域に干渉すべきではないという視角が育つのだ。
主体の確立
コスマルスキーによれば、こうした変化が「似ているようで違う、もう一つの流れが勢いを増した」と説明している。それは、人権やプライバシーの自由に関する考え方や、人間には自然な欲求、自然な傾向があるという考え方である。こうした考え方の背後には、すべての宗教的信仰の基礎として主体を確立したルター、形而上学の基礎として主体を導入したデカルトといった先人の思想があったと考えられる(フーコーは、13世紀初頭以降に、すべてのキリスト教徒に対して、少なくとも1年に1回は跪いて、自分の犯した過ちのことごとくを、一つも見落とすことなく、一つ一つ告解しなければならぬという命令が人間を、語の二重の意味において《subject》[臣下=服従した者と主体]として成立させることにつながったとみている)。
こうして、「自らの欲望を至上」とするマルキ・ド・サドの思想が誕生する(ここでは、関谷一彦著「サドの『閨房哲学』の思想系譜とリベルタン文学としての位置」を参照)。彼は『ソドム百二十日』において、「自然がわれわれの心の奥底に刻んだ唯一の法則は、だれであれ他人を犠牲にして、自ら楽しむことである」と、登場人物のキュルヴァルにいわせている。さらに、1795年に出版した『閨房哲学』の「フランス人よ」において、「問題になるのは、欲望する者が満足するということだ」とのべている。これは自分の快楽がすべてであるという見方であり、「サドにとっては個人の欲望がすべてであり、この点においてルソーとは全く相容れないと言ってよい」と関谷は指摘している。さらに、「情欲を生み出す器官とは当然のことながら性的器官であり、こうした器官のみが人間を幸福に導くという考えはサドの哲学である」という。
おそらく、「このような態度は、やがて同性愛の欲望にもおよんでいった」とコスマルスキーが指摘するように、ここで紹介したような思想的系譜が「自律した成人が自分の体をどうしようと勝手だ、それは自分たちの問題であって国家の問題ではないという認識」の広がりをもたらすことになる。その意味で、LGBTであろうとなかろうと、だれに対しても「国家当局がだれと寝るべきかを指示すべきではない」という主張が現れても不思議ではない。セックスとセクシュアリティ(性的特質)は、政治や道徳、あるいは社会規範に依存しない領域であり、相互同意のルールが満たされ、危害の事実がない限り、セクシュアリティは個人の問題とする見方が広がるのである。
国家の巻き返し:「変態」の排除
だが、フーコーにいわせれば、国家は、死なせるか生きるままにしておくという古い権利に代わって、生きさせるか死のなかへ廃棄するという権力をふるうようになる。それは、身体にかかわる規律(人間の身体の解剖-政治学)と人口の調整(人口の生-政治学)にかかわっている。前者は、身体の調教、身体の適性の増大、身体の力の強奪、身体の有用性と従順さとの並行的増強、効果的で経済的な管理システムへの身体の組み込みを保証する。後者は、繁殖や誕生、死亡率、健康の水準、寿命、長寿といったものに関係している。その結果として、国家は、同性愛やホモセクシャルを、その傾向や異性への無関心、容姿などをもつ特別な人間とみなし、「変態」と位置づけ、治療すべき病人とするのである。
こうして、先天性の性行動障害をもつ特別な人々がいるとする精神医学も誕生する。これは、「変態」たる性行動障害が先天性なのか、それとも後天性なのかという議論をさかんにする。ジークムント・フロイトは、人間は、みな最初は両性具有であるが、子どもと親の関係の問題、不適切な発達、エディプス・コンプレックスの結果、正常な発達経路ではなく、異常な同性愛の発達経路が活性化してしまい、生殖や出産ができなくなるといった見方を説いた時期もある。
性革命
性に関する社会通念に対する否定や伝統的な性的行動からの離脱といった「性革命」が1960年代半ばに欧米諸国で起きる。その引き金になったのは、二つの「キンゼイ報告」だ(米国の白人男女約1万8000人の性に関する調査報告)。1948年に発表された「人間における男性の性行為」と、1953年発表の「人間女性における性行動」である。報告書を書いたアルフレッド・キンゼイは、「規範」と「変態」の対比から決定的に離れ、完全な異性愛者から完全な同性愛者までの尺度を開発したのである。その結果、ほとんどの人は、正規分布の統計的法則に従って、そのスケールの中間に位置することがわかった。
こうして、20世紀後半には、ソドム(同性愛者)が神の怒りを社会にもたらすという前近代的な恐怖はなくなった。1960年代から1970年代にかけて、国によって異なるスピードでソドミーに対する法律が廃止され、同性愛の傾向を持つ人々は、以前ほどそれを隠さなくなってゆく。「大きな節目は、1974年(診断の位置づけが曖昧だった時期)に精神医学の診断リストから同性愛が削除され、2013年にようやく削除されたことである」と、コスマルスキーは指摘している。
LGBT運動
だが、歴史には、紆余曲折がある。1969年6月28日未明、ニューヨーク市警察がニューヨーク市グリニッジビレッジにあったゲイクラブ、ストーンウォール・インを急襲したことからはじまった「ストーンウォール暴動」が起きる。この警察による「嫌がらせ」により、バーの常連客や近隣住民の間で暴動が起こり、警察が従業員や常連客を乱暴に連れ出したため、バーの外のクリストファー通りや近隣の通り、近くのクリストファー公園で6日間にわたる抗議行動や法執行機関との激しい衝突が続いたのである。このストーンウォール暴動は、米国および世界における同性愛者の権利運動のきっかけとなる。
1970年以降、LGBT運動はカウンターカルチャーとみなされ、「反社会的」な運動の一つとして少しずつ広がりをみせるようになる。この現象の時代背景を探ると、いくつかの説明が可能となる。
労働者であり消費者でもある人々のうち、生産手段としての労働力が重視された古典的資本主義は、一夫一婦制の家族単位を前提に、労働者の学校・病院・兵舎・工場への移動に力点を置いていたが、消費者がより必要とされるようになると、家族抜きの各人の趣味や興味に応じた消費への対応が求められるようになる。つまり、この新しい資本主義は、さまざまな欲望を持ち、最小限の安定性を持つ主体およびその変化から利益を得る。それは、家族や結婚への「伝統的価値観」とは異なる価値観を誘発した。
あるいは、グローバルな「近代の独裁」、つまり近代的でなければならないという社会的強制が、性的なものを含むあらゆる明確なアイデンティティを「侵食」し、不安定にするモーターとして作用した、とみなすこともできる。自分の性的アイデンティティを創造的に再定義しなければ、すなわち、「伝統的」で「つまらない」異性愛を超えなければ、各人はある種の非近代的で逆行的で後進的な人間であるとの強迫観念のようなものがLGBT運動を支えた面があるだろう。
ギデンズの見方
これに対して、アンソニー・ギデンズは別の説明の仕方をしている。経済的、人口的な必要性ではなく、パートナーたちの喜びや快適さのための関係である、彼が「純粋な関係」と呼ぶものが規範となったことがLGBTへの理解や支援につながっているというのである。
そこで、ギデンズ著『親密さの変容:現代社会におけるセクシュアリティ、ラブ、エロティシズム』(1992年)を繙くことにしよう。このなかで、ギデンズは、「感情的秩序」に焦点を当てながら、「ロマンティック・ラブ」、「可塑的セクシュアリティ」(plastic sexuality)、そして「純粋な関係」(pure relationship)という概念に親密さの変容を考察している。
「可塑的セクシュアリティ」はわかりやすい。それは、生殖の必要性から解放された、近代的避妊法や新しい生殖技術の普及とともに広がった。自由につくりかえうるようなセクシュアリティは男女間の親密さをめぐる関係にも影響をおよぼす。
ここでいう「関係」は「他者との密接で継続的な感情的結びつき」を意味している。ギデンズは、「純粋な関係」を、「ある社会的関係が、それ自体のために、他の人との持続的な関係から各人が得ることができるもののために結ばれ、それが、各人がそのなかに留まるのに十分な満足をもたらすと両者が考える限りにおいてのみ継続する状況を指す」としている。そのうえで、彼は、「ある時点で、どちらかのパートナーの意志で、多かれ少なかれ、関係を解消することができるのが、純粋な関係の特徴である」とのべている。
ギデンズが問題にしているのは、私的領域の民主化である。公的領域における民主主義化は、「当初、男性のプロジェクトであったが、やがて女性も参加するようになり、そのほとんどが自分たちの闘いによって実現した」。問題は、個人的な生活の民主化である。このように考えると、親子の関係、夫婦の関係、パートナーの関係など、私的領域におけるさまざまな形態での民主化という視角から、この新しい親密さを問う必要性に気づかせてくれる。
「うっせいわ!国家当局」
ここでは、これ以上は論じない。わかってほしいのは、ここで紹介したような人類の変化・変容のなかで、性の問題も考えなければならないことである。それは、キリスト教、主権国家を抜きに語れない。
私は時代の変化に敏感でありたいと思っている。その意味で、過去に拘泥するプーチン大統領のやり方に批判的である。ただし、「純粋な関係」を覇権国家の覇権維持のために広げようとするやり方にも反対だ。とくに、人、社会集団、国家のアイデンティティを、それらの過去の文化的差異を考慮することなく国家が無理やり統合しようとするやり口には、性別や年齢の差異を含む人々の個々の多様性をも破壊しようとする面があることを指摘しておきたい。
その意味で、ウクライナにおいて2022年6月20日、議会が「女性に対する暴力および家庭内暴力の防止及び対策に関する欧州評議会条約」(イスタンブール条約)を批准したことが思い出される。2011年に署名しながらも、条約に「ジェンダー」という用語が使われているため、教会や保守的な政治家からの抗議により批准が遅れていたお国柄であるにもかかわらず、主権国家を欧州側に少しでも近づけるために、国民の代理人であるはずの議員は国民のことなどすっかり忘れて平然と大切な価値観を踏みにじったのだ。すでに、同性カップルにシビル・パートナーシップを登録する権利を与える法案が議会に起草されている状況をみると、主権国家が政治的な理由で右往左往していることがよくわかる。
2023年4月6日、この日は反LGBTとして広く批判されているハンガリーの児童保護法に対して、欧州連合(EU)加盟国が法的訴訟に参加できる期限であった。これは、欧州委員会が2022年に起こした訴訟において、欧州議会とともに第三者として行動する国として参加するもので、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、オーストリア、アイルランド、デンマーク、マルタ、スペイン、スウェーデン、フィンランド、スロベニア、フランス、ドイツ、ギリシャの15カ国が加わることになった。
2021年6月に承認されたハンガリーの法律には、18歳未満の視聴者を対象としたメディアコンテンツや教育教材において、同性愛や性別変更の描写を禁止または大幅に制限する条項が含まれていた。このため、この法は明らかに性的指向に基づく差別であり、欧州連合のすべての基本的価値観に反するとして、2022年7月、欧州委員会は、国内法に変更を課す権限を持つ欧州司法裁判所(ECJ)に提訴したのである。これに、EU加盟の15カ国が加わったことになる。だが、イタリア、エストニア、ラトビア、キプロスは、2021年にハンガリーの法律を非難する集団書簡に首脳が署名していたことを忘れてはならない。これらの国は、訴訟に名を連ねることはなかった。対照的に、2022年、旧共産圏で初めて同性カップルの結婚と養子縁組を認めたスロベニアは、今回の訴訟に名乗りを上げた。
このように、つぶさにLGBT問題について考えてみると、この問題に国家がでしゃばることで、各国の国民の自由な選択権が毀損されていることがよくわかる。
本当は、「LGBTであろうとなかろうと、だれに対しても「国家当局がだれと寝るべきかを指示すべきではない」という主張」こそ、もっともっと広がってほしいと願っている。「うっせいわ!国家当局」なのである。
(敬称略)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
・ISF主催トーク茶話会:川内博史さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
・ISF主催公開シンポジウム:「9.11事件」の検証〜隠された不都合な真実を問う
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)がある。