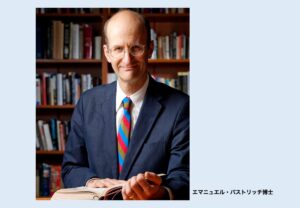大転換する世界と日本の生きる道―「アジア力の世紀」へ―(後)
安保・基地問題・「グレート・リセット」へ
2021年1月ダボス会議(世界経済フォーラム)がオンラインで開催された。
そこでは、習近平・中国国家主席が基調講演をし、次いでプーチン・ロシア大統領、モディ・インド首相、メルケル・ドイツ首相、マクロン・フランス大統領、フォンデアライエンEU委員長が続いた。そしてアメリカ新大統領バイデンは欠席した。それに同調するかのように、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ。英連邦構成のいわゆる「ファイブ・アイズ」の首脳たちも欠席した。
それは、単なる「パクス・アメリカーナ」の終焉を意味しているだけでない。2世紀以上にわたる「パクス・アングロアメリカーナ」の終焉をも象徴している。そのコロナ以後の現実が、中国の牽引下に多極化しながら「大転換する世界」が、ダボス会議のありように表出していたのである。
しかも今次のダボス会議の主題は、「グレート・リセット」だ。世界をあるべき元の状態に戻し、根本から〝つくり変える(リセット)〟戦略を議論することを意味している。
欧米中心の「近代」世界は終わった。そして近代終焉後のいま人類は、経済力を軸に見る限り、「近代」以前。植民地主義以前の世界へと立ち戻り、国際秩序を〝つくり変え〟ようとしている。ポスト・アメリカの展望と多極化世界の戦略を、世界の指導者たちが議論するというのである。
「大転換する世界」への展望と戦略を、コロナ後の世界の創出に向けて議論することを、それは意味している。実際、大転換する多極化世界の実相は、すでに世界の様々な現場に表出していた。
かくして、21世紀グローバル情報革命下で、中国やインド、インドネシア、メキシコなどを含むかつての途上国世界の国々が、飛躍的な経済発展を遂げた。南北逆転と東西逆転が、米中日逆転とともに同時進行し、その三重の逆転劇の主役を、中国が演じている。その現実が、中東の混乱と混沌を引き摺りながら、アジア、アフリカ、ラテンアメリカにも及んでいる。
・二重運動の中で
いま「大転換期の世界」で「二重運動」が展開している。その展開下で、新興覇権国家と現存覇権国家とが、熾烈な権力政治ゲームを展開している。時代を前に進めていこうとする勢力と、時代を後ろに引き戻そうとする勢力とのせめぎ合いである。その二重運動が、19年末以来のコロナ・パンデミック禍で、〝過ぎ去りつつある〟現存覇権国家アメリカの主導下に、熾烈な展開を見せている。
現存覇権国アメリカは、コロナ禍で世界第二の大量罹災者と死亡者を出しながら(いや、それ故にこそ)、21年9月、中東戦争の拠点、アフガンスタンからの撤退を正式決定した。そして新自由主義(ネオリベ)路線下で進展した超格差社会化を是正し、地球環境保全と医療福祉重視に力点をおいた、グリーン・ヘルス・ソーシャル・ニューディール政策を、国策の中心に据えようとしている。
併せて、トランプ政権下で進められた、排外主義的で自国中心主義的な「アメリカ・ファースト」の動きを逆転させて、国際協調主義路線への復帰を図りながら、「民主主義拡大」路線の復権をアメリカ外交の基本方針に据え始めている。それを、現存覇権国家アメリカの国際的リーダーシップの根底に据えて、軍事覇権主義体制の強化を進め始めている。その延長上に、アメリカは、米中〝新冷戦〟を推進している。その最先端に、新彊ウイグル族〝ジェノサイド(人種絶滅)〟問題を据えて、対中「新冷戦」の推進を図り始めた。
その時改めて、アメリカの同盟国ニッポンの立ち位置が問い直されてくる。日米間の同盟の流儀の問直しと言い換えてもよい。そして、かつてアメリカ「帝国の高揚」期につくられた「日米安保」と、それを基礎にした「日米同盟」なるもののあり方に、「帝国の終焉」期のいま、コロナ禍以後の世界で見直しが求められている
求められているのは、「同盟の流儀」に関する見直しである。それを、「アメリカ流の生き方」、アメリカニズムの見直しと言い換えてもよい。もし私たちが、〝日米同盟〟下で慣れ親しんできた「アメリカ流の生き方」を、コロナ禍という世紀大の人類史的な危機の中で捉え直すなら、その生き方が、三様の落とし穴を持っている現実に気づく。その三様の「同盟の落とし穴」を明らかにしていきたいと思う。
3.同盟の陥穽
・軍事安全保障の落とし穴
第一に、日米安保は、核兵器と巨大空母を中心とした、世界最大の精強な軍事力を軸に、「抑止力」と「攻撃力」によって日本の安全保障を維持することを国策とする。その日米安保条約と日米同盟による生き方が、いまコロナ渦で、壮大な非現実と非効率の上に成り立っているという「同盟の陥穽」。
たとえ「尖閣有事」が展開したとしてもアメリカが、日本救出のために軍事力を投入することは、二重の意味でありえない。日米首脳会談で、アメリカは、オバマやトランプからバイデンに至るまで、繰り返し、日米安保条約第5条(有事の際の米軍来援規定)は、尖閣有事の際にも適用されると公約し続けている。
しかしアメリカが、米中戦争のリスクを冒してまで、日本領土防衛に駆けつけることは、ありえないことだ。米国側極秘外交文書は繰り返しそのことを示唆し続けている。春名幹男氏が名著『仮面の同盟』(文春新書、2015年)の中で明らかにしたところだ。
それ故、コロナ禍と地球環境劣化の今日、求められているのは、安全保障観の転換である。安全保障の主軸を、医療福祉や健康、地球環境保全に重心移動させた「人間の安全保障」や「環境安全保障」である。いわゆるSDGs(持続可能な開発目標)の最大化こそが、軍事安全保障に代わる、もう一つの安全保障戦略の主軸として求められているのである。
逆に、軍事力強化を軸に日米同盟と日米安全保障を描く「同盟の流儀」は、いまや機能不全に陥り始めている。「日米同盟」のベクトルを、「人間と環境の安全保障」へと切り替えること。その切り替えが、コロナ禍の中で求められていることだ。
・経済的な落とし穴
第二に、日米安保形成時期に世界経済の過半を占め、消費と投資に関して、世界最大の経済力を有していたアメリカ市場への過度な依存を軸に、「日米同盟」の強化拡大をはかる「同盟の流儀」は、壮大な非現実と非合理性に遭遇するだろう。
いまや日米安保形成期から冷戦終結当時と違って、日本経済のアメリカ市場への依存度は縮小を続けている。そして逆に、アメリカ市場に代わって、中国をはじめとするアジア市場の持つ意味が年々拡大し続けている。たとえば、主要国・地域の輸出依存度に関して、1985年当時、対米貿易が、日本の貿易総額に占める比率は29.8%だった。
他方で、対ソ連・中国・東欧諸国との貿易が占める比率は、わずか1.6%に過ぎなかった。しかし2020年には、日本の対米貿易は貿易総額の14.7%と半減する一方で、対中貿易(香港を含む)は、貿易総額の26.5%に達している。そしてASEAN諸国を含めたアジア全体の貿易額は60%近くにまで増大している。
しかも、コロナ渦が本格化する前の19年に日本を訪問した中国人(香港人を含む)は1189万人であったのに対して、アメリカからは17万人、中国からの訪日客の1/7でしかなかった。
「アメリカがくしゃみをすれば、日本は風邪をひく」と揶揄された時代は、いまや遠い過去の話になってしまった。逆に、中国やASEANとの、とりわけ中国との相互依存と共生とを抜きにして、日本経済がもはや成り立っていかない世紀へと変貌しているのである。「パクス・アメリカーナ」から「パクス・アシアーナ」への転換が、軍事だけでなく、経済でも、同じように求められているのである。
その転換のためには、「日米同盟」のベクトルを、アメリア・ファーストから、中国とASEANを軸に、EUをも視野に入れた、アジア・ユーラシアとの共生。いわばユーラシア・ファーストへと転換させて、その中に日本経済のありようを組み込んでいくことが求められている。
それを「脱亜入欧」から「連欧連亜」への道と言い換えてもよい。
・政治的理念の落とし穴
第三に、政治的理念の観点からみた「日米同盟」の陥穽である。
かつて、戦後改革の中で日本政治システムの師表として位置付けてきた「アメリカン・デモクラシー」は、今日、様々な陥穽をあらわにしている。「デモス(民衆)」の「クラチア(権力)」の仕組みとしてのアメリカン・デモクラシーが、その本来の機能を果たしえなくなっているのである。
21世紀情報革命下でアメリカ資本主義が、「新自由主義(ネオリベ)」政策を基軸とし、金融株主中心の富裕層に裨益する「カジノ資本主義」へと変貌した。そのために1%の超富裕層が、国の資産の99%を占有する「超格差社会」へと、アメリカは変貌した。
その変貌を、アメリカ政治の金権化が後押しした。デモクラシーに代わって「金権政治(プルートクラシー)」が、政治の主軸になり続けている。「金持ち」の「金持ち」のよる「金持ち」のための政治が、すなわち金権政治が、政治理念としてのアメリカン・モデルを、機能不全に変えているのである。
金権政治化の動きは、2000年代初頭以来、米国最高裁判決によって、選挙資金規正を事実上なくしたことに起因する。
かつてクリントン再選時の1996年大統領選挙で投じられることが法的に許容された選挙資金総額は、9億ドルであった。それが、数次にわたる米国最高裁(特に2010年「市民連合」判決)をへて、今日、最大許容額は100億ドル(邦貨で1兆円)を超えるまでなっている。2016年大統領選挙で、全米に100以上のゴルフ場を持つ〝不動産王〟トランプの勝利を可能にした所以である。
まさに、アメリカ流「デモクラシーの死」であり、「プルートクラシ―(金権政治)の誕生」である。
いまアメリカ社会は、ネオリベ政策とカジノ資本主義下で、ポピュリズムと分断の危機にさらされ続けている。20年大統領選挙後、敗北したトランプ陣営の白人低所得者たちが、連邦議会を襲撃し、内戦もどきの政治劇を演じていた。その政治劇が、「デモクラシーの死」を露わにしている。

shot of election 2020
全米で5億丁(1人1丁)以上の銃器が出回り、銃犯罪が絶えることのないアメリカ社会の変貌が、官界や産業界、学術界やメディアに支えられた軍産官学複合体国家としてのアメリカ政治の現実を照射している。
ワシントン初代大統領以来、日本を含めた政治的後発国が〝師表〟とし続けてきたアメリカ政治の理念が、もはや世界政治を取り仕切るモデルとしても、政治的イデオロギーとしても機能していない。
にもかかわらず、そのアメリカが、「デモクラティック・ピース」論の大義名分下で、世界に、とり政治的経験の希薄な途上国世界に、「デモクラシー」を広めようとする。そのためにアメリカは、「同盟国」とともに、軍事的経済社会的な手段を総稼働させて、「制裁」と内政干渉を繰り返し、軍事力外交を展開する。
その時、私たち日本に求められるのは、「デモクラシー」なるものの再定義だと言ってよい。その上で、「日米安保」の再定義と再検証を進めたほうがよい。その再検証が、「日米同盟」のありようの見直しを求めている。その見直しが私たちに、コロナ禍で毎日1万人単位の死者を出し続けるアメリカの現実を直視させて、こう問いかけ続けている。「デモクラシーはいま機能しているのか」と。
「日米同盟」という「同盟の流儀」が、その理念とイデオロギーの点からもまた、問い直される所以である。
 進藤榮一
進藤榮一
北海道生まれ。1963年京大法卒。法博。筑波大学大学院名誉教授。国際アジア共同体学会会長、アジア連合大学院機構理事長。プリンストン大学等で客員教授等。著書に『アメリカ黄昏の帝国』『分割された領土』等多数。