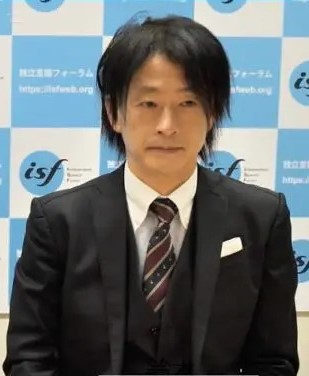アフリカで続く動乱の背景に欧米「新植民地主義」
国際この夏、ニジェール、ガボンとアフリカでクーデターが相次いだ。
西アフリカに位置するニジェールでは、反乱軍が政権掌握したあと支持者が大規模なデモを起こし、フランス大使館が襲撃されて玄関の国旗が破られ、表札が踏みにじられた。その後もサッカー場で何度も集会が行なわれている。
中心となっているのは、M62という市民団体である。隣国マリでの対イスラムテロ組織との戦い「バルカン作戦」のためフランスが派遣していた部隊が、マリおよびブルキナファソのクーデターによって撤兵し、ニジェールに移ってきたことに反対する15の団体が集まってできたものだ。代表のアブドゥレイ・セイドゥ書記長は冤罪の疑いのある放火の罪で1月末から収監されており、その釈放はデモ隊の要求の1つだった。
セイドゥ書記長は、バルカン作戦のフランス軍撤退要求の理由として、次の3つを挙げる。
①マリとの協力を妨げる
②テロリストよりも多くの民間人を殺害した
③戦争物資ではない機材やトラックを見かける
この3つのうち、③は、新植民地主義批判である。アフリカへ行くと、突然不釣り合いな最新のバスやトラックが走っていることがある。借款で貸手の国から購入したものだ。現地の実情を無視して、欧米の基準の法律と規格をつくり、工事のために必要な機器資材は輸入させる。欧米諸国が援助したといっても紐付きであって、自国に戻ってくる構造になっている。中国がよく批判されるが、彼らは自国の労働者まで送ってくるので目立つだけの話である。普通はエンジニアや監督要員を本国から送って、地元の安い労働力だけを利用する。決して技術移転などはしない。
「列強はアフリカ人の利益には関心がありません。彼らにとって重要なのは、影響力の戦い、アフリカでの経済戦争を行なうことです。アフリカ人に産業開発のための融資はしたがりません。なぜでしょうか? 天然資源の加工を通じて工業化を支援すると、彼らは自分自身の競争相手になってしまうからです。これが、アフリカ大陸に何10億ドルもの資金が貸し出されているにもかかわらず、いまだに工業化されていない理由を説明しています」(セネガルの経済学者パパ・デンバ・ティアム博士)
そして、この貸付を理由に国際金融機関が過酷な予算措置を課し、国家はますます弱体化し、国民は貧困に陥り、すでにひどい格差がさらに拡大した。
第1次世界大戦で過酷な賠償金を課したためにナチスドイツを産んでしまった教訓から、アメリカは、太平洋戦争の戦後処理において日本に対して賠償金を請求するのではなく、むしろ逆に復興支援して大きな下請け工場、市場とする政策をとった。高度成長が終わった頃からさかんに日米経済摩擦が起きたが、日本がアメリカ製品の巨大な市場になるはずだった目論見が外れたため、力づくで押さえようとしたのが原因である。
だが、もともと植民地として資源を奪われるだけの存在だったアフリカでは産業の素地がなく、そのようなかたちで利益を得るという選択肢は、はじめからなかった。なまじ産業を興すとデンバ・ティアム博士の言うように、競争相手をつくって自分の首を絞めることになる。そこで、独立しても前と変わらぬ収奪の対象でありつづけたのである。
植民地時代と違うのは、現地人による政府ができており、現地の権力者が私腹を肥やすようになったということであった。業者から賄賂を受け取るといった汚職だけでなく、権力を使って「合法的」にも行なわれている。たとえば、コメの栽培に適し、悠々2期作もできるのに、衛生上の問題があるなどと言って禁止し、外国から輸入して独占して儲ける。また、外国からの支援を受けるNGO(非政府組織)は利権そのものである。
ちなみに、戦後日本においては個人ではなく、自由民主党という組織をつくり、野党を買収しつつ政権を独占するメカニズムがつくられた。それでも、汚職まみれ、利権あさりだったのは変わらないが、財閥解体があり、もともと産業があったおかげで一般国民にも恩恵が及んだ。軍隊も禁止したため、武装勢力が政権奪取を企てることもなかった。アフリカでは、富は特権階級に独占される一方で、軍隊だけは出来ていた。
また、冷戦の東西対立の中で、共産陣営(ソ連とその手先としての北朝鮮)が反乱勢力に対して「解放支援」を行なった。かくして、クーデターはアフリカの宿痾になったのである。
第2次世界大戦後の植民地解放で、マグレブ(地中海沿岸アラブ圏アフリカ)やアジアでは独立戦争に発展した。しかし、サハラ以南のアフリカの独立は現地の人々が勝ち取ったものではなく、宗主国の都合によるものであった。植民地が新植民地主義に移行しただけである。

旧宗主国・フランスに守られたガボン独裁政権
中央アフリカのガボンは、旧フランス領の典型であった。1950年代、フランスは、ベトナム、次いでアルジェリアと独立戦争に悩まされ、国内の政情も不安定で短命政権が続いた。そんな中で、戦後政界から身を引いていたナチスドイツへの抵抗の英雄ドゴールが、事態収拾の切り札として大統領になり、憲法を改正して現在の第5共和制ができた。
彼はアルジェリアの独立を認め、反対するフランスの反乱軍も抑えた。同時にほかの旧植民地の独立も認めた。これは、ある意味、アルジェリアの教訓を生かし、ソ連などの後ろ盾を得て独立運動が起きる前に、先回りして各国に親フランスの指導者を置いて影響力を確保するためであった。
ガボンも1960年に独立した。初代ムバ大統領は、当初は反フランス派も抱き込んで政権運営をしていたが、独立4年後の1964年に反フランス派がクーデターを起こすも失敗すると、独裁を強化。1967年に死去すると、フランスの意向に沿って副大統領のオマール・ボンゴが後を継いだ。
1973年の石油ショックで産油国としてガボンは大きく儲けて国民を豊かにする機会を得た。しかし、結局、ボンゴ大統領とフランスの石油会社エルフ、そして彼らと共謀したフランスの政治家たちの資金となっただけで、国民生活は改善しなかった。
1990年、民主化を求める暴動があったが、フランスがボンゴ政権を守り、鎮圧した。しかし、ボンゴ大統領の私利私欲、縁故主義は目に余るものがあった。またフランス国内でエルフ石油の世界中での不正告発があり、その中で、ガボンとの癒着も明るみに出て大規模な裁判も起きた。そこで、フランス政府は距離をとるようになった。2009年のオマール・ボンゴ大統領の死後、息子のアリが後継者となった。
現在では、フランスとガボンの政界レベルでの黒い関係は断ち切られている。昨年6月にガボンが英連邦に加盟したのが、1つの証左といえる。だが、政権の腐敗は変わらない。今次クーデターでは、アリ・ボンゴ大統領の側近連中のところで札束の詰まったトランクが次々に公開されている。アリ大統領自身は2018年に脳卒中を起こし、代わりにフランス人の夫人が牛耳っているといわれる。
独立に際して、各国とも西洋の選挙・政治制度をいきなり当てはめて民主主義国家の体裁をとった。しかし、司法など政権チェック機関は無きに等しかった。旧宗主国が代わってチェックするわけでもなく、逆に短期的な安定や経済的利益の擁護のために、腐敗した政権や無能な政権と結託した。選挙もとりあえず形だけすればいいというものだった。冷戦の真っ最中であったので、親ソ連共産主義勢力の勝利を阻止するために複数政党制にしなかった。1990年頃、ガボンをはじめアフリカ諸国で民主主義運動が起こるが、冷戦の終結により複数政党制の確立が可能となったことも一因である。
軍事クーデターで政権奪取した者も選挙で「民主主義」のお墨付きをもらって独裁を維持する。選挙の不正は当たり前でも、一応、選挙で選ばれたという事実だけは残る(これは何もアフリカに限らない。ロシアのプーチンがそのいい例だ)。
たとえば、ニジェールの隣国ブルキナファソで昨年のクーデターによって失脚したブレーズ・カンパオレ大統領は、自らもクーデターで政権奪取したあと27年間政権の座にあったが、その間4回選挙をし、5回目の出馬に向けて憲法改正を準備していた時に、今回のクーデターにあった。
歴史学者のアシル・ムベンベ氏は、8月4日のル・モンド紙への寄稿で、このような民主主義の歪曲はフランスの「道徳的・知的敗北」であり、フランスの政治指導者らに大きな責任があると指摘する。彼らは皆、不正な選挙に拍手を送りつつ民主主義の守護者のふりをした。そのことがアフリカの民衆への民主主義と人権そのものへの幻滅を煽ってしまった。
そもそも、日本でいえば大正・昭和と同じぐらいの社会状況、民衆の状況になっていたウクライナやマグレブ、東南アジアと違って、サハラ以南のアフリカは日本の江戸時代の田舎と変わらない程度であった。その実情を正面から見すえた、それにふさわしい、徐々に民主主義に進む道はあったはずだが、模索することはなく、いきなり欧米の「民主主義」が導入された。
クーデターや選挙不正などによって民主主義が機能不全に陥っているのではない。そもそも、宗主国がいい加減な民主主義を導入したためだ。
また「民主主義」は、貧困も解決できなかった。さらにイスラムテロ組織が欧米とは違うアイデンティティを与えて不満層を取り込みつつ拡大した。これを潰してくれるとの希望をもって迎え入れられたフランス軍も期待外れで、住民の不安は解消されなかった。
この状況の中で、人々は、フランスに同化した憎むべき政権を排除するクーデターを支持したのである。
ニジェールとアメリカ・ロシア・フランス
ところで、ガボンとニジェールのクーデターには大きな違いがある。両国ともクーデターのあと、民衆が街に繰り出したが、ニジェールではロシア国旗と反フランスのプラカードを掲げていたのに対して、ガボンではそのようなものは一切なかった。
ガボンのクーデターの首謀者ブリス・オリギ・ンゲマ将軍はアリ・ボンゴの親戚であり、大統領を排除するための宮殿革命だといわれる。
ニジェールではロシアのプロパガンダによってクーデターが起きた。今回、クーデターにロシアは直接関与していないが、プロパガンダによる民衆の教化が行なわれていた。M62もロシアの影響を大きく受けている。
いま「ロシア」と書いたが、実際にはプリゴジンのワグネルおよびその関連企業である。貧困、若者の失業といった問題を解決できない親欧米の権力者、それと癒着するフランス人、イスラムテロ組織を撲滅できないフランス軍。これに対してロシアは伝統的な価値観の擁護、欧米支配からの脱却、多極化世界を訴える。ロシアを、アフリカの人々の間の兄弟愛と協力などを支援する正義の味方のように見せかける。
ガボンはいわばよくあるパターンのクーデターで、このまま収束するのであろうが、ニジェールは複雑な状況になっている。ダラダラと関係各国の駆け引きが続いているのだ。
ニジェールも加入する、西アフリカ15カ国からなるECOWAS(西アフリカ諸国経済共同体)は反乱軍が権力掌握を発表した直後にナイジェリアの首都アブジャで開かれた緊急会議で、ニジェール反乱政府に対して原状復帰に1週間の猶予を与え、さもなければ武力行使も辞さないとした。各国の軍トップによる作戦会議も行なわれ、待機部隊の動員も発表された。しかし、軍事介入は起きなかった。以来、ECOWASは、軍事介入したい勢力といま軍事介入はできないという勢力に分かれて動けずにいる。
反乱政府は、フランスとの防衛協定およびそのほかのニジェールに展開する約1500人のフランス軍兵士の駐留を規定する協定の破棄宣言をし、即時撤退を要求した。「フランスの声」とされるラジオ・フランス国際放送(RFI)とフランス24の放送が停止された。駐ニジェールのフランス大使はペルソナ・ノン・グラータとされ、8月25日に48時間以内に退去する命令が出された。フランス外務省はAFPに対し「反乱者にはこの要請を行なう権限はなく、大使の承認は合法的に選出されたニジェール当局からのみ得られるものである」と説明した。
マクロン仏大統領は9月15日、「ニジェールではフランス大使館で大使と外交官が文字通り人質に取られている。食料の配達を阻止されているので、備蓄している軍用糧食で食事をしている」と述べた。マクロンの性格からしてもフランスの立場からしても反乱政府を認めるわけにはいかず、ECOWASが介入するのに賛成している。
ただしこの強硬姿勢はEU(欧州連合)では浮き上がっている。アメリカはニジェールに兵力1000人規模の基地を持っているが、ブリンケン国務長官は、すぐに「受け入れられる軍事的解決策はない」と軍事介入に反対した。また、クーデター後に新しい駐ニジェール大使を任命した。その認証は反乱政府によって行なわれるわけで、反乱に対する暗黙の承認ともいえる。
クーデターの直前までアメリカはニジェール軍の訓練をしていた。反乱政府の参謀総長ムサ・バルム将軍はアメリカで訓練を受けており、以前からパイプ役にしている。ニジェールの基地は対ジハードテロ対策とアフリカにおけるアメリカ利権の確保のためにも重要である。
9月7日、アメリカ軍はニジェール駐留軍の再配置を開始したと発表した。これまでフランス軍兵士と共有していた首都ニアメの基地を最小限の人数だけ残して離れ、アガデス(北部)の基地に移す。フランスとは一線を画した。反乱政府もフランスに対しては条約を破棄し撤兵を求めているが、アメリカには求めていない。民衆デモでもアメリカは名指しされていない。
ロシアの方もプリゴジンの急死でややこしくなった。いままでならば、アフリカはプリゴジンが仕切っていて勝手にやらせておけばよかった。よく誤解されるところだが、金銭的にも、アフリカについてロシアがプリゴジン・ワグネルを支援していたのではなく、プリゴジン・ワグネルがロシアを支援していた。この駆け引きの背景にはウクライナの戦争がある。
ニジェールはマリ、ブルキナファソと集団安全保障条約を結び「サエル国家同盟」を結成した。万が一、軍事介入となれば、マリ、ブルキナファソも参戦するわけで、下手をするとロシアとアメリカ、フランスの直接の戦闘ということになる。ウクライナで避けようとしていたことがこのアフリカの地で起きてしまうのである。
(月刊「紙の爆弾」2023年11月号より)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ISF主催公開シンポジウム:WHOパンデミック条約の狙いと背景~差し迫る人類的危機~
● ISF主催トーク茶話会:小林興起さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内