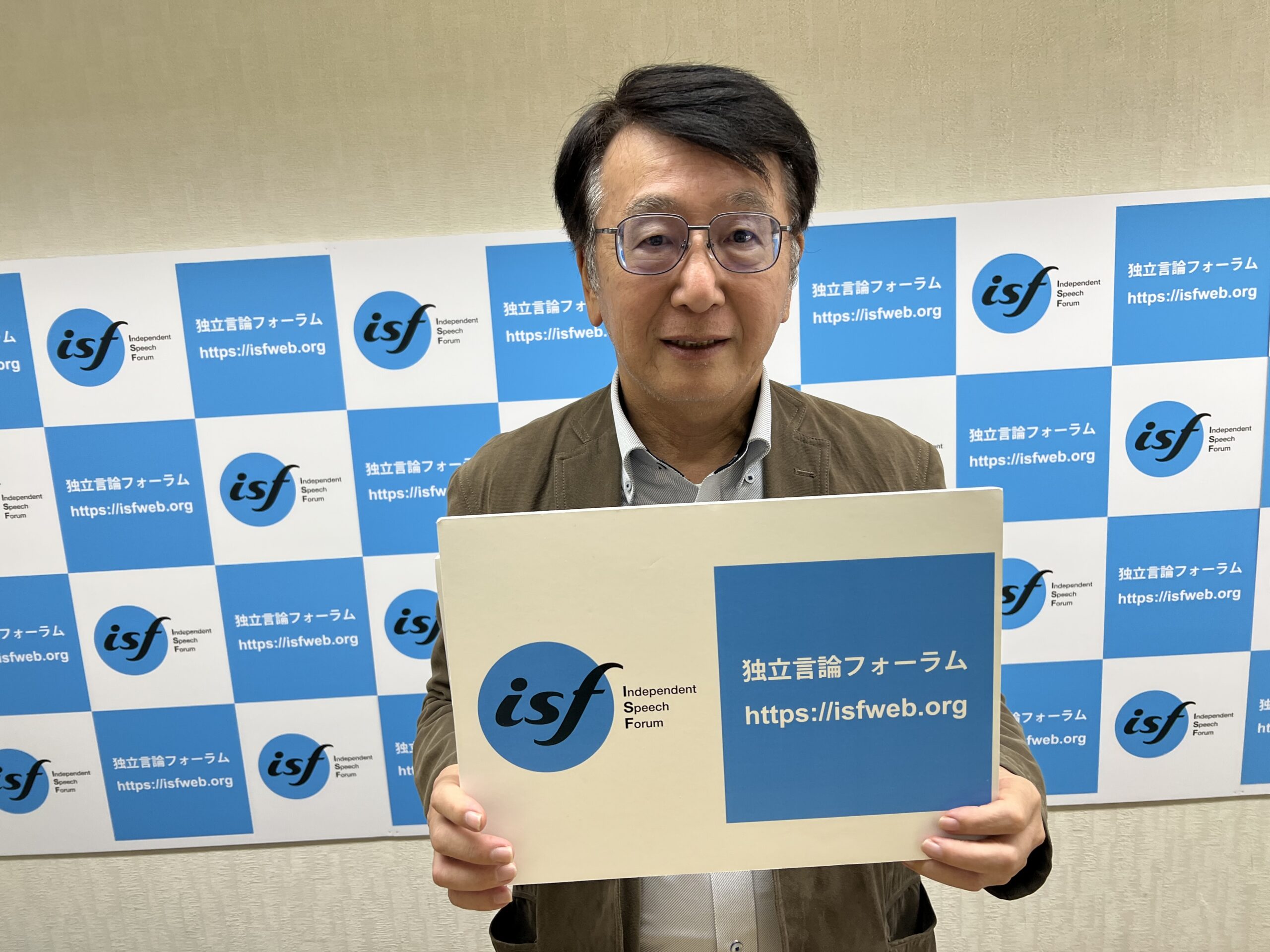【書評】塩原俊彦『知られざる地政学 覇権国アメリカの秘密 上巻』―「科学の政治化」に警戒を
映画・書籍の紹介・批評
既にISFで関連する連載が進行中ですが、主要寄稿者の一人である塩原俊彦氏による新著『知られざる地政学』(以下、本書)が、社会評論社から今年9~10月に刊行されました。上下巻で700頁を超える大著ですので、2回に分けて紹介します。上巻では「総論」として、「米国の覇権を支える構造分析」が展開されます。
ロシア・ウクライナの問題について、2014年の『ウクライナ・ゲート』(社会評論社)から23年の『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社)に至るまで、多くの著作をものして、ロシアのみならず、米国の政策も批判的に分析してきた塩原氏。実は『サイバー空間における覇権争奪』(社会評論社、19年)等の著作もあり、科学技術に詳しい経済学者でもあります。
「まえがき」に「ウクライナ戦争を契機に、世界の覇権をめぐる動きについてじっくりと考えた」(7頁)とあるように、世界中で有害な介入政策を続ける米国の覇権の背景を科学技術の観点から問い直す著作である、といえると思います。根幹となる解釈図式は、「科学技術の推進」→「安全性の軽視」→「米国の影響力拡大」が米国の覇権の源泉(8頁)、というものです。通常、地政学とは、「民族や国家の特質を、主として地理的空間や条件から説明しようとする学問」として理解されています(『デジタル大辞泉』、
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%9C%B0%E6%94%BF%E5%AD%A6/)。この見方に対して、本書の科学技術重視の視点は、表紙にあるように「新たな視角からの再構築」ということができるでしょう。
第1章「米国の覇権をめぐる理解」
第1章では、英語の頭文字を取って「NBIC」と呼ばれるナノテクノロジー、バイオテクノロジー、情報技術、認知科学の分野への国家支援が、米国の覇権維持につながる、という基本的な認識が、米商務省の報告書に基づいて解説されます(18-19頁)。第2章を先取りする形で、「科学の政治化」という重要概念が提示されます。例えば気候変動の主な原因を二酸化炭素排出に求めるIPCC等主流の見方は科学的に決着した事実では全くなく、異論を唱える科学者も少なくありません。にもかかわらず、「国家そのものや、個人や組織が大規模なミスインフォメーション(誤報)やディスインフォメーション(意図的で不正確な情報)を流して、自らの利害に有利な状況をつくり出」(20頁)す、という事態です。気候変動に関わるパリ協定は、直接温暖化ガスを出さない「核発電」(原子力発電は誤訳とされる)の大国であるフランスの首都で結ばれた、という事実も見逃せません(23頁)。他方で塩原氏自身は、原因は何であれ気候変動を心配しており、IPCC等とは反対の立場である石油業界にも科学に関する不誠実な態度が見られる、と指摘することを忘れません(24-25頁)。
第2章 「科学の政治化」
第2章では、第1章で導入された議論を受けて、「科学もまた、権力闘争の場」「だからこそ、科学は政治を味方につけることで、権力闘争を勝ち抜こうとする」(30頁)といった基本認識が示されます。「科学の政治化」という概念を詳しく論じた科学者であるウィリアム・ハッパーの「政府が科学に資金を提供する場合、政治化は避けられない」(33頁)という洞察は、本書を導く糸となるものでしょう。
そのような科学の政治化の歴史的実例として、ソ連時代の科学者トロフィム・ルイセンコの「冬小麦の苗を低温処理し、春に播種すると高収量が得られる」(38頁)という見解が挙げられます。今から見れば間違った学説ですが、これがスターリンに気に入られたことで、科学的に正当とみなされ、生物学という科学を歪曲してきた、と論じられます。
ソ連のような“後進国”だからそのような事件が起こった、と考えるのは傲慢であると私には思われ、その証拠が1989年以降に欧米で起きた「低温核融合」事件です。通常は太陽のように極めて高温でないと起きないとされる核融合が常温で実現したという主張ですが、後に誤りと判明しました。この事件の背景には、研究費獲得を巡る大学間の競争や、この技術を大々的に利用したい政治家らの熱狂があったとされます。
米国は「科学と結託した覇権国」であり、核発電、遺伝子組み換え、AIは安全だ、と
いう「気高い噓」(プラトン)を最先端科学の美名の下に広め、自らの優位確立・拡大に利用しているという洞察(59頁)。こうした見解は、「科学者・専門家の多数派意見に従うのが無難」といった事大主義的な傾向からは決して出てこないものだと思います。
第3章 知的財産権と米国の覇権
第3章では、特にTRIPSというWTO加盟国に義務付けられた貿易協定、法的枠組みに焦点が当てられます。「知的財産権の貿易関連の側面に関する協定」です。TRIPSは、WTOの紛争解決機構を利用しつつ、表面上は、個人主義・普遍性・一般性といった一見理想的な原則を体現するかのように見えます。ただその裏側としては、グローバル化という大義の裏側に、知的財産権に関する米国の国内基準の強制という利己的な二重基準がある、と指摘されます。実際に、他国が自国経済を保護するような動きを少しでも見せると、米国がTRIPSに基づき提訴する、といった傾向が見られます。南アフリカによるエイズ患者のための安価な医薬品を並行輸入するための法案すら、訴訟の対象になったわけですから、命に関わる重大事態といえます。TRIPSは普遍性を装いつつ、「米国主導の科学技術の優位を固定化することをねらった」(81頁)ものだ、ということを押さえておきましょう。
第4章 科学技術の「進歩」と情報操作
第4章は本書の主要部分であり、200頁近くにわたります。核発電、遺伝子組み換え・ゲノム編集、サイバー技術、AIを具体的題材として、科学の政治化の米国の覇権への影響が分析されます。そこではマスメディアと政府の密接な協力も、多数派向けの情報操作の点では、大きな役割を果たしてきたとされます。「政府が情報源であるという構図が変わらないため、マスメディアは政府による情報操作に脆弱だ」「そもそもなにが問題かの問題設定すらもマスメディアに委ねられてしまっている」(95頁)という指摘は、日本にもかなり当てはまるものでしょう。
核発電
最初に論じられる核発電は、3・11を経験した我々日本人にとって馴染み深いものでしょう。核爆弾と同様の原理である核分裂を用いた発電方式である核発電は、1951年に米国で実験が成功し、53年のアイゼンハワー大統領による「平和のための原子」演説で世界中に知られることになりました。この演説に対する塩原氏の評価は、「米国が開発した核エネルギー技術を積極的に世界に提供することで、第三世界を自陣営に取り込むだけでなく、ソ連陣営に対する優位も確保できるとみた米国の覇権戦略であった」(99頁)という厳しいものです。平和という言葉に騙されてはならない、という意味も恐らく込められているのでしょう。
メディアによる核発電推進への協力事例としては、1957年のディズニーの映画Our Friend the Atomが挙げられています。日本ではあまり知られていませんが、66年にミシガン州のエンリコ・フェルミ核発電所で、部分的炉心溶融が起こり、100万人単位の避難が計画されていました(102頁)。そこまでの過酷事故でありながら、米国のメディアは殆ど報道せず、5週間もたってから、『ニューヨーク・タイムズ』が”mishap”(ちょっとした不運)に過ぎないものとして伝えたと聞けば、主要メディアがどれだけ取り込まれていたかが分かります。
日本でも1955年から「平和のための原子」キャンペーンが展開され、読売新聞・日本テレビをはじめ、多くのメディアが協力しました(110頁以下)。同時期の『鉄腕アトム』にも一言言及されます。考えてみれば、アトムは人工知能を搭載し、核エネルギーで動く兵器ともいえますので、本書の問題設定とも関わりが深いものです。こういったキャンペーンにより、哲学者で被爆者の森滝市郎のような著名な核廃絶指導者ですら、核エネルギーの平和利用に騙されてしまった、と総括されます。
遺伝子組み換え・ゲノム編集
我々の日常生活に深く関わる食の安全の問題。それを潜在的に深く脅かしうるのが、遺伝子組み換えとゲノム編集の技術です。前者は当該の生物への外来遺伝子の導入を行うものであり、後者は当該の生物の遺伝子の範囲内で改変を行う技術である、という違いがあります(160頁以下)。
遺伝子組み換えは遺伝子操作・遺伝子工学とも呼ばれ、種の壁を越えて人為的に形質転換を起こし、世代を超えて遺伝的性質を伝える技術です(119頁)。高度な技術であることは間違いないのですが、複雑な生命過程への介入を行い自然界に存在しない生命の形態を作り出すため、未知のリスクが伏在していることは否めません。にもかかわらず、米国科学アカデミーは、1987年の報告書で、遺伝子操作された生物に「特異な危険性はない」と決めつけます(127頁以下)。92年になると、米食品医薬品局(FDA)は、ほとんどの遺伝子組み換え作物と、非組み換え作物は同じように安全、とさえみなすようになります(128、130頁)。私が補足しておくと、このFDAが、長期の安全性を確認することなく、コロナワクチンに「緊急使用許可」を出した組織であることは、「医食同源」の観点からも、感慨深いものです。レーガン・ブッシュ両政権の下で確立した「危険であると証明されるまでは安全であるとみなす」(130頁)という楽天的な原則は、事実上の人体実験を正当化しているのでは、と私は疑っています。
今日では忘れられつつあるのかもしれませんが、実は日本の昭和電工も、1989年ごろに、遺伝子組み換えを巡る大問題を起こしていました。同社が生産したL―トリプトファンという食品が、好酸球増加・筋肉痛症候群という病気を引き起こし、19人もの死者を出した、という疑惑です。にもかかわらず、米国の裁判所は、この事件について、遺伝子組み換え自体ではなく、あくまで製造工程の問題にすぎないと断定しました。米FOXニュース傘下の地方テレビ局が、モンサント社の遺伝子組み換えの牛成長ホルモンについてのデータ改ざん事件を取り上げようとしたところ、広告主のモンサントからの圧力で番組が放送中止に追い込まれたという事件も起きました。主要メディアもまた、一連の情報操作の共犯者となってきた実態が見えてくるといえるでしょう。塩原氏は、こうしたリスクの矮小化・隠蔽を介して、遺伝子工学が既成事実化した過程と、核兵器と同根の核発電が世界中に広まっていった過程に、共通点を看取しています(以上、136頁以下)。
こういった文脈で塩原氏は、新型コロナウイルスを巡る重大な疑惑にも斬り込んでいます。2023年末に、経営科学出版から『The Real Anthony Fauci人類を裏切った男』として全3巻の邦訳が刊行されている、ロバート・F・ケネディ・ジュニアのベストセラーに依拠しています(https://www.trannet.co.jp/works/view/13943)。ケネディの緻密な分析、および米独立系メディア・『インターセプト』の調査報道によれば、後に新型コロナは自然発生である、と強硬に主張した米国立アレルギー感染研究所所長のアンソニー・ファウチらは、当初メールで人工的改変の跡が存在する可能性が高い、と真剣に議論していたことがわかっています。インターセプト連載は、以下で閲覧できます。
https://theintercept.com/series/origins-of-covid/
塩原氏が「遺伝子組み換えを生物・化学兵器として利用する研究が進められていた可能性を否定することはできない」と、慎重な表現ながら踏み込んだ洞察を示していることには、敬意を表したいと思います(以上145頁以下)。本稿執筆中には、精緻な分析により、コロナ人工説やコロナワクチンの問題点について訴えてきた京都大学の宮沢孝幸准教授が、2024年5月をもって退職に追い込まれるという発表もありました。これもまた、科学が政治化しているが故に起こる事件ではないでしょうか。
デイリースポーツ:「ワクチン問題告発の京大准教授が退職へ『大学から最後まで理解を得ることはかなわず』宮沢孝幸氏今後は『まったくの白紙』」、2023年10月31日。https://www.daily.co.jp/gossip/2023/10/31/0016979353.shtml
こういったリスクが否定できない遺伝子組み換え技術に対して、日本の厚生労働省等は、米国の方針に追随して、当該生物の遺伝子の切り取りを行うだけのゲノム編集は安全だ、といった説明を繰り返してきました。ところがこの分野の重要文献であるスティーブン・M・ドルーカー『遺伝子組み換えのねじ曲げられた真実 私たちはどのように騙されてきたのか?』(守信人訳、日経BP、2016年)によれば、ゲノム編集が行う遺伝子の順番の変更もまた、遺伝子の性質に影響することが判明しています。こうした事実にもかかわらず、トマト・マダイ・トラフグ・トウモロコシ等のゲノム編集作物は日本で既に商品化されており、しかも表示義務はありません。ちなみに既述の遺伝子組み換え食品については、2017年に安倍政権は、「厳格化」の美名の下、「組み換えでない」という表示を事実上不可能にすることで、区別を不可能にした、という巧妙な情報操作の実態が暴かれます。日本の主要メディアも厳格化という表面上の名称に騙されてか、あるいは巨大スポンサーたる食品業界の圧力によってか、批判的視点が乏しい、という指摘も重要です。
こういった日米の極めて甘い規制に対して、ゲノム編集は遺伝子組み換えと本質的に変わらないと判断しているのがEUです。EUは予測されるリスクに先行的に対処する「予防原則」を採用して慎重に対処している、という事実も知っておかねばならないでしょう(以上、157頁以下)。既述の「危険と証明されるまでは安全」といった、冒険的とも呼びたくなる方針では、最先端技術の潜在的脅威から我々の命を守ることはできない、といえるでしょう。
サイバー空間
エネルギーや食品に劣らず、現代人の日常生活に多大な影響を及ぼすようになってきた情報技術(IT)。その舞台たるサイバー空間でも、米国は「デジタル・ミレニアム著作権法」(DMCA、1998年制定)をグローバルスタンダードとして世界中に広めることで、覇権を拡大してきた、と論じられます(197頁)。ソーシャルメディアが行ってきた「自主検閲」としての「コンテンツ・モデレーション」を正当化する通信品位法(CDA)と同様の内容を、米国政府は各国とのデジタル貿易協定に盛り込み、グーグル、フェイスブック等の自国の巨大IT企業を守ろうとしてきた経緯も見逃せません。補足しておくと、例えば、グーグルの子会社たるユーチューブは、コロナワクチンについて自らが「誤情報」とみなした内容を含む動画を、削除し続けてきました。
https://support.google.com/youtube/answer/13813322?hl=ja
かつてはサイバー空間は共有資産、「グローバルコモンズ」である、という考え方もありましたが、2011年のホワイトハウス文書「サイバー空間の国家戦略」はデジタルインフラを「国家資産」とみなすようになりました(201頁)。公共空間だったはずのものが私物化されてきた、ともいえるでしょう。グーグル等の「テック・ジャイアンツ」が儲かれば、米国政府の税収も増える、という思惑も当然あるということです(226頁)。グーグルが「ニュース・ショーケース」という仕組みにより、ニュース提供者たるメディア企業への支払いをしていることは、日本でも報道されました。巨大ITによる「ただ乗り」を防ぐことは必要ですが、こうした一見正当な「支払い」により巨大ITがメディアの「顧客」となり、批判的な検証報道ができなくなる、といった懸念も生じ得ると私は思います。サイバー空間においても、日本政府が米国の覇権に追随しているのに対して、EUは2018年の「一般データ保護規則」(GDPR)によって、プライバシー保護を図り米国に対抗している、という構図(207、226頁)ができていることは、遺伝子組み換え・ゲノム編集にも似ています。
人工知能(AI)
一般メディアでも、チャットGPT等、生成AIを巡る話題は多くなっていますが、塩原氏から見れば、こうした傾向は「対象となる科学技術がある程度普及したあとで急に叫ばれるようになった『規制事実化』への最後のあがきのようにしかみえない」(231頁)とされます。AIについては、人間の知能を超え得る完全自律型のAGI(Artificial General Intelligence、いわば一般人工知能)の可能性すら、取り沙汰されるようになっています(243頁)。ウクライナ・ロシアの戦争では、自律型ドローンが投入されています(245頁)。こういった経緯と可能性を踏まえて、AI規制の必要性は核兵器に劣らず重要、と訴えてきたのが100歳になったヘンリー・キッシンジャーです(264頁)。AIの応用では、中国がその人口に見合った膨大なデータ量と、中央集権的体制が相まって、比較的有利な立場にある、ともされます(258頁)。私が想起するのは、監視カメラとも連動して、個人の行動を点数で格付けし、それが就職や結婚にまで影響しうる、とされる中国が既に実現している「信用スコア」です。参考:NHK「クローズアップ現代 個人情報格付け社会 ~恋も金回りもスコア次第!?~」、2019年2月12日。https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4245/
ところが一般には恐らくあまり知られていないのは、米国の国防高等研究計画庁(DARPA)もまた、「社会的行動、社会経済的地位、個人的特徴に基づいて人々を分類すること」という「ソーシャルスコアリング」によく似た「信頼度スコア」なるものを研究している、という事実でしょう。塩原氏は、機械学習のデータに白人と男性のものが多いなど、本質的に偏向を持ち公平でないAIの負の側面に警鐘を鳴らしています。その上で、AIに関する既得権益を持つ人々が、発展途上とされる国々の人々に自分達の基準を既成事実として押し付けて支配する「デジタル・コロニアリズム」に対する警戒も促しています(以上271頁以下)。
AI全体についても、遺伝子組み換え等と同じように、EUは規制に前向きであり、日本はやはり米国に追随しがち、と塩原氏は評価していますが(260頁)、悲観的にならざるを得ない現状です。
第5章 覇権国アメリカの扇動とエスタブリッシュメントの正体
第5章では、まずは塩原氏がこれまでの著作でも再三論じてきたウクライナ戦争が、再論されます。プーチン大統領によるウクライナ軍の能力の過小評価、それをもたらした諜報機関・FSBの「大失態」等ロシア側の問題に加えて、バイデン大統領やヴィクトリア・ヌーランド国務次官らによる世界中の「民主化」を「宣教師的」使命と考えて介入を繰り返す米国の「リベラルな覇権主義」も批判されているのが、既存のウクライナ問題本に対する大きな違いです(281頁)。塩原氏はウクライナ戦争の終わらせ方についても考察していますが、ここで重要になるのが「戦略的共感」または「戦略的感情移入」という概念です。これは敵国の立場になって考え、敵国を追い詰めすぎないようにする外交上の態度です。即時停戦と無前提の交渉開始と妥協による和平を唱える著者は、この概念にのっとり、ウクライナ政府が目指すクリミア奪還は行き過ぎ、と見なします。なぜなら2014年のクリミア併合は同年に米国も深く関与して起こした「マイダン革命」(またはクーデター)への反応であり、ロシアから見れば奪還の試みは侵略と見られてしまう、とされるからです(以上292頁以下)。
第5章の末尾で塩原氏は、米国の覇権を実質的に握っているとされ、「既存権力体制」等と訳される「エスタブリッシュメント」(本稿ではエスタブと略記)についても分析を展開しています。『ニューヨーク・タイムズ』記者だったレナード・シルクと、その息子の歴史研究者マーク・シルクの共著『The American Establishment』(1980年)によると、エスタブはビジネス界と政府に対する「第三の力」として定義されます。彼らは、エスタブの所属先として、ハーバード大学、『ニューヨーク・タイムズ』、フォード財団、外交問題評議会、(『フォーリン・アフェアーズ』の発行元)等を挙げています。エスタブは民主、共和といった党派性を超えた存在とされ、Center for a New American Security(CNAS)のような好戦的シンクタンクとも親密な関係にあるとされます―マイダン革命の立役者となったヌーランド氏もCEOを務めた所です。CNASの資金源が、ボーイング、ロッキード、レイセオンといった軍事企業であることも、象徴的です。これに対して、米国政治の異端者たるトランプ前大統領がエスタブをグローバリスト、ネオコンと同列とみなし、まさに米国の敵として非難しており、塩原氏はそこに相当な正当性を認めています。本書のこれまでの議論のつながりとしては、エスタブこそが、遺伝子組み換えのようなリスクをはらむ技術を推進し、莫大な利益を得てきた、といった関係がある、と論じられます。こういった論調は、今日の論壇において貴重だと思います。本書のエスタブ論は、俗に「ディープ・ステート」といった概念が引き合いに出され、しばしば無根拠な形で語られてきた、大統領や議会などの公的権力以外の権力構造に焦点を当てるものとして、大きな価値があると私は考えています。米国の議会証言により知られるようになったことですが、政府機関・NGO・学術機関・巨大IT企業等からなる「検閲産業複合体」が、エスタブにとって不利な情報や事実を削除・排除して、実質的な世論誘導を行ってきたことも、ISF読者の皆さまには知っておいていただきたいです。(下巻へ続く)
※塩原氏の講演会「ウクライナ戦争をどうみるか〜情報リテラシーの視点から」が12月2日(土)の14時から、北多摩西教育会館で開かれます。詳細は次のページをご覧ください。
https://isfweb.org/event/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!
 嶋崎史崇(市民記者・MLA+研究所研究員)
嶋崎史崇(市民記者・MLA+研究所研究員)
1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。 論文は以下で読めます。https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評とインタビューに力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント:https://x.com/FumiShimazaki