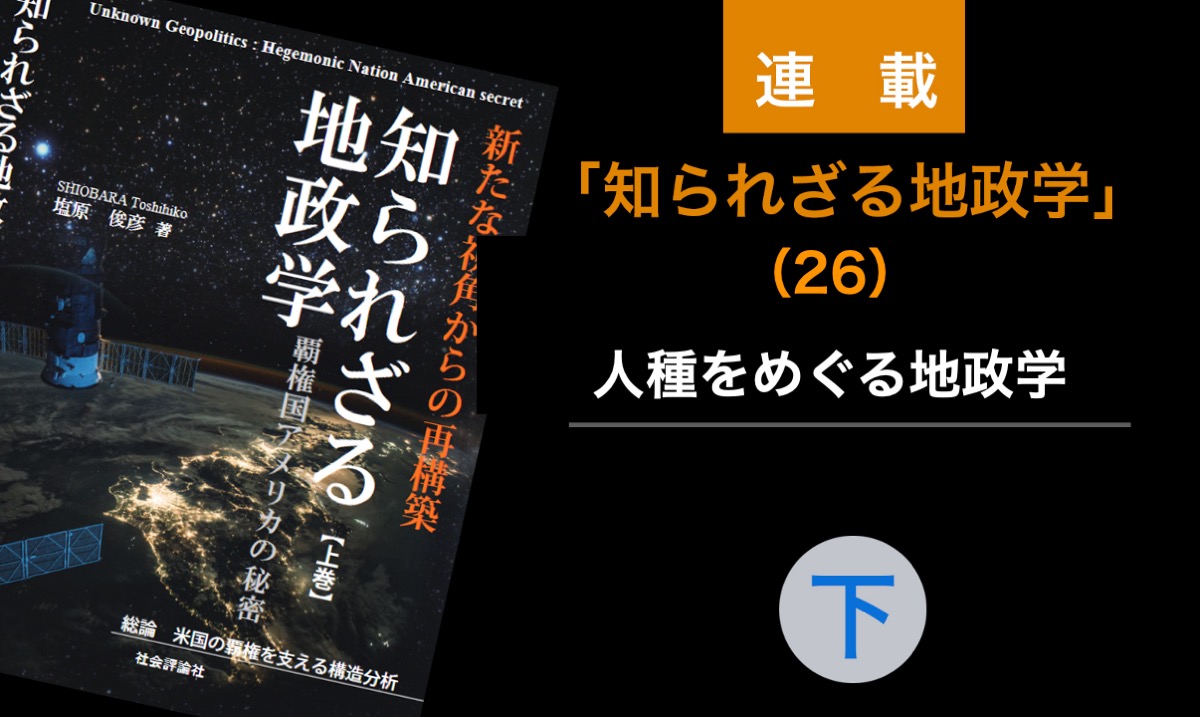
「知られざる地政学」連載(26) 人種をめぐる地政学(下)
国際
「知られざる地政学」連載(26) 人種をめぐる地政学(上)より
「人種は実在しない」と科学がいう皮肉
論文「人種と遺伝学対遺伝学における「人種」」によると、「分類学用語として、人種は物理的にも遺伝的にも異なる亜種を非公式に細分化したものである」が、「ホモ・サピエンスという種は、物理的にも遺伝的にも異なる亜種にさらに細分化することはできない」。さらに、2003年、ヒトゲノム計画(HGP)の第一段階が、現在地球上に存在する人類はDNAレベルで平均99.9%同一であり、人種に遺伝的根拠はなく、人種間よりも人種内の方が、遺伝的変異が大きいことを証明したことで、「遺伝的カテゴリーとしての「人種」という考え方は、おそらく一掃された」と指摘している。これもまた、現代の科学なるものが生み出した結論であることが何とも皮肉である。「科学の政治化」を前提とすれば、この結論に対しても、簡単に首肯することはできまい。加えて、拙著『知られざる地政学』〈上巻〉において、つぎのように指摘しておいた。
「「”The “ヒトゲノムは常に誤記だった」という興味深いタイトルのThe Economistの記事によると、「すべての赤ちゃんは両親のどちらにもない数十種類の変異を持った状態で生まれてくる」のであって、本来、固有のヒトゲノムは存在しないのだ。だからこそ、人間はほとんど同じであるが、その違いは重要であるとみなして突然変異に注目する。」
つまり、科学は「進化」するのであって、一時期の科学の結論が正しいかどうかはわからない。決して鵜呑みにはできないのである。
広がる「人類=社会的構築物」説
新しい遺伝学の成果は、「人種は社会的構築物である」(Race Is a Social Construct)という主張に通じている。100年以上も前に、米国の社会学者W.E.B. Du Boisは、異なる集団間の社会的・文化的差異を理解するための説明に、人種を生物学的説明として用いることに疑問を呈していた(『黒人の再建』を参照)。
さらに、マイケル・ユーデル著『仮面を剥がされた人種:20世紀の生物学と人種』(2014)では、「今日われわれが理解しているような生物学的人種概念は、優生学の差異理論に端を発し、1930年代から1940年代にかけて、生物学における進化論的統合のなかで、集団遺伝学者と進化生物学者によって再創造され、現代の生物学的思考に統合された」と指摘されている。この「統合」後、多くの科学者が「いわゆる人種集団間の固定的な遺伝的差異という優生学的・類型論的概念を否定するようになり、その代わりに、人間の人種を、それらの集団間の遺伝子の頻度の変動によって区別される動的集団として理解するようになった」というのがユーデルの主張である。
「批判的人種理論」
最近になって注目されているのは、「批判的人種理論」(Critical Race Theory, CRT)である。CRTは、「人種は人間の物理的に異なるサブグループの自然で生物学的な特徴ではなく、有色人種を抑圧し搾取するために使用される社会的に構築された(文化的に発明された)カテゴリーであるという前提に基づいて緩やかに組織された法的分析の枠組み」である(2023年10月25日に更新された「ブリタニカ」を参照)。批判的人種理論家は、人種差別は、白人と非白人、とくにアフリカ系アメリカ人との間に社会的、経済的、政治的不平等を生み出し、維持するために機能している限りにおいて、米国の法律と法制度に内在していると主張する。
こう考えると、人種差別は主として個人的な信念の問題ではなく、アメリカの制度に構造的に埋め込まれているものだから、人種差別を根絶するための誠実な努力には、制度がどのように機能するかを変えることが必要となる。単に人種隔離をなくし、あからさまな人種差別政策を禁止するだけでは十分ではないのである。
ほかにも、CRTは、「人種」の概念は科学に根拠があるのではなく、むしろ人々によって(しばしば冷笑的に)定義されているとみなす(The Economistを参照)。人は複数の交差するグループのメンバーであり、一つのグループのメンバーとしてだけみることは、人々の間の重要な違いを無視する危険がある、と主張する見方(キンバーレ・クレンショーによる「交差性」[intersectionality]の主張)もCRTのなかにある。
なお、CRTは、2013年に結成された、人種差別と反黒人暴力、特に警察の横暴と闘うことを目的とする「ブラック・ライブズ・マター(BLM)」運動の拡大に拍車をかけた。この結果、ドナルド・トランプ大統領とその政治的盟友は、BLMのデモ参加者を「凶悪犯」と非難し、警察や私有地への暴力的攻撃について虚偽の非難を行うことで、周知の人種差別的ステレオタイプを明確に支持するようになった。こうして、2017年1月に大統領に就任したトランプは、CRTを「有害なプロパガンダ」であり、「我々の国を破壊する」と断じた。その結果、2023年1月に公表された資料によると、「2021年1月以来、42の州が、人種差別や性差別に関する議論を制限する反CRT法案を提出している」という。2024年2月の段階では、九つの州でCRTを教えることが禁止された(WPを参照)。
米国企業におけるDEI運動
ついでに、2020年にジョージ・フロイドが殺害された後、アメリカ企業はダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン(多様性、公平性、包括性)制度(DEI)の導入を急いできたことを書いておきたい。2022年までにS&P500の4分の3がチーフ・ダイバーシティ・オフィサーを置き、上場企業の5分の2以上が従業員の人種的多様性を高める目標を設定したとThe Economistは紹介している。2015年、コンサルタント会社のマッキンゼーは、従業員の性別や人種の多様性と企業の収益性の間に正の相関関係があることを明らかにしたことから、米国企業内では、人種の多様性の確保が大真面目で語られるようになっている。たとえば、2021年8月、証券取引委員会はナスダック(NASDAQ)のダイバーシティ関連規則案を承認した。この規則の目的は、ほとんどのナスダック上場企業が、少なくとも1人の女性取締役と、もう1人の代表権の低いマイノリティまたはLGBTQ+を自認する取締役を擁することを義務づけた。この結果、人種については、2023年以降、ナスダック上場企業は少なくとも1人の白人以外の取締役を置くか、置かない理由を説明しなければならなくなっている。
だが、ハーバード・ロースクールのジェシー・M・フリード著「ナスダックの多様性ルールは投資家を害するか?」では、この規則が投資家の利益になるとナスダックが主張していることに対して、「役員室における性別や民族の多様性が株主価値を高めるという主張の裏づけとなる実証的証拠はほとんどない」と批判している。さらに、実際、厳密な研究結果(その多くは一流の女性経済学者によるもの)は、取締役会の多様性を高めることが実際には株価の下落につながることを示唆しているという。ゆえに、ナスダックが提案するルールの実施は、投資家にとってリスクをもたらす可能性があると主張している。
世界を覆う根深い人種差別
考えてほしいのは、覇権国アメリカに根深くすくっている人種差別という視角が世界をいまなお覆っているという現実についてである。イスラエルとパレスチナの抗争は、ユダヤ人とパレスチナ人の争いという人種差別の面を色濃くもっている。あるいは、米国の中国封じ込め政策もまた人種差別という側面があるのかもしれない。
残酷なのは、人工知能(AI)の訓練の場においても、人種差別が露わになっている点だ。2024年1月19日付のNYTによると、AIを訓練するための画像はそのほとんどが白人の画像であり、その結果、「AIシステムによってつくられた白人の顔は、本物の白人の写真よりもリアルであると認識された」というのだ。技術開発の場においても、人種差別が内在化されてしまっているのだ。
考えてみれば、その昔、キリスト教文明なるものに導かれていた人々は「黄禍論」なる議論を大真面目に展開した。私は「論座」において、「中国の危険性とは?:「ソフトパワー」の精神的基盤は何なのか」という記事で、黄禍論について紹介したことがあるから、ここでは、この議論は割愛するが、キリスト教文明なるものがいかに「普遍性」のないものであるかについて肝に銘じておく必要がある。
「分ける」という人間知性の原理を否定するわけではない。他方で、「融合」するという原理もあることを強調しておきたい。この「融合」という視角こそ、新しい地政学の根幹をなすべきであると、私は考えている(もちろん、この背後には、「核分裂」と「核融合」という二つのエネルギー爆発のアナロジーがあり、後者がそう簡単ではないことも想定されている)。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ISF主催トーク茶話会:天野統康さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
ISF主催トーク茶話会:原一男監督を囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)



























































































































































































