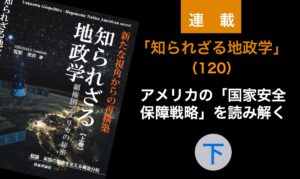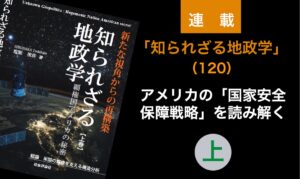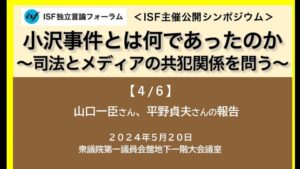「知られざる地政学」連載(41)国際法の地政学(上)
国際
国際法は地政学的考察の基本対象である。ゆえに、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』の「第6章 国際法からみた戦争」(151~181頁)において、国際法について詳しく論じたことがある。簡単にいえば、ヨーロッパ大陸法としてのヨーロッパ公法(国際法)に縛られないかたちで、海洋国家のイギリスがヘゲモニー国家となったことで、このヨーロッパ公法を侵食し、ある意味で、同じ海洋国家であったアメリカがその侵食を加速させた。それが現在のグローバルな国際法につながっている。そこにあるのは、ヨーロッパ公法の骨抜きであり、簒奪だ。都合のいい解釈で、アメリカの利害に沿った法的規制が国際法の名のもとで執行されている。しかし、そこには、何の合法性(legitimacy)もない。
新著『帝国主義アメリカの野望』においても、「第5章 アメリカ支配の栄枯盛衰」の「第一節 国際法の変遷とアメリカによる支配」でアメリカの身勝手な国際法支配について考察しておいた。ここでは、最近の出来事をめぐって、帝国主義アメリカを髣髴とさせる身勝手なふるまいについて紹介したい。
ICC、ネタニヤフ首相への逮捕状請求
国際司法裁判所(ICC)のカリム・カーン主任検察官は5月20日、イスラエルとハマスの両指導者らに対し、人道に対する罪の容疑で逮捕状を請求すると発表した。これは、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とハマスのヤヒヤ・シンワルを同列に扱う強い非難であり、イスラエルのガザでの行動に対する国際的な警戒の高まりをさらに強めるものであった。
ネタニヤフ首相とイスラエルのヨアヴ・ガラント国防相については、①イスラエルが戦争兵器として飢餓を利用したとされること、②ガザへの人道支援を文書で妨害したこと、③戦争中にイスラエルが行った、民間人に広範かつ無差別な被害を与えた行為が犯罪にあたるということだ。とくに、ガラントは2023年10月9日に発表した声明のなかで、「我々は人間という動物と戦っている」(We are fighting human animals)という暴言を吐いている。
これに対して、アントニー・ブリンケン米国務長官は、米国はICCの決定を「基本的に拒否する」とのべた。「我々は、検察官がイスラエルとハマスとを同列に扱うことを拒否する」とした。ジョー・バイデン大統領も、「この検察官が何を暗示しているにせよ、イスラエルとハマスの間に等価性はない」と声明のなかでのべている。
人権をまったく無視するイスラエルと、そんなイスラエルを支援するアメリカに大義はまったくない。この点を世界中の人々は肝に銘じるべきだろう。
ローマ規程から距離をとるアメリカ
ここで、ICCについて、基本的な知識を確認しておく必要がある。『帝国主義アメリカの野望』では、つぎのように書いておいた。
「アメリカは、国ではなく個人に対する訴えを審理する国際刑事裁判所(ICC)にも参加していない。国際社会が懸念するもっとも重大な犯罪を管轄するICC 設立を決めた国際刑事裁判所ローマ規程は1998 年に国連総会が招集した外交会議で採択された。戦争犯罪、人道に対する罪、ジェノサイド、そしてまだ定義されていない侵略の罪を訴追するためICC が2002 年に正式に設立される。しかし、ビル・クリントン政権時代のアメリカは2000 年に、ローマ規程に署名したものの、結局、クリントン大統領はジョージ・W・ブッシュ大統領に対し、この条約を上院に提出しないよう申し送った。ローマ規程は、政治的操作に対する慎重なセーフガードを欠き、国連安全保障理事会への説明責任を果たすことなく広範な権限をもち、状況によっては非締約国の国民や軍人を管轄すると主張することで国家主権を侵害する、重大な欠陥のある制度であると結論づけたからである。
アメリカはローマ規程に拘束されず、米国人に対するICC の権限を認めないと主張しつづけることで、ヘゲモニー国家としての特別な地位を維持しようとしているようにみえる。だが、それはアメリカの身勝手な世界支配を主張するにすぎず、何の正当性もない。」
今回の件でいえば、ICCの主任検察官による逮捕状請求を「拒否する」のは勝手だが、アメリカの発言は「イスラエル贔屓」の戯言にすぎないように思われる。
崩れるアメリカの主張
ここで、冷静な議論を展開しよう。ケンブリッジ大学の国際法研究者マーク・ウェラーの主張を参考にしながら、「世界標準」に準拠した議論を紹介したいと思う。
まず、アメリカはイスラエルと同様、ローマ規程から離れることを選んだから、「国際条約はその締約国となった国だけを拘束する」との見解からすると、ICCは国際条約に基づくものであり、イスラエルのような非加盟国に影響をおよぼす事態に関与することはできないと主張していることになる。
だが、アメリカがいうほど、事態は単純ではない。2021年2月5日、ICCの第一予審法廷(Pre-Trial Chamber I)は、ICCローマ規程の締約国であるパレスチナ情勢における同裁判所の領域的管轄権は、1967年以降イスラエルによって占領された地域、すなわち東エルサレムを含むガザとヨルダン川西岸に及ぶと多数決で決定した。この決定は、この状況における裁判所の管轄権の領土的範囲を明確にする判決を求める検察官の要請を受けたものである。ICC検察官は、捜査開始のためのローマ規程上の法定基準はすべて満たされていると結論づけた。なお、パレスチナ国は国連事務総長に加盟文書を寄託することでローマ規程に加盟し、2015年4月1日にパレスチナ国に対してローマ規程が発効した。2021年のICCの決定により、パレスチナはローマ規程の締約国であり、規程の履行に関する事項については他の締約国と同様に扱われる権利を有することが確認された。この判決により、2014年6月13日以降にパレスチナ占領地で行われた犯罪の捜査に道が開かれたのである。
したがって、裁判所の管轄権はパレスチナの領土内で行われた行為や、パレスチナの国民が海外で行った行為にもおよぶ。すなわち、イスラエル兵がガザやヨルダン川西岸で行った行為も、パレスチナ臣民がイスラエル領内で行った暴挙も、ICCの司法権の対象となるのである。
アメリカの専横
ここで、アメリカがICCに対して行った専横を思い出す必要がある。アメリカはICCに対し、2003年に規程に加盟したアフガニスタンでの自国軍人の行為に関する調査を取りやめるよう、多大な圧力をかけることに成功したのだ。
ドナルド・トランプ大統領(当時)の政権はICCのファトゥ・ベンソウダ検察官に制裁を科し、アメリカ政府はアフガニスタンでの捜査の可能性をめぐって裁判所と加盟国を報復措置で脅した。このような圧力にもかかわらず、2020年3月、ICCは調査を進めることが可能であり、アメリカの残虐行為が疑われるものを調査対象に含めるという裁定を下す。しかしその後、ICCの新しい主任検察官であるカリム・カーンは、米軍関係者や当局者の行為に関する調査を「優先順位を下げる」ことを決定した。この決定は、人権擁護団体や被害者から批判を浴びた。彼らは、米軍関係者や当局者が犯した犯罪が法廷で訴追されることを望んでいた。アメリカとその同盟国を調査から除外するという決定は、ICCが世界で最も強力な国々を相手にする能力に疑問を投げかけたことになる。
奇しくも、この批判を受けたカーンが逮捕状請求を求めた点に、浅からぬ因縁を感じる人は多いはずだ。
これに対して、ICCがウラジーミル・プーチン大統領とその関係者をウクライナ戦争に関連して訴追すると発表したとき、アメリカはICCに拍手を送った。このときの状況は、いまのネタニヤフ首相への逮捕状請求と似ている。ロシアはローマ規程に署名しなかったが、ウクライナは自国の領土に関連してローマ規程が適用されることを受け入れた。したがって、非締約国の兵士がウクライナで行った残虐行為について、ICCが審理する可能性があるのだ。
注目すべきは、トランプ時代と同じように、ICCに制裁を科そうとする動きがアメリカ議会にあることである。上下院において、共和党と民主党の議員が超党派で、アメリカ人や同盟国の人々に対する調査を行うICCのスタッフに対して、アメリカ国内の不動産取引を禁止し、アメリカ人のビザ発給を制限する「違法裁判所対策法」が浮上している。
注目すべきは、The Hillが、「民主党議員の大多数は、バイデン大統領が「言語道断」と非難したICCの告発に反対しているようにみえる」と指摘している点だ。だれが違反しようとも国際人道法を執行しようとするICCを称賛する、バーニー・サンダース上院議員(バージニア州選出)のような「まともな」民主党議員は少数にすぎない。多くの民主党議員は共和党議員と同じく、民主国家イスラエルとテロリスト集団ハマスの戦時行動を同一視する国際裁判所を非難している。だからこそ、米議会の民主党と共和党の指導部は5月31日、ネタニヤフを上下両院合同会議の演説に招く書簡を送ったのだ。
こうしたことから、富豪であるアメリカ系ユダヤ人の肩をもつことで、彼らからの支援を受けつづけようとする、カネに弱い議員の実態が透けてみえる。要するに、カネのためにイスラエルのユダヤ人の非人道的行為を非難することさえできないのだ。そればかりか、彼らに加担して、民間人の殺戮に間接的に手を貸すことに何の躊躇もない。
これでは、植民地の住民を殺戮しまくった昔の帝国主義国と同じやり口ではないか。植民地の住民を宗主国の「人間動物園」に入れて展示した感性は、先のイスラエル国防相のWe are fighting human animalsという発言と軌を一にしているのだ(「人間動物園」については、連載【26】人種をめぐる地政学〈上〉を参照)。
このため、イェール大学ロースクール国際法教授オナ・ハサウェイは、『フォーリン・アフェアーズ』の記事のなかで、ICCを攻撃することは、「アメリカがグローバルな正義を支持するのは、敵対国に適用するときだけだということを示すことになる。そうすることで、法の支配に対するアメリカのコミットメントは、目先の私利私欲が許す限りしかおよばないことを示唆している」と書いている。随分慎重な言い回しだが、要するに、アメリカは私利私欲に基づいて世界支配をしてきたし、いまもつづけようとする帝国主義国家なのだ。
「イスラエル贔屓」アメリカの横暴
アメリカは「イスラエル贔屓」であるために、イスラエルにだけ「甘い」基準を適用している。公然と「ダブルスタンダード」を使い分けることで、恥じ入ることもない。それを明確に示しているのは、ICCのミャンマーにおける追及に対するアメリカの態度だ。ミャンマーは国際人権規約を締結していないにもかかわらず、国際司法裁判所(ICJ)はイスラム教徒の少数民族であるロヒンギャの強制移住に関して、ミャンマーの政権メンバーを追及している。
多くのロヒンギャがバングラデシュに押し込められている。ICCは、ミャンマーにおけるロヒンギャに対する軍政の行為について管轄権を主張し、その犯罪は少なくとも、ローマ規程の締約国であるバングラデシュにおいて最終的な効力をもつものである、とあえて主張している。奇妙なことに、アメリカはICCによるこの権力の「横暴」に対して声高に抗議していない。要するに、アメリカは露骨なダブルスタンダードを使い分けているのだ。
ICJでの動き
同様に、個人による犯罪ではなく国家間の事件を扱うICJは、国際的な公益のために行動すると主張するいわゆる第三者によって提起された事件にますます対応できるようになっている。たとえば、ガンビアは2019年11月11日、イスラム協力機構加盟57カ国を代表して、ミャンマーがジェノサイド条約に基づいて義務づけられている、ラカイン州でロヒンギャに対して行われたジェノサイド行為を防止し処罰する義務を果たしていないとして、ICJに提訴した。その結果、ICJは2020年1月23日、ミャンマーに対し、自国の軍隊および非正規武装部隊がこれらの行為を行わないようにすることを含め、ジェノサイド条約に規定されている行為の実行を防止するため、「自国の力の及ぶ範囲内であらゆる措置をとる」よう命じる命令を下した。
2022年、ICJは裁判所の管轄権に対するミャンマーの予備的異議申し立てを却下し、条約の中心的目的はジェノサイドの防止と処罰を確実にするという全締約国の「共通の利益」であり、ガンビアはこの「共通の利益」に照らして、同じ締約国に対して手続きを開始する権利を有すると指摘した。つまり、ICJは、どのような国家であっても、他国に居住する外国人が享受する基本的権利を擁護することができると認めている。同様に、南アフリカは今年初め、ICJでイスラエルに対する暫定命令を獲得し、国連のジェノサイド条約の遵守とガザへの人道援助の提供を要求した際、人道に関する国際法を擁護する役割を担った。
「知られざる地政学」連載(41)国際法の地政学(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う
☆ISF主催トーク茶話会:安部芳裕さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:浜田和幸さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)