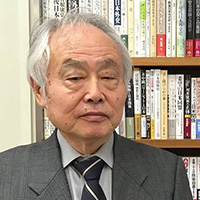「対米従属」から脱却し、 「東アジア共同体」の実現をめざそう
国際近年激しさを増す米中対立の中で、ヨーロッパ各国も巻き込みながら「中国包囲網」を形成するような動きも活発化し、軍事的緊張が一段と高まりつつある東アジア。そうした動きの中心に日米同盟と自衛隊がある中、日本に住む私たちが、この地域が再び戦禍に見舞われることのないようにするにはどうすべきなのか?
東アジア共同体・沖縄(琉球)研究会共同代表や、国際アジア共同体学会共同理事長なども務めておられる鹿児島大学名誉教授の木村朗さんに、東アジア情勢について、これまでの経緯や現状、今後の展望についてお話を伺いました。
(聞き手:「アジェンダ」編集委員・谷野隆 2021年7月23日インタビュー取材)
・「冷戦終了」とNATOの拡大
現在の状況をお話しする前に、前提としてポスト冷戦後の「新世界秩序」について考えてみます。
1989年から91年、ベルリンの壁崩壊からソ連消滅で米ソ二極対立の世界秩序が崩壊して、「アメリカが一方的な独り勝ちをした」というような宣伝がされました。それを象徴する言葉がパパ・ブッシュの「新世界秩序」です。1992年に提起された「ウォルフォウィッツ・ドクトリン」も同じ発想で、アメリカの世界支配体制を絶対的なものにして、ライバルの登場を許さないという戦略です。

The Berlin Wall near the grounds of the Topography of Terror Museum in Central Berlin, Germany
冷戦終了に関して改めて考える必要があるのは、ソ連とワルシャワ条約機構が消滅したのになぜ、もう一方の軍事同盟であったNATOが存続したのか、日米安保が存続したのか、ということです。私はこれについて合理的な理由は無く、基本的には軍産複合体の生き残り戦略だったと思っています。
NATOは、大きな脅威は基本的に無くなったのに、新たな脅威を、テロだとか、ならず者国家とか、そういうものに求めていった。これは加盟国に対する直接の脅威ではなく、冷戦終結後は域外の脅威への対処を新戦略に取り入れ、メインに対応する組織に変わっていった。1999年3月のコソボ空爆は、NATOに対する侵略でもないのに、初めてNATOが軍事作戦を行った最初の事例で、「新しい戦争」「21世紀型の戦争」と言われました。

Vilnius, Lithuania – September 3, 2015: NATO flag waving by the wind
その後もNATOは縮小・解体するどころか拡大を続け、当時10カ国だった加盟国が今では30カ国になっています。客観的に見て、私はロシアの脅威はほとんど無いと考えています。むしろロシアのほうがNATOを脅威に感じている。なぜなら、ソ連邦は崩壊し、東ヨーロッパが離れて、旧ソ連やロシア帝国にいた地域、国々さえも独立して、一部はNATOに加わった。NATO諸国によって完全に包囲され、一方的に脅威を受けているのはロシアなんです。バルト三国(私はその一国のリトアニアを2019年に訪問した)やポーランドは、過去の経緯からロシアに対する脅威感を持っていますが、ロシア側から侵略する意図、可能性はほとんどゼロだと思います。
しかし、「ロシアの脅威」をでっちあげながらNATOは拡大してきました。2014年にクリミアがロシアに「武力で併合された」ことで欧米各国は経済制裁を続け、日本もこれに同調していますが、これも実態は違います。詳細は省きますが、発端はウクライナで親欧米派の策略によって親ロ政権が追い払われ、ロシア系住民への迫害が強まったことにあります。

Map of Crimea, Ukraine. Detail from the World Atlas.
ウクライナ東部が内戦状況となる中、ウクライナからの分離・独立とロシアへの編入を問う住民投票が国際監視下でクリミアで行われましたが、8割以上の住民の圧倒的支持でそれが決まったのです。もともとクリミアはロシア領であり、ウクライナ出身のフルシチョフ書記長が1954年にウクライナに割譲させたという経緯があります。最初に脅威を受けたのはロシアやロシア系住民の側であり、「武力併合」もいいがかりに近いことがわかります。
・米中対立をどう見るか
もう一つの「脅威」とされているのが中国です。アメリカは1972年にキッシンジャーが訪中して以降、「一つの中国」政策を基本的に維持しながら、中国を「国際社会」に関与させるという政策できました。中国は、国力、経済力が2000年以降急速に大きくなり、2010年にはGDPで日本を追い抜き、世界第2位となりました。長期的、相対的に衰退する傾向が鮮明なアメリカにとって、中国は2010年前後から初めて脅威的な存在になりつつあります。
ロシアと中国のどちらかと言えば、アメリカのネオコンの人々は旧ソ連や東ヨーロッパ出身の人が多くて、ロシアに対する反感、憎しみ、敵視が強い。また民主党系の人々は、ヒラリー・クリントン、ビル・クリントンに代表されますが、中国との関係では「共存共栄」、「米中共同覇権」的な構えをとってきました。
オバマ政権の途中から、「リバランス政策」で安全保障の重点をヨーロッパから東アジア・太平洋に移す動きが出てきましたが、まだ本格的なものではなかった。それに明確な変化を与えたのがトランプ政権の登場です。「再びアメリカを偉大な国にする」ために、「米中共同覇権」や、中国がアメリカに代わって覇権国家になるのは許さないという強い意思の下、政権の前半では貿易戦争はじめ経済、金融面での対立が前面に出ていましたが、後半になるにつれ、軍事、安全保障を含むすべての分野で、中国を本格的に主要な敵とするように舵をきったのです。

“Long Beach, California, USA – May 20th, 2012: Man holding a sign with the photo of Obama with gay and lesbian decoration during the 2012 Long Beach Lesbian and Gay Pride Parade.”
これには昨年からのコロナ・パンデミックの影響も大きいと思います。アメリカが最も犠牲者が多く、経済的な打撃が伝えられる一方、中国は当初、武漢で大きな被害を受けながらも短期間で収束させ、経済的に世界中のほとんどの国が大幅なマイナスを記録する中で、成長を見せました。長期的なアメリカの衰退と中国の台頭が、コロナによってさらに加速する状況になったことが、アメリカの人々に超党派で危機感を抱かせるに至ったのです。
客観的に見て、東アジアで米中の軍事力が拮抗しつつあることは間違いありません。もちろん世界的な軍事力は圧倒的にアメリカ優位、これは変わりません。けれども、経済力であと10年もしないうちに世界一になろうとしている中国が、それに合わせて軍事力をある程度拡大するのは、正当化するわけではありませんが、自然なことでもある。
しかしそれは必ずしも中国が「第二のアメリカ」のような軍事大国になろうとしているということではない。核兵器も増やしていないし、空母は三隻目を持ちつつありますが、アメリカの巨大な最新型の空母とは比べものにならない。ただし、「第一列島線」と言われる沖縄からフィリッピンまでの海域・空域で、中国が軍事的な影響力を強めつつあるのも事実です。
このように見ると、覇権国家として軍事的な支配を東アジア・太平洋地域においても独占してきたアメリカが、中国にその一角を崩され、経済的にも追い上げられ、追い抜かれそうになっていることに、アメリカ国民の多くがものすごい焦りを超党派で抱くようになった。これが、オバマ政権末期から現在までの大きな時代の流れだと思います。
だから私は、中国が意図的・挑発的にアメリカを刺激して今日の米中対立を引き起こしたというよりも、米中の覇権交代の移行期という大局的な流れの中でアメリカ側が力でそれを押し返そうという動きが本格的に始まった結果だと見ています。
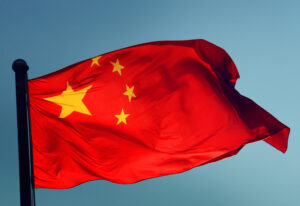
Chinese Flag Waving Patriotism Concept
ただ、私自身は「米中新冷戦」という言い方については、かつての「米ソ冷戦」と同じような形で世界的に一般化するとは思っていません。なぜなら、すでに中国は世界経済との相互依存体制が引き返しのできないところまできています。アメリカと日本、ヨーロッパの一部が中国封じ込めに動こうとしても、他の多くの国々は簡単には応じないでしょう。
元々イタリアは中国が提唱する「一帯一路構想」に積極的でしたし、ドイツはロシアとのパイプライン建設もあってロシアとの関係を進めようとしています。ただし、そういった融和的な動きは、トランプ政権・バイデン政権から強い圧力を受けており、最近はかなりアメリカに同調するようになりつつあります。
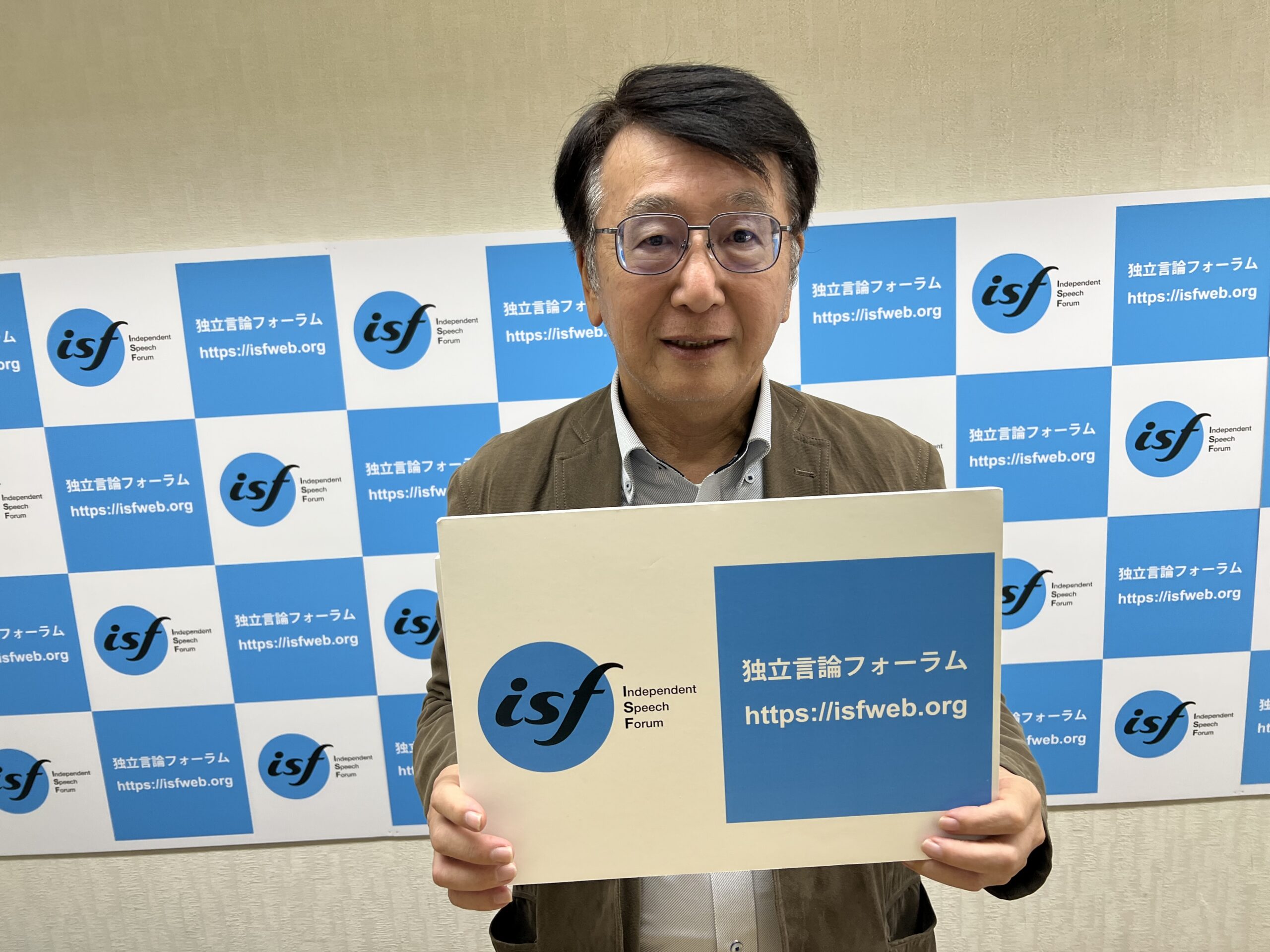 木村朗ISF編集長
木村朗ISF編集長
独立言論フォーラム・代表理事、ISF編集長。1954年北九州市小倉生まれ。元鹿児島大学教員、東アジア共同体・沖縄(琉球)研究会共同代表。九州大学博士課程在学中に旧ユーゴスラヴィアのベオグラード大学に留学。主な著作は、共著『誰がこの国を動かしているのか』『核の戦後史』『もう一つの日米戦後史』、共編著『20人の識者がみた「小沢事件」の真実』『昭和・平成 戦後政治の謀略史」『沖縄自立と東アジア共同体』『終わらない占領』『終わらない占領との決別』他。