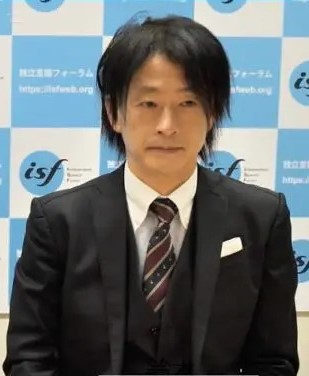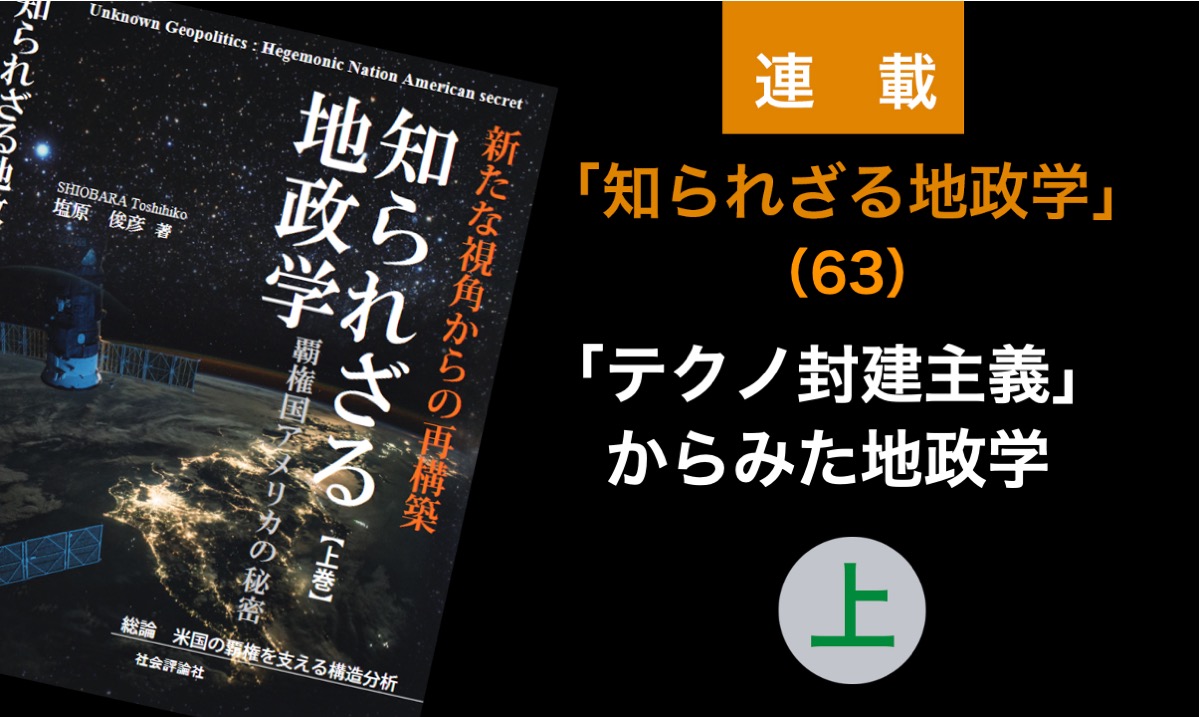
「知られざる地政学」連載(63):「テクノ封建主義」からみた地政学(上)
国際
ものごとを一度に全方位からながめることはできない。そこで、重要になるのは視角だ。今回は、現在、地球上を覆っている最先端のシステムを「テクノ封建主義」という視角から分析したい。そうすることで、米大統領選後の世界統治のあり方を考えるヒントになると思うからである(なお、この執筆は2024年11月3日時点でなされている)。
『テクノ封建主義:資本主義を殺したもの』
ギリシャの財務大臣を務めたこともある経済学者ヤニス・ヴァルファキス(下の写真)は、2023年に『テクノ封建主義:資本主義を殺したもの』(Yanis Varoufakis, Technofeudalism: What Killed Capitalism, The Bodley Head, 2023)を出版した。同書のなかで、ヴァルファキスは、アメリカの大手ハイテク・プラットフォームが封建主義を復活させたと主張している。彼自身の言葉で表現すると、「資本主義に取って代わりつつあり、多くの文脈ではすでに取って代わっていると信じるに至ったシステム」を「テクノ封建主義」(technofeudalism)と呼んでいる。
彼の考えでは、インターネットの私有化と2008年以降の金融政策の組み合わせにより、とくに「クラウド資本」が実体資本を駆逐した。その結果、表題の「テクノ封建主義」が生まれたというのである。「クラウド主義者」は、プラットフォームの領地とデータ兵器によって価値を引き出している。テクノ封建主義は、資本主義とは対照的に、利益をレントに、市場競争を独占力に置き換えているらしい(後述するように、ヴァルファキスの主張を私は支持しているわけでない。ただ、この視角は興味深いのである)。

ヤニス・ヴァルファキス(Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images)
(出所)https://jacobin.com/2023/10/cloud-capitalism-technofeudalism-serfs-cloud-big-data-yanis-varoufakis
彼は、中世の農奴が自分の所有地でもない土地で労働するのと、アマゾンのようなプラットフォームに出品して販売しようとする業者が似ている点に注目している。その販売業者はアマゾンの厳しいルールに従わなければならない一方で、販売業者はアマゾンに分け前を支払わなければならない。つまり、グーグル(アルファべート)、メタ(フェイスブック)、アマゾン、アップル、マイクロソフトといった「ビッグテック」ないし「テック・ジャイアンツ」の運営するプラットフォームが中世時代の「荘園」、あるいは、封建領主の「領地」にあたるとみなしている。このとき、領主(プラットフォーマー)は、プラットフォームという「荘園」ないし「領地」を販売業者に使わせてやっている。このため、販売業者はその使用料として、一種の「地代」(レント)を支払う必要が生まれる。
領主(プラットフォーマー)による独占:具体例
ここで、領主たるプラットフォーマーが具体的に何をやっているかをみておこう。もっともわかりやすいのは、アップルのiOSとグーグルのAndroid OSという二つのプラットフォームのうち、どちらかを選択した消費者に対して、独占的なサービスを提供することで消費者たるユーザーを集める一方、その場で販売に従事する売り手には、そのプラットフォーム(荘園ないし領地)の使用料を払わせるのである。
たとえば、アップルはセキュリティーなどを理由にスマートフォン「iPhone」上で外部企業による非正規アプリストアの開設をかたくなに認めてこなかった。正規ストア(App Store)で配信する有料アプリには自社の決済システムの利用を義務づけ、原則として一つのアプリ販売につき15~30%の手数料(コミッション)を徴収してきたのである(注1)。
「農奴」によるタダ働き
この「荘園」で働いているのは「農奴」である。農奴は領主から賃金をもらっているわけではない。中世の農奴は領主から住居と食料をあてがわれ、労働力を賃金なしに提供していた。同じように、いまの農奴は、領主たるプラットフォーマーが賃金をまったく支払わないにもかかわらず、タダ働きをしている。
いまの農奴は、プラットフォームを利用して、検索をしたり、写真や動画をアップロードしたり、あるいはメールを受送信したり、買い物をしたりしている。このとき、多くのプラットフォームのユーザーは無償でサービスを提供してもらっていると誤解している。実際には、この「サービス提供」を通じて、プラットフォーマーは、ユーザーに関するさまざまの情報をかき集め、それを情報パッケージとして販売したり、あるいは、たくさんの農奴の出会いの場そのものをつくり上げたりして、「荘園」の価値を高めている。つまり、領主たるプラットフォーマーの提供するサービスを無償で受け取っているようにみえても、実際には、ユーザーはプラットフォーマーのためにタダ働きをしていると考えられる。テック・ジャイアンツのような巨大企業は、数億人もの農奴を地球上にかかえているとも言えるのだ。
具体的なタダ働き
たとえば、領主たるプラットフォーマーは、さまざまなアプリケーションソフト(apps)がスマートフォン経由で位置情報を集めて、それを複数の会社に売却している。2018年12月10日付ニューヨーク・タイムズによれば、2秒ごとの位置情報は、匿名性は確保されながらも、本人の合意のないままに宣伝広告などのために売却されており、他の情報と組み合わせれば、簡単に個人が特定できるとしている。少なくとも75の会社がローカル・ニュースや気象情報などを得るために利用されているappsから位置情報を受け取っているという。1000以上の人気アプリが位置情報をシェアできるコードを含んでいる。グーグルのアンドロイドでは、こうしたコードつきの約1200のアプリが見つかったほか、アップルのiOSでは約200のアプリで同じようなものが見つかったという。
あるいは、フェイスブック(メタ)は2016年に初めて「FBLearner Flow」と名づけたものに導入し、位置情報、デバイス情報、Wi-Fiネットワークの詳細、動画の利用状況、類似性、友人関係の詳細(ユーザーが友人とどの程度似ているかなど)などのデータをすべてFBLearner Flowに送られるようにしている。ユーザーの生活の一側面をコンピューターでシミュレーションするために使用され、その結果は企業顧客に販売されている。
こう考えると、ヴァルファキスの主張するように、いまやインターネットのプラットフォーマーは、彼らの利益を、市場からではなくデジタルな荘園から得ていると言えるのではないか。だからこそ、資本主義ではなく「テクノ封建主義」なる時代に突入しつつある、と彼はみているのだ。
歴史的封建制をめぐって
ここで、ヴァルファキスのこの視角を拡大してみたい。そこで、まず、歴史的な封建制について復習しておこう。
西ヨーロッパの場合、領主の親玉が国王にすぎず、国王を含めて、各領主が領地ごとに税を徴収していた。いわゆる封建制のもとで、国王は忠誠と引き換えに封土を封臣に与え、戦争時に彼らから兵力の提供を受けたほか、平時には税を徴収した。他方で、国王は基本的に自分の領地から税を取り立てて、自分の家計を賄っていたのである。したがって、国内のあらゆる領民から直接、国王が税を徴収するようなケースは稀であったと考えられる。王国の政府は国王の家産と一致しており、国庫はいわば国王の家産を管理するにすぎなかった。
教会との関係に注目しつつ、ローマ帝国末期やビザンツ帝国をみてみよう。まず、西ローマ帝国は5世紀に滅びる。その後、11世紀はじめまで西欧世界の大部分は基本的に皇帝教皇主義のもとにあった。政治的権力が教会の権威者の任命権をもち、皇帝、王、封建領主が教会の司教を任命できたし、教会の会議を召集する権限をもっていたし、教会法を公布することさえできた。これに対して世俗的権力から離れてローマ教会と直結する修道会組織、クリュニー修道院が修道院・教会の改革運動を開始するようになる。グレゴリウス7世はこのクリュニー修道院出身者で、彼によってローマ教会は革新される。
神聖ローマ皇帝、ハインリヒ4世が叙任権を行使するようになると、グレゴリウス7世はこれに抗議し、両者の関係が尖鋭化する。ハインリヒはグレゴリウスを教皇の座から引きずり下ろす動きに出たのだが、これに対してグレゴリウスはハインリヒを破門した。王位の簒奪にもつながりかねない切り札をグレゴリウスは切ったことになる。その結果、諸侯や民心が離れ、ハインリヒは1077年、教皇への直接の謝罪を余儀なくされた。だが、破門が解除されても王位については不明確で、それがその後の対立につながった。戦争を経て、グレゴリウスは1080年、ハインリヒの破門と廃位を宣言したのだが、ハインリヒはローマに攻め込み、クレメンス3世を擁立して教皇位に就け、自分はクレメンス3世から王冠を授けてもらう。ローマから逃げ出したグレゴリウス7世はサレルノで1085年に死亡した。
グレゴリウス7世の死後も叙任権闘争は継続する。結局、ヘンリー5世とカリクストゥス2世によって1122年に結ばれた「ヴォルムス協約」によって叙任権闘争に決着がつく。この協約によって、皇帝は叙任権をあきらめることになったが、教会は皇帝の権利(レガーリエン)として公の官職、財政的利用権、土地所有を認めた。これにより、封主と封臣とのゲルマン的封建制(レーエン制)が確立することになる。同時に、教会の世俗的所有として、国王の贈与によるもの、私人の贈与によるもの、教会の宗教的力によるものの三種類が明確に区分されるようになる。こうして、少なくともカトリック教会が勢力圏の西欧では、皇帝教皇主義的な時代が終焉を迎えるのである。それは、西欧独自の社会制度の変化をもたらす。
フリードリッヒ2世の重要性
世俗法による支配を意図的に推進したのが神聖ローマ帝国の皇帝で、シチリア王国の国王でもあったフリードリッヒ(フェデリコ)2世だ。彼は1224年にナポリ(フェデリコ2世)大学を設立し、神学や教会法に重きを置くのではなく、ローマ法を主要科目とし、官僚育成に務めた。1231年には、世襲によって王となったシチリア王国(南イタリアとシチリア)を法治国家とするための「憲法」として「メルフィ憲章」を公表するに至るのだ。中世に忘れられていたアリストテレスといったギリシャ哲学を学べる状況にあったナポリ大学に学んだからこそ、トマス・アクィナスはキリスト教思想とアリストテレス哲学を統合したスコラ哲学の大成者になりえたと思われる。
法治国家の形成上、法のもとでの公正を保つには、裁判権や警察権を封建領主や聖職者(大司教・司教などの高位聖職者として地方に任官され、そのまま領主のようになった人々が多数いた)から奪い、裁判に必要な裁判官、検事、弁護人を独立させる一方、警察権に基づく捜査の独立性を確保し、経済的に恵まれない人でも裁判に訴えられるようにすることが必要になる。ゆえに、裁判官、検事、弁護人などの専門の職業をもつ人物を養成するためにナポリ大学が必要とされたのだ。フリードリッヒ2世は、裁判の公平期すために、裁判官の任地での仕事の期間を1年としたという。これは腐敗問題を考えるうえで興味深い。裁判官や警官という超越的地位にたつ者が腐敗しやすい現実をよく知っていたのだ。他方、教会法では、告訴されると有罪になり、控訴権が認められていなかった。メルフィ憲章では、明確に控訴権が認められており、控訴先は皇帝となっていた。ローマ法をもとにしているメルフィ憲章では、もちろん、実証する証拠がなければ有罪にはならない。
加えて、フリードリッヒ2世は教会が徴収していた税金とは別に領主が徴収していた徴税権を奪い、シチリア国王だけが徴税権をもつ仕組みに改めたかったに違いない。だが各地の領主が徴税をしてきた背後には、各領主が自ら武装し、その配下に騎士や兵士をかかえてきたという伝統があった。領主はその常備兵を養うために資金を必要としていたのだ。国王も封建諸侯並みの常備兵をもっていたが、封建領主から武力を取り上げて国家全体の防備のための常備軍に統合することはそう簡単ではなかった。王は諸侯に求めて兵士を集め敵と戦うことはできた。だが、それには諸侯の武力を温存し一定の忠誠心をもたせることが不可欠だった。諸侯は国外の敵と戦うだけでなく自分の領地内の不穏分子を攻撃するために武装していたから、この武力を失うことは全財産の喪失に直結しかねない一大事であった。こうみてくると、徴税権の問題は軍事力の問題に直結していることがわかる。ゆえに封建諸侯から徴税権を奪取するのは困難であった。フリードリッヒ2世はメルフィ憲章では臨時特別税の課税権を国王がもつとしたにすぎなかったのである。その後フィレンツェ共和国の官僚だったマキャヴェッリこそ常備軍の必要性を説いたのであり、この主張が徐々に認められていく。
「国王」としての米大統領
このようにみてくると、いまの米大統領を国王に見立てることは荒唐無稽ではない。連邦制をとるアメリカでは、いまでの州兵がいるし、州自体の徴税権もある。さすがに、巨大プラットフォーマーである「ビッグテック」ないし「テック・ジャイアンツ」には、兵隊もないし徴税権もないが、その代わり、いざとなれば反乱分子となる農奴たるユーザーが国境を越えて存在する。あるいは、少なくとも自らの「荘園」(プラットフォーム)内では、その場で商売をする売り手たる販売業者から手数料を徴収することもできる。
ごく一般化していえば、封建制は、主君たる支配者と臣下との間の完全に双務的な契約関係を根幹とし、軍事報酬と報酬(封土)がセットになっている。双務的契約関係のもとでは、主君が義務を果たさなければ、臣下から関係を破棄できる。こうした封建制は10世紀から13世紀の西洋に存在した。
こうした封建制理解に従うと、いまの国王たる大統領は、領主たるプラットフォーマーに軍事的貢献という義務を課すことも、ユーザーを下賜する権限もないから、昔の封建制とはまったく異なっているように映る。しかし、後述するように、政府はプラットフォーマーと軍事契約を結ぶことで、その能力をいかすことができる。あるいは、補助金を供与して研究開発をバックアップすることもできる。
このため、中世の封建制とは異なるやり方で、国王たる大統領はプラットフォーマーと「持ちつ持たれつ」の関係を構築することが可能であると言える。
「知られざる地政学」連載連載(63):「テクノ封建主義」からみた地政学(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:アメリカ大統領選挙と分断する社会〜激動する世界の行方
☆ISF主催トーク茶話会:高橋清隆さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:原一男さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)がある。