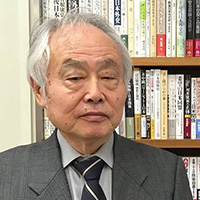第37回 一審判決を破棄し、まさかの有罪
メディア批評&事件検証「ええっ!嘘。こんな判決があっていいのか??」。私はただただ絶句するしかなかった。2018年8月3日午前10時半から殺人罪に問われた勝又拓哉被告(当時)の控訴審東京高裁102号法廷で開かれ、判決の言い渡しが行なわれた。藤井敏明裁判長は、一審・宇都宮地裁の無期懲役判決を破棄し、改めて無期懲役を言い渡した。
藤井裁判長は、一審について捜査段階で勝又被告が自白した場面を録音・録画した映像から犯罪事実を認定したことが違法であるとしたうえで、複数の状況証拠などから総合的に評価し、有罪と認定した。
判決の言い渡しは、まるで映画館でミステリーを見ている1コマのように感じた。藤井裁判長は、録音・録画した映像から犯罪認定したことを違法と断じ、一審判決を破棄した。
瞬間、法廷内はどよめいた。おそらく、法廷内の人々の脳裏には「無罪」の二文字が浮かんだに違いない。実は私もつぎは無罪判決が出るか、最悪でも一審への差し戻しが言い渡されると思った。その期待も束の間、藤井裁判長の口から発せられた言葉は、無謀にも自判して「無期懲役」だったからたまげた。法廷は落胆のため息に包まれた。
この控訴審は、予備的訴因を裁判所が促して検察に請求させて認めた裁判であった。殺害の場所や日時が全く新しい証拠が出たに等しいものだった。だからこそ、無罪の判決でなければ、せめて一審に差し戻すべきものではないのか。
その内容については、裁判員裁判の一審では審理を全くしていない。長年の司法改革の悲願だった一般市民が裁判に参加する裁判員制度が崩壊しかねない。いや、もうここにきては崩壊させたと言っても過言ではない判決だったと思う。まさにこの連載のタイトルでもある「絶望裁判」そのものである。
一審がとんでもない裁判だったが、控訴審も判決内容をみると、これといって有罪の決め手となる根拠は見当たらなかった。それなのに東京高裁が実質有罪の決め手としたのは、一審で商標法違反のことか、殺害のことか、どちらのことか判断できないとされた勝又被告が母にあてた手紙だったから開いた口が塞がらない。これがこの今市事件の第一級の証拠なのか。
藤井裁判長は「手紙は母親に殺人を犯したことを謝罪したいと作成した」。実刑判決でざわついた法廷の中で淡々と判決理由を読み上げていった。
手紙は14年2月、被告が別件である商標法違反での勾留満期日の午前中に大友亮介検事の取り調べで殺人容疑を初めて認めたとされる直後に書いた。実は栃木県警と宇都宮地検の間には、同県警の要請で勝又被告を「殺人容疑で逮捕するためにじっくりと別件の商標法違反容疑で時間をかけて調べる」という密約が交わされていたのだ。それを裏付けるように同容疑で2回逮捕している。殺人容疑を何が何でも力づくでも認めされるために長期身柄を確保したかったのだ。
ところが予期せぬアクシデントが起きた。大友検事が密約を破り、殺人の調べを始めたのだ。県警にとって予想もしないフライングだった。当時の警察庁の幹部たちが怒り心頭だったことが後に私の耳にも秘かに入った。私は朝日新聞社会部記者時代に警察庁担当で知り合いか多いのだ。話を戻そう。
もちろん大友検事から突然殺人について調べられた勝又被告も身に覚えのない容疑に驚いたことだろう。何が何だかわからないような調べで、その恐ろしい時間を逃れるための手段だったのだろうが「やってもいないことをやったと言わされ、事実でもないことで母親ら家族に迷惑がかかることを一刻も早く知らせる手紙だった」ようだ。その手紙の一部を引用する。
「中に入っている間、今回でその間がもしばれなかったら、うまれかわろうと思ってたけど……でおくれ……今まで、本当のちゃんとした親孝行をして来なかったことを、今はげしく後悔しています。(中略)今回、自分で引き起こした事件、お母さんやみんなに、めいわくをかけてしまい、本当にごめんなさい、僕がしたことは、世間やマスコミなどは、お母さんの育て方が悪いとかいうと思うけど、でも、お母さんは何一つ悪くありません、お母さんは、しっかりと、僕を育てました、僕が自分の意志で、自分で、まちがった選択をしてしまったのです」。

Hands holding stationery, envelopes, ballpoint pens, coffee and pens placed on the table
東京高裁の控訴審では、一審判決は本件手紙の記載内容のみからは「事件」の趣旨が必ずしも明らかとは言えないとするが、その「事件」が本件殺人を指すことは明白であると断言した。いかに控訴審判決の内容を簡単に記述する。
記載された内容のうち被告人が、商標法違反事件で起訴された当日である14年2月28日の午前中に大友検事から本件殺人につき取り調べを受け、その犯人であることを認める簡略な供述調書の作成に応じたことに符合しており、その趣旨は上記事件で勾留中に本件殺人について発覚しなかったら、生まれ変わろうと思っていたが、もはや手遅れであるという趣旨と認められる。
さらに後段の記載のうち「今回、自分で引き起こした事件」という文言は「自分でひきおこした」という以上、母親と共同で行った商標法違反事件を指すとは考えられず、「僕が自分の意志で、自分で、間違った選択をしてしまった」と記載されていることからしても、自分が単独で行った事件を指すものと理解され、しかも、被告人がそれを行ったことについて、世間やマスコミなどが、母親の育て方が悪いというと思うというのであるから、それだけで重大な事件であるということになり、前段の記載と併せ、本件殺人を指すものと読むのが合理的であり、ほかに被告人による事件として想定しうるものはないとした。
最後の段落についても「こんな親不孝な息子で本当にごめんなさい、もう、息子じゃないと思われてもかまいません。あんな事をしてしまって、本当にごめんなさい、こんな親不孝な息子でも、お母さんの残りの人生を大事に過ごしてほしいです、お体をお大事に」と結ばれている。
この記載は、それ以前の記載内容と併せれば、本件殺人を犯すという親不孝をし、その罪の重さにより将来にわたって親孝行をする機会がなくなったなどという気持ちから、母親に謝罪するものと理解することができるとしている。
東京高裁はさらに大友検事の一審での証言で被告人は14年2月21日の取り調べにおいて、勝又被告が本件殺人の犯人であることが公になれば、マスコミに報道されるなどして、姉や母に大きな迷惑が掛かることが気になるので、姉と面会して大変なことをしたことを告げた後でなければ供述することができない旨を説明しており、そのような時期に作成された本件手紙が同月24日に被告人と接見した姉を介して母親に渡されたものである。以上の経過は本件手紙の趣旨を前記のように読むこととよく整合するとしている。
そのうえで犯人でないにもかかわらず、母親に対し、自分が本件殺人を犯したとして謝罪することは通常あり得ないものと考えられ、被告人が犯人でないとすれば被告人が本件手紙を作成したことを合理的に説明することは困難であると自信満々の説明だ。
最後の段落についても「こんな親不孝な息子で本当にごめんなさい、もう、息子じゃないと思われてもかまいません。あんな事をしてしまって、本当にごめんなさいねこんな親不孝な息子でも、お母さんの残りの人生を大事に過ごしてほしいです、お体をお大事に」と結ばれている。
この記載は、それ以前の記載内容と併せれば、本件殺人を犯し、その罪の重さにより将来にわたって親孝行をする機会がなくなったなどという気持ちから、母親に謝罪するものと理解することができるとしている。
これが裁判所のリードで検察に殺害場所、犯行日時を大幅に変更させ、それを認めた上で決定的な証拠と位置づけたものなのか。その予備的訴因変更である内容は、裁判の後半にまるで新しい審理対象を提示させて、被告人の防御権を侵害することを無視した違法裁判と言えるのではないか。一審の法廷で湧き上がった霧が晴れることを期待した控訴審の法廷ではさらに深くなってしまったのである。
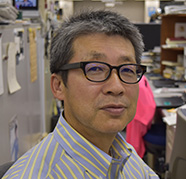 梶山天
梶山天
独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。