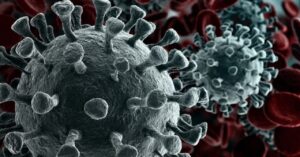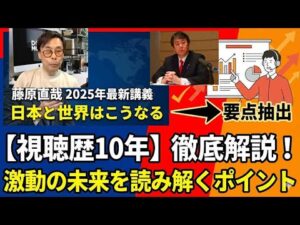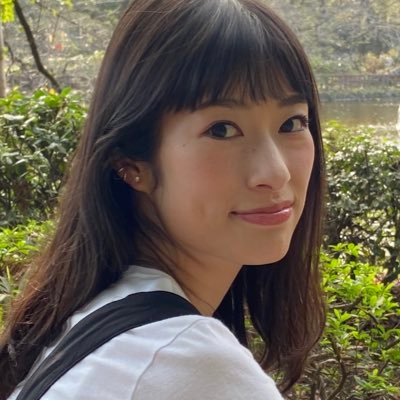第5回 根源を見据え、未来を展望する マーケットの手前にある生活文化にこだわる佐藤真起さんに聞く
社会・経済・スペース・オルタの37年
――スペース・オルタの紹介からお願いします。
佐藤――生活クラブ生活協同組合神奈川が1985年に自社ビル(オルタナティブ生活館)の地下に開設した多目的ホールで、日本の生協運動が作った唯一の文化ホールです。スペース・オルタナティブの意味で、新横浜駅から徒歩10分の位置にあり、120人規模で、演劇、講演会、上映会、コンサートなどに利用されてきました。

スペースオルタでの脱原発集会の様子

2022平和力フォーラムのチラシ
利潤ではなく生活の豊かさを追い求める”社会的企業“として、日本の生協は世界的にみても規模が大きく、社会的なポテンシャルはかなり大きいのですが、その運動の意義が十分に社会化され、社会そのものを変えていくには、まだまだこれからだと思います。
――生活文化にこだわり、その深層や多様性を掘り下げてきた。
佐藤――生活文化とは何か、新しい生活文化をどうつくるかが一番の興味でした。生活文化を基軸にして消費文化を相対化していくことで、オルタナティブを探る。そのために随分といろんなことに関心を持ちました。
貸しホールとして市民のパフォーマンスの場を提供する活動のほかに、私がプロデューサーとして企画する初期のシリーズに「民俗をみる」があります。民俗学者の宮本常一さん(1907~1981年)や、姫田忠義さん(1928~2013年)の民族文化映像研究所の仕事に影響を受け、主に映像作品の紹介や芸能の紹介を企画しています。
生活文化の基層を、足で地域に入って調査し、生活文化の地域性や具体性を探る。村落で生活している人たちが、どういう記憶、どういう希望を持っているのか。マーケットではなく、冠婚・葬祭をはじめ、生活している人の現実を写し撮ったドキュメンタリー群の紹介です。月に2回の上映で1回に2本から4本、全部で150本くらいの映像を見る機会を継続しました。上映後には感想を語り合う場を作り、日本列島に受け継がれてきた生活文化の原像を一緒に学びました。
その学びの流れの一つに、現在もオルタナティブ生活館を稽古場の一つに、30年以上続いている黒川さんさ踊りを学ぶ横浜グループの活動サポートがあります。その結果、ここ30年近く、毎年末に岩手の芸能を首都圏で学ぶ3グループが集い、一番近場の篠原八幡神社に稽古納めで踊りを奉納する「魂鎮(たましずめ)」も開いてきました。生産地である地方発の文化を消費地で学ぶ場の継続です。
ドキュメンタリー企画では「他者の痛みを知る」というシリーズでマイノリティ、社会的弱者の生活実感を少しでも知るための映像群の紹介や講演なども手がけてきました。
生活クラブ生協が自社ビルを建てたのは、日本経済がバブルに向かって右肩上がりで組合員が増えて行った時期で、安全・安心なオルタナティブな食材だけでなく、オルタナティブな文化創出にアプローチしたのです。
――佐藤さんがかかわったのはなぜですか。
佐藤――大学時代の恩師、粉川哲夫さん(当時・和光大学教授・哲学、1941年~)に感化され、卒業後、仲間たちとラジオホームランというミニFMの自由ラジオを下北沢でやっていたのですが、ちょうどその頃、ドキュメンタリー専門の上映館が下北沢にできたのです。鈴なり壱番館という名で、最初の上映作品が青林舎(現:シグロ)の土本典昭さん(映画監督、1928~2008年)の新作『海盗り』でした。その上映運動に少しかかわったのがきっかけです。当時、開設予定のスペース・オルタのプロデューサーを探していた生活クラブ神奈川の当時のトップ横田さんが青林舎と懇意で、私にやってみないかと話が来たのです。
私は編集の仕事をしていたのですが、活字というスタティック(静的)な媒体より、動きのあるライブな媒体の仕事に興味を感じつつあったので、スペース・オルタを引き受けることにしました。
もともとロフトジャズやコミューンに興味があり、ニューヨーク滞在中の粉川さんに誘われ、大学時代に北米でそれらの見聞を広めたこともあって、フリースペースの運営はそれほど遠い仕事ではなかったのです。ミュージシャンやアーティストたちが業界のしきたりを離れ、自分で納得のいく演奏の場をつくるロフトジャズや、それまでの家族関係を組み替え、より納得のゆく生活の場をつくろうとしていたコミューンの運動が、オルタナティブの原像として見えていたからかもしれません。
また、この仕事を始めた頃、前出のラジオホームランの活動を通じて知り合ったアメリカ人のパフォーマンス・アーティストと家をシェアーしていたため、海外から来日した際に彼を訪ねて来るインプロビゼーション系、パフォーマンス系のアーティストたちとの出会いもありました。初期の自主企画では、それらの来日アーティストに友達価格で、随分とスペース・オルタにも出てもらいました。
――先端のジャズを新横浜で生で聴けるのはすごいですが、聞き手がどれだけいたのでしょう。
佐藤――糸井重里の「おいしい生活」が流行し、西武百貨店が欧米から前衛的なミュージシャンを“生活の新しい味”として積極的に招聘していた時期で、そのアーティストたちがスペース・オルタで演奏してくれました。そういう意味では、観客が掘り起こされていた時代でした。でもそれがだんだんとマニアックになっていったのも事実です。
新しいものと古いもの、表層と基層を同時に見ようと、いろんな企画を立ち上げました。生活文化の基層ということで、生命力の基層や社会関係の基層への関心を抱きながら、日本の古典や民俗文化・芸能、また世界の先住民族の文化や運動への関心が中心の企画となっていきます。
1988年、反原発と平和・環境問題へのメッセージを掲げ、AIM(アメリカン・インディアン運動)リーダー、デニス・バンクス氏が来日し、Run for Run and Lifeという各地のサポーターを繋いでのランニングがありました。私は神奈川でサポートしたのですが、その流れでアイヌ民族に出会いました。それぞれの生活を取り巻く近代文明を対象化するには、その地の先住民族を理解しなければならない。日本を理解するにはアイヌのことを理解する必要があり、アメリカのいまを理解するにはアメリカン・ネイティブのいまを理解しなければならない。
・先住民の権利を求めて
――1980~90年代、先住民の権利が議論されるようになりました。1993年が国連先住民の10年の始まった年でした。
佐藤――1993年は忘れられない年です。当時、国連では認められていたにもかかわらず、日本政府はアイヌを先住民族と認めていなかったので、認めさせるための運動が必要と思いました。
それまで毎年、大太鼓をたたいて北海道を平和行脚していた日本山妙法寺のお坊さんたちがいたのですが、ちょうどこの年、米、加、独、スイスなど多国籍のグローバル・ウォークが合流しました。エコロジーを啓蒙しながら、3年かけて世界を旅してきた旅団がこの行脚に合流するということで、私たちもそこに合流し、事務局を担うことになりました。
「いのちと平和への巡礼1993」と題したこの行脚はコアメンバーが10数名。サラワクの先住民や北米のメディスンマン、メディスンウーマンも招聘し、また各地からも途中参加する人たちもいて、多い時には40名ほどにもなり、食材を各地で喜捨してもらいながら自炊で1日25〜30キロを歩き、野宿のほかは教会やお寺、ライダーハウスなどに泊まらせてもらいながら2カ月半かけて北海道を横断するというものでした。
訪れた自治体の窓口にはコアメンバーが必ず出向き、アイヌが先住民族であり国連が先住民族の10年を掲げたことを伝え、それに対してアイヌモシリ(北海道)の自治体として、どのような施策を考えているかを問うていきました。夜は各地の市民運動を担う方々に出会い交流するというもので、私はスペース・オルタを切り盛りしながらバックアップの事務局を務め、当時、藤野でパーマカルチャーの紹介・実践をしていたカナダ人のトレーシ・ロリオさんが随行事務局を務め、彼女の友人でオーストラリア熱帯雨林情報センターのアンニャ・ライトさんも全コースを踏破しました。
――国内におけるアイヌ民族の運動にもつながります。

アイヌ感謝祭のチラシ
佐藤――それまでも外の市民運動とリンクしてコンサートを作ったり、1992年にコロンブス500年で角川書店が復元したサンタマリヤ号が横浜港に寄港した時、これを快く思わない知人のアイヌと一緒に反対の意思表示をし、カムイノミの場をつくったり、オルタの機能を外の市民運動で発揮することを心がけていましたが、これほどどっぷりとアイヌの運動にかかわることになるとは思ってもいませんでした。
私も巡礼の期間中、主だった箇所で4度ほど行脚に参加し、旭川でスェットロッジに参加したり、アイヌの聖地を水没させる二風谷ダム建設反対を表明したり、二風谷で開かれた世界先住民族会議に参加したりしています。この巡礼がきっかけで道南上ノ国の夷王山ではコシャマイン慰霊祭が毎年開かれるようになり、今年で29回を数え、来年にはコシャマイン記念碑の建立を目指し活動しています。また、首都圏のアイヌたちの群像を捉えた「TOKYOアイヌ(2010年、監督・森谷博/映像製作委員会製作)」というドキュメンタリーも仲間と作りました。
――佐藤さんは北海道出身です。私も北海道出身で、しかも屯田兵の子孫です。屯田兵はまさにアイヌ民族に対する侵略者でした。
佐藤――私は、道南の森町の生まれで、小学1年の途中で江差町に移り中学2年までを過ごし、函館の高校に通いました。道南は「和人地」で、アイヌはいなかったなどと言っていましたが、流入してきた和人たちの横暴に怒り道南地域で起きたアイヌ民族による最初の大規模な蜂起を「コシャマインの“乱”」(1457年)と教えられ育った私はまさしく侵略者の息子でした。先住の民アイヌにとって“乱”などではなく、自分たちの元々の生活と権利を守るための正当な“闘”いだったのです。
夷王山には勝山館という和人地の墳墓群があるのですが、その中にアイヌ墓があることがわかり、アイヌの骨がいくつか出て来ています。和人とアイヌが全く別々に暮らしていたのではなく、異民族同士が大自然の中で交誼を結び婚姻や交流があった。そこに焦点を当てて、闘いの歴史だけでなく共生の歴史、郷土史を見直そうという気運が、コシャマイン慰霊祭を続けてきた上ノ国町で起こりつつあります。上ノ国町教育委員会や観光ガイド協会の方々が、私が事務局を務めるコシャマイン慰霊祭実行委員会に、今年から名を連ねてくれるようになりました。
――交流の多様性があるのに、一面的にしか記憶されない。しかも和人の側の一方的な記憶で語られる。
佐藤――闘いの中で語り継がれてきた記憶だけではなく、平時の生活の中で育まれてきた記憶と文化をどう継承するか?同化政策の中で奪われていったアイヌ的生活を再現できるアイヌの土地権や使用権の復活が必要です。志あるアイヌたちが生活文化を自らの内に復活させるためには、そのことを学び、実践するための経済的余裕や時間的余裕を持つ必要もあります。”生活文化総体の復活“というと余りにもハードルが高いように聞こえますが、ニュージーランドの先住民族マオリたちのように、30年余りの年月で見事に民族文化の復興をなし遂げてきた例もあります。
アイヌの土地返還訴訟も大事ですね。カナダでもオーストラリアでも一部返還しています。アイヌの文化をきちんと伝承するための場所が必要です。この山はアイヌが自由に使えるという山があれば大いに意味がある。土地所有権でなくても土地利用権の主張もありうる。
――これまでのアイヌ施策は同化、同和の延長です。恭順させる姿勢に変化はない。アイヌの文化や歴史をリスペクトする姿勢になっていない。
佐藤――アイヌを含む先住民の生活文化や儀式に触れ、独特の緩さ、明るさ、風を感じながら、あたたかな人々のつながり、流れている時間、先祖とのつながり、人生を賭けて生きてきた誇り高い人々の生きるということの質感に学びたいですね。
和人の側は、帝国の歴史以来、巨大な権威を演出する和人の儀式をつくりあげてしまいました。天皇制の下、天皇下血、歌舞音曲中止、大嘗祭、即位の礼、それにいま話題の国葬も、祈るという“心の構え”が等身大の人々の暮らしからかけ離れています。
実は北米ネイティブの祈りの儀式では、決して自分のことを祈ってはならないという考えがあります。「Thanks for All My Relations」という有名な祈りの言葉は、私のことを祈るのではなく、私につながるすべてのものに感謝をささげ、その全てのものが私のいまを生かしてくれるというエコロジカルな世界観が前提になっています。
北米先住民やアイヌの儀式には、厳かさとともにどこか暖かな風と時間が流れていて、ヒトの生活文化を考える時、私にとってその「厳しいおおらかさ」がとても重要なことと感じられるのです。
――権威主義と現代科学技術が重なり合って、ますます抑圧的世界が形成されています。
佐藤――SNSとAIが作り出す新たな現実が注目されています。マイクロソフトが2016年に世に送り出したAIチャットロボット「Tay」が、SNS(Twitter)に登場してわずか16時間後に停止され、現在もそのアカウントがロックされていることは有名です。SNSの世界からヘイト発言を学習し、人種差別、女性蔑視、陰謀論を含めて聞くに堪えないヘイト発言を、AIが濫発し出したことが原因でした。
ハリウッドを中心に数多くの近未来映画がありますが、明るい未来を描いた映画は見たことがありません。テクノロジーの発展の先には、巨大な権力の集中があり、社会は分断、混乱かあるいは過剰な静謐さが現れ、格差が激化し、人々にとって生きにくい世界になるというイメージがずっと反復されています。
・福島原発かながわ訴訟
――ユートピアがディストピアになるのは、原発問題が典型例です。佐藤さんは脱原発運動にもずっとかかわってきました。
佐藤――原発事故後、福島から神奈川に避難してきた方々の中から事故の原因と責任、そして失われた生活文化総体の賠償を求め、福島原発かながわ訴訟が闘われています。
かながわ訴訟第1陣は東京高裁で12回目の公判が行われ、2023年度中に高裁判決が出る見込みです。今年7月には、かながわ訴訟の第2陣の裁判も始まりました。
スペース・オルタは地域の文化的道具として、この生活者としての闘いを支援し、集会サポートからイベント企画の制作、チラシ、機関紙、裁判資料集にTシャツの制作などを担ってきました。独自に脱原発市民会議かながわという緩やかな組織も運営しながら、脱原発の世論形成にトライしてきました。

脱原発世直しコンサート
――原発訴訟は実にたくさんあります。稼働差し止め訴訟もあれば、株主訴訟もあれば、避難者訴訟もあります。避難者訴訟は各地で闘われています。
佐藤――避難者による避難先での集団訴訟は全国で30以上あり、そのなかでかながわ訴訟は5カ所目の訴訟です。2019年2月のかながわ訴訟第1陣の横浜地裁判決では、東京電力と国に事故の責任を認めました。しかし、その賠償の上乗せ額はあまりにも少しで、避難者が奪われた生活文化総体にとうてい釣り合うものではありません。
スペース・オルタも照明や音響などの電気を福島からもらっていた。つまり、リスクをフクシマに押し付けて、電気だけをもらっていていいのかということです。
原発事故によって故郷を剥奪され、生活文化総体を奪われる。これは、植民地において支配された人々や先住の地から追いやられる先住民、それに内乱や戦争で生まれる夥しい難民と同じ位相の被害です。
――民事訴訟は法律の制約があって、不法行為に基づく損害賠償請求の形式をとります。もちろん、膨大な経済的被害が生じましたから、避難者は損害賠償請求をしていますが、経済的に計算できない被害の方が大きい。絶対に無視できない。
佐藤――それを平気で無視する精神があることに、私も避難者たちも改めて驚愕しているわけです。
マーケットや交換価値だけを考えれば、2000~3000万円渡して、「他のどこかで暮らしてよ」と言えば済むかもしれません。でも、交換できないものがある。人格権もそうだし、記憶、価値観、育んでくれた生活総体――他の土地では手に入れられない、交換不可能なものに対しては本来、お金を出すことでは済まない。それでは、あるべき賠償とはどういうものなのかが問われている。
ドイツのメルケル首相が、ドイツでメルトダウン事故が起きたら、その賠償だけでドイツが吹っ飛んでしまうと考えたと聞きます。彼女の対応にはリアリティが感じられる。誰が考えても責任の取りようがない。賠償のしようがない。だから、脱原発が倫理的結論になる。
ところが、日本では、どんな事故を起こしても賠償を抑えることで、「このくらいの事故は起こしても事業として成り立つ」という話にしようとしている。元最高裁判事が東電の要請で意見書を出していて、今回の東電の対応を高く評価して、今回の日本の事故対応スキームは国際標準として誇れるものだという。
かつては絶対事故を起こさないという安全神話に乗っていました。どう考えてもあり得ないのに絶対安全と言って、現実に目を閉ざしていました。目を閉ざすように仕向けられてきた。ところが、今後は「これくらいの事故を起こしても大丈夫だよ」「持続可能な、サステナブルな事業として展開しうるんだ」というスキームを作ろうとしている。これに反対しないといけない。賠償金をしっかりとって、今度事故を起こしたら国が立ち行かないくらいの賠償額にしないと、同じことが繰り返されます。
 前田朗
前田朗
(一社)独立言論フォーラム・理事。東京造形大学名誉教授、日本民主法律家協会理事、救援連絡センター運営委員。著書『メディアと市民』『旅する平和学』(以上彩流社)『軍隊のない国家』(日本評論社)非国民シリーズ『非国民がやってきた!』『国民を殺す国家』『パロディのパロディ――井上ひさし再入門』(以上耕文社)『ヘイト・スピーチ法研究要綱』『憲法9条再入門』(以上三一書房)『500冊の死刑』(インパクト出版会)等。