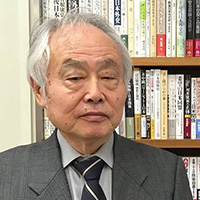【書評】塩原俊彦『知られざる地政学 覇権国アメリカの秘密 下巻』 ―落日の旧超大国から距離を置く必要性
映画・書籍の紹介・批評
書評 塩原俊彦『知られざる地政学 覇権国アメリカの秘密 上巻』―「科学の政治化」に警戒をはこちら
本書上巻の総論では、特に米国の科学技術推進により、世界全体が安全性軽視による被害に遭った分野として、核発電、遺伝子組み換え・ゲノム編集、サイバー空間、人工知能が論じられました。下巻の各論では、これら4分野に対応する形で、エネルギー、食糧、サイバー空間、金融の分野における米国の戦略が、中国やロシアのような競争相手との比較も含めて、地政学を意識した分析の俎上に載せられます。
第1章 エネルギー
第1章は本書の半分近くを占める主要部分です。著者には『パイプラインの政治経済学―ネットワーク型インフラとエネルギー外交』(法政大学出版局、2007年)、『ガスプロムの政治経済学』(アマゾン電子書籍、2013年初版、16年、19年改版)といった著作があり、エネルギーは専門中の専門という事情もあるでしょう。核エネルギー、石油、天然ガスの3分野に亘る各国間の覇権争奪が論じられます。
核エネルギー
まず莫大な発電量と、巨大な事故リスクや長期の最終処分の問題が表裏一体である核エネルギーが議論の俎上に載せられます。米国は実は1979年のスリーマイル島事故で打撃を受け、2016年まで新規原発の稼働ができず、この分野の覇権を喪失している、と評価されます(18頁以下)。米国の主要な核発電メーカーであるウェスチングハウスが東芝に06年に買収されたことは、よく知られているでしょう(22頁)。『ニューヨーク・タイムズ』報道によると、23年6月の時点で、米国資本企業は既にウラン濃縮をやめており、ロシアの国営企業ロスアトムに依存している、といった実態があります(21頁)。劣勢に置かれた米国は小型モジュール炉という新技術に賭けており、日本でも岸田文雄首相らが導入を主張したこともあります。塩原氏は世界原子力協会の資料を読み解きつつ、人口が多い地域にも存在する石炭火力発電所が、小型モジュール炉に置き換えられる可能性に警鐘を鳴らします(25頁以下)。
世界の核発電所建設市場の7割を占め、ウラン濃縮で1位、ウラン採掘で2位とされるロスアトムを中心に、核エネルギー分野で覇権を築いているのがロシアです(32頁)。同社が核兵器開発にも関わっているという事実からは(43頁)、ロシアでは核兵器と核開発の表裏一体性がより露骨に現れている、ともいえるでしょう。ロスアトムはEU加盟国にも核燃料を供給していますが、核燃料がウクライナ戦争に関わる対ロシア制裁の対象外という事実を知ると(33頁)、制裁のご都合主義的な現実が見えてきます。ロシアは欧州のみならず、インド、イラン、韓国、中国、トルコなど世界中に核発電炉を輸出しており、地政学上の勢力拡大につなげています(34頁以下)。
その中国は、建設中の核発電設備容量では世界1位、稼働中の設備容量で2位となっています。中国がロシアとも連携しつつ、第4世代高温ガス炉を先駆的に実現し、パキスタン、アルゼンチンに対して、核発電炉の輸出契約を結んでいる様を、塩原氏は「虎視眈々」と形容しています(44頁以下)。
石油
核エネルギーについてはスリーマイル事故以来、後れを取ってきた米国ですが、伝統的には石油を重視する戦略を採用してきたことが知られています。2000年代後半からは、シェールオイルの産出量が増え、米国は18年には世界一の産油国に上り詰めました(57頁)。16年に、ロシアがOPECと連携して、原油価格を抑え、割高なシェールオイルの優位をなくそうとしたという事実は、まさしく覇権争奪という言葉を使うのに相応しい事態でしょう(51、57頁)。実際にシェールオイルの高コスト体質は、労働力不足とも相まって問題になっており、2023年1月には『フィナンシャル・タイムズ』紙が「シェール革命の終焉」という記事を掲載するほど、先行きが不透明になっています(61頁)。
米国と対峙する中国の石油事情に目を向けてみますと、経済成長に伴う旺盛な需要を国内生産では到底賄いきれず、世界中からの安定的な確保に躍起になっている現状が垣間見えてきます(65頁以下)。日本の一般メディアでも話題になることが多い中国の一帯一路は、米国と同盟国、インド海軍等による海上包囲網を回避して、陸上で輸送路を確保するための戦略だという研究者、R・A・ケラニックの指摘は、背景として知っておかねばならないでしょう(66頁)。特に中国が原油輸送路として重視するのがパキスタンとの回廊ですが、パキスタンはいわゆる「債務の罠」にかかり、中国がパキスタン領内のパイプライン付近に警備要員を置くことが認められるようになりました。こういった状況は、かつて日本が満鉄周辺を支配した方法と類似している、という著者の指摘は、地政学的に極めて重要でしょう。債務の罠の他の実例としては、中国企業に自国のある港の管理権を売却したスリランカ、送電網の管理権を中国企業に25年間委ねたラオス、中国に領土の一部を割譲したタジキスタン等が挙げられています(75頁以下)。
もう一つの米国の競争相手であるロシアの石油戦略は、ウクライナでの戦争に関わってくるため、特に関心を集める話題でしょう。開戦後、ロシアの原油生産量は一時急落しましたが、欧米以外の買い手を見つけて急速に回復しています。アジアの中でも、インドのロシアからの輸入増は顕著であり、強かな戦略がうかがえます(97頁以下)。ロシア産原油の輸入を禁止している国々も、インド、中国、トルコ等を経由して、それらを原料とするディーゼル、軽油等の石油製品を購入している、という事実を聞かされると、制裁の実効性の乏しさが見えてきます(100頁以下)。
天然ガス
近年、石油よりも環境負荷が低いエネルギー源として注目を集めている天然ガスを巡っては、より熾烈な覇権争奪が起こっているようにも見えます。石油におけるシェールオイルに対応する非在来型天然ガスの代表格が、米国で近年生産量が増えているシェールガスです。米国は、環境負荷や地震誘発といったリスクを軽視しつつ、急速にシェールガス採掘を進めてきました。特に欧州市場を巡って、大量の天然ガスを比較的安価に供給してきたロシアと、LNGの輸出増加を目論む米国の利害が正面から衝突していました。
そこで問題になるのが、ロシアと欧州を結ぶパイプライン・ノルドストリーム(NS)1・2です。これらのパイプラインは、ロシアと対立するポーランドとウクライナを回避するという重要な意味もあります。特に新設のNS2を米国が問題視する理由として、塩原氏は①天然ガス供給の増加によって、欧州に対するロシアの影響力が強くなること②ロシアが従来ウクライナに対して支払っていたパイプライン通行料を不要にし、ウクライナが弱体化すること③米国がロシア産ガスの輸出量を減らして、自国製品の輸出増に繋げたいから―の三つを挙げています(116頁)。実際に米国は、かねてNS2建設に反対し、協力する企業に対する制裁を課したこともありました。そうした異例の状況の中、ドイツの抵抗もあり、2021年9月にNS2の建設は完成しました。操業開始の見通しが立たないまま、ウクライナでの戦争勃発後の22年9月に、NS1と2の爆破事件が起こったわけです(119頁以下)。
日本の一般メディアは、欧米メディアの報道を受けて、当初はロシア犯行説を有力とみなし、その後、欧米メディアの方向転換を受けて、「親ウクライナ派」なる謎の勢力による犯行であろう、という情報を流しています。つまり主体的な検証がなされているとは言い難いわけです。そうした状況の中、23年2月に、独自取材に基づき、NSを破壊したのは米国とノルウェーである、という記事を出したのが、ベトナム戦争以来の功績があるベテラン記者、シーモア・ハーシュです。
この記事には、バイデン大統領とヌーランド国務次官が、ウクライナ戦争勃発前に、ロシア侵攻の場合、NSはお終いである、と堂々と予告していた動画が収録されています。ハーシュは度々米国政府の噓を暴いてきたジャーナリストです。彼は米国がNSを破壊した理由は、欧州諸国がロシアのガスに依存する限り、ウクライナへの支援をためらうからだ、と分析しており、塩原氏も支持しています(以上121頁以下)。
誰の犯行であったにせよ、米国の天然ガス産業にとっては、まさに「好機到来」でしょう。米国企業が、欧州企業に対して、LNGの長期契約を求め、ロシア産ガスの締め出しを本格化させているという事実からは、米側の戦略の冷徹ぶりが見て取れます(127頁)。欧米側の制裁に対抗して、ロシア側は天然ガスを「武器化」し、輸入代金をルーブルで支払うよう要求しています(128頁)。こうした措置は恐らく、対ロ制裁発動後も、ルーブルの相場が想定以上に持ちこたえている事実と無関係ではないのでしょう。窮地に陥った欧州が、ロシアからのパイプライン経由の輸入は減らしても、LNGの購入量を増やしたという事実からは(149頁)、制裁の不徹底と欺瞞性を看取しないわけにはいきません。
決済通貨以外のロシアの対抗措置としては、特に中国、ベラルーシ等への輸出拡大が挙げられます(143頁以下)。それに加えて、BBCが伝えた余剰ガスの大量焼却は、戦争と政治対立が生んだ環境的悲劇といえるものでしょう(145頁)。
第2章 食料
食料安全保障という概念は、ISFも2023年9月に「食料危機」についてのシンポジウムを開催し、日本の自給率の異常な低さや、他国で使えなくなった農薬や食品添加物の“最終処分場”とされてきた実態に光を当ててきました。塩原氏は、「食料支援などを通じた影響力の行使によって、覇権につなげる動き」(176頁)に焦点を当てます。特に米国の食料援助は、現物支給が中心であるため、自国に都合の良いものを海外に渡す自国優先の傾向が見られる、と分析しています(194頁)。具体的には、食糧支援を口実に遺伝子組み換え作物の普及が推進され、例えばイラク戦争後には、米国主導の占領当局が制度を変更し、現地の農民に遺伝子組み換え種子の使用を事実上強制してきました。現地農民が多国籍企業から毎年種子を購入させられる、という支配構造も確立されました(181頁以下)。米国際開発庁と種子大手のモンサント社等の協業による所業ですが、しかも米政府幹部と同社には、いわゆる回転ドア人事による癒着が見受けられます(187頁)。
イラクと並んで、犠牲となった国が、ウクライナです。同国は2007年に遺伝子組み換え栽培は禁止していました。この慎重な方向性が、14年に米国も関与して起こされたマイダン革命後に根底から転換され、組み換え作物が普及するようになりました。米国のみならず、世界銀行とIMFという国際機関が、融資の条件として新自由主義的な規制緩和をウクライナ政府に行わせた、という指摘も極めて重要です(189頁以下)。そのIMFには、1990年代に財政破綻したアルゼンチンに、強力な除草剤であるグリホサート・ラウンドアップと、それに耐性を持つ遺伝子組み換え種子を、モンサントと協力して押し付けた、という重大な“前科”があります(195頁)。
米国の競争相手である中国は、膨大な人口を養うための食料安保を重視し、2022年からは遺伝子組み換え技術が本格的に解禁されました。中国は種子を「農業のチップ」と見なすほど重視しているとされます。貿易による食料確保に余念のない中国ですが、「米国のように、リスクを伴う新しい農業技術を相手国に普及させて、それをテコにして相手国政府や国民を米国政府の意向に従うように強制しつつ、米国企業の利益増大にもつなげる」といった露骨な作戦は取っていない、という塩原氏の指摘は重要です(以上198頁以下)。ロシアについてもまた、中国と同じく米国に比べて技術的に立ち遅れているという事情もありますが、同様の傾向にあるとされます(208頁以下)。日本の情報環境では、ロシアや中国がいわば悪魔化され、その反動でこれらの国々と対立している米国が善玉として理解されがちです。けれども、実態に即すと、全ての分野で米国側が常により人道的とは限らない、という本来は当たり前の事実に気付くことが必要です。
第3章 サイバー空間
サイバー空間については、インターネット環境を誰がどの地域に提供するかが決定的に重要であり、その覇権を巡って米国とその競争相手国は激しい闘争を繰り広げています。戦争等の緊急事態の際に、自国内に対立する他国由来の回線しかないと、即座に遮断されて通信が崩壊する、といった事態が想定されるからです。中国企業も参画するロサンゼルスと香港を結ぶ光ファイバーの海底ケーブルの敷設計画に対して米国政府が警戒し、中国と東南アジア・中東・西欧を繋ぐケーブルを巡っても、米国との間に工事の受注を巡る「暗闘」が繰り広げられた、とされます(232~240頁)。
塩原氏のこれまでの著書や記事の読者にとって馴染みがあるのは、イーロン・マスク率いるスペースX社による衛星「スターリンク」を巡る話題でしょう。スターリンクがウクライナ軍にも提供され、ドローンの運用などについて、ウクライナの戦争遂行に貢献している、といった事情のことです。国家の命運を左右しかねない通信インフラの問題が、個人の恣意により決められるという実態があります。だからこそ、EU、中国、ロシア、インド等は独自の衛星通信システムを構築しつつあり、他分野では危機感が薄い日本ですら、「みちびき」という衛星測位システムを開発しています(以上240頁以下)。
前章では食料技術を巡って中国が立ち遅れていることを確認しましたが、第5世代移動通信システム(5G)については、中国が優位を築きつつある、ということは重要です。トランプ政権が、中国メーカーを米国5G市場から追放し、報復として中国も一部の米国製チップの輸入を禁じたといった応酬は、まさにサイバー空間を巡る覇権争奪の表れです(253頁以下)。
「産業のコメ」と称されるほど重要な半導体を巡っても、各国間で過酷な攻防が繰り広げられています。半導体が安全保障上も決定的な役割を果たすことから、中国やロシアが民間企業に対して露骨な介入をしてきたことは、よく知られています。それに対してより見えにくいのは、日米欧といった国々による民間領域への干渉政策です。特に米国は、「2022年チップ・科学法」において、国家が前面に出て、何の疑問もなく補助金による民間企業活動への介入を行い、塩原氏は「中国やロシアという国家と、米国という国家の違いを見出すのは困難なほどだ」という厳しい見方を示します。EUの「欧州チップ法」も同じような「政策主導型投資」を実践しているとされます。劣勢の米国は、莫大な補助金を投じて韓国のサムスンや台湾のTSMCの工場を誘致したりしていますが、著者は国家主導で親米諸国による供給網を構築することの実現可能性に、疑問を投げかけます。実際に、中国製品は再梱包され、第三国経由で米国に入っている、とされます。「国家主導は官僚の腐敗を広げるだろう」、また、この分野での技術革新の速さに鑑みれば、「官僚が思いつきで半導体サプライチェーンを構築しようとしても、すべて水泡に帰す結果をもたらすかもしれない」といった予測は、『官僚の世界史 ─腐敗の構造』(社会評論社、2016年)の著者ならではと感じます(以上256-272頁)。
近年進歩が著しい人工知能(AI)を巡っても、中国と米国の激しいせめぎ合いが見られます。実際に2021年公開の米議会「AIに関する国家安全保障委員会」報告書では、中国は10年以内に米国を凌駕しうる、と認められています。同報告書では、AIの軍事利用の可能性として、ディープフェイク等による情報戦、サイバー攻撃の高度化、バイオテクノロジーへの応用に注目しています。米国防総省は、グーグルのような民間企業を取り込みつつ、軍人の戦闘訓練等に、AIの応用を進めています。対する中国では、「軍民融合」の方針が深刻な腐敗を招きつつ、優生学に繋がりかねない大規模な出生前検査や、ウイグル人・チベット人ら少数民族の遺伝子収集、過去の行動履歴を分析する「社会信用体系」による個人の格付け、監視システムの構築等が、AIを応用しつつ推進されているとされます。
AIの応用には懸念が多いですが、塩原氏は米国の大学で議論が活発になされていることに、希望を見出しています。それに対して日本の大学は政府の助成金に依存し、「科学の政治化」に屈して、積極的に議論をしようとしない、という「絶望的状況」について嘆いています。(以上273-285頁)。
第4章 金融
第4章の主役は通貨です。ウクライナ戦争に伴う資産凍結を含む対ロシア制裁については、ドルの武器化による米国の覇権確保、という動きがみられました(289頁)。そんなことができるのは、米ドルには世界的な決済通貨、外貨準備通貨として莫大な需要があるからです。米国が国債を低金利で発行できている理由も、そこにあるとされます。米国が事実上の拒否権を持つIMFもまた、「ドルの価値を守る最終的なアンカー」だったと看破されます(293、296頁)。
そのIMFによると、2023年第1四半期に、世界の外貨準備通貨の約6割が米ドルです。ドル覇権は、まだ決定的に揺らいではいないものの陰りが見えている、と塩原氏は慎重に評価しています(294頁)。なぜなら、ウクライナ戦争の対ロシア制裁は、米ドル取引からの離反こそが、米国の支配から逃れることになる、と多くの国々に教えることになったからです。そうした脱ドル化の動きの中心にあるのは、やはり経済大国になった中国であり、22年の人民元決済は前年比で37%も増えたとされます(305頁)。中国と近い関係にあるロシアでは、元建て債券の発行が急増しており、国債の元建て化すら検討されているとのことです(308頁以下)。
対ロシア制裁では、国際的な決済システムであるSWIFTから、ロシアが締め出されたことも話題になりました。このSWIFTはベルギーに本部があり、これまで二次制裁をちらつかせる米国の圧力に抗しきれなかった経緯があるため、塩原氏は「米国の執行機関」とみなしています。このSWIFT覇権に対抗するのが、「クロスボーダー銀行間決済システム」(CIPS)という元による決済システムを2015年に構築した中国であり、5年で決済額を17倍にするなどの急成長を見せています(314頁以下)。ロシアもまた、全ての通貨に対応する独自決済システムSPFSをつくり、抗っています(317頁)。中国とロシアが加入するBRICSが、独自の通貨を導入できれば、ドル覇権を相対化しうるものになりうるでしょう。多くの資源を持ち、加盟国を増やしているBRICSの潜在的な成長見通しは、G7を上回っている、という事情もあります(321頁以下)。
こういった通貨を巡る国際的な覇権争奪が見られる中、塩原氏が注目するのが最新技術である暗号通貨です。暗号通貨の中には、ビットコインのように発行主体が国家ではないものもありますが、本書が分析の対象とするのは、中央銀行デジタル通貨(CBDC)です。CBDCは法定通貨のデジタル版であり、中銀の管轄領域内では受け入れ義務があります。金融関係者だけが利用するホールセールCBDCと、一般市民や企業も使えるリテールCBDCの2種類があります(333頁以下)。
ドル覇権を維持したい米国はCBDCにあまり前向きではないとされますが、特にリテーCBDCに積極的に取り組んでいるのが中国です。というのも、リテールCBDCは個人・企業の決済を監視し、恣意的に凍結し、支配することが可能だからです。CBDCが意味するのは「国家の絶対的支配」「立方体のソヴィエト権力」だ、というある有識者による評価さえあります(354頁)。中国のCBDCであるe-CYNは、公共料金、交通、ショッピング、政府サービスといった分野で幅広く利用されており、22年末の時点で既に136億元分が流通しているとされます(368頁)。消費者にとっては便利でもあるのでしょうが、e-CYNの管理者たる中国人民銀行が、資金の流れを追跡、監視できてしまう、というプライバシー上の大問題もあります。しかも、個人の行動を点数化・格付けする「社会信用体系」と連動させる可能性すらあります(369頁)。こうした全体主義的な国家支配を可能にしかねないCBDCの側面と、ビットコインのように国家の独占的通貨発行権を相対化する機能を対比すると、暗号通貨の持つ両義性が見えてくると私は思います。
暗号通貨についても、日本政府はやはり米国の意向を忖度し、曖昧な態度を取っているのは、遺伝子組み換えや人工知能等、他の分野と似たような傾向のようです。
CBDCの危険性を熟知する塩原氏の結論は明確です。覇権国・米国という「一国の通貨を世界通貨のように扱う体制自体が誤り」とされ、さらに対案として、J・M・ケインズが1944年に提唱した新しい国際通貨「バンコール」の採用を提唱します。各国に対して、限定的な信用枠が与えられますが、余剰分は発行元となる「清算同盟」に返却せねばならないので、特定の国が黒字をため込むことが抑制されるのが特色です(372頁以下)。ドル支配により本来不当な利益を上げてきた米国の既存の覇権と、中央集権的なCBDCによって将来の覇権奪取を狙う中国の間にあって、経済学からの建設的な提案であるといえるでしょう。
終わりに:米国一極支配の終焉を見据え、外交と科学技術戦略の見直しが必要
「結びにかえて」では、宇宙を巡る覇権争奪への一瞥が投げかけられます。宇宙開発の分野においてすら、米国は日本や欧州を従えてこれまで覇権を握ってきましたが、中国とロシアが、グローバルサウスの国々を取り込みつつ対抗する、という構図が見られます。
「あとがき」では、著者が最も言いたかったことが集約されていると思われます。斜陽の覇権国である米国は、日本と欧州等を引きずり込み、あらゆる分野でなりふり構わず、挑戦者である中国の弱体化を図っている、と総括されます。本書でも中国やロシアに対する批判的視点は随所で見られましたが、それは一般の人々を虐げる主権国家一般に向けられていました。つまり中国やロシアが民主的でないのはわかりやすいですが、米国もまた、民主主義の美名の下、「特別階級」の利益を狙っているという意味では固有の悪がある、と著者は指摘します。「何も知らないことを知らない政治家、EUや米国の制度をマネするだけの官僚、肩書だけの蛸壺に生きる学者、はったりだけのマスコミ人」という言葉は辛辣ですが、日本のエスタブリッシュメント全体が自らの不誠実や不勉強を反省すべきだ、ということでしょう。「一人ひとりが自らの無知蒙昧に気づき、そこからの脱却のために誠実に前に歩むしかないのではないか」という本書最終ページの一言は、経験豊富な学者からの、生き延びるための学びの勧めのように聞こえてきます。
以上が上下2巻本の大著である本書の概要です。最先端の科学技術を含む多分野にわたる著者の調査・研究の深さと、批判精神の鋭さの一端が伝わったでしょうか。特に英語、ロシア語等の外国語論文、公文書、報道等を幅広く読み込み、専門性の高い科学技術の分野にあっても、多数派の見方を鵜呑みにせず、自分の頭で考え、判断することを放棄しない姿勢は、広く参考になるものだと思います。本来であれば、衰えたとはいえなお100万人単位の読者数を持つ新聞等従来型メディアこそ、このくらい見識が必要だ、と私は考えています。逆に言うと、こうした徹底的な調査を怠るから、WHOやIAEAといった権威あるとされる国際機関の主張に従うしかない、といった事大主義的な傾向が生まれているのでしょう。
本書の記述全体を通じて改めて気付かされるのは、落日の旧超大国ともいえる米国が、BRICS諸国の猛烈な追い上げを受け、既得権益や覇権を防衛しようとして、「科学の政治化」といった不当な情報操作まで用いて、あがき続けているという実情です。しかも日本は、そうした世界の趨勢を見ることなく、米国に無批判に追随し続けています。欧州にもウクライナ戦争で垣間見えたような対米従属の嫌いはありますが、それでもまだ旧文明国としての気概を見せ、抵抗を示す傾向もあるといえるでしょう。BRICS諸国も自分達の利益のために米国に対抗しているのですが、米国の一極支配の弊害を考えると、多極化には歓迎すべき側面もあると私は考えます。米国主導のQUADに加わりながら、BRICSにも名前を連ねるインドの強かさは印象的ですが、日本もまた、国際社会において生き延びるために、多元的外交や独自の科学技術戦略が必要となるでしょう。
これほど学ぶところが多い『知られざる地政学』ですが、一般読者には、分厚過ぎ、詳し過ぎ、また高過ぎる(上下巻で9000円近い)と感じられるかもしれません。そこで入門として大いに役に立つのが、今年9月以来続けられている塩原氏の同名のISF連載です。この連載も基にして、本書の本質部分をまとめた新書本が刊行されれば、初学者への啓発効果は大きいと思います。志ある出版社の目にこの提案が止まることを希望しつつ、本稿を閉じることにさせていただきます。
※塩原氏の講演会「ウクライナ戦争をどうみるか〜情報リテラシーの視点から」が12月2日(土)の14時から、北多摩西教育会館で開かれます。詳細は次のページをご覧ください。
https://isfweb.org/event/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!
 嶋崎史崇
嶋崎史崇
独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki