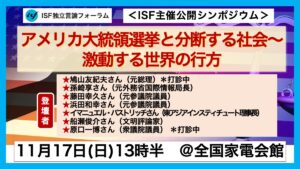東アジア共同体形成の意義と課題をめぐる考察 ―木村朗氏との対話を手掛かりに―(上)
国際序―東アジアへの着目
東アジアの連携を説く言説は、日本においても1990年以後、活性化している。この点との関連で、筆者個人の研究上で出会った出来事をここで述べさせていただくならば、1994年3月16日付の朝日新聞夕刊(東京版)の文化欄における廣松渉の寄稿記事は筆者にとって衝撃的であった(1)。
「東北アジアが歴史の主役に」という横書きで白抜きの大きな活字の下に、「欧米世界観は崩壊へ」と書かれ、さらに記事の中央に縦書きで「日中を軸に「東亜」の新体制を」と記されていた寄稿文である。括弧付きとはいえ「東亜」の新体制という表現は「右翼」的に見えて、この記事の掲載後は日本の思想界で一定の波紋を広げた。
しかし、その内容は廣松流の「反体制的」で「左翼」的なものであった。廣松は問う、「……五百年つづいたヨーロッパ中心の産業主義が根本から問い直されている」時代、「近い未来には、東北アジアが主役をつとめざるをえないのではないか」と。
そして「東亜共栄圏の思想はかつては右翼の専売特許であった。日本の帝国主義はそのままにして、欧米との対立のみが強調された。だが、今では歴史の舞台が大きく回転している。(改行)日中を軸とした東亜の新体制を! それを前提にした世界の新秩序を! これが今では、日本資本主義そのものの抜本的な問い直しを含むかたちで、反体制左翼のスローガンになってもよい時期であろう」と廣松は強調する。
そこから彼は、「商品経済の自由奔放な発達には歯止めをかけねばならず、そのためには、社会主義的な、少なくとも修正資本主義的な統御が必要である」として「ポスト資本主義の二十一世紀の世界」を展望しつつ、「エコロジカルな危機がこれだけ深刻化している今日、これは喫緊の課題であると言わねばなるまい」と述べて、文章を締め括っている。
ヘーゲル・マルクス研究を基にして、近代的な主客二元論の徹底した批判で知られる廣松渉が、死の床に臥せながら逝去の2か月ほど前に書いた「東北アジア」への「期待」は、いまだ欧米志向の強かった日本の学問・思想界にも新たな波紋を広げたことは間違いない。
それはちょうど、1992年の鄧小平の南巡講話によって中国が「社会主義市場経済」を柱として本格的に世界に乗り出そうとする時期でもあった。晩年の廣松がその主著『存在と意味』第2巻の刊行に注力し、1993年末にそれを刊行したのち(2)、病と闘いながらも、時代のそうした変容を見抜いて記事にしたためた彼の「慧眼」(3)には驚かざるを得ない。
廣松は現代中国の「発展」を見てはいないが、この30年近くも前の彼の提言は、東アジアの平和を考えようとするとき、避けて通れない問題提起ではあった。そして筆者自身も、こうした廣松の言説に触発されながら、この時期あたりから東アジアを強く意識するようになった。その後、筆者は中国、台湾、韓国などに頻繁に足を運ぶようになり、21世紀に入ってからは南京大学や北京外国語大学などの客員教授も経験して、東アジアへの関心をますます深めていったのである。
……このように、個人史的な事柄に属する内容を場違いを厭わずに記したのは、その個人史が、ちょうど東アジア共同体論の展開と軌を一にしていたからだ。いわゆる「中国の台頭」とも重なりながら、世界が東アジアを無視して進むことがあり得ない状況となってきたのである。だが、「新冷戦」などと煽って、実情以上に誇張された中国脅威論が示すのは、覇権をめぐる米国(そしてそれに追随する日本)およびヨーロッパの危機感の表れであろう(4)。
「欧米との対立」ではなく、東アジアから発する欧米をも含めた「世界」における平和と共生は、いかにして可能なのか。「戦争法案」成立や軍備の拡充(あるいは自衛隊の「南西シフト」)、さらには「敵基地攻撃」論が語られる時期に、だからこそ、いかにして北東アジアからの平和構築への戦略を描くことが可能なのか。この点がいま問われなければならないという思いが、強く筆者の脳裏をよぎる。
社会学者として筆者はこれまで、国家間の「国際関係」ではなく、国境を越えた人間間の「人際(にんさい)関係」(および民間団体間の関係である「民際関係」も)こそ重要だとして、人びとのトランスナショナルな「移動」と「共生」に関心を寄せてきた(西原 2018a)
そこから見えてくる東アジア共同体論への期待と課題を、本稿では主題として語ってみたいと考えている。そのためには、社会学という狭い枠を超えて、政治学や平和学などとの対話も必要となってくる。そこで本稿では、この問題に活発に発言し、活動・実践も継続的に行っている、政治学者でありかつ同時に平和学者でもある木村朗氏に焦点を合わせて、東アジア共同体論に言及していくことにしたい。そのためにはまず、東アジア共同体論の概要に関して論及しておくべきだろう(5)。

Earth, diversity, race,SDGs
1.日本における東アジア共同体論の展開
ここでは、日本における東アジア共同体論の、とくに21世紀における展開に限定して、その概略を述べておくことにしたい。もちろん、日本における東アジア共同体論の展開を語ろうとするとき、歴史的には1930年代後半の「東亜共同体」論をすぐに思いつく人もいるだろう。
しかしながら、この議論は、それ以前の「アジア主義」の潮流とも相まって、「東亜新体制」⇒「大東亜共栄圏」につながる系譜であったことは間違いないので、日本盟主論や偏頗な欧米批判などとともに、それには批判的に対峙するほかない。ただしこの「東亜共同体」論の周辺には、三木清のように日本中心・アジア自閉に対して批判的な言説も見られたし、それはそれで再検討に値する部分もあるが、ここでは詳細に立ち入ることはしない(6)。
さて、アジア太平洋戦争後、日本のアジア侵略への反省もあって、また中国の新中国建設や、さらには朝鮮半島での朝鮮戦争後の分断国家における閉ざされた独裁体制の出現もあって、北東アジア各国では「内向き」な時期が続いていた。
東アジア全体としては、ASEANの発足(1967年)はきわめて重要な転機の一つだが、こと北東アジア(7)に関しては、1972年の日中国交回復はあったものの、1978年末の中国の改革開放政策決定から1992年の社会主義市場経済への政策転換、あるいは1987年の韓国、台湾の民主化の流れなどが生じて、ようやく1990年代に入って北東アジアが、海をも挟んで(ただし友好と敵対の両方の関係を含むが)一定のまとまりある地域・リージョンの自覚が芽生えてきたように思われる(後述も参照)。

ASEAN member states, infographic and map. Association of Southeast Asian Nations, a regional intergovernmental organization with 10 member countries, shown with green color. Illustration. Vector.
そうしたなかで――民間レベルでは――すぐ後で述べる森嶋通夫の「東アジア共同体」の提唱などが現れ、そして一気に新たなミレニアムあるいは21世紀に入ってから、日本において東アジア共同体論の活性化が見られるようになったのである(8)。
そこで、背景となる日本国内の時代状況を見ておきたい。ただし、ここでは国家レベルではなく、日本における「地方」(地方自治体)および「民間」のレベルに着目し、かつ沖縄を中心にして、東アジアへの着目の動きの概略を見ておきたい。
まず、1993年頃からの沖縄の大田昌秀県政下でのアジアとの連携を核とする「国際都市形成構想」の本格的開始(1996年決定)、および1997年の(アジアからの参加者を含めた連帯の動きが見られた)沖縄独立のための「激論会」(「沖縄独立の可能性をめぐる激論会」実行委員会編 1997)が着目に値するだろう。
ただし、こうしたことが伏線となりながらも、1998年の大田知事の知事選敗北、保守系の「沖縄イニシアティブ論」や「二一世紀日本の構想」の提唱(2000年)などから、さらに21世紀の00年代中ごろ以降の普天間基地の辺野古への移設を明示化した「ロードマップ」の作成、保守系の仲井眞県政への移行(以上は2006年)、自治権拡大を期待した道州制案の消滅(2009年)といった流れの中で、そして最後は東アジア共同体志向を明確にしていた民主党鳩山政権の崩壊とともに、地方/民間ベースの東アジア共同体(そして関連する沖縄独立)の構想もいったんは潰えたかに見えた。
だが、2010年に松島泰勝らによる「琉球独立宣言」が出され(松島・石垣 2010)、さらに松島らによって「琉球民族独立総合研究学会」も設立される(2013年)。そして、ここではさらに、この独立論の動きと深く絡み合いながら、「東アジア」関連のいくつかの新しい運動の流れにも同時に着目することができる。
すなわち、まず上述の国際都市形成構想から前述の鳩山政権を経たのちに、東アジア共同体研究へと本格的に進む組織的な流れが生まれた。それは、2013年の「東アジア共同体研究所」(理事長は鳩山元首相:以下では「研究所」と略記)の設立であり(東アジア共同体研究所編 2014)、次いで翌2014年には沖縄の那覇に同研究所の「琉球・沖縄センター」が開設されたという流れである。
 西原和久
西原和久
砂川平和ひろばメンバー:砂川平和しみんゼミナール担当、平和社会学研究会・平和社会学研究センター(準備会)代表、名古屋大学名誉教授、成城大学名誉教授、南京大学客員教授。著書に『トランスナショナリズム序説―移民・沖縄・国家』、新泉社、2018年、などがある。